前回の続きです。
ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)には放射線防護に用いられる諸量についての詳しい解説も載っていて、吸収線量から等価線量や実効線量を導くのに必要な放射線加重係数や組織加重係数をどのように決定したかも書いてあります。これらの具体的決定過程は「付属書B 電離放射線の生物影響」に載っています。目次を本記事の末尾に示しましたので御参照下さい。さて組織荷重係数の話です。
組織荷重係数としては表の第1列の値が推奨されていますが、これは第2列に記した値を使いやすいように丸めたものです。第2列の値はPubl.60の付属書Bの表B-20に記載のもので、放射線による個体への全損害に対する各臓器の寄与を、全臓器の和を1として表した値です。では各臓器の寄与とは何かと言えば、次の式で定義されるものです。l(エルの上線付き)が少し見にくいようですが御容赦下さい。
損害寄与=F*l/l*(2-k) ---式1
F ;致死がんの確率と重度の遺伝的影響
l/l ;相対的寿命損失
l ;各臓器の致死がんの寿命損失
l ;各臓器の致死がんの寿命損失の全体平均
(2-k);非致死がんの相対寄与
k ;全がん中の致死がんの割合
Fは色々な実験や疫学調査から得られた測定値です。致死がんは各臓器で死亡するまでの平均年数が異なりますので、寿命損失という形での定量的損害評価をするためにl/lという係数を掛けます。寿命損失とは文字通り、各臓器の致死がんにかからなかった場合の平均余命とかかった場合の平均余命の差です。これは放射線以外の原因も含む全ての致死がんについての平均です。
ここまでは致死がんの寄与ですが、非致死がんもなんらかの被害を与えると考えてその相対寄与を(2-k)という形で与えています。ここには多少恣意的とも言える考えが入っています。すなわち、致死がん発生数をF、非致死がん発生数をNとして、損害を次式で仮定します。
損害=F+kN ---式2
全がん発生数をAとすれば以下の式が成り立ちます。
A=F+N
F=kA
ゆえに
N=A-F = F/k -F
損害=F+k(F/k -F)=F(2-k)
かくて(2-k)という係数が導かれます。なお、ここでのFは症例数としたので式1の確率(人口当たりの症例数)とは一応は別の量ですが、A,F,Nとも人口で割れば式1と同じ量になり、理論は同様なものとなります。
ごらんの通り式2で非致死がんによる損害をkNと仮定したのですが、ここは「治癒可能ながんの誘発による損害に重みをつけるどんな試みも、その過程は主観的にならざるを得ないが、」(p158)ということで、まあ妥当そうな仮定を置いたということになるのでしょう。
-------------
ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)日本語版の目次
(括弧内は項目番号)
第1章 緒 言 --------------------- 1 (3)
第2章 放射線防護に用いられる諸量------------ 5 (17)
第3章 放射線防護の生物学的側面------------- 14 (42)
第4章 放射線防護の概念的な枠組み------------ 31 (99)
第5章 提案された行為と継続している行為に対する防護体系- 41 (133)
第6章 介入における防護体系--------------- 61 (210)
第7章 委員会勧告の履行----------------- 66 (226)
勧告の要約----------------------- 82
付属書A 放射線防護に用いられる諸量----------- 95
付属書B 電離放射線の生物影響--------------107
付属書C 放射線の影響の重要性を判断するための基礎----193
付属書D 委員会刊行物のリスト--------------227
ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)には放射線防護に用いられる諸量についての詳しい解説も載っていて、吸収線量から等価線量や実効線量を導くのに必要な放射線加重係数や組織加重係数をどのように決定したかも書いてあります。これらの具体的決定過程は「付属書B 電離放射線の生物影響」に載っています。目次を本記事の末尾に示しましたので御参照下さい。さて組織荷重係数の話です。
| 組織・臓器 | 推奨値 | 表B-20 |
|---|---|---|
| 生殖腺 | 0.20 | 0.183 |
| 卵巣 | 0.020 | |
| 骨髄 | 0.12 | 0.143 |
| 結腸 | 0.12 | 0.141 |
| 肺 | 0.12 | 0.111 |
| 胃 | 0.12 | 0.139 |
| 膀胱 | 0.05 | 0.040 |
| 乳房 | 0.05 | 0.050 |
| 肝臓 | 0.05 | 0.022 |
| 食道 | 0.05 | 0.034 |
| 甲状腺 | 0.05 | 0.021 |
| 残りの組織・臓器 | 0.05 | 0.081 |
| 皮膚 | 0.01 | 0.006 |
| 骨表面 | 0.01 | 0.009 |
組織荷重係数としては表の第1列の値が推奨されていますが、これは第2列に記した値を使いやすいように丸めたものです。第2列の値はPubl.60の付属書Bの表B-20に記載のもので、放射線による個体への全損害に対する各臓器の寄与を、全臓器の和を1として表した値です。では各臓器の寄与とは何かと言えば、次の式で定義されるものです。l(エルの上線付き)が少し見にくいようですが御容赦下さい。
損害寄与=F*l/l*(2-k) ---式1
F ;致死がんの確率と重度の遺伝的影響
l/l ;相対的寿命損失
l ;各臓器の致死がんの寿命損失
l ;各臓器の致死がんの寿命損失の全体平均
(2-k);非致死がんの相対寄与
k ;全がん中の致死がんの割合
Fは色々な実験や疫学調査から得られた測定値です。致死がんは各臓器で死亡するまでの平均年数が異なりますので、寿命損失という形での定量的損害評価をするためにl/lという係数を掛けます。寿命損失とは文字通り、各臓器の致死がんにかからなかった場合の平均余命とかかった場合の平均余命の差です。これは放射線以外の原因も含む全ての致死がんについての平均です。
ここまでは致死がんの寄与ですが、非致死がんもなんらかの被害を与えると考えてその相対寄与を(2-k)という形で与えています。ここには多少恣意的とも言える考えが入っています。すなわち、致死がん発生数をF、非致死がん発生数をNとして、損害を次式で仮定します。
損害=F+kN ---式2
全がん発生数をAとすれば以下の式が成り立ちます。
A=F+N
F=kA
ゆえに
N=A-F = F/k -F
損害=F+k(F/k -F)=F(2-k)
かくて(2-k)という係数が導かれます。なお、ここでのFは症例数としたので式1の確率(人口当たりの症例数)とは一応は別の量ですが、A,F,Nとも人口で割れば式1と同じ量になり、理論は同様なものとなります。
ごらんの通り式2で非致死がんによる損害をkNと仮定したのですが、ここは「治癒可能ながんの誘発による損害に重みをつけるどんな試みも、その過程は主観的にならざるを得ないが、」(p158)ということで、まあ妥当そうな仮定を置いたということになるのでしょう。
-------------
ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)日本語版の目次
(括弧内は項目番号)
第1章 緒 言 --------------------- 1 (3)
第2章 放射線防護に用いられる諸量------------ 5 (17)
第3章 放射線防護の生物学的側面------------- 14 (42)
第4章 放射線防護の概念的な枠組み------------ 31 (99)
第5章 提案された行為と継続している行為に対する防護体系- 41 (133)
第6章 介入における防護体系--------------- 61 (210)
第7章 委員会勧告の履行----------------- 66 (226)
勧告の要約----------------------- 82
付属書A 放射線防護に用いられる諸量----------- 95
付属書B 電離放射線の生物影響--------------107
付属書C 放射線の影響の重要性を判断するための基礎----193
付属書D 委員会刊行物のリスト--------------227










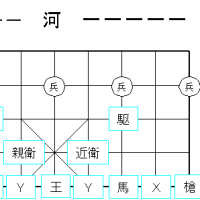
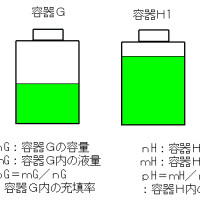
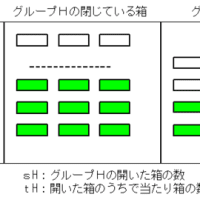
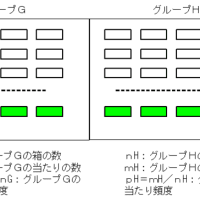
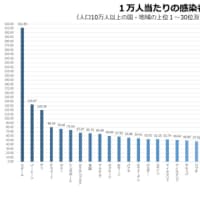
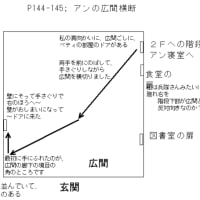
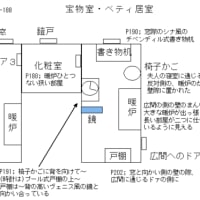
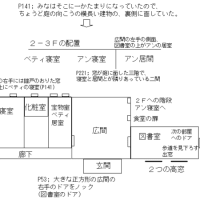
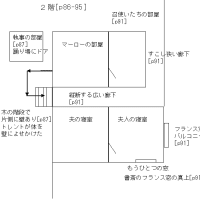
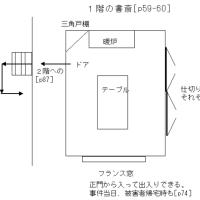






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます