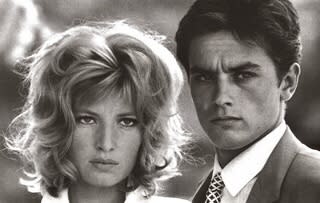ブルックナーという作曲家の名前を聞いたこと、ありますか。大作曲家ですけど。たぶんご存知ないでしょうね。 でも例えば、 バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、シューマン、ショパン、チャイコフスキー、マーラー・・ こう並べると、名前くらいは知ってる、というかたは多いと思います。
ブルックナーは一般的な知名度はない。でもクラシック音楽の世界に踏み込むと、否応なくその名前を聞くことになります。だって、巨人ですから....

サザンカが咲き始めました。でもなぜか、八重のものしかまだ見ていません。

今日書きたいことは、タイトルに示した通りです。その例としてブルックナーの話をします。

アントン・ブルックナー (1824〜1896, オーストリア)
ブルックナーの生涯を見ると、色々なことがいちいち遅い。作曲を学んだのも、書き始めたのも、そして音楽界で認められたのも、遅い。 1824年9月、オーストリアのリンツ郊外、小さな村で生まれています。
父親が、教会のオルガン奏者で学校の校長先生もしていたので、成長過程で音楽の環境はありました。でもその父親もブルックナー少年が12歳の時亡くなります。 16歳の時、補助教員の免許を取り、翌17歳から、小学校で補助教員を始めます。また教会でオルガンを弾いたり、時には村人たちの踊りにヴァイオリンで伴奏したりもしたと言います。 彼は静かに、ひたひたと音楽の勉強を続けて行きます。

クロガネモチの赤い実。まだ、たわわというほどは生ってなかったな。昨日撮りました。
1948年 24歳、聖フローリアン修道院のオルガニストに採用される。
1955年 31歳、作曲家にして音楽理論家 ジーモン・ゼヒターに師事。ここからやっと本格的な作曲の勉強が始まります。 あ〜... 遅いよ*** 例えば「享年」を見ると、モーツァルトは35、シューベルトは31、メンデルスゾーンは38、ショパンは39で亡くなっています。彼ら天才たちからすれば、31歳はもう晩年です。ブルックナーはまだ作曲家としての人生が始まっていません。

逆光の中で撮ったダリア。逆光も花の赤色も眩しかった。
1861年 37歳、ゼヒターの元での修行を終える。翌1862年、ワーグナーの音楽に出会い、強く刺激を受けます。この頃からそろそろ管弦楽曲(オーケストラの音楽)の作曲が始まります。でもまだ、習作の段階です。
ブルックナーは生涯で、自分で番号を付した交響曲を9曲残しました(第9番は未完)。それ以外にも宗教曲、オルガン曲等があります。
その第1番交響曲の完成が1866年、42歳の時。早熟の天才たちと比較するのは余り意味がないですが、モーツァルトの交響曲第1番は8歳のときに、、またメンデルスゾーンも13歳くらいで充分完成された交響曲を書いています。(レコードで聴けます)
交響曲作家としてのブルックナーの人生は42歳で始まり、以降亡くなるまで交響曲を書き続けて行きます。

一昨日撮ったキダチチョウセンアサガオ。まだ花期が続いているのが驚きです。
1868年 44歳、ウィーン国立音楽院の教授に就任。17歳で小さな村の補助教員として出発した、教師としてのブルックナーがここまで来ました。ですがまだ、作曲家としては全く評価されていません。
1873年 49歳、交響曲第3番の初稿を完成、1877年 52歳、第3交響曲を改定し第2稿とする。そして、この第2稿の交響曲をブルックナー自身の指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で初演(お披露目、というところですね)します。52歳です。が、大失敗に終わります。演奏が終わる頃、聴衆はほとんど残っていませんでした。(ただ、残った数少ない観客の中に若きマーラーがいた、というのは音楽ファンとしては興味深いエピソードです)
ブルックナーは72歳で生涯を終えますので、結局生きているあいだは評価されず仕舞いだったのか? と思われますでしょうか。・・そういう運命にはなりませんでした。

ヒイラギモチ。珍しく葉に斑が入っていました。昨日の撮影です。(『セイヨウヒイラギ』の、葉にトゲの少ない品種の可能性もあります)
1884年、交響曲第7番を初演。これが成功し、当時の音楽界で初めて、ブルックナーは作曲家としての評価を得ます。60歳です。亡くなる12年前です。遅咲きと言えばそうでしょう。ですが、彼の才能はさらにその後、開花して行くのです。
1887年、交響曲第8番の第1稿を完成、1890年、第2稿の改訂を終了させる。66歳。この稿が現在でも演奏される、交響曲第8番です。演奏時間 約80分。作曲家ブルックナーの最高傑作とされます。
その後も作曲の筆を止めず、第8番第1稿完成後に着手していた交響曲第9番の完成を目指します。
が、過酷な運命はこの真の最高傑作、交響曲第9番の完成を許しませんでした。第3楽章までは書き上げたものの最終楽章の完成に至る前に、ブルックナーは力尽きます。1896年、72歳でした。

卵みたいなワイヤープランツの実、タネ。

私にはブルックナーの存在は、奇跡としか思えません。天才でも秀才でもない、普通の人、しかしコツコツとした努力で才能を開花させました。 その音楽は、よく言われることですが、宇宙を感じさせるものです。世界中に今現在も熱狂的なファンを数多く持ちます。 交響曲の分野に限ればベートーヴェンを越える、とするファンも多くいます。私もその一人です。 才能の開花に年は関係ない、そう思わせてくれる偉大な作曲家です。
一応、第9番の録音を貼りますが、全体で60分近く、第1楽章だけでも25分もあります。クラシック音楽に興味のない方には苦痛だと思います。そういう人はスルーして下さい。出来れば、最初の3〜5分くらいでも聴いて貰えると嬉しいです。 カール・シューリヒト指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏、1961年。
※ この動画(と言っても音楽のみ)が削除されていました。
そこで貼り直します。指揮者、演奏団体は上記と同じです。ブルックナーの9番はシューリヒトが最も優れていると考えます。 2019/04/06更新.