木曜日から土曜日まで放心状態もいいところだったが、日曜日にようやく復活した。
夫も実家から戻って来て、子どもたちは二人揃ってキャンプへ行っているので、なつやすみプロジェクトに突入する。
「台所ベコベコ床大作戦」
うち(自宅)は1980年代に建った中古住宅である。
阪神大震災よりずうっと以前、つまり建築基準法が今よりもずうっとゆるくて、テキトーなおうちがいっぱい建っていた時代である。
そしてそのころ「メーターモジュール」というのが一時流行ったらしい。
日本の昔ながらの建築は「尺モジュール(910mm単位)」なのだが、安い輸入材は「メーター(1000mm単位)」で来る。「ならメーターで設計して建てたらいいじゃん」という一件合理的な話である。
ところがそうするとその他の建材(コンパネ、断熱材など)も「メーターモジュール」でないといけないわけなのだが、ところがどっこい、わざわざそんなもの輸入すると高くつくのである。
さて、うちはその「メータモジュール」の中古住宅である。
前の持ち主の奥さんは「メーターモジュールでたてたから廊下が広いのよ」とおっしゃっていた。疑うことを知らないっぽいいい人だったなあ。確かに廊下は広い。
ところが壁を開けてみると、中の断熱材は尺モジュールの断熱材が入っているのである。つまり「50cmの間隔に45cmの断熱材が入っている」というわけ。これはもはや断熱材と言えるのかどうかさえわからない始末である。
畳屋さんに「床がベコベコする。ひょっとして根太が腐っているかもしれないから見た方がいい」と言われて、ヒーとなって開けてみたら、根太はピンピンしているのだが、100cmの間隔に91cmのコンパネを乗せようとしているから「コンパネの端っこが根太に乗らない=落ちている」状態になっていた。マジか。家ってこんなんでも建つのか。
しかしそれでも30年平気で建っているわけだし、先の震災時も無事だった。震度6を超えたらダメかもしれないが、家ってこんなんでもなんとかなるもんなのだ。
で、ようやく「台所の床」の話。
前から台所も床がベコベコしていたのだが、ここ何年かそれが顕著になってきた。
これは開けてみるしかあるまい。と思いつつも開けずにいた。
理由のひとつは台所は毎日使うところだから床を開けるとなると大変だから。もうひとつは水回りゆえ「根太が腐っている」ということもあり得たからである。
根太が腐ってたら早く開けた方がいいのだが、そこはそれ。臭い物にはフタをしておきたいと。見て見ぬ振りをしておきたいと。
でも。
しかし。
この夏「ふたりとも子供がいない」という絶好の機会を利用して開けてみることにしたのである。

まず敷いてたPタイルをはがす。
左手に出て来ているのが古い床。

一番上の板をめくってみた。

ここがベコベコしているところ。
ベコベコっつうか、「陥没している」。

穴をあけてみる。
根太はピンピンしてた。よかった。
もちろん断熱材などは入っていない。
板の切れ目に根太が来てないことがわかるだろうか?

はがしてみると、「一番上の板」「2層目」ではなくて、全部が一体となっている12ミリの床材だということがわかった。
今でも普通に使われているタイプの安床材なので、ホームセンターで一枚買ってくる。980円なり。
それにあわせて「一枚分」はがして、

根太に角材を追加する。

3つ前の写真と比べてみると分かるかな。床材がのせられるようにしている。

で、980円の床材をはめこむ。
歪みなどもあり、かなり強引にはめこんだ。
オットの「うおー」とか「むあー」とかいう声が響き渡る。
「根太に床が乗っていない」ことに加え、「経年劣化で床材自体がへたれてきている」せいでベコベコになっているということがわかった。
たしかに12ミリ程度のベニヤ床、30年以上毎日毎日踏みしめていたらそれはへたれるだろう。
まだ何カ所かベコベコしているところはあるものの、一番気になるところは解消されたし、あとは床下収納周りのベコベコを補強材いれてもらって解消してもらい終了。
いつか床を全とっかえしないといけないかもしれないが、そのときはシンクの高さも調整したり場所を考えたりと、抜本的なところから行おう、ということで今回はこれで終わり。
Pタイルも壊れてきているので、10年あまり同じだった赤×白のポップな台所からイメージチェンジすることにした。
木もいいが、やはり水回りなのでクッションフロアにする。
テラコッタ柄をネットで注文。
どのていど「なんちゃって感」が出るのかは来てのお楽しみ。
つづく。
夫も実家から戻って来て、子どもたちは二人揃ってキャンプへ行っているので、なつやすみプロジェクトに突入する。
「台所ベコベコ床大作戦」
うち(自宅)は1980年代に建った中古住宅である。
阪神大震災よりずうっと以前、つまり建築基準法が今よりもずうっとゆるくて、テキトーなおうちがいっぱい建っていた時代である。
そしてそのころ「メーターモジュール」というのが一時流行ったらしい。
日本の昔ながらの建築は「尺モジュール(910mm単位)」なのだが、安い輸入材は「メーター(1000mm単位)」で来る。「ならメーターで設計して建てたらいいじゃん」という一件合理的な話である。
ところがそうするとその他の建材(コンパネ、断熱材など)も「メーターモジュール」でないといけないわけなのだが、ところがどっこい、わざわざそんなもの輸入すると高くつくのである。
さて、うちはその「メータモジュール」の中古住宅である。
前の持ち主の奥さんは「メーターモジュールでたてたから廊下が広いのよ」とおっしゃっていた。疑うことを知らないっぽいいい人だったなあ。確かに廊下は広い。
ところが壁を開けてみると、中の断熱材は尺モジュールの断熱材が入っているのである。つまり「50cmの間隔に45cmの断熱材が入っている」というわけ。これはもはや断熱材と言えるのかどうかさえわからない始末である。
畳屋さんに「床がベコベコする。ひょっとして根太が腐っているかもしれないから見た方がいい」と言われて、ヒーとなって開けてみたら、根太はピンピンしているのだが、100cmの間隔に91cmのコンパネを乗せようとしているから「コンパネの端っこが根太に乗らない=落ちている」状態になっていた。マジか。家ってこんなんでも建つのか。
しかしそれでも30年平気で建っているわけだし、先の震災時も無事だった。震度6を超えたらダメかもしれないが、家ってこんなんでもなんとかなるもんなのだ。
で、ようやく「台所の床」の話。
前から台所も床がベコベコしていたのだが、ここ何年かそれが顕著になってきた。
これは開けてみるしかあるまい。と思いつつも開けずにいた。
理由のひとつは台所は毎日使うところだから床を開けるとなると大変だから。もうひとつは水回りゆえ「根太が腐っている」ということもあり得たからである。
根太が腐ってたら早く開けた方がいいのだが、そこはそれ。臭い物にはフタをしておきたいと。見て見ぬ振りをしておきたいと。
でも。
しかし。
この夏「ふたりとも子供がいない」という絶好の機会を利用して開けてみることにしたのである。

まず敷いてたPタイルをはがす。
左手に出て来ているのが古い床。

一番上の板をめくってみた。

ここがベコベコしているところ。
ベコベコっつうか、「陥没している」。

穴をあけてみる。
根太はピンピンしてた。よかった。
もちろん断熱材などは入っていない。
板の切れ目に根太が来てないことがわかるだろうか?

はがしてみると、「一番上の板」「2層目」ではなくて、全部が一体となっている12ミリの床材だということがわかった。
今でも普通に使われているタイプの安床材なので、ホームセンターで一枚買ってくる。980円なり。
それにあわせて「一枚分」はがして、

根太に角材を追加する。

3つ前の写真と比べてみると分かるかな。床材がのせられるようにしている。

で、980円の床材をはめこむ。
歪みなどもあり、かなり強引にはめこんだ。
オットの「うおー」とか「むあー」とかいう声が響き渡る。
「根太に床が乗っていない」ことに加え、「経年劣化で床材自体がへたれてきている」せいでベコベコになっているということがわかった。
たしかに12ミリ程度のベニヤ床、30年以上毎日毎日踏みしめていたらそれはへたれるだろう。
まだ何カ所かベコベコしているところはあるものの、一番気になるところは解消されたし、あとは床下収納周りのベコベコを補強材いれてもらって解消してもらい終了。
いつか床を全とっかえしないといけないかもしれないが、そのときはシンクの高さも調整したり場所を考えたりと、抜本的なところから行おう、ということで今回はこれで終わり。
Pタイルも壊れてきているので、10年あまり同じだった赤×白のポップな台所からイメージチェンジすることにした。
木もいいが、やはり水回りなのでクッションフロアにする。
テラコッタ柄をネットで注文。
どのていど「なんちゃって感」が出るのかは来てのお楽しみ。
つづく。



















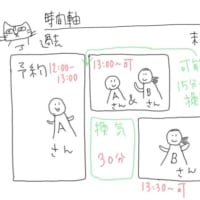
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます