日本の英語教育関係者の中で一番困りものなのが大学入試二次試験英語問題の作成者です。日本語を使わないで英語力を測定する方法はいくらでもあるにもかかわらず、英文和訳やら和文英訳といった化石英語を出題し続けています。その結果、受験英語を熱心に勉強すると日本語を介在させずには気が済まない悪癖がついてしまうことが少なくありません。守旧派でなければ入試問題を作成する位まで出世できないのが、象牙の塔の現状なのでしょう。
大学入試英語より英語問題としてはるかにまともなのがTOEICです。アカデミックな英語より実用英語を優先するのは理にかなっています。しかし、問題用紙の持ち帰りも認めないやり方はあこぎとしか言いようがありません。あれほど高い受験料をとるのであれば、問題用紙の持ち帰りどころかリスニングCDと模範解答をおみやげにつけてもいいと思います。
英検はTOEICよりさらにましです。一次試験の合格ラインを六~七割にして基礎がいい加減なまま上の級に誘導するやり方は早急に改めてほしいものの、問題用紙の持ち帰りができて正解をすみやかに公表するのは良心的で、問題自体も日本語の介在が少ない素直なものがほとんどです。
加えて英検のサイトを見ると、過去一年間に出題された問題を一級から五級まで無料で演習できます。英検の試験問題 をご覧ください。
ただ、英検に受かろうとしてやみくもに受験するのは一番お金が無駄になります。英検の試験問題 に自宅で取り組めば無料です。注意しなければならないのは合格点がクリアできたからといって安易に上の級に進まないことです。六~七割の正解率で上に進むと同じ級で何度も失敗する英検難民になって英検協会を儲けさせる可能性大です。
英検の試験問題 をやって六~七割の正解率を出せる過去問があれば過去問集を買って解説をしっかり読んで、七~八割正解できるようになってから受験するのがよいでしょう。余裕で合格しても油断することなく、合格した級の英検の試験問題 がコンスタントに九割以上正解できるようにしておくと、基礎力に不安はなくなります。もちろん日常学習としては試験対策よりも英語対策を優先し、問題演習よりも読書を重視するようでないとしっかりした英語力はつきません。
最近、漢検の儲け過ぎがニュースになっています。ただ、検定と名がつけばむやみやたらと金をつぎ込む受験者の側にも大いに問題があると思います。
大学入試英語より英語問題としてはるかにまともなのがTOEICです。アカデミックな英語より実用英語を優先するのは理にかなっています。しかし、問題用紙の持ち帰りも認めないやり方はあこぎとしか言いようがありません。あれほど高い受験料をとるのであれば、問題用紙の持ち帰りどころかリスニングCDと模範解答をおみやげにつけてもいいと思います。
英検はTOEICよりさらにましです。一次試験の合格ラインを六~七割にして基礎がいい加減なまま上の級に誘導するやり方は早急に改めてほしいものの、問題用紙の持ち帰りができて正解をすみやかに公表するのは良心的で、問題自体も日本語の介在が少ない素直なものがほとんどです。
加えて英検のサイトを見ると、過去一年間に出題された問題を一級から五級まで無料で演習できます。英検の試験問題 をご覧ください。
ただ、英検に受かろうとしてやみくもに受験するのは一番お金が無駄になります。英検の試験問題 に自宅で取り組めば無料です。注意しなければならないのは合格点がクリアできたからといって安易に上の級に進まないことです。六~七割の正解率で上に進むと同じ級で何度も失敗する英検難民になって英検協会を儲けさせる可能性大です。
英検の試験問題 をやって六~七割の正解率を出せる過去問があれば過去問集を買って解説をしっかり読んで、七~八割正解できるようになってから受験するのがよいでしょう。余裕で合格しても油断することなく、合格した級の英検の試験問題 がコンスタントに九割以上正解できるようにしておくと、基礎力に不安はなくなります。もちろん日常学習としては試験対策よりも英語対策を優先し、問題演習よりも読書を重視するようでないとしっかりした英語力はつきません。
最近、漢検の儲け過ぎがニュースになっています。ただ、検定と名がつけばむやみやたらと金をつぎ込む受験者の側にも大いに問題があると思います。











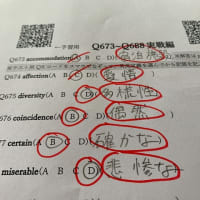


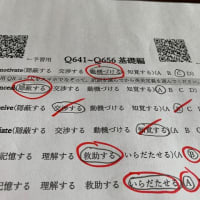

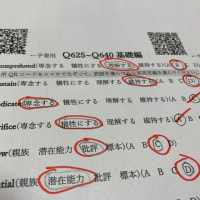





僕は今年から受験生なのですが、大学入試の英語問題は確かに「化石」ですね^^;意訳しなければわかったことにならない、というのはどうも納得がいかないですし、なにより英語のインプットの阻害につながるのは、受験生側としてはとても残念です。
でも、english x english式の試験がセンター試験で出題されたのはうれしいことですね。english x englishを愛読している僕にとっては、今年度のセンター試験は良問です^^
とはいえ、大学入試二次試験の英語問題に批判的な声が広がれば、変わらざるを得なくなるでしょう。入試英語に限らず、「プロは説明のつかないことをやってはいけない」と私は考えています。「説明責任社会」を実現するために、まずは自分自身の説明責任をしっかり果たしていきたいと思っています。