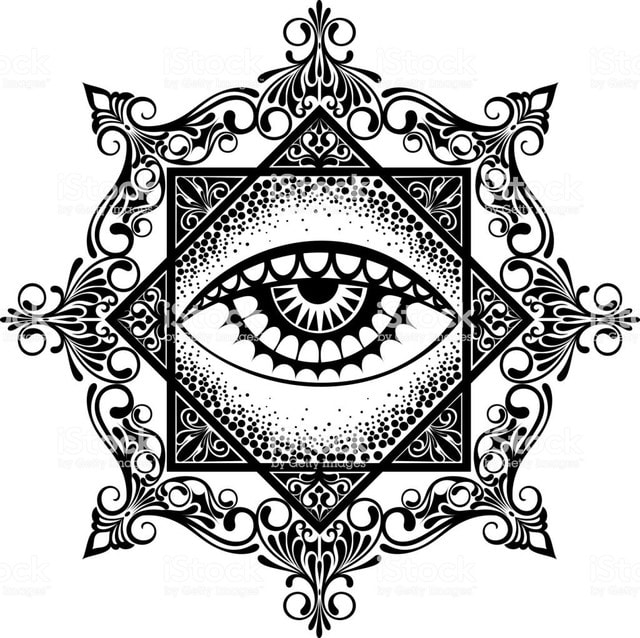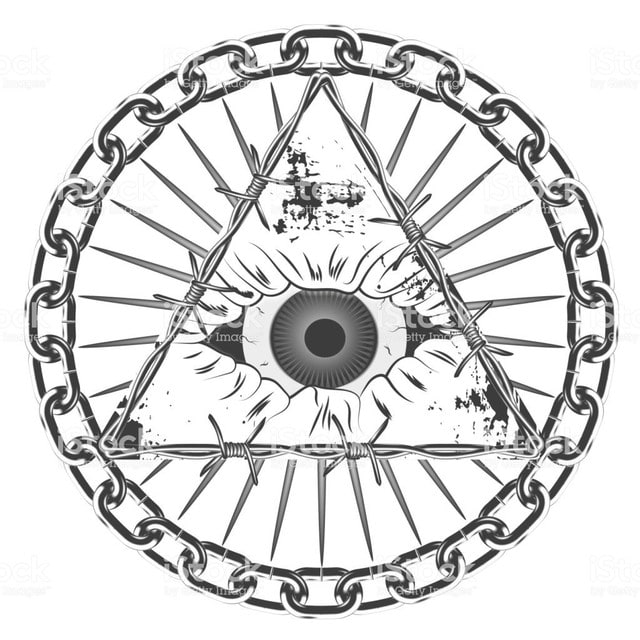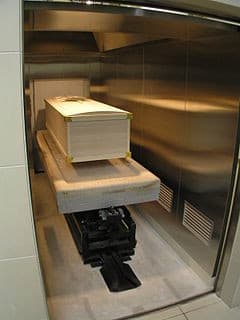透析患者の場合,透析継続の中止後,大多数の患者が10日前後で死に至る.
欧米では透析中止による死亡が決して稀な事象ではないとは言えよう.透析継続の中止アメリカでは透析中止が先行して死亡(with-drawalfromdialysisbeforedeath)に至る比率が近年20-25%に達して,死因の第2位または第3位を占めていると報告されている4).透析中止による死亡を「生命の自然経過」と受け止めたい意向を示すもの
スペインのHD・CAPD患者の死亡116例の分析では,30名(25.8%)が透析中止による死亡であり,・mentalincapacity・がその主因だという7).イギリスの75歳以上58例の解析によれば,透析中止による死亡は全死亡の38%であり,高齢者では高率である8).
透析非導入と透析継続中止国内外の現況と課題
大平整爾医療法人社団カレス アライアンス 日鋼記念病院腎センター(現,札幌北クリニック)
はじめに末期慢性腎不全患者は,医師から現症(腎機能の低下度および全身状態など)並びにその後の治療法の選択肢に関して説明を受ける.相当以前から定期的な受診を続けていた患者と然らざる患者とでは,①医師からの説明,②医師-患者間の質疑応答などを経て,③患者自身の納得と理解,④家族などの協力度合い,⑤医療者・家族の勇気付け,など様々な要因によって,医師の提示した治療法の受諾・非受諾(医師の立場からは導入・非導入)へ至る道程はかなり異なってくる.医師は自説を押し付けるのではなく,まず患者の言い分を傾聴することから始めなければならない.また,医師は患者との対話が開始された後,できる限り速やかに患者・家族から信頼感を得ることが肝要である.然らざれば,如何に公平な説明や情報の提供を行っても有効なものとはなり得ない.一方で一旦透析療法が開始されても,種々の合併症や加齢に伴う障害の出現などのためにその継続が困難か苦痛となり,透析継続の中止が患者・家族または医療側から考慮せざるを得ない状況が生まれてくる.これ等の事態は近年次第に増加し,医療者および受療者の関心度を深めている.本論ではこれにかかわる諸問題を概説したい.1現代医療の根幹医の倫理は,①自主性(autonomy),②無害性
(nonmaleficence),③慈愛(beneficence),④正義(justice)の4点にあるとされている.リスボン宣言はこれを受ける形で,患者の権利をより具体的に述べている(表1).これ等を要約すれば,現代医療の根幹は「患者の自己決定権の尊重」にあると言うことができよう.この故に,患者は医師から自らに関する医療情報の真実を包み隠さず提示されることを要求し得る権利を有し,医師にはそのように行うべき責務が課せられているものとなる.インフォームド・コンセント(IC)はま透析非導入と透析継続中止127透析非導入と透析継続中止国内外の現況と課題大平整爾医療法人社団カレス アライアンス 日鋼記念病院腎センター(現,札幌北クリニック)[透析医療におけるCurrentTopics2002]NoninitiationtoandWithdrawalfromDialysisTherapy~CurrentStatusandProblemsintheWorldandJapan~Kidneycenter,NikkoMemorialHospital(now,SapporoKitaClinic)SeijiOhira表1患者の権利に関するリスボン宣言1.患者は,自分の医師を自由に選ぶ権利を有する.(医師選択の自由)2.患者は,何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利を有する.(医師独立性・倫理性への期待権)3.患者は,十分な説明を受けたのちに,治療を受け入れるかまたは拒否する権利を有する.(提示医療計画への受諾と拒否権)4.患者は,自分の医師が患者に関するあらゆる医学的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する.(守秘義務への期待権)5.患者は,尊厳をもって死を迎える権利を有する.(尊厳死選択の権利)6.患者は,適当な宗教の聖職者の助けを含む精神的および道徳的慰めを受けるか,またはそれを断る権利を有する.(宗教的,道徳介入の受諾権と拒否権)〔1995年9月,第47回世界医師会(注:1981年宣言を改定)〕
ず医師が患者の言い分を傾聴した後に情報の提供と説明を加え,両者間で質疑応答がなされ,患者の理解と納得のうえで,患者自身が医師の提案に対して諾否を自己決定するというプロセスである.当然ながらこの過程は,あらゆる検査や治療の開始に際して欠かせない必要事項となる.2患者の自己決定権と医師の裁量(権)患者の自己決定権は,「エホバの証人輸血事件」で最高裁判決が示したように,憲法上保障された人格権の重要な一端をなすものであり,医師が道徳的・倫理的な心得えとして具備すべきもの以上に強い強制力を持って,医師にその順守を迫るものである.しかし,医師が患者の自己決定権を容認し患者の求める情報を提供するにしても,患者が理解不十分であったり逡巡を示したりして,患者の自己決定が常に円滑に進むものではない.あるいは,患者が意思を明確に表明したとしても,患者の決定が医療の専門家の立場からみて必ずしも妥当ではないと判断される状況が出現するものである.したがって,医師の都合・利益,傲慢や怠惰に根差す一方的な父権主義はむろん排除されなければならないが,医師が患者に対して共感と寄り添いを示しつつ指導的な協力あるいは協力的な指導は完全には排除されるべきではなかろう.つまり,「患者による自己決定」というプロセスには,患者と医師の共同作業の工程(shareddecisionmaking)が多くの場合に必要になると考える.このように考えを進めると,患者の自己決定権には一言で言い切ってしまえない複雑で微妙な側面が存在する.3透析非導入と透析継続中止の現況1) 透析非導入これに関しては,Hirschらの見解がしばしば引用されている(表2)1).表2の中で,2)~5)の項目のような状態では,透析を開始しても患者に望ましいQOLの向上が求め得ず,また,透析の実際の施行に著しい困難が伴うものであるために,積極的な透析導入を患者側に勧められないのは理解でき妥当な見解であろう.これに対して,項目1)と6)では見解の別れるところであろう.痴呆の透析患者導入は問題が多いが,原則的には患者の
事前指示(書)か代理人の判断に委ねられるものと考える.詳細は拙著2)3)を参照していただきたい.6)については,時にこのような患者に接するが,根気よい説明や薬剤などによって対処できる場合も少なくはなく,一概に否定的なことにはならないように思われる.さて,医学的に腎機能低下が顕著で透析導入が適応とされながら諸般の事情から非導入となる患者の数や比率に関しては,正確なデータに接していない.欧米では当該患者が腎疾患専門医を受診する前に家庭医がその判断をすることがあって,家庭医が言わば・gatekeeper・の役を果たしてしまう場合があると聞き及ぶ.同様な事情は日本でも有り得ることと推測される.家庭医または初診医と専門医相互の密な連絡が必要であろうと考える.北海道のアンケート調査3)(道内の12施設)によれば,1994-1998年の5年間に22例で透析非導入が決定されている.その理由を複数回答からみると,①悪性腫瘍末期14例(64%),②高度の痴呆15例(68%),③心筋梗塞などによるきわめて劣悪な循環動態11例(50%),④DIC9例(41%),⑤重度の心肺機能低下12例(55%)であり,非導入は医師と家族間で話し合われて決定されている.いずれの症例も著しく全身状態が不良で,透析療法を開始しても病態の好転とQOLの向上を望み得ないと判定されたものである.医療側からみて患者が判断力を有し,かつ,透析施行が可能な症例での非導入例は存在しなかった.医師が透析療法を適応と考えて患者に勧めて患者が強固に拒否する事例は必ずしも少なくはないが,このような
症例でもほとんど大半がその後医療側の説明・説得で透析導入が患者により受諾されるのが実態であると感じている.2)透析継続の中止アメリカでは透析中止が先行して死亡(with-drawalfromdialysisbeforedeath)に至る比率が近年20-25%に達して,死因の第2位または第3位を占めていると報告されている4).・deathbywith-drawalfromdialysis・(WD:透析中止による死亡)を既述のように・withdrawalfromdialysisbeforedeath・(死亡に先行した透析中止)とUSRDSが死因分類を変更したのは,透析中止による死亡を「生命の自然経過」と受け止めたい意向を示すものであろう3)5).さて,アメリカにおけるWDの比率には,地域格差が存在するごとくであり,Cohenら6)によるアメリカおよびカナダ8施設の調査ではWDに伴う死亡は全死亡の8-53%であるという.透析中止率は施設間格差のほかに人種間の差異も顕著であり,白人で81.5人/1,000patient-yearsであるのに対して,黒人では34.2人であった.スペインのHD・CAPD患者の死亡116例の分析では,30名(25.8%)が透析中止による死亡であり,・mentalincapacity・がその主因だという7).イギリスの75歳以上58例の解析によれば,透析中止による死亡は全死亡の38%であり,高齢者では高率である8).対象症例数,施設の特性さらに担当透析医の方針などによって,透析中止率には相当な相違が出てくるものと推測されるが,欧米では透析中止による死亡が決して稀な事象ではないとは言えよう.日本における透析継続中止の実態は,その詳細が未だ十分に把握されていない.日本透析医学会の統計調査委員会が毎年報告する資料によれば,2000年導入慢性透析患者の死因分類で「自殺/拒否」の項目をみると0.9%(25/2,641)とされている9).死因に占める「自殺/拒否」の比率は過去,ほぼ1%内外で大きな変動は見られていない.統計調査に現れにくい側面があろうと推測される.調査期間を1994-1998年の5ヵ年に限定して私共が行った北海道12施設のアンケート調査3)によれば,透析死亡患者のうち透析継続の中止による死亡率は1-2%であった.また,筆者が所属する日鋼記念病院で1996-2000年の5ヵ
年に死亡した139例の分析では,透析継続中止による死亡は3例(死亡時年齢:41歳,63歳,77歳)で透析中止死亡率は2.2%と算定された.わが国においてもより多数例の詳細な調査分析が必要であるが,透析継続の中止を選択して死に至る事例は,現時点では欧米に較べて著しく少ないとは言えそうである.4日本人のがん告知および延命治療に対する意識朝日新聞(平成12年10月23日版)が行った世論調査の結果によれば,がん告知を望む一般人は76%に達しているが,告知する立場の医師では「知らせるほうがよい」と答えた比率は53%であり,かなりの乖離が認められる.本人は「知らせてほしい」と高率でその意向を示しながら,それぞれの家族への告知に否定的な比率は46%に及んでいてここにも相当な差異が存在している.延命治療に関しても同様で,自分自身の延命治療を希望する人はわずかに17%,つまり70%超の人々は自らの延命治療を望まないとしながらも,家族への延命治療については40%超が希望するとしている.人それぞれの生死は専らその人自身にかかわり,したがってどの道を如何に進むかはその人自身の意向に従うべきものなのであるが,実際には一個人の生死はその人だけの事象として止まらず,周辺の人々を巻き込み大きな影響を与えるものと言わなければならない.がん告知や延命治療の可否に対する日本人の意識調査の結果にそれが如実に現れている.透析非導入や継続中止の決定にも当事者の意向を最大限に尊重する原則は曲げられまいが,決定の過程に幾度か居合わせた筆者自身の感想からは先の場合と同様に,当該者を囲む近親者の意向が大なり小なり影響するものだと実感している.5透析患者の心肺蘇生に対する受け止め方表記に対す大変興味深い日米の調査結果が,時を隔てずに報告された(表3).心肺蘇生(CPR)を要する状況はきわめて重篤な病態であるが,日本ではその時点での健康状態次第でCPRを希望するとする者が42%であるのに対して,アメリカでは透析(血液)中の心肺停止に対してCPRを希望する率が87%に達している.日本の透析患者が現時点の健康に不十分感・不満感・
不安感などを有しているらしいことが想像できる.これに対して,アメリカの透析患者が透析中の心肺停止に対して87%という高率でCPRを望むのは,生命に対する強い執着心からであろうか.Mossらはきわめて重篤な患者がCPRで次々に救命されるテレビドラマの影響をその理由の一つにあげて,実際の臨床の現場での厳しい成績を患者に教育する必要性を述べている.CPRに対して高率に期待感を表明するアメリカ人が,一方では先に見てきたように,わが国に較べて著しく高率に透析継続の中止を決定する一見相反する現象は,自己の生命の終焉に対して確固として自己主張を行うということを意味するのであろう.一方,日本の透析患者は,①痴呆・末期癌状態でCPR希望:12%,②痴呆状態での透析継続希望:18%,③末期癌状態での透析継続希望:45%,という意思を示しており,終末期状態での透析継続を望まない言わば生命に対して淡泊な態度とでも言うべき比率は相当に高率であるにもかかわらず,透析継続の中止が実際に決定・実行される事例は少なくとも統計に現れている範囲では低率である.概念として末期状態での生存を望まず否定しているが,実行に移し得ない決断力の欠如・世俗のしがらみなどの諸条件が隠されているからなのであろうか.心身の苦痛・苦悩がある程度以上排除可能であれば,末期状態であっても大多数の患者は生命の永らえることを望むのが人の性さがであろうと推測されるが,わが国の透析患者がそうした好ましい環境にいるからであろうか.あるいは,担当医と生命の行く末
を率直に話し合う機会を双方が回避しているためであろうか.数多くの不明な問題が残されているように感じている.6透析療法における共同による意思決定(RPA/ASN)RPA(RenalPhysiciansAssociation)並びにASN(AmericanSocietyofNephrology)が発表している表題に対するRecommendationSummary10)の一端を紹介したい.[勧告1]では,共同(医師と患者)の意思決定の重要性が説かれている.患者が意思決定能力を欠く場合には,法的な代理人が設定される.患者の同意がある場合には,共同の意思決定に家族・友人および腎疾患治療チームのメンバーが加わってよいとされ,患者自身の主体性が尊重されていることがうかがわれる.[勧告2]ではインフォームド・コンセントまたは拒否の内容が説明されている.担当医が患者に診断・予後および治療上の選択肢(実施可能な透析方法,透析を開始せず保存的療法を継続する場合の終末期ケア,期間を限定した透析の試行,透析の中止と終末期ケア)を説明することを義務としている.かなり具体的な勧告と言うべきであろう.「医師は,患者または法的代理人が意思決定のもたらす結果を理解していることを確認する必要がある」とする点は,当然ながら重要な視点であろう.[勧告4]は,医療チームと患者または法的代理人
との間に,意見不一致がある場合の解決策に触れている.「系統的な取り組み」を勧め,①予後についての不十分な意思疎通または誤解,②個人的または対人的見解の揺れ,③価値観の相違など,を調整するべきとしているが具体性に欠けており,実際には最も難しい側面であろう.「透析が緊急を要する状況下では,意見相違の解決を探りながら,もし患者または法的代理人が透析を求めるのであれば,透析を開始しなければならない」と勧告しているのは,アメリカの医師が一定の状態の患者に対して透析開始を相当に強い態度で勧めない状況があるためであろう.[勧告5]では,医療チームが患者から事前指示(書)を得るべく努力するように説いている.[勧告6]が透析の非導入または透析の中止(with-holdingorwithdrawal)に関する勧告である(表4)10).全体的に患者の自己決定権を尊重する妥当な記述であるが,患者の選択が逡巡,恐怖感や誤解などによって医療者側からみて必ずしも適正ではない場合に,どの程度,医療者側が患者の決定に干渉すべきなのかに難しさがあろう.本勧告の「1」では・shareddecision-making・が謳われており,患者の言い分をそのまま受諾することが常には正しくはないと考えるが,節度ある干渉でなければならないであろう.[勧告7]では特殊な患者群に言及し,「非腎疾患を原因とする終末期状態または医学的な理由から透析の技術的な施行が不可能な急性・慢性腎疾患患者では,透析の非導入または透析継続の中止を考慮することが適切である」と述べている.[勧告8]では,透析を必要とするが予後が不確実で透析開始について関係者間でコンセンサスに達していない患者にあっては,期間限定の透析試行(time-limitedtrial)の検討を勧めている.最後の[勧告9]は,緩和ケア(palliativecare)に関する項目である.非導入または継続中止を選択した患者自身およびその家族への種々のケアが,引き続き行われるべきだとする勧告である.終末期または緩和ケアと言っても,癌腫・脳出血・心筋梗塞など様々なケースがあって一括することは難しい.透析患者の場合,透析継続の中止後,大多数の患者が10日前後で死に至る.したがって,透析患者の終末期ケアは非導入または継続中止の時点から始まるのではなく,それに先行する必要性が大きい.以上,概観してきたRPA/ASNの勧告は大原則としてよく論議が尽くされた提案だと言えようが,個々の事例に遭遇してこの原則をどのように具体的に演繹していくかは,必ずしも容易ではないと考えられる.7透析非導入並びに透析継続の中止が選択されたことに対する事後評価患者が透析という高度に人為的な手段を回避または中止して自然経過として死に至った個々の事例は,適正な尺度で評価されることが望ましい.亡くなった当の本人から評価を得ることはできず推測の域を脱しないが,Cohenら11)は・deathasgoodorbad・に幾つかの項目を掲げて点数化する方式を提案している.その詳細は原著11)か拙著3)を参照して頂きたいが,試みるに値するものである.一人の患者の死去の様々な意味の影響が家族・近親者に止まらず,それ等の人々の感情や仕草が移入または投影されて医療スタッフにも及ぶことを銘記しておきたい.8透析非導入または透析継続中止の手順医学的な見地からは必要と考えられる治療を開始しないか,これまで継続してきた治療を中止するかというような事態は医療が始まって以来,かなり卑近に存在してきたであろうと推測される.それがわが国で実際上どのように行われてきたかは不詳であるが,相当な部分がいわゆる「以心伝心」か「阿吽の呼吸」とい透析非導入と透析継続中止131表4透析の非導入または透析の中止(RPA/ASN0)10)―抜粋
うべき不明瞭な形での断行(善意ではあっても医師の独断)であった懸念が大きい.患者の自己決定権・個の尊厳を尊重する現代では,すでに馴染まない容認されない事態の運び方であろう.生死を分かつ状況下での医師-患者・家族との話し合いはなかなか率直にはいかず,日頃から患者・家族との対話を厭わずに根気よく続けることが肝要であり,医師たる者はすべからく一定レベル以上のコミュニケーション・スキルを身に付けることが求められよう.図1は腎疾患々者に対して,透析導入が医学的に判断される第一段階から様々な過程を経てその患者が死亡に至るまでのフローチャートである.ここに記したすべての段階で,医師・患者間で良好な意思疎通があるよ
うに臨床医は心掛けたいものである.9終末期透析患者が望むもの透析の非導入,透析の継続中止いずれもその決定に関与することは,医療者にとってpainfulかつtrau-maticな難行である.患者がハイテクノロジーによる延命よりも死を選択するという事態は医療者にとってはショックな出来事であり,医療人はこれを自らの医療行為への屈辱・侮辱と受け止め,敗北感を募らせがちである5).患者がこれ等の選択を決断する諸要因を可能な限り探り排除しようとすることが,医療チームに課せられた第一義的責務であろう(表5).しかし,ひとの命と現在の
医療に限りがあることは認めざるを得ず,したがって,非導入・継続中止という実態を100%回避することは不可能であろう.そして,その決断は現代医療の敗北では決してないと考えられる.さて,透析患者殊にこの人々が終末期に至ってなにを最も求め,なにを最も重要な事柄としているかを医療者が知ることは,きわめて重要であろう.ここでは,Steinhauserら12)が末期癌患者・家族・医療関係者を中心にこの問題を分析しているので紹介し,参考に供したい.患者が重要だとして掲げた事項を重要度順に列記すると以下のごとくであった.① 疼痛からの解放② 神と共にある安寧(atpeacewithGod)③ 家族の存在④ 鮮明な意識⑤ 治療の選択権⑥ 良好な経済状態⑦ 生命・生活の有意義感(feellifewasmean-ingful)⑧ 心的葛藤の帰着⑨ 自宅での死亡一方,患者を看取った家族ではその順序が①②③⑤④⑦⑥⑧⑨のようであった.これが医師では,①③②⑦⑤⑧④⑥⑨となっている.重要度上位3つに大き
な差異はなく三者の認識が一致している.医師が「生命・生活の有意義感」を第4位に掲げているのに対して,患者自身はこれを第7位に掲げているなど,微妙なしかし恐らくきわめて重要だと思われる食い違いが認められる.ここには現れていないが,Steinhauserらは,末期癌患者が大いに気に掛ける点に,家族および社会への負担(burden)があるとしている.患者が望み重要としている事項の認識には立場による違いが大きく,かつ,同一グループでも個人差が無視できないことを知っておきたい.表5は医療者の立場から憶測した筆者の個人的な見解に基づく「透析継続中止を決意する」諸要因であり,個々の患者に接した場合には,熟慮されなければならないと痛感している.先にアメリカの報告にみたように,透析非導入率や透析継続中止率には施設間格差が大きく,それぞれの施設の特性や治療する患者の特性(病態,重篤度・生命感・家族関係など)は,当然関係してくるであろう.その他に,担当医の属性(受けてきた教育・経験,生命感,価値観など)も大いにこの問題に関与すると考えられるのであり,医師に対する生命倫理領域の教育・習練や事例分析などを今後,強化することを考えなければならないであろう.おわりに治療の非開始,一旦開始した治療の中止は,患者自身が決定する専任事項なのであるが,医療者は医療の最終の仕上げとして関与せざるを得ない重要な案件と認識する必要がある.
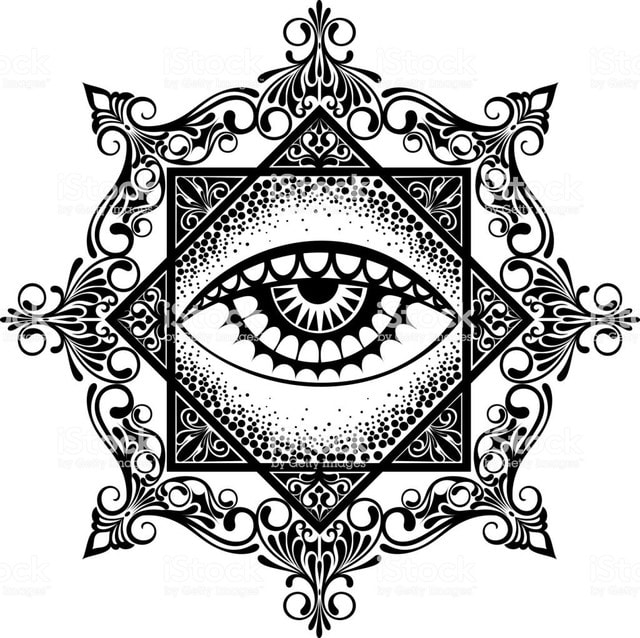
欧米では透析中止による死亡が決して稀な事象ではないとは言えよう.透析継続の中止アメリカでは透析中止が先行して死亡(with-drawalfromdialysisbeforedeath)に至る比率が近年20-25%に達して,死因の第2位または第3位を占めていると報告されている4).透析中止による死亡を「生命の自然経過」と受け止めたい意向を示すもの
スペインのHD・CAPD患者の死亡116例の分析では,30名(25.8%)が透析中止による死亡であり,・mentalincapacity・がその主因だという7).イギリスの75歳以上58例の解析によれば,透析中止による死亡は全死亡の38%であり,高齢者では高率である8).
透析非導入と透析継続中止国内外の現況と課題
大平整爾医療法人社団カレス アライアンス 日鋼記念病院腎センター(現,札幌北クリニック)
はじめに末期慢性腎不全患者は,医師から現症(腎機能の低下度および全身状態など)並びにその後の治療法の選択肢に関して説明を受ける.相当以前から定期的な受診を続けていた患者と然らざる患者とでは,①医師からの説明,②医師-患者間の質疑応答などを経て,③患者自身の納得と理解,④家族などの協力度合い,⑤医療者・家族の勇気付け,など様々な要因によって,医師の提示した治療法の受諾・非受諾(医師の立場からは導入・非導入)へ至る道程はかなり異なってくる.医師は自説を押し付けるのではなく,まず患者の言い分を傾聴することから始めなければならない.また,医師は患者との対話が開始された後,できる限り速やかに患者・家族から信頼感を得ることが肝要である.然らざれば,如何に公平な説明や情報の提供を行っても有効なものとはなり得ない.一方で一旦透析療法が開始されても,種々の合併症や加齢に伴う障害の出現などのためにその継続が困難か苦痛となり,透析継続の中止が患者・家族または医療側から考慮せざるを得ない状況が生まれてくる.これ等の事態は近年次第に増加し,医療者および受療者の関心度を深めている.本論ではこれにかかわる諸問題を概説したい.1現代医療の根幹医の倫理は,①自主性(autonomy),②無害性
(nonmaleficence),③慈愛(beneficence),④正義(justice)の4点にあるとされている.リスボン宣言はこれを受ける形で,患者の権利をより具体的に述べている(表1).これ等を要約すれば,現代医療の根幹は「患者の自己決定権の尊重」にあると言うことができよう.この故に,患者は医師から自らに関する医療情報の真実を包み隠さず提示されることを要求し得る権利を有し,医師にはそのように行うべき責務が課せられているものとなる.インフォームド・コンセント(IC)はま透析非導入と透析継続中止127透析非導入と透析継続中止国内外の現況と課題大平整爾医療法人社団カレス アライアンス 日鋼記念病院腎センター(現,札幌北クリニック)[透析医療におけるCurrentTopics2002]NoninitiationtoandWithdrawalfromDialysisTherapy~CurrentStatusandProblemsintheWorldandJapan~Kidneycenter,NikkoMemorialHospital(now,SapporoKitaClinic)SeijiOhira表1患者の権利に関するリスボン宣言1.患者は,自分の医師を自由に選ぶ権利を有する.(医師選択の自由)2.患者は,何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利を有する.(医師独立性・倫理性への期待権)3.患者は,十分な説明を受けたのちに,治療を受け入れるかまたは拒否する権利を有する.(提示医療計画への受諾と拒否権)4.患者は,自分の医師が患者に関するあらゆる医学的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する.(守秘義務への期待権)5.患者は,尊厳をもって死を迎える権利を有する.(尊厳死選択の権利)6.患者は,適当な宗教の聖職者の助けを含む精神的および道徳的慰めを受けるか,またはそれを断る権利を有する.(宗教的,道徳介入の受諾権と拒否権)〔1995年9月,第47回世界医師会(注:1981年宣言を改定)〕
ず医師が患者の言い分を傾聴した後に情報の提供と説明を加え,両者間で質疑応答がなされ,患者の理解と納得のうえで,患者自身が医師の提案に対して諾否を自己決定するというプロセスである.当然ながらこの過程は,あらゆる検査や治療の開始に際して欠かせない必要事項となる.2患者の自己決定権と医師の裁量(権)患者の自己決定権は,「エホバの証人輸血事件」で最高裁判決が示したように,憲法上保障された人格権の重要な一端をなすものであり,医師が道徳的・倫理的な心得えとして具備すべきもの以上に強い強制力を持って,医師にその順守を迫るものである.しかし,医師が患者の自己決定権を容認し患者の求める情報を提供するにしても,患者が理解不十分であったり逡巡を示したりして,患者の自己決定が常に円滑に進むものではない.あるいは,患者が意思を明確に表明したとしても,患者の決定が医療の専門家の立場からみて必ずしも妥当ではないと判断される状況が出現するものである.したがって,医師の都合・利益,傲慢や怠惰に根差す一方的な父権主義はむろん排除されなければならないが,医師が患者に対して共感と寄り添いを示しつつ指導的な協力あるいは協力的な指導は完全には排除されるべきではなかろう.つまり,「患者による自己決定」というプロセスには,患者と医師の共同作業の工程(shareddecisionmaking)が多くの場合に必要になると考える.このように考えを進めると,患者の自己決定権には一言で言い切ってしまえない複雑で微妙な側面が存在する.3透析非導入と透析継続中止の現況1) 透析非導入これに関しては,Hirschらの見解がしばしば引用されている(表2)1).表2の中で,2)~5)の項目のような状態では,透析を開始しても患者に望ましいQOLの向上が求め得ず,また,透析の実際の施行に著しい困難が伴うものであるために,積極的な透析導入を患者側に勧められないのは理解でき妥当な見解であろう.これに対して,項目1)と6)では見解の別れるところであろう.痴呆の透析患者導入は問題が多いが,原則的には患者の
事前指示(書)か代理人の判断に委ねられるものと考える.詳細は拙著2)3)を参照していただきたい.6)については,時にこのような患者に接するが,根気よい説明や薬剤などによって対処できる場合も少なくはなく,一概に否定的なことにはならないように思われる.さて,医学的に腎機能低下が顕著で透析導入が適応とされながら諸般の事情から非導入となる患者の数や比率に関しては,正確なデータに接していない.欧米では当該患者が腎疾患専門医を受診する前に家庭医がその判断をすることがあって,家庭医が言わば・gatekeeper・の役を果たしてしまう場合があると聞き及ぶ.同様な事情は日本でも有り得ることと推測される.家庭医または初診医と専門医相互の密な連絡が必要であろうと考える.北海道のアンケート調査3)(道内の12施設)によれば,1994-1998年の5年間に22例で透析非導入が決定されている.その理由を複数回答からみると,①悪性腫瘍末期14例(64%),②高度の痴呆15例(68%),③心筋梗塞などによるきわめて劣悪な循環動態11例(50%),④DIC9例(41%),⑤重度の心肺機能低下12例(55%)であり,非導入は医師と家族間で話し合われて決定されている.いずれの症例も著しく全身状態が不良で,透析療法を開始しても病態の好転とQOLの向上を望み得ないと判定されたものである.医療側からみて患者が判断力を有し,かつ,透析施行が可能な症例での非導入例は存在しなかった.医師が透析療法を適応と考えて患者に勧めて患者が強固に拒否する事例は必ずしも少なくはないが,このような
症例でもほとんど大半がその後医療側の説明・説得で透析導入が患者により受諾されるのが実態であると感じている.2)透析継続の中止アメリカでは透析中止が先行して死亡(with-drawalfromdialysisbeforedeath)に至る比率が近年20-25%に達して,死因の第2位または第3位を占めていると報告されている4).・deathbywith-drawalfromdialysis・(WD:透析中止による死亡)を既述のように・withdrawalfromdialysisbeforedeath・(死亡に先行した透析中止)とUSRDSが死因分類を変更したのは,透析中止による死亡を「生命の自然経過」と受け止めたい意向を示すものであろう3)5).さて,アメリカにおけるWDの比率には,地域格差が存在するごとくであり,Cohenら6)によるアメリカおよびカナダ8施設の調査ではWDに伴う死亡は全死亡の8-53%であるという.透析中止率は施設間格差のほかに人種間の差異も顕著であり,白人で81.5人/1,000patient-yearsであるのに対して,黒人では34.2人であった.スペインのHD・CAPD患者の死亡116例の分析では,30名(25.8%)が透析中止による死亡であり,・mentalincapacity・がその主因だという7).イギリスの75歳以上58例の解析によれば,透析中止による死亡は全死亡の38%であり,高齢者では高率である8).対象症例数,施設の特性さらに担当透析医の方針などによって,透析中止率には相当な相違が出てくるものと推測されるが,欧米では透析中止による死亡が決して稀な事象ではないとは言えよう.日本における透析継続中止の実態は,その詳細が未だ十分に把握されていない.日本透析医学会の統計調査委員会が毎年報告する資料によれば,2000年導入慢性透析患者の死因分類で「自殺/拒否」の項目をみると0.9%(25/2,641)とされている9).死因に占める「自殺/拒否」の比率は過去,ほぼ1%内外で大きな変動は見られていない.統計調査に現れにくい側面があろうと推測される.調査期間を1994-1998年の5ヵ年に限定して私共が行った北海道12施設のアンケート調査3)によれば,透析死亡患者のうち透析継続の中止による死亡率は1-2%であった.また,筆者が所属する日鋼記念病院で1996-2000年の5ヵ
年に死亡した139例の分析では,透析継続中止による死亡は3例(死亡時年齢:41歳,63歳,77歳)で透析中止死亡率は2.2%と算定された.わが国においてもより多数例の詳細な調査分析が必要であるが,透析継続の中止を選択して死に至る事例は,現時点では欧米に較べて著しく少ないとは言えそうである.4日本人のがん告知および延命治療に対する意識朝日新聞(平成12年10月23日版)が行った世論調査の結果によれば,がん告知を望む一般人は76%に達しているが,告知する立場の医師では「知らせるほうがよい」と答えた比率は53%であり,かなりの乖離が認められる.本人は「知らせてほしい」と高率でその意向を示しながら,それぞれの家族への告知に否定的な比率は46%に及んでいてここにも相当な差異が存在している.延命治療に関しても同様で,自分自身の延命治療を希望する人はわずかに17%,つまり70%超の人々は自らの延命治療を望まないとしながらも,家族への延命治療については40%超が希望するとしている.人それぞれの生死は専らその人自身にかかわり,したがってどの道を如何に進むかはその人自身の意向に従うべきものなのであるが,実際には一個人の生死はその人だけの事象として止まらず,周辺の人々を巻き込み大きな影響を与えるものと言わなければならない.がん告知や延命治療の可否に対する日本人の意識調査の結果にそれが如実に現れている.透析非導入や継続中止の決定にも当事者の意向を最大限に尊重する原則は曲げられまいが,決定の過程に幾度か居合わせた筆者自身の感想からは先の場合と同様に,当該者を囲む近親者の意向が大なり小なり影響するものだと実感している.5透析患者の心肺蘇生に対する受け止め方表記に対す大変興味深い日米の調査結果が,時を隔てずに報告された(表3).心肺蘇生(CPR)を要する状況はきわめて重篤な病態であるが,日本ではその時点での健康状態次第でCPRを希望するとする者が42%であるのに対して,アメリカでは透析(血液)中の心肺停止に対してCPRを希望する率が87%に達している.日本の透析患者が現時点の健康に不十分感・不満感・
不安感などを有しているらしいことが想像できる.これに対して,アメリカの透析患者が透析中の心肺停止に対して87%という高率でCPRを望むのは,生命に対する強い執着心からであろうか.Mossらはきわめて重篤な患者がCPRで次々に救命されるテレビドラマの影響をその理由の一つにあげて,実際の臨床の現場での厳しい成績を患者に教育する必要性を述べている.CPRに対して高率に期待感を表明するアメリカ人が,一方では先に見てきたように,わが国に較べて著しく高率に透析継続の中止を決定する一見相反する現象は,自己の生命の終焉に対して確固として自己主張を行うということを意味するのであろう.一方,日本の透析患者は,①痴呆・末期癌状態でCPR希望:12%,②痴呆状態での透析継続希望:18%,③末期癌状態での透析継続希望:45%,という意思を示しており,終末期状態での透析継続を望まない言わば生命に対して淡泊な態度とでも言うべき比率は相当に高率であるにもかかわらず,透析継続の中止が実際に決定・実行される事例は少なくとも統計に現れている範囲では低率である.概念として末期状態での生存を望まず否定しているが,実行に移し得ない決断力の欠如・世俗のしがらみなどの諸条件が隠されているからなのであろうか.心身の苦痛・苦悩がある程度以上排除可能であれば,末期状態であっても大多数の患者は生命の永らえることを望むのが人の性さがであろうと推測されるが,わが国の透析患者がそうした好ましい環境にいるからであろうか.あるいは,担当医と生命の行く末
を率直に話し合う機会を双方が回避しているためであろうか.数多くの不明な問題が残されているように感じている.6透析療法における共同による意思決定(RPA/ASN)RPA(RenalPhysiciansAssociation)並びにASN(AmericanSocietyofNephrology)が発表している表題に対するRecommendationSummary10)の一端を紹介したい.[勧告1]では,共同(医師と患者)の意思決定の重要性が説かれている.患者が意思決定能力を欠く場合には,法的な代理人が設定される.患者の同意がある場合には,共同の意思決定に家族・友人および腎疾患治療チームのメンバーが加わってよいとされ,患者自身の主体性が尊重されていることがうかがわれる.[勧告2]ではインフォームド・コンセントまたは拒否の内容が説明されている.担当医が患者に診断・予後および治療上の選択肢(実施可能な透析方法,透析を開始せず保存的療法を継続する場合の終末期ケア,期間を限定した透析の試行,透析の中止と終末期ケア)を説明することを義務としている.かなり具体的な勧告と言うべきであろう.「医師は,患者または法的代理人が意思決定のもたらす結果を理解していることを確認する必要がある」とする点は,当然ながら重要な視点であろう.[勧告4]は,医療チームと患者または法的代理人
との間に,意見不一致がある場合の解決策に触れている.「系統的な取り組み」を勧め,①予後についての不十分な意思疎通または誤解,②個人的または対人的見解の揺れ,③価値観の相違など,を調整するべきとしているが具体性に欠けており,実際には最も難しい側面であろう.「透析が緊急を要する状況下では,意見相違の解決を探りながら,もし患者または法的代理人が透析を求めるのであれば,透析を開始しなければならない」と勧告しているのは,アメリカの医師が一定の状態の患者に対して透析開始を相当に強い態度で勧めない状況があるためであろう.[勧告5]では,医療チームが患者から事前指示(書)を得るべく努力するように説いている.[勧告6]が透析の非導入または透析の中止(with-holdingorwithdrawal)に関する勧告である(表4)10).全体的に患者の自己決定権を尊重する妥当な記述であるが,患者の選択が逡巡,恐怖感や誤解などによって医療者側からみて必ずしも適正ではない場合に,どの程度,医療者側が患者の決定に干渉すべきなのかに難しさがあろう.本勧告の「1」では・shareddecision-making・が謳われており,患者の言い分をそのまま受諾することが常には正しくはないと考えるが,節度ある干渉でなければならないであろう.[勧告7]では特殊な患者群に言及し,「非腎疾患を原因とする終末期状態または医学的な理由から透析の技術的な施行が不可能な急性・慢性腎疾患患者では,透析の非導入または透析継続の中止を考慮することが適切である」と述べている.[勧告8]では,透析を必要とするが予後が不確実で透析開始について関係者間でコンセンサスに達していない患者にあっては,期間限定の透析試行(time-limitedtrial)の検討を勧めている.最後の[勧告9]は,緩和ケア(palliativecare)に関する項目である.非導入または継続中止を選択した患者自身およびその家族への種々のケアが,引き続き行われるべきだとする勧告である.終末期または緩和ケアと言っても,癌腫・脳出血・心筋梗塞など様々なケースがあって一括することは難しい.透析患者の場合,透析継続の中止後,大多数の患者が10日前後で死に至る.したがって,透析患者の終末期ケアは非導入または継続中止の時点から始まるのではなく,それに先行する必要性が大きい.以上,概観してきたRPA/ASNの勧告は大原則としてよく論議が尽くされた提案だと言えようが,個々の事例に遭遇してこの原則をどのように具体的に演繹していくかは,必ずしも容易ではないと考えられる.7透析非導入並びに透析継続の中止が選択されたことに対する事後評価患者が透析という高度に人為的な手段を回避または中止して自然経過として死に至った個々の事例は,適正な尺度で評価されることが望ましい.亡くなった当の本人から評価を得ることはできず推測の域を脱しないが,Cohenら11)は・deathasgoodorbad・に幾つかの項目を掲げて点数化する方式を提案している.その詳細は原著11)か拙著3)を参照して頂きたいが,試みるに値するものである.一人の患者の死去の様々な意味の影響が家族・近親者に止まらず,それ等の人々の感情や仕草が移入または投影されて医療スタッフにも及ぶことを銘記しておきたい.8透析非導入または透析継続中止の手順医学的な見地からは必要と考えられる治療を開始しないか,これまで継続してきた治療を中止するかというような事態は医療が始まって以来,かなり卑近に存在してきたであろうと推測される.それがわが国で実際上どのように行われてきたかは不詳であるが,相当な部分がいわゆる「以心伝心」か「阿吽の呼吸」とい透析非導入と透析継続中止131表4透析の非導入または透析の中止(RPA/ASN0)10)―抜粋
うべき不明瞭な形での断行(善意ではあっても医師の独断)であった懸念が大きい.患者の自己決定権・個の尊厳を尊重する現代では,すでに馴染まない容認されない事態の運び方であろう.生死を分かつ状況下での医師-患者・家族との話し合いはなかなか率直にはいかず,日頃から患者・家族との対話を厭わずに根気よく続けることが肝要であり,医師たる者はすべからく一定レベル以上のコミュニケーション・スキルを身に付けることが求められよう.図1は腎疾患々者に対して,透析導入が医学的に判断される第一段階から様々な過程を経てその患者が死亡に至るまでのフローチャートである.ここに記したすべての段階で,医師・患者間で良好な意思疎通があるよ
うに臨床医は心掛けたいものである.9終末期透析患者が望むもの透析の非導入,透析の継続中止いずれもその決定に関与することは,医療者にとってpainfulかつtrau-maticな難行である.患者がハイテクノロジーによる延命よりも死を選択するという事態は医療者にとってはショックな出来事であり,医療人はこれを自らの医療行為への屈辱・侮辱と受け止め,敗北感を募らせがちである5).患者がこれ等の選択を決断する諸要因を可能な限り探り排除しようとすることが,医療チームに課せられた第一義的責務であろう(表5).しかし,ひとの命と現在の
医療に限りがあることは認めざるを得ず,したがって,非導入・継続中止という実態を100%回避することは不可能であろう.そして,その決断は現代医療の敗北では決してないと考えられる.さて,透析患者殊にこの人々が終末期に至ってなにを最も求め,なにを最も重要な事柄としているかを医療者が知ることは,きわめて重要であろう.ここでは,Steinhauserら12)が末期癌患者・家族・医療関係者を中心にこの問題を分析しているので紹介し,参考に供したい.患者が重要だとして掲げた事項を重要度順に列記すると以下のごとくであった.① 疼痛からの解放② 神と共にある安寧(atpeacewithGod)③ 家族の存在④ 鮮明な意識⑤ 治療の選択権⑥ 良好な経済状態⑦ 生命・生活の有意義感(feellifewasmean-ingful)⑧ 心的葛藤の帰着⑨ 自宅での死亡一方,患者を看取った家族ではその順序が①②③⑤④⑦⑥⑧⑨のようであった.これが医師では,①③②⑦⑤⑧④⑥⑨となっている.重要度上位3つに大き
な差異はなく三者の認識が一致している.医師が「生命・生活の有意義感」を第4位に掲げているのに対して,患者自身はこれを第7位に掲げているなど,微妙なしかし恐らくきわめて重要だと思われる食い違いが認められる.ここには現れていないが,Steinhauserらは,末期癌患者が大いに気に掛ける点に,家族および社会への負担(burden)があるとしている.患者が望み重要としている事項の認識には立場による違いが大きく,かつ,同一グループでも個人差が無視できないことを知っておきたい.表5は医療者の立場から憶測した筆者の個人的な見解に基づく「透析継続中止を決意する」諸要因であり,個々の患者に接した場合には,熟慮されなければならないと痛感している.先にアメリカの報告にみたように,透析非導入率や透析継続中止率には施設間格差が大きく,それぞれの施設の特性や治療する患者の特性(病態,重篤度・生命感・家族関係など)は,当然関係してくるであろう.その他に,担当医の属性(受けてきた教育・経験,生命感,価値観など)も大いにこの問題に関与すると考えられるのであり,医師に対する生命倫理領域の教育・習練や事例分析などを今後,強化することを考えなければならないであろう.おわりに治療の非開始,一旦開始した治療の中止は,患者自身が決定する専任事項なのであるが,医療者は医療の最終の仕上げとして関与せざるを得ない重要な案件と認識する必要がある.