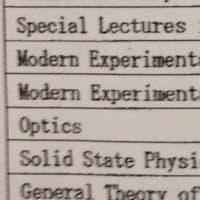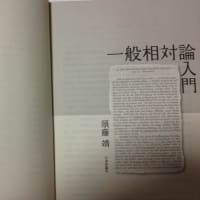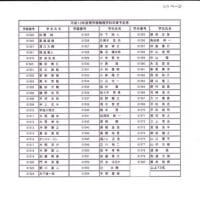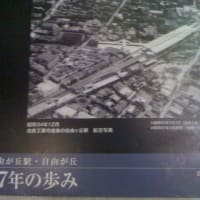ダイオードは整流するための電子部品。
p型からn型の一方向に電流を流すが、その逆には実質的には流さない。
この特性を積極的に使って、信号を検出したり、交流電圧から直流電圧をつくる。
前者の利用方法にはESD(静電破壊)から回路を保護する回路がよく知られている他、
有名ではないけど、ある閾値以上の電気信号を検出するディテクターや、ラジオなどの検波器に利用されている。後者はスイッチングレギュレーターやトランスフォーマーに利用されている。
積極的に利用していない場合も、CMOS素子のソースやドレインとバルクの間はpn接合になっているので、スイッチ方向の電流が貫通しないように、バルクの電位は素子の中で最も大きいか最も小さい電位に保たれて使用されている。
いつでもスイッチがオンするには、pn接続にp型側がn型側よりVbi(閾値)だけ電位が高くなる必要がある。
この電位は、p型とn型の真性半導体に対する電子のポテンシャルエネルギーの相対的な差で決まるので、
それぞれのタイプの半導体にインプラントしたpタイプとnタイプのそれぞれの不純物イオンの濃度によって決まるものである。
これら2つのタイプの半導体を接合させると、接合表面の電位が等しくなるまで、電子とホールが反対方向に移動する。そして、移動前のVbiの勾配分と正負逆の電界が打ち消されるまで移動し、
移動した後には電子がいた原子にはプラスのイオンが残り:これは、インプラしたドナー原子(P:りん、など)のイオン化したものであるから、このイオンの位置が検出できれば、ドナー電子のプロファイルがわかる・・・、一方ホールがいた原子にはマイナスのイオンが残る:こちらの位置は、Si結晶の各原子なので、どこの位置のものかは確定できないものである。アクセプタの原子に近傍のSi原子から補っていた電子は、このSi原子たちからは補う必要なく、nタイプ側から常に補われうる状態となっている。ドナーやアクセプタの価電子のエネルギーはSi原子の伝導体の最小のエネルギーに近い値で、常温で電子が容易に励起される。このとき、逆に価電子エネルギーまで落ちる(Pの原子起動に束縛される)確率もそんざいする。そうこうして結局は、励起されている電子やホールの数がキャリアとしての駆動力を決めている。
参考書の説明には、pn接合の平衡状態を説明するときに、
バランスするまでnからpへ電子が移動し、pからnへホールが移動するというけど・・・・
この後者はありうるのだろうか?n側にはどんどんプラスのイオンが残り、電子の移動速度も速い、一方ホールは相対的にプラスの電荷をもっているから、どうしてこんな空間に移動できるのだろうか?n側にホールが生まれるには、電子の不足する原子が必要だ。Pなどのドナーは電子がもともと多い構造だ・・・
それに、p側の領域に電子がn側からやってきたら、ホールはこの電子と対消滅するのが楽なはずじゃないだろうか??
空房層はこれらのプラスマイナスのイオンが残った領域である。
n側のイオンの総量と、p側にイオンの総量が等しくなるように、電界が形成されるのだが、
この積分がVbi:接合ポテンシャルである。
ホールが移動するのはとても考えにくいのだが・・・
どなたか実際を知っていたり、ご意見などあればコメントください!
どんな教科書も、たいていはホールがn側に移動するかのように書かれていますが・・・ホントなの?!
因みに、私がサイエンスを目指し、理学部に進学した理由のひとつは、
このようにしっかりと考えて理解し納得することがしたいからである。
が、ここからは、教科書の暗記情報を鵜呑みにするわけにはいけない・・・・
それでは、いくら勉強しても、本末転倒である!
p型からn型の一方向に電流を流すが、その逆には実質的には流さない。
この特性を積極的に使って、信号を検出したり、交流電圧から直流電圧をつくる。
前者の利用方法にはESD(静電破壊)から回路を保護する回路がよく知られている他、
有名ではないけど、ある閾値以上の電気信号を検出するディテクターや、ラジオなどの検波器に利用されている。後者はスイッチングレギュレーターやトランスフォーマーに利用されている。
積極的に利用していない場合も、CMOS素子のソースやドレインとバルクの間はpn接合になっているので、スイッチ方向の電流が貫通しないように、バルクの電位は素子の中で最も大きいか最も小さい電位に保たれて使用されている。
いつでもスイッチがオンするには、pn接続にp型側がn型側よりVbi(閾値)だけ電位が高くなる必要がある。
この電位は、p型とn型の真性半導体に対する電子のポテンシャルエネルギーの相対的な差で決まるので、
それぞれのタイプの半導体にインプラントしたpタイプとnタイプのそれぞれの不純物イオンの濃度によって決まるものである。
これら2つのタイプの半導体を接合させると、接合表面の電位が等しくなるまで、電子とホールが反対方向に移動する。そして、移動前のVbiの勾配分と正負逆の電界が打ち消されるまで移動し、
移動した後には電子がいた原子にはプラスのイオンが残り:これは、インプラしたドナー原子(P:りん、など)のイオン化したものであるから、このイオンの位置が検出できれば、ドナー電子のプロファイルがわかる・・・、一方ホールがいた原子にはマイナスのイオンが残る:こちらの位置は、Si結晶の各原子なので、どこの位置のものかは確定できないものである。アクセプタの原子に近傍のSi原子から補っていた電子は、このSi原子たちからは補う必要なく、nタイプ側から常に補われうる状態となっている。ドナーやアクセプタの価電子のエネルギーはSi原子の伝導体の最小のエネルギーに近い値で、常温で電子が容易に励起される。このとき、逆に価電子エネルギーまで落ちる(Pの原子起動に束縛される)確率もそんざいする。そうこうして結局は、励起されている電子やホールの数がキャリアとしての駆動力を決めている。
参考書の説明には、pn接合の平衡状態を説明するときに、
バランスするまでnからpへ電子が移動し、pからnへホールが移動するというけど・・・・
この後者はありうるのだろうか?n側にはどんどんプラスのイオンが残り、電子の移動速度も速い、一方ホールは相対的にプラスの電荷をもっているから、どうしてこんな空間に移動できるのだろうか?n側にホールが生まれるには、電子の不足する原子が必要だ。Pなどのドナーは電子がもともと多い構造だ・・・
それに、p側の領域に電子がn側からやってきたら、ホールはこの電子と対消滅するのが楽なはずじゃないだろうか??
空房層はこれらのプラスマイナスのイオンが残った領域である。
n側のイオンの総量と、p側にイオンの総量が等しくなるように、電界が形成されるのだが、
この積分がVbi:接合ポテンシャルである。
ホールが移動するのはとても考えにくいのだが・・・
どなたか実際を知っていたり、ご意見などあればコメントください!
どんな教科書も、たいていはホールがn側に移動するかのように書かれていますが・・・ホントなの?!

因みに、私がサイエンスを目指し、理学部に進学した理由のひとつは、
このようにしっかりと考えて理解し納得することがしたいからである。
が、ここからは、教科書の暗記情報を鵜呑みにするわけにはいけない・・・・
それでは、いくら勉強しても、本末転倒である!