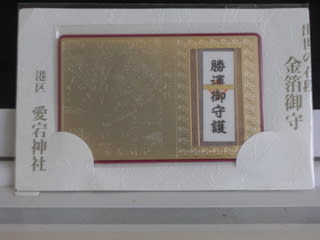国立新美術館
スペインのシュールレアリスムの画家、サルバドール・ダリの展覧会に足を運んだ。

写真や映像、金細工や彫琢を含めれば、250点にも及ぶ大回顧展。
過去最大級の規模である。
当日は連休の中日、しかも「高校生無料デー」という条件も手伝ってか、入場規制されるほどの盛況ぶりである。
初期の作品に、まったくダリらしさがないのに驚いた。
素人の、日曜画家程度の構図、画力のものもある。
ゴッホも初期はまったく作風が違っていた。
ピカソは14歳の頃に、子どもと思えないほどの、才気の萌芽が感じられる絵を描いていた。
画風が変化するのは珍しくない――というより普通は変遷を辿りゆくものだから、驚く話ではないのだが『常識的な』絵がやや意外だった。

<ラファエロ風の首をした自画像>
こちらは、ポスト印象派の影響を受けた筆致で、後年のダリの作風を予想させるものではない。
それ以外にも、点描を用いたスーラ風のものや、ピカソへの崇敬を思わせる絵など、試行錯誤し昇華していった痕跡がみとめられる。
会場が混雑しているのは、入場者が多いから、というだけではない。
ダリの絵は、メッセージ性が高く、謎が多く、主題が非常に複合的である。
芸術作品には「一目見て理解できるもの」「全く理解できないもの(或いは観覧者が理解を放棄したくなるもの)」がある。
後者は――例えば、キャンバスをカッターで引き裂いただけのものなど(私見である)。
ダリの絵は、そのどちらでもない。
後年の写実性の高い作風は、描きこまれているひとつひとつは理解しうるものであるのに、総合的に把握することは難しい。

<姿の見えない眠る人、馬、獅子>
この絵は、裸婦にも見えるが馬にも獅子にも見える物体が描きこまれている。
観覧者たちは、絵の前で一瞬戸惑いをおぼえる。
そこで説明文を読み、またその視線を絵に食い込ませ、ようやくひとつの解を得る。
それでも、彼のメッセージを完璧に理解してはいない。
もっと深淵なものが潜在する。
ひとつひとつの絵で、皆、逡巡をおぼえるため、どうしても列の進みは遅々となるのだ。

<ラファエロの聖母の最高速度>
これなども遠目では何を描いたか、判別しづらい。
今回の回顧展ではじめて知ったのは、ダリが「広島、長崎の原爆に大きな衝撃を受けていた」ということだ。
大きな災害により「自分の仕事に何の意味があるのか?」と創作意欲を失うクリエイターも多い。
「この現実を越えられるのか」と自問の末、身動きが取れなくなるのは、よくあることだ。
ダリが超人であるのは、その衝撃を己が作品に注ぎ込み、常に探求していたことである。

<ビキニの3つのスフィンクス>
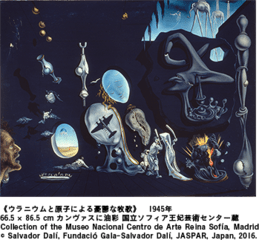
<ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌>
いずれも「原子力爆発」がテーマに据えられている。
精神分析や科学、相対性理論にまで踏み込み、絵画や映像等にもその天稟を発揮していく。
その世界観には、ただ圧倒されるばかりである。
セルバンテスは「プティングの味を知るには、それを食べるしかない」という名言をのこした。
ダリの世界を些少なりとも知りたいなら、その作品に触れるしかない。

にほんブログ村





























 出世の石段は足を止めることなく、一気に登る。
出世の石段は足を止めることなく、一気に登る。



 だから大丈夫でしょう!」と
だから大丈夫でしょう!」と