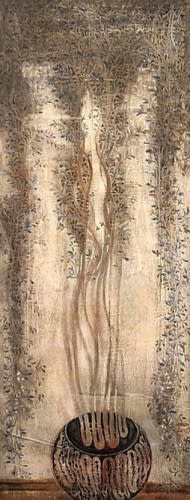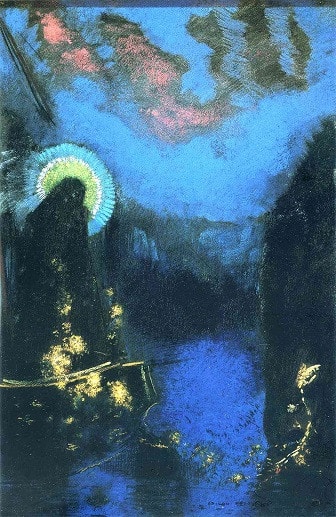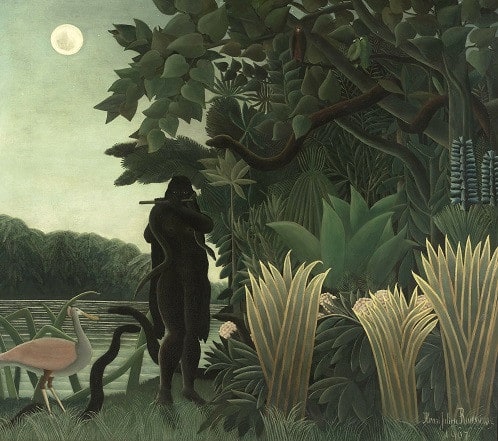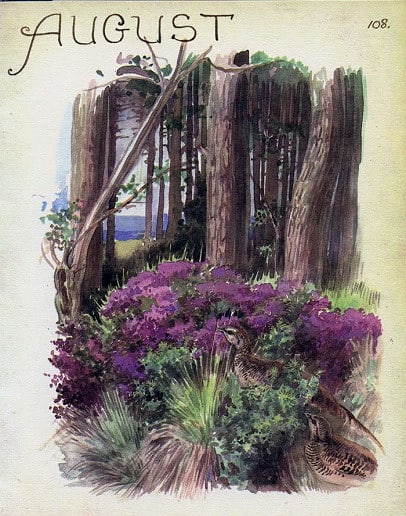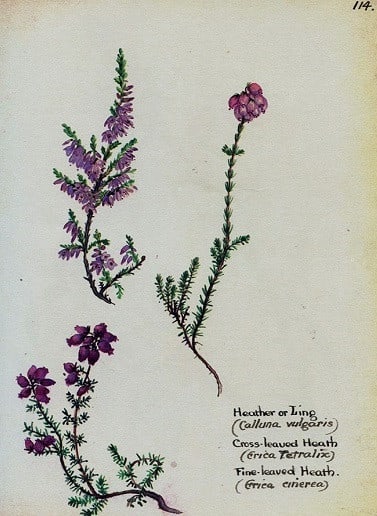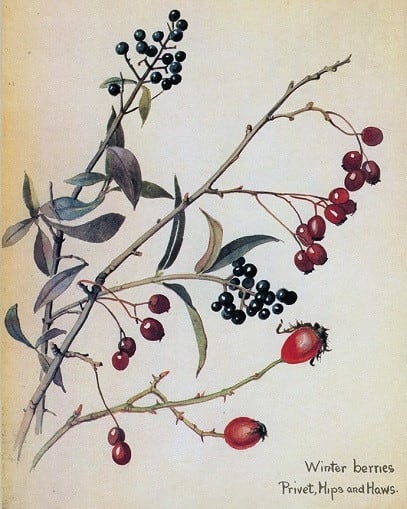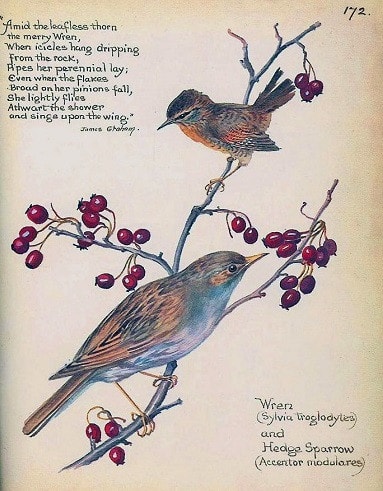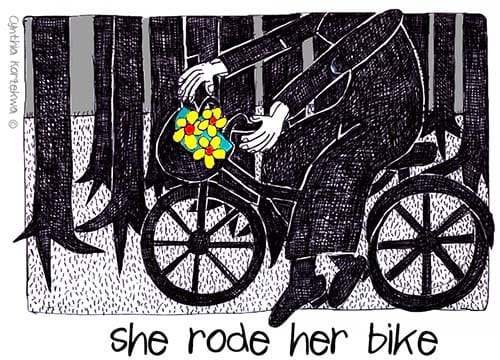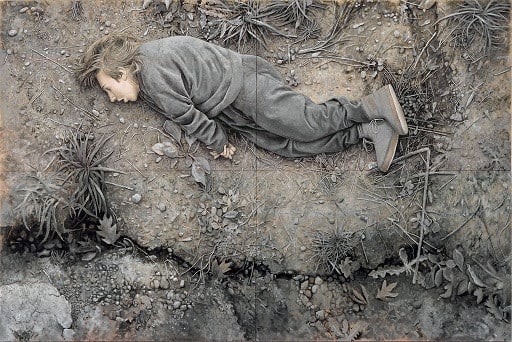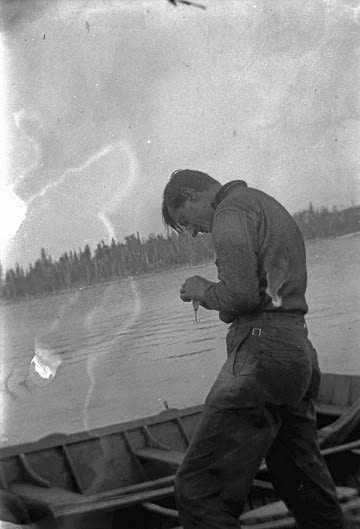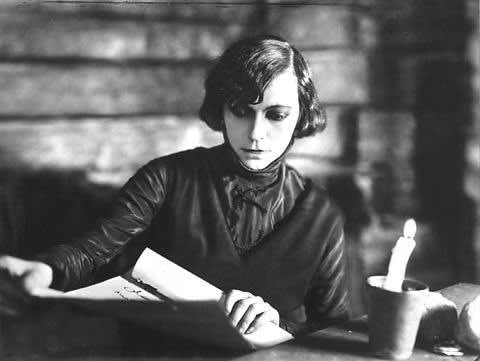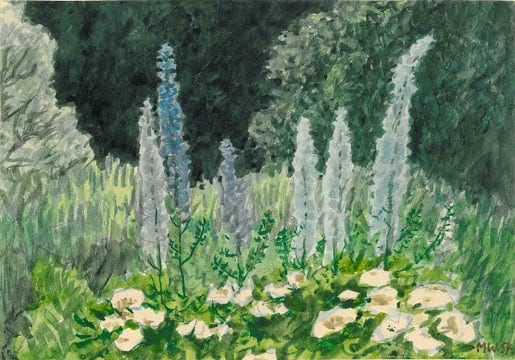Arvo Pärt - My Heart's in the Highlands ポール・ゴーギャン Paul Gauguin(1848-1903) ゲッセマネの園で祈るキリスト
ポール・ゴーギャン Paul Gauguin(1848-1903) ゲッセマネの園で祈るキリスト
Christ in the Garden of Olives(1889)油彩 Oil 73 x 92cm Norton Museum of Art
いつからか
内なるハリガネムシに突き動かされ
水へ飛び込まねばとふらつく
カマドウマを見るように
シモンペトロがユダを見ている
水
搖らめく光
溢れ温かく爽やかな
この世に轉び出る前の
樂園
邑からの帰り道いつも途中まで
ついて來る男の独り言めいた囁きを
耳の奧でもう一度聴いている
ユダは後頭部から一方の目へ
昏く明るく巻き上がりながら
透り貫けてゆく痺れるような空漠に
身を潜らせ続け
己が接吻する相手がナザレの
イエスとして連行されるなら
他の誰かにすればよい
何をしてもしなくても
次次神神の怒りを買い
窶(やつ)れ果てた若者は最期の
日日潭(ふち)の縁に凭(もた)れ水底から
搖らめき昇り來る己が面影
を待ち侘びたと云う
小さな黄に搖れる影
囁き亙る仄かな馨
月に小暗き翳差し
憧れに根差した汞(みずがね)の
樹が恨みの實を滴らす
同じ顔が蒼白く歪み浮腫んで
冷え冷えと石畳の床に反射する
灯明りに血溜りが搖れ
蕩けゆく唇に觸れた細く長き悲鳴が
頽れゆく三半規管にいつまでも木霊する
汞の仄かに煌き滑る樹膚に映る顔
が鎖した瞼の底から浮び上がって來る
ように主の頬に映る己に接吻する
のは目覚めれば跡形もなく憶えておらぬ
夢の中今宵夢の外で
十二人の内の誰かにせねばならぬ
先刻より胡散臭げに睨め付け
己だけが主を理解し守つている積りの
独り善がりの石頭にすれば
主は哀れまれ奇蹟を起こされる
かも知れぬ
己がためには起こされぬ
ゆえ人がため起こされる
よう御膳立てすれば
皆平伏する奇蹟を起こされ
主の天下となる
やも知れぬ
Sting - Desert Rose フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh(1853-1890)
フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh(1853-1890)
ひまわり Sunflower London National Gallery
シモンペトロの眸の後ろでは未だ時折
かつてと似た怒りの炎が搖らめき
重なり合って漣のように
皴の寄った水面に散り敷き
指を浸すように伝い降りて來る葉影に
吸い上げられて主の眼差しの傍らで
不意に退いてゆく
何故眞實は主の下に集うのか
集うのみにて何故主を守らぬか
何故主は愚かさを正し悪を退けぬか
愚かさは何故主を慕うあまり悪と化し
傷つけ打ちのめさんとするか
何故主は埋もれた夢や忘れられた眞實
眠れる願いや涸れた望みを引き出し
薄日差す凍える心に置いたまま
それが力を振り絞り咲かんとするを
信じ微笑み見守り励ますか
咲けぬものが打ち萎れ斃れ伏す時
その掌の中で甦り咲き誇れる幻を
猶も信じ勞り愛でるのか
主の袖を鷲掴み
シモンペトロはもどかしく
千切れ落ちる言の葉を接ぐ
吾と衣を取り換え吾が坐る巖に
坐られてくだされ今すぐ
今宵曇った眼に主が吾に
吾が主に映るよう
疑い虞るればそれは形を得
牽き出されよう闇の奧から
奔流となり灌ぎ込む
闇を見つめる眼差しの奧から
反射し殖え視野を覆い
膨れ上がり払い除けんとすれば
血塗れになるその血はすべて
吾が血
その目は澄んで微笑んでいる
ように見え
底知れぬ哀しみに満ちている
シモンペトロの埃塗れの脂ぎった頭巾を被り
シモンペトロの擦り切れ経たった草履を履き
シモンペトロの坐るごつごつした岩の傍らで
主は待っていた
赦し救うため
遙か昔や遠い未來の
見たことも聞いたことも會うことも
なき連綿と続く数限りなき人人を見晴かす
その目が闇の中近づくユダの目と耳と咽を貫き
明明と燃やす
木木を隔てる空隙だけが燃え
汞の鏡張りの木が炎に包まれ姿を顕す
誰にも見られず
己さえそこに在ると知らなかった
鏡張りの木が
光速で広がり進む主の眼差しの縁より浮び上がる
絶対零度の全てを止める焱に燃え
縺れ躓き倒れかかると
ユダは抱き止められた
虞るるな
相応しきときところ
全き眞の形で願いは叶う
命の限り担い支え命盡きても支え続けん
主の清らな頭巾を被り
主の小さな草履を履き
主が独り 張り裂ける胸を励ましながら歩んだ園の
誰にも聴こえぬ神の言の葉が戦ぐ木の間で
主の馨に慄き開き切ったシモンペトロの瞳孔に
ユダが頽れ主に支えられるのがぼんやり映った
霧に鎖された鍵穴から己の内を看るように
シモンペトロは赤黒く暗転する霧に額から突込む
節くれ立った手で引き攣り泳ぐように目の奧の霧を掻き毟り
払い除け主の御手からユダを削ぎ落さんと
轉がる巖のように走り
背後から從者の劍を抜き放ち
驚く從者の耳をシモンペトロは削ぎ落した
その耳が聴いたかも知れぬ
主の赦しを追い散らし飛び立たせようと
相応しき地へこの世にはなき空の彼方へ
KONGOS - Traveling on エル・グレコ El Greco(1541-1614)ゲッセマネの園で祈るキリスト
エル・グレコ El Greco(1541-1614)ゲッセマネの園で祈るキリスト
The Agony in the Garden 油彩画 Oil Toledo Museum of Art
目を鎖し立ち盡し
主の言われしまま三度
シモンペトロは主を知らぬと呟く
鷄が時をつくる前蒼き静寂の裡
吾は知らず吾は居らぬ居らぬ吾の
裡に御座す主を知らずいまここに
居るは主を裡に護る名無き抜け殻
主の命の炎だけを映し宿し
その温もりに涕し融け消ゆる
一足ごとに踏むと沈む
霜柱で出來た人が融けながら
二人に別れ夢の中のようにふらつき
互いに遠ざかるシモンとペトロの
透き通った影が棚引きながら
煙のように裂けて落された耳の形に蟠(わだかま)り
葉擦れと羽搏きの入り交じる
幽き音が木霊しつつ零れ出てゆく
全き空を明明と照らし出す閃く命の火
耀ける向日葵の日輪の黄金色
六価クロムに鼻から脳を灼き盡され
焼け野原に削ぎ落された耳だけが赦しを聴き
命の火は吸い出され灌がれて
燃え続けいつしか褪せゆく花びら一ひら一ひらの裡
Black - Wonderful Life 首を吊るユダ(ロマネスク時代)サン・ラザール大聖堂(オートン フランス)
首を吊るユダ(ロマネスク時代)サン・ラザール大聖堂(オートン フランス)
Judas hangs himself La cathédrale Saint-Lazare, Autun
眩く耀く谷を埋め盡くす向日葵
何處より來たりしか
背を向け歩み去り続けた己に
額から減り込んで想わず目を開くと
見たこともなき向日葵の花が
全天を覆う光の重く沈んで來る漲る焱を振り仰ぎ
六価クロムが音もなく果てしなく降り注ぎ
五感を抉りその澪で暗黒の哀しみの滴を沈ませる
何處までも落ち込む滴は光速の孔となり
命を無の彼方へと進め退ける
昏き紫の闇が大気を吸い上げ灰の匂いが漂う
昏いので見えぬ黄の花がどす黒く立ち枯れている
全てが独りの息を吸うことも吐くことも出來なくなった
項垂れた姿からフィボナッチの螺旋を巻き
死の谿を埋め尽くす灼熱のようでも極寒のようでもある
内から灼け焦げ干からびた虞と憎しみ
渇き涸れ枯れ果ててなお
花開かんと永劫の深き潭より首を擡(もた)げる
ユダの木
刺客たちがもうやって來る
敵からか味方からか
過去からか未來からか
怒りからか後悔からか
外からか内からか
两方から四方八方から
鏡張りの中心から空漠の果てから
全ての死角から
いつからか
遙か昔からそこに在る
絞め殺しの木
中心に聳え立っていた
大樹の幹の形の空洞を
いつまでも撫で摩り
吾身と抱き締め
つま先立ち浮き上がり裏返り
どこまでも
似て非なる姿を接ぎ矧ぎ仁王立ち
虞るるなと主は云われた
遙か昔
星星が舞ひ神が人に近くあらせられし時
人の心に果てしなき虞れと
神を真似ればいつしか神となり
人を虞れさせんとする憧れが芽生えた
神の力を以て世界を変え命を弄び
愚かな人人のためと称し
力を奮い人を制し支配せんとすれば
持ち堪えられず頽れ毀れ滅ぶ
主を神と人との子と信じ
神の心を想い人の力を盡し
持てるものを分ち互いに尊び助け
生きる
なら最期の時に顕れる内なる扉の
鍵となり死に瀕した手の中に
ユダは顕れその胸には燃え尽き
破れた心臓の形の鍵穴が開くかも知れぬ
自ら鍵差し回される度抉られながら闇となり
閾となり人として盡くされた全き命が
赦され変容するのを支える
いつかすべての命は変容し
鍵は鍵穴に差し回されたまま
人は生れ人は死に
失われし己を探して
足下に引き摺り踏み拉くのを已め
傷だらけの己を清め弔い
背中合せの己の半身と再び向い合い
一つに重なり眠る日が來るかも知れぬ
Levon Minassian - Bab'aziz Salvador Dalí Les atavismes du crépuscule (Phénomène obsessif) サルバドール・ダリ
Salvador Dalí Les atavismes du crépuscule (Phénomène obsessif) サルバドール・ダリ
D'après "L'Angélus" de Millet ca. 1933 Oil on wood 13.8×17.9cm Kunstmuseum Bern
ミレー《晩鐘》の悲劇的神話 (パラノイア的=批判的解釈) 1933頃 板・油彩 ベルン美術館
それは闘牛みたいな繪
殺された牛が二頭刺さったままの槍から
血を滴らせながら斃れた闘牛士の
小さな遺骸を悼んでいる
のではなくミレーの「晩鐘」で
項垂れた男女二人は埋葬したばかりの
死んだ赤ん坊を悼んでいる
とダリは想い描いた
ミレーの繪をX線で見ると二人の間の地面に
赤子の亡骸のように見えるものが描かれていて
上から土を掛ける如く地面が描かれ
塗り潰されているとダリは云う
男の頭から荷車に積んだ壜と袋が
血の流れる鍵になり虚空に棚引く
女の背に荷車の舵棒のように
その鍵の彷徨へる先端が刺さり
首を垂れ女は男の胸に空いた
鍵孔へ失われた子を戻さんとして叶はぬ
ASMR - Rainy Sound & Solfeggio 528Hz Csalogány(Luscinia megarhyncos) HAYASHI-NO-KO - ハリエンジュ
HAYASHI-NO-KO - ハリエンジュ
日差しが翳り花の影に一瞬
俯いた顔が廻って消える
永遠が一瞬に繰り返される
春の間亡き人を憶い甦らせる冬が來て
落ちゆく葉の下で鎖された水鏡の縁へ
顔を出す古き虞れと哀しみの聲なき木霊
くっきりと晴れやかに心から望めば
羊歯の葉がゆっくりと解けて蜥蜴になり
轉がる鍵穴になり鍵となって歩み入り
命から命を開く
虞れいきり立つ心が恕されて涕に融け
羽搏き昏き大地を覆い曉に和し歌うまで
待っている
ASMR - Binaural Sound Lhasa de Sela - Con Toda Palabra HAYASHI-NO-KO シダ
HAYASHI-NO-KO シダ



M.C.エッシャー Escher House of Stairs リトグラフ Lithograph Novembre 1951年11月



月明り 銀色に木が搖れる
木霊が息をのむように闇に吸い込まれ
痕が搖蕩(たゆた)う
オリーヴの園の闇に彷徨(さまよ)う視線の
仄かな明るさが満ち退く
御身を吾身に吾身を御身に
自らを吹き消し見失ったすべてを越え
曉へ回帰する闇の閾から滑り落ち
水孔から滴りユダとシモンペトロの涕が
凍って銀河を果てしなく遠ざかる
失われし永劫の道を帰るため
ユダの木が暗黒の道を点点と照らす
内側に人けなき空漠を抱えた鏡張りの幹が
燃えながら六価クロムの雨を涕する内から
燃えながら神の言の葉を聴かんと闇に沈んだ
黄の耳の花を咲かせているユダの木
 Potseluy Judah Merab Abramishvili მერაბ აბრამიშვილი(1957-2006)
Potseluy Judah Merab Abramishvili მერაბ აბრამიშვილი(1957-2006)
ユダの接吻 メラブ・アブラミシュヴィリ(16 March 1957 – 22 June 2006)