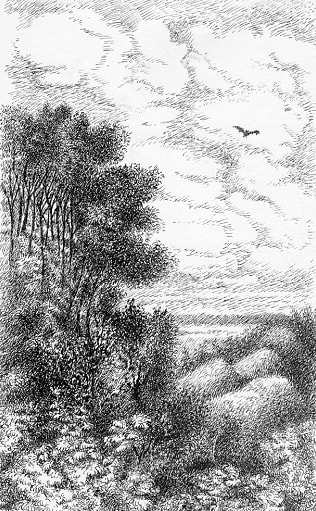窓際に窓を向いて一人ずつ坐る席がある
盆を手に並んでいるとき、空いているな、と想うが
いつも中程のテーブルに坐った
ときどき窓越しに遠くの山が見えた
ぼんやりと重なり合い、その上を
ゆるやかに流れ落ちていく空があった
昔、空は頭上の遙か高くで流れていた
雲や風が動いているのではなく
空がそれらを運び、澄んだ空が満ちてくると
遠くの山々までが、間近に運ばれてくるのだった
空席に腕をかけ、ぼんやり眼をひらいていると
昏くなったガラスに後頭部が映り、まばらな
木々の向こうに地平線が縮んでくるのがわかる
隅のほうで雲の柱が立ち昇る
そのかすかな振動を背後に感ずると
視線が波紋のように落ちていく
腹の底まで沈んでのび広がり
ひしゃげた網膜に水が溜まる
背後の視野
焦点を解くと、頭蓋骨までの間に空洞が広がる
昏く翳った山々の向こうに動かぬ雲が立ち昇り
よくみると、それはひび割れで、固くとじている
いつの頃からか空は動かなくなり
垂れ込めて空っぽになり
ひび割れた殻になった
縁まで水が溜まっている
視線が絡まり合い、枯葉のように沈んでいる
葉脈だけになった胡桃の葉
梯子のように降りていく
下のほうに殻が引っ掛かっている
古い夢の空洞だけを残して
飛行場のあまり使われていない端に
大きな胡桃の木があった
いまでは大きな切り株になっている
それでも毎年細い芽が生え
だれかが丹念にそれを折っていた
風の吹き荒ぶ滑走路を遠ざかっていくと
背後で大きな枝がざわざわと揺れ
堅い殻に包まれた実が柔らかな土の上に
ばらばらと降ってくるのが聴こえる
胡桃の木の下にいると頭痛がして
長くおれないそうだ
殻に包まれた小さな脳が
腹の底に沈んだ袋に呼びかける
胡桃の殻に浮かんでくる顔
かすかに笑っているような皴があって
目をとじている
背後には温かく木洩れ日が満ちて
透けた葉越しに高く空が流れている

落したことがあるだろうか
ばら色の柔らかな光が瞼を貫き
遠くの山々が、握り締めた手の下で
一瞬低くなる ふいに空が固く暗くなり
その下で明るく満ちていたものが
山々の向こうへ流れ出した
空を追って狂ったように飛び去っていく
銀色の腹の下で、太い雲の柱が次々と立ち昇る
握り締めた桿と砕けた歯よりもかたいものに
はね返された視線が、真っ暗にガラスに飛び散った
掌を見ると白く、へしゃげた豆が
薄い皮膚の下でいつまでも震えている
視線は指の間を遠ざかり、背後へと貫ける
遠くまで行けるけれども、背後には水溜りがある
遠くに山々があり、ふもとに木々が茂っている
そこへ行くためには水溜りを越えねばならぬ
それを広げずに、その上を飛ぶことはできなかった
空があった 遠ざかりながら澄みわたり
山々の向こうへあふれ去っていった空が
食堂でテレビを見ていたら
着膨れたアナウンサーの向こうで、ゆっくりと
枯れた芝生を動き回っている栗鼠がいた
身体が前へ跳ぶと、尾がふわりと追った
アグラで霧で飛べなかったことがある
米屋の前でトラックが止まったとき
群れていた雀が一瞬波のようにすべて飛び立ち
すぐにまた舞い降りた
遠ざかっていく砂埃と雀たちの羽搏きの間で
ふさふさと尾をのばして何匹も栗鼠がいた
栗鼠はなにかに驚いて逃げても、すぐに忘れて
また戻ってきて撃たれてしまうという
遠い声が呼びかける
記憶とは憶えていることではなく
忘れて初めて戻ってくることかもしれぬ
ふわふわした尾が背後を覆うと
山々が最初の星を戴いて冷たく頭上に聳え
芝の途切れたところからせせらぎが聴こえてくる
地面に落ちた小さな脳が呼びかける
ふわりと跳んでゆき、手に取る
冬になると枯葉も粉々になって土が冷たい
どこに埋めたのだったか
空っぽの蔭が呼びかける
もう空が星々の川を運んでくる
ふわりと栗鼠が跳ぶ
赤い肢裏がきらりと光り
かさかさと殻が落葉の土手を転がり落ちて
やがて芽を出す実は忘れられたまま
なかば土に埋もれ、まどろんでいる
 ふり返ると、テーブルの上に Randall Jarrell The Bat-Poet Pictures by Maurice Sendak
ふり返ると、テーブルの上に Randall Jarrell The Bat-Poet Pictures by Maurice Sendak
胡桃が一つ転がっている
音もなく
頭蓋骨の縫合を解くには、豆を使うのだそうだ
大豆を詰めてふやかす
頭という字の中にも豆がある
眼窩を覗き込んだら
押し合っている豆が見えるかもしれぬ
空洞でばらばらにふやけた夢が押し合うと
煙を上げて古いひび割れが動き出す
豆が出たら頭は砕け首だけになる
豆という字ももとは器の形だった
中身はどこへいったのか
栗鼠は落ちた大枝の上に坐り
一面に生えた芝が翳っていくのを見ていた
水から遠ざかりながら
皴の寄った顔を笑っているようにとざして
栗鼠がふわりと動くのを見た
ふわふわした大きな尾と、ふさふさと毛の生えた
耳がなければ、いたみの記憶で空が固くなる
高く流れる空の下で忘れた声に耳を傾ければ
頭上に見えない木が生い茂っていることに気づく
 硬い殻に包まれた実がめざめて
硬い殻に包まれた実がめざめて
太い幹がゆさゆさと伸びてゆく
目を上げてそこにふわりと戻ってくれば
撃たれても、空を見失うことはないだろう
廃棄された操縦席は固くひび割れた坐面から
埃のような綿がはみ出ていて冷たかった
坐って泥の被った窓を眺めた
足を動かすとつぶれたマッチ箱があり
かすかな匂いが背後に枯葉を敷きつめていった
かさかさと音がして、行ったり来たりしているものがいた
戻ってきてほしかった
歯を食い縛らず、桿から手を放して握り合わせると
掌に胡桃ができた
右の窓から靄を上げて緑の山の間を流れる川が見え
左の窓から一本の雲の柱が見えた
飛行機は枯葉の渦を撒きながら
柱に向かって一直線に飛んだ
そして、そこにささった
窓から這い出すと、それは太い幹で
柔らかく透明な中に
暁の光が小さな泡に包まれて昇っていた
遠くから風が吹いてきて、なにもかも忘れる
ずっと上まで昇っていくと
まぶしく照らされた記憶の鈴がなっている
風に鳴ると空が澄みわたり
山々が地平線から集まってくる
ふもとに林が広がっている
枯葉を跳んで、栗鼠がやってくる
黒い目に、硬い殻が映る
殻にも目があって
遙か高くで流れていく空が映っている
それから一緒に跳んでゆく
ふわふわした尾をゆっくりなびかせながら
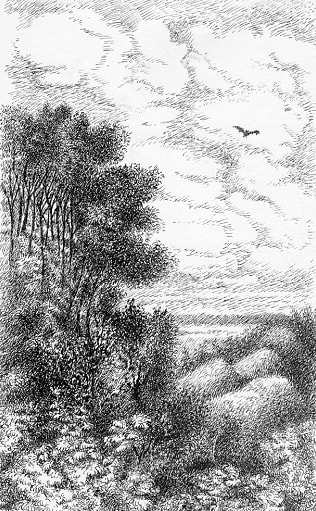

盆を手に並んでいるとき、空いているな、と想うが
いつも中程のテーブルに坐った
ときどき窓越しに遠くの山が見えた
ぼんやりと重なり合い、その上を
ゆるやかに流れ落ちていく空があった
昔、空は頭上の遙か高くで流れていた
雲や風が動いているのではなく
空がそれらを運び、澄んだ空が満ちてくると
遠くの山々までが、間近に運ばれてくるのだった
空席に腕をかけ、ぼんやり眼をひらいていると
昏くなったガラスに後頭部が映り、まばらな
木々の向こうに地平線が縮んでくるのがわかる
隅のほうで雲の柱が立ち昇る
そのかすかな振動を背後に感ずると
視線が波紋のように落ちていく
腹の底まで沈んでのび広がり
ひしゃげた網膜に水が溜まる
背後の視野
焦点を解くと、頭蓋骨までの間に空洞が広がる
昏く翳った山々の向こうに動かぬ雲が立ち昇り
よくみると、それはひび割れで、固くとじている
いつの頃からか空は動かなくなり
垂れ込めて空っぽになり
ひび割れた殻になった
縁まで水が溜まっている
視線が絡まり合い、枯葉のように沈んでいる
葉脈だけになった胡桃の葉
梯子のように降りていく
下のほうに殻が引っ掛かっている
古い夢の空洞だけを残して
飛行場のあまり使われていない端に
大きな胡桃の木があった
いまでは大きな切り株になっている
それでも毎年細い芽が生え
だれかが丹念にそれを折っていた
風の吹き荒ぶ滑走路を遠ざかっていくと
背後で大きな枝がざわざわと揺れ
堅い殻に包まれた実が柔らかな土の上に
ばらばらと降ってくるのが聴こえる
胡桃の木の下にいると頭痛がして
長くおれないそうだ
殻に包まれた小さな脳が
腹の底に沈んだ袋に呼びかける
胡桃の殻に浮かんでくる顔
かすかに笑っているような皴があって
目をとじている
背後には温かく木洩れ日が満ちて
透けた葉越しに高く空が流れている

川端 龍子 機 影
暁の空を飛んで、木々の上になにかを落したことがあるだろうか
ばら色の柔らかな光が瞼を貫き
遠くの山々が、握り締めた手の下で
一瞬低くなる ふいに空が固く暗くなり
その下で明るく満ちていたものが
山々の向こうへ流れ出した
空を追って狂ったように飛び去っていく
銀色の腹の下で、太い雲の柱が次々と立ち昇る
握り締めた桿と砕けた歯よりもかたいものに
はね返された視線が、真っ暗にガラスに飛び散った
掌を見ると白く、へしゃげた豆が
薄い皮膚の下でいつまでも震えている
視線は指の間を遠ざかり、背後へと貫ける
遠くまで行けるけれども、背後には水溜りがある
遠くに山々があり、ふもとに木々が茂っている
そこへ行くためには水溜りを越えねばならぬ
それを広げずに、その上を飛ぶことはできなかった
空があった 遠ざかりながら澄みわたり
山々の向こうへあふれ去っていった空が
食堂でテレビを見ていたら
着膨れたアナウンサーの向こうで、ゆっくりと
枯れた芝生を動き回っている栗鼠がいた
身体が前へ跳ぶと、尾がふわりと追った
アグラで霧で飛べなかったことがある
米屋の前でトラックが止まったとき
群れていた雀が一瞬波のようにすべて飛び立ち
すぐにまた舞い降りた
遠ざかっていく砂埃と雀たちの羽搏きの間で
ふさふさと尾をのばして何匹も栗鼠がいた
栗鼠はなにかに驚いて逃げても、すぐに忘れて
また戻ってきて撃たれてしまうという
遠い声が呼びかける
記憶とは憶えていることではなく
忘れて初めて戻ってくることかもしれぬ
ふわふわした尾が背後を覆うと
山々が最初の星を戴いて冷たく頭上に聳え
芝の途切れたところからせせらぎが聴こえてくる
地面に落ちた小さな脳が呼びかける
ふわりと跳んでゆき、手に取る
冬になると枯葉も粉々になって土が冷たい
どこに埋めたのだったか
空っぽの蔭が呼びかける
もう空が星々の川を運んでくる
ふわりと栗鼠が跳ぶ
赤い肢裏がきらりと光り
かさかさと殻が落葉の土手を転がり落ちて
やがて芽を出す実は忘れられたまま
なかば土に埋もれ、まどろんでいる

胡桃が一つ転がっている
音もなく
頭蓋骨の縫合を解くには、豆を使うのだそうだ
大豆を詰めてふやかす
頭という字の中にも豆がある
眼窩を覗き込んだら
押し合っている豆が見えるかもしれぬ
空洞でばらばらにふやけた夢が押し合うと
煙を上げて古いひび割れが動き出す
豆が出たら頭は砕け首だけになる
豆という字ももとは器の形だった
中身はどこへいったのか
栗鼠は落ちた大枝の上に坐り
一面に生えた芝が翳っていくのを見ていた
水から遠ざかりながら
皴の寄った顔を笑っているようにとざして
栗鼠がふわりと動くのを見た
ふわふわした大きな尾と、ふさふさと毛の生えた
耳がなければ、いたみの記憶で空が固くなる
高く流れる空の下で忘れた声に耳を傾ければ
頭上に見えない木が生い茂っていることに気づく

太い幹がゆさゆさと伸びてゆく
目を上げてそこにふわりと戻ってくれば
撃たれても、空を見失うことはないだろう
廃棄された操縦席は固くひび割れた坐面から
埃のような綿がはみ出ていて冷たかった
坐って泥の被った窓を眺めた
足を動かすとつぶれたマッチ箱があり
かすかな匂いが背後に枯葉を敷きつめていった
かさかさと音がして、行ったり来たりしているものがいた
戻ってきてほしかった
歯を食い縛らず、桿から手を放して握り合わせると
掌に胡桃ができた
右の窓から靄を上げて緑の山の間を流れる川が見え
左の窓から一本の雲の柱が見えた
飛行機は枯葉の渦を撒きながら
柱に向かって一直線に飛んだ
そして、そこにささった
窓から這い出すと、それは太い幹で
柔らかく透明な中に
暁の光が小さな泡に包まれて昇っていた
遠くから風が吹いてきて、なにもかも忘れる
ずっと上まで昇っていくと
まぶしく照らされた記憶の鈴がなっている
風に鳴ると空が澄みわたり
山々が地平線から集まってくる
ふもとに林が広がっている
枯葉を跳んで、栗鼠がやってくる
黒い目に、硬い殻が映る
殻にも目があって
遙か高くで流れていく空が映っている
それから一緒に跳んでゆく
ふわふわした尾をゆっくりなびかせながら