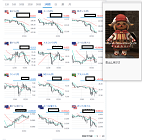景気刺激のカンフル剤の無制限投入に続き、昔のCitixの債務不履行を思い起こさせる「徳政令」要求まででてくる中国。「なんでもあり」のリスクに海外企業は今後どう動くのだろうか。現法化させられた外国金融機関の中国拠点で考えても、今後「毒食らわば皿まで」の共倒れ覚悟派と「とてもやってられない」と逃避する派の2つの極端な選択に分かれるのではないかとも思う。ある意味中国に生産拠点を置く海外企業は「将来の大市場かつ大生産拠点」を希望に中国共産党の無理難題にも耐えるか、「過去のすべてを失っても傷口を広げないようにするか」の二者択一が迫られるような、(新型肺炎ではないが)そんな寒気と悪寒がしている。なぜか1970年代の海外不良債権発生時と同じニオイのように感じるのだが、心配性の老人の私だけだろうか。 . . . 本文を読む
新型肺炎の拡大が続くなか、中国企業の間に契約不履行の免責を求める「不可抗力条項」の適用を探る動きが広がっている。すでに約100社が中国の貿易振興機関から証明書を受け取った。債務や違約金を減免するかは取引先との交渉や裁判次第だが、外国企業にとって新たなリスクが生じた形だ。(1面参照)中国の法令は不可抗力を「予見不能、回避不能かつ克服不能な客観的状況」と定義する。一般に企業間の契約には、一企業では対応できない「天災地変」「戦争」「公権力による命令処分」などが発生した場合、製品納入や代金支払いなどの不履行を免責する条項を入れることが多い。新型コロナウイルスによる肺炎のまん延を受けて、中国国際貿易促進委員会は1月末、不可抗力に当たる事実が発生したことを示す証明書の発行を始めた。証明書そのものは「免罪符にはならないが、当事者間の交渉で用いられる可能性がある」(長島・大野・常松法律事務所の川合正倫弁護士)という。(中略)不可抗力条項の柔軟な運用も施策の一つに位置づけられ、行政や裁判所の判断が中国企業寄りになりやすいとの指摘がある。中国企業と取引がある外国企業にとっては納入時期や違約金などを巡り、譲歩を求められる局面が出てきそうだ。(*日経 記事より) . . . 本文を読む
談話室にアサヒ飲料の自動販売機が置いてあり、無料WiFi(AES暗号化されたものも)利用可能でした。朝食と夕食は、談話室でとりたいとお願いして、[看護師さんに車イスを押してもらい)移動して投稿しておりました。 . . . 本文を読む
ダウ反発(29276)「前週に出た米経済指標がいずれも好調で、決算発表を終えた米主要企業の業績も底堅く、先高観を背景にした買いが優勢だった。新型肺炎への懸念から朝方は小幅安となる場面もあったが、売りは続かなかった」。原油続落(49.57)「中国の新型肺炎で同国を中心に企業活動が減速し、原油需要を抑えかねないとの見方から売りが優勢になった」、金は続伸(1579.5)。債券続伸(利回り低下1.57%)「新型肺炎の広がりが中国を含む世界経済に悪影響を及ぼすとの見方が強く、相対的に安全資産とされる債券が買われた。9日時点で新型肺炎の中国本土の死者数は、2003年に大流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)による世界全体での死者数を超えた。中国を中心に企業活動の停滞につながっている。中国の経済活動の停滞はほかの国にも影響する可能性が高く、米CNBCは10日に「1~3月期の米国の成長率は1.2%程度になりそうだ」という調査結果を伝えた。この日の10年債の最低利回りは1.54%、最高利回りは1.57%だった。金融政策の影響を受けやすい2年物国債相場は続伸した。利回りは前週末比0.01%低い1.39%で取引を終えた」。日経先物夜間引けは23690。 . . . 本文を読む
韓国社会では越えられないものと、越えてはいけないとされるものがある。世界有数のIT(情報技術)先進国にあってなお残る目に見えない壁を、全員失業中の貧しい家族と、IT(情報技術)企業を経営する裕福な社長一家の交わりを通して描いた悲喜劇が、9日(日本時間10日)の米アカデミー賞で作品賞を含む4部門を受賞した映画「パラサイト 半地下の家族」である。(中略)韓国は巨大財閥が富を独占し、2018年の平均月収でみると、上位20%の富裕層が92万円に対し、下位20%の貧困世帯は12万円(いずれも7~9月期)の「両極化(格差)」社会。人の一生は生まれた家庭によって定まる「金のさじ、銀のさじ、土(泥)のさじ」の"スプーン階級論"が浸透している。一般家庭では、深夜まで掛け持ちの学習塾通いから人生が始まる無限競争社会。受験地獄を耐え抜いても就職は親のコネが幅を利かし、結婚の際も男性が住宅を用意するのが習わしだ。結局、親のカネがずっとついて回ると、あぶれた多くの若者は不満を募らせる。(中略)数々のスキャンダルのうち最も非難を浴びたのは子どもの不正入学だった。受験という本来は貧しい人にも平等、公正であるべき聖域にまで、特権を持ちこんだエリートに対する市民の怒りが頂点に達した。17年大統領選では、こうした社会の二極化や不平等を解消するという文在寅(ムン・ジェイン)氏の訴えが若者の心に刺さった。急スピードで国際化しても、半地下住宅に住まざるをえないような取り残された人たちのにおいが映画では格差の象徴とされている。ポン・ジュノ監督は韓国特有のディテールが外国人に理解してもらえるか心配だったようだ。だが貧富の格差が世界中に広がるなかで、徹底した細部へのこだわりが国際社会から評価され、英語以外の言語で初の作品賞受賞という、映画史を変える偉業に輝いた。(* 日経 記事より) . . . 本文を読む