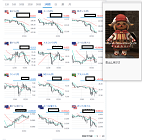株小反落(23827)「中国で新型肺炎の感染者数が急増したと伝わり、海外投資家による株価指数先物への売りが出た。2月物の日経平均ミニ先物とオプションのSQ(特別清算指数)算出を14日に控え、持ち高調整目的の売買が交錯し上げに転じる場面もあった。前日発表した2019年10~12月期連結決算(国際会計基準)が大幅減益だったソフトバンクグループ(SBG)が後場に急落し、1銘柄で日経平均を63円押し下げた。「TモバイルUS親会社のドイツテレコムはSBG傘下の米スプリントの買収条件の再交渉を迫っている」(英紙フィナンシャル・タイムズ電子版)と伝わり、スプリントとTモバイルUSの合併に不透明感が広がった」。債券は下落(利回り上昇マイナス0.035%)「日銀が実施した国債買い入れオペ(公開市場操作)は応札額を落札額で割った応札倍率が前回を大幅に上回り、債券需給の引き締まり観測が後退した。オペ結果公表後の午後の取引で売りが増え、一時は同0.010%高いマイナス0.030%まで上昇した。朝方は買いが優勢だった。新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への悪影響が引き続き警戒され、長期金利は同0.005%低いマイナス0.045%へ低下する場面があった。日銀によるオペの結果を受けて、午後には幅広い年限で売りが出た。新発2年債利回りは前日比横ばいのマイナス0.155%と、午前の取引水準から0.005%上昇した。新発5年債利回りは同0.005%高いマイナス0.135%となっている」 . . . 本文を読む
日米欧ロに中国、インド、韓国を加えた世界7極の協力に基づく国際熱核融合実験炉(ITER、イーター)の建設がフランス南部で進んでいる。太陽が輝くのと同じ「核融合反応」で、実用的なエネルギー生産が可能かを実証するのが目的だ。2025年の稼働を目指し、建設がヤマ場を迎えている。ITERは大きなドーナツ形の真空容器の中に、セ氏1億度を超える超高温の重水素と三重水素(トリチウム)を閉じ込めて核融合を起こさせる。重水素、三重水素は水素の仲間(同位体)で、海水中など自然界に存在する。完成すれば熱出力は50万キロワット。注入したエネルギーの10倍以上のエネルギーを発生できる。ただ核融合の技術実証が目的で発電はしない。(中略)「いずれ既存の原子炉をも代替していく」とは言え、核融合に対しても原子力反対の意見はあるだろう。合意づくりも課題だ。国内では量子科学技術研究開発機構(QST)が、ITERより小型の実験炉「JT-60SA」を茨城県那珂市で建設中だ。20年9月の稼働を目指す。重水素だけを使い核融合反応を模擬するにとどまるが、ITERに先立つ実験を通じ、ITERでどのような実験をどう進めるべきかの知識と経験を得る。ITERの現場から科学者、技術者が訪れて実験に参加する予定だ。また青森県六ケ所村にもQSTの研究施設があり、実用炉に向けての材料研究などが進んでいる。(編集委員 滝順一)
. . . 本文を読む
ダウ反発(29551)「12日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発した。前日比275ドル08セント(0.9%)高の2万9551ドル42セントで終え、過去最高値を更新した。新型肺炎の拡大の勢いが落ち着きつつあるとの見方から投資家がリスク選好姿勢を強め、幅広い銘柄に買いを入れた。中国当局が毎日公表する新型肺炎の新規の感染者数の増加幅は足元で縮小し始めた。中国を中心に世界経済の一段の下押し圧力になるとの見方は和らいだ。中国関連とされる化学のダウや建機のキャタピラーが上昇した。新型肺炎のまん延で株価は下げ基調にあったウィン・リゾーツなどカジノ関連株も軒並み上昇した。原油先物価格が持ち直し、石油株が上昇したことも指数を押し上げた」。原油続伸(51.17)「新型肺炎の感染拡大の勢いが弱まりつつあり、原油需要の減少懸念が後退した。石油輸出国機構(OPEC)が12日に発表した月報で、2020年の世界の石油需要見通しを引き下げた。新型肺炎の感染拡大を理由に挙げた。OPEC加盟国とロシアなどの非加盟国は協調減産の強化を検討している。需要見通しの引き下げによりOPECは減産強化への前向きな姿勢を示したとの思惑が市場に広がり、相場を押し上げたとの指摘があった。米エネルギー情報局(EIA)発表の週間の米石油在庫統計を受けて相場は伸び悩んだ」、金は小反発(1571.6)。債券は続落(利回り上昇1.63%)「新型肺炎に対する過度の懸念が和らいだことから、米主要株価指数がそろって過去最高値を更新した。リスク資産に資金が向かい、相対的に安全資産とされる債券は売られた。財務省が午後に発表した10年債入札では応札倍率が上昇した。落札利回りが3年半ぶりの水準に低下したなかでも底堅い需要がみられ、入札は「好調」と受け止められた。ただ、13日に30年債の入札を控えていることもあり、好感した買いは限られた。」。日経先物夜間引けは23960。12:38更新 . . . 本文を読む
イランは11日、41回目の革命記念日を迎えた。同国の核開発を抑える多国間合意から離脱して制裁を科す米国と対立するだけでなく、合意維持に努めてきた欧州との間にも亀裂が入り、経済の苦境と政治の孤立は深まる。米国との直接衝突はひとまず回避したが、イランを巡る危機は消えず、日本や世界の経済を揺るがすリスクとして残る。11日にテヘランで開かれた恒例の式典では、出席したイラン革命防衛隊の士官ら保守強硬派の支持者から、反米、反イスラエルの革命スローガンが聞かれた。対外関係を重視する保守穏健派だとされるロウハニ大統領も演説で「米国の圧力には屈しない」と強調した。イランの世論は2019年秋から「反政府」と「反米」の間で大きく振れた。19年11月、政府がガソリン価格を突然引き上げ、市民らの抗議デモが各地で起きた。1月3日、米軍が革命防衛隊の精鋭「コッズ部隊」のソレイマニ司令官を殺害すると、デモは反米に転じた。その後、革命防衛隊がウクライナの旅客機を撃墜したと認めると、市民らは再び政府を批判した。革命記念日には反米の機運が盛り上がった。在欧のイラン専門家によると、反米と反政府の双方のデモに参加する市民も多い。米国の制裁で原油の輸出量が急減し、外貨不足、輸入停滞、補助金の削減が一般の生活水準を下げている。閉塞感が社会を覆い始めた。(中略)イランでは穏健派ロウハニ氏の立場が一段と弱まっている。米紙ニューヨーク・タイムズによると、ウクライナ機撃墜について同氏が真相を伝えられたのは発生から2日以上も後のことだった。21日投票のイラン国会議員選では現職の穏健派議員の大半が、強硬派寄りの資格審査組織に出馬を阻まれた。1月の反政府デモに参加した若い男性は吐き捨てた。「こんなのは選挙じゃない」(*日経 記事より) . . . 本文を読む