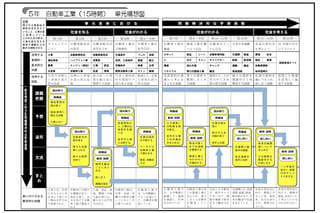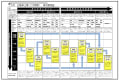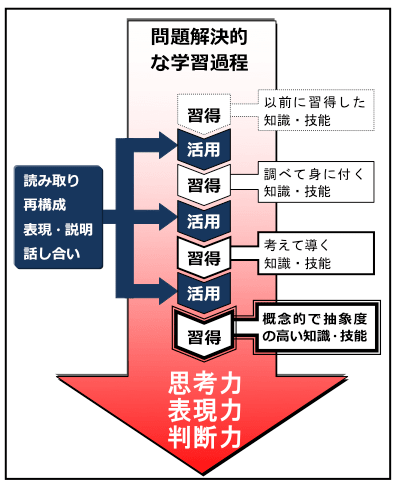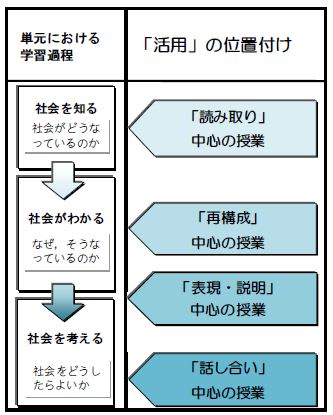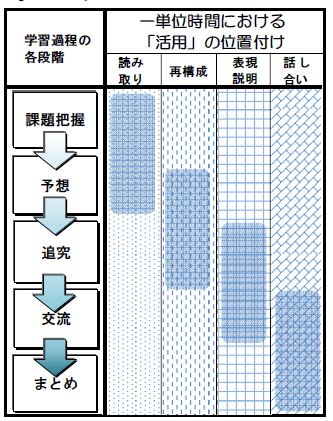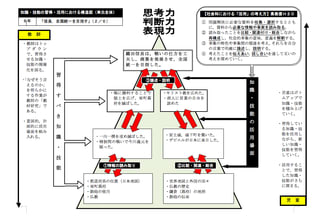
夏からずいぶん間が空いてしまいましたが・・・(苦笑)
社会科関係の記事の続編です。
社会科における4つの言語活動を
問題解決的な学習過程に位置付ける際、
「どのように教材研究をおこなうか?」
ということも重要になってくると思います。
その際に参考にしたのが、北俊夫先生の「知識の構造図」です。
この構造図をヒントにして、
言語活動の位置づけをこのように作ってみました。
【6年社会 戦国時代の単元構想】
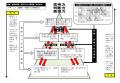
(↑クリックすると拡大します)
【6年社会 織田信長の授業構想】
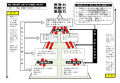
(↑クリックすると拡大します)
教師は、上からこのピラミッドを造っていきます。
すなわち「最終的におしえたいことは何か?」という、概念的な高位の知識をまずは設定するのです。
そして、その知識を身につけさせるにはどのような知識が必要か?
という観点から、知識のレベルを下げていき、ピラミッドを造っています。
逆に児童の思考は下からです。
授業中に児童は、基礎的、基本的な知識技能を習得活用しながら、
知識をどんどんどんどん上に積み重ねていきます。
積み上げる際に必要になってくるのが、
========
「言語活動」
========
なのです。
教師は上から(トップダウン)
児童は下から(ボトムアップ)
おすすめの教材研究です。