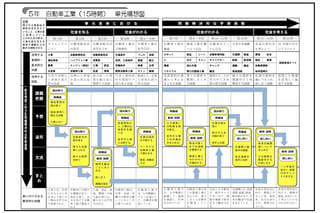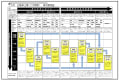4つの言語活動(読み取り/再構成/表現・説明/話し合い)を、
問題解決的な学習過程に位置付けることは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」と「活用」の小刻みな繰り返し
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
であることを前回説明しました。
その具体例として、授業の一こまを紹介します。

ただし、45分の中で、
全ての4つの言語活動を一気に網羅するのは毎回は厳しいです。
この例は、あくまでも
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「問題解決的な学習過程に位置付ける」
「小刻みな繰り返し」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
のサンプルとしてみていただければと思います。

(↑ クリックすると拡大します)
問題解決的な学習過程に位置付けることは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」と「活用」の小刻みな繰り返し
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
であることを前回説明しました。
その具体例として、授業の一こまを紹介します。

ただし、45分の中で、
全ての4つの言語活動を一気に網羅するのは毎回は厳しいです。
この例は、あくまでも
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「問題解決的な学習過程に位置付ける」
「小刻みな繰り返し」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
のサンプルとしてみていただければと思います。

(↑ クリックすると拡大します)
問題解決的な学習は,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基礎的・基本的な知識および技能の「習得」・「活用(=言語活動)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を繰り返し,進めていくと考えます。
その過程を経て、思考力・判断力・表現力等の育成を目指します。
これについて,北俊夫氏(2008)は,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「一旦身につけた知識や技能は,それらを活用して学習することをとおして,
身に付けた知識や技能をさらに確実なものとしたり,
新たな知識や技能を習得したりする機会にもなる。
また,問題意識を持って,すでに習得している知識や技能を活用して
新しい知識や技能を獲得(習得)していく過程が探究している姿である。
(中略)
活用や探究によって,習得した基礎的・基本的な知識はさらに定着したり,
新たな知識・技能(調べて身に付く知識・技能,考えて導く知識・技能,
概念的で抽象度の高い知識・技能など)が習得される。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
としています。
北氏の言うとおり,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」と「活用」は相互に関連し合って
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おり,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」「活用」の双方向的な流れを意識しながら
「活用(=言語活動)」を問題解決的な学習過程に位置付ける
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ことで,知識が確実に定着すると考えます。
また知識の質が,
=================
・考えて導く知識・技能
・概念的で抽象度の高い知識・技能
=================
へと深まる過程をとおして,社会的な思考力や表現力・判断力が身に付くと考えます。
これまで述べてきた問題解決的な学習過程における「習得」と「活用(=言語活動)」の関係を
以下のようにまとめてみました。
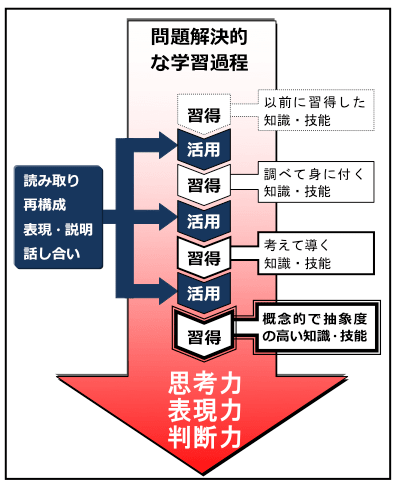
※ この図を具現化した授業モデルは次回紹介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基礎的・基本的な知識および技能の「習得」・「活用(=言語活動)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を繰り返し,進めていくと考えます。
その過程を経て、思考力・判断力・表現力等の育成を目指します。
これについて,北俊夫氏(2008)は,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「一旦身につけた知識や技能は,それらを活用して学習することをとおして,
身に付けた知識や技能をさらに確実なものとしたり,
新たな知識や技能を習得したりする機会にもなる。
また,問題意識を持って,すでに習得している知識や技能を活用して
新しい知識や技能を獲得(習得)していく過程が探究している姿である。
(中略)
活用や探究によって,習得した基礎的・基本的な知識はさらに定着したり,
新たな知識・技能(調べて身に付く知識・技能,考えて導く知識・技能,
概念的で抽象度の高い知識・技能など)が習得される。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
としています。
北氏の言うとおり,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」と「活用」は相互に関連し合って
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おり,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「習得」「活用」の双方向的な流れを意識しながら
「活用(=言語活動)」を問題解決的な学習過程に位置付ける
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ことで,知識が確実に定着すると考えます。
また知識の質が,
=================
・考えて導く知識・技能
・概念的で抽象度の高い知識・技能
=================
へと深まる過程をとおして,社会的な思考力や表現力・判断力が身に付くと考えます。
これまで述べてきた問題解決的な学習過程における「習得」と「活用(=言語活動)」の関係を
以下のようにまとめてみました。
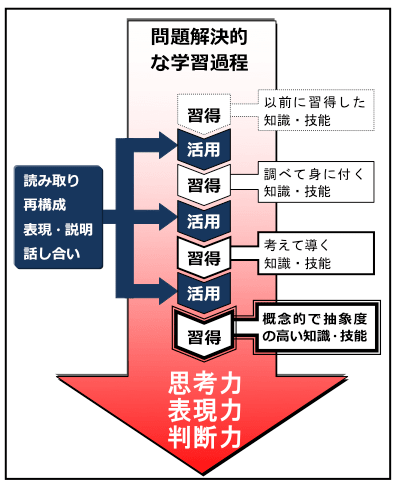
※ この図を具現化した授業モデルは次回紹介します。
社会科における4つの言語活動(基礎的・基本的な知識・技能の活用)
について、それぞれのイメージを以下のように作ってみました。
━━━━━
読み取り
━━━━━

━━━━━
再構成
━━━━━

━━━━━
表現・説明
━━━━━

━━━━━
話し合い
━━━━━

について、それぞれのイメージを以下のように作ってみました。
━━━━━
読み取り
━━━━━

━━━━━
再構成
━━━━━

━━━━━
表現・説明
━━━━━

━━━━━
話し合い
━━━━━

小学校社会科において,以下のような学習活動を,
言語活動(基礎的な知識・技能の活用)と、とらえてみます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
━━━━━
読み取り
━━━━━
問題解決に必要な資料を収集・選択するとともに,資料から必要な情報や事実を読み取る。
━━━━━
再構成
━━━━━
読み取ったことを比較・関連付け・総合しながら再構成し,社会的事象の意味,意義を解釈する。
━━━━━
表現・説明
━━━━━
事象の特色や事象間の関連を考え,それらを自分の言葉で表現する。
━━━━━
話し合い
━━━━━
考えたことを伝え合い,話し合いをとおして,互いの考えを発展させる。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上の「言語活動(=活用)」を、
問題解決的な学習過程に以下のように位置付けてみました。
■単元全体に位置付けた場合
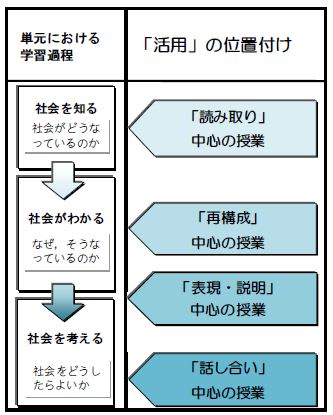
■単位時間に位置付けた場合
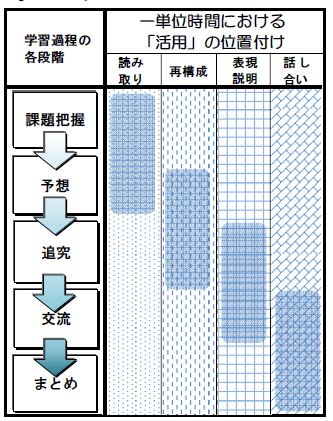
言語活動(基礎的な知識・技能の活用)と、とらえてみます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
━━━━━
読み取り
━━━━━
問題解決に必要な資料を収集・選択するとともに,資料から必要な情報や事実を読み取る。
━━━━━
再構成
━━━━━
読み取ったことを比較・関連付け・総合しながら再構成し,社会的事象の意味,意義を解釈する。
━━━━━
表現・説明
━━━━━
事象の特色や事象間の関連を考え,それらを自分の言葉で表現する。
━━━━━
話し合い
━━━━━
考えたことを伝え合い,話し合いをとおして,互いの考えを発展させる。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上の「言語活動(=活用)」を、
問題解決的な学習過程に以下のように位置付けてみました。
■単元全体に位置付けた場合
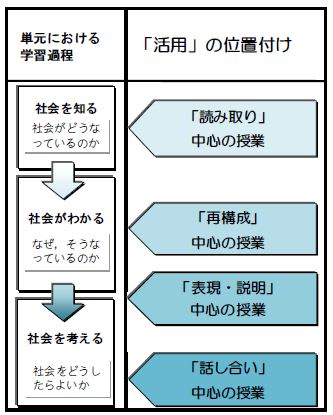
■単位時間に位置付けた場合
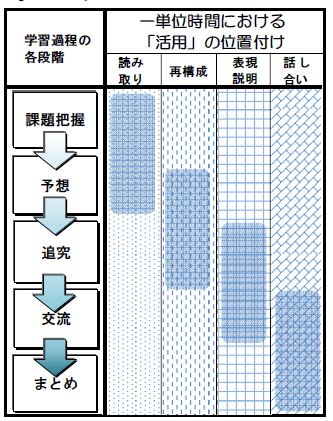
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(5)
~思考を促すための便利ツール~
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
「思考を促す授業」を構成する上で、とても有用なツールを紹介
します。もちろん、黒板とチョークの使用は大前提なのですが、そ
れらと併用することで最大限の効果をあげる以下の3点です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)実物投影機
2)マグネットスクリーン(黒板に貼れる簡易スクリーン)
3)プロジェクター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらのツールを活用し、「大きく」映すということが、児童の
思考も「大きく」促していくことにつながるのです。
==============================
○地図帳の地名探しの際に、位置を即座に確認できる。
○各種グラフの読み取りで、特徴や変化などを全員で読み取れる。
○写真資料の読み取りで、各自が見つけた細かい情報を確認できる。
==============================
大きく映すことにより、一人一人が読み取った事象を全員で確認
することができます。すなわち「情報の共有」がとても容易になる
のです。情報が共有できるということは、そこで生じた「はてな?」
も共有できるということです。このことで、学級全体の思考をダイ
ナミックに促す事が可能となります。
具体的なテクニックを紹介しましょう。以下は歴史授業における
活用例とその反応です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・大仏の写真を実物投影機で黒板に映し、鼻や目を実物大で提示
→「なぜ、どうやって、こんな大きな大仏を造ったのだろう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・参勤交代のイラストを大きく提示し、細かい情報の読み取り
→「様々な特徴を持つ人が沢山いる。役割は何だろう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
黒板に貼り付けたスクリーンにパッと映すだけで、子どもたちの
思考が大きく促された事を実感できました。
このツールは子どもの思考を促すだけではありません。大きく映
せるということは、授業構想も大きく広げるのです。結果、教材研
究における教師自身の思考をも促す事に繋がります。その思考の促
しが、授業、ひいては子どもたちの学力に反映されていき、大きな
相乗効果を生んでいきます。
ICT活用の重要性が叫ばれている昨今、これらのツールは多くの学
校現場に導入されているはずです。児童の思考を促し、確かな学力
をつけるためにも、積極的な活用をお勧めします。
(パソコンと併用すれば、効果はさらに高まると思います。)
┃┃ 思考を促す社会科授業(5)
~思考を促すための便利ツール~
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
「思考を促す授業」を構成する上で、とても有用なツールを紹介
します。もちろん、黒板とチョークの使用は大前提なのですが、そ
れらと併用することで最大限の効果をあげる以下の3点です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)実物投影機
2)マグネットスクリーン(黒板に貼れる簡易スクリーン)
3)プロジェクター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これらのツールを活用し、「大きく」映すということが、児童の
思考も「大きく」促していくことにつながるのです。
==============================
○地図帳の地名探しの際に、位置を即座に確認できる。
○各種グラフの読み取りで、特徴や変化などを全員で読み取れる。
○写真資料の読み取りで、各自が見つけた細かい情報を確認できる。
==============================
大きく映すことにより、一人一人が読み取った事象を全員で確認
することができます。すなわち「情報の共有」がとても容易になる
のです。情報が共有できるということは、そこで生じた「はてな?」
も共有できるということです。このことで、学級全体の思考をダイ
ナミックに促す事が可能となります。
具体的なテクニックを紹介しましょう。以下は歴史授業における
活用例とその反応です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・大仏の写真を実物投影機で黒板に映し、鼻や目を実物大で提示
→「なぜ、どうやって、こんな大きな大仏を造ったのだろう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・参勤交代のイラストを大きく提示し、細かい情報の読み取り
→「様々な特徴を持つ人が沢山いる。役割は何だろう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
黒板に貼り付けたスクリーンにパッと映すだけで、子どもたちの
思考が大きく促された事を実感できました。
このツールは子どもの思考を促すだけではありません。大きく映
せるということは、授業構想も大きく広げるのです。結果、教材研
究における教師自身の思考をも促す事に繋がります。その思考の促
しが、授業、ひいては子どもたちの学力に反映されていき、大きな
相乗効果を生んでいきます。
ICT活用の重要性が叫ばれている昨今、これらのツールは多くの学
校現場に導入されているはずです。児童の思考を促し、確かな学力
をつけるためにも、積極的な活用をお勧めします。
(パソコンと併用すれば、効果はさらに高まると思います。)
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(4)
ー「隠す」ことで思考を促すー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
社会科授業において、児童の思考を促すために私がよく行うのは
「教材加工」です。社会科の命は資料ですが、例えばその一部を「
隠して」提示するのです。
5年「日本の国土」の授業場面で具体的に説明します。
授業冒頭、プロジェクタで大きな世界地図を提示しました。しか
し実は、その世界地図にはあるものが抜けています。見た瞬間子ど
もたちが叫びました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先生、日本がないですよ!?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実は、世界地図から日本をきれいに消していたのです。そこで、子
どもたちに日本の場所はどこかを「口頭」で説明させました。
「中国の東」「太平洋の西側」「韓国の隣」など、子どもたちは
張り切って発表します。しかしその度に、言葉通りだけれども日本
の位置とは全く違う位置をわざと指差します。子どもたちからは、
「違う、そこじゃない!」とブーイングの嵐です。
指で示せば簡単なのに、言葉で位置を説明するのはとても難しい
事に子どもたちは気が付きました。そこで、もどかしがっている彼
らに発問です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地図帳には国の位置を簡単に説明できる、ある線が2種類あります。
それは何か調べましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子どもたちは、夢中になって教科書や地図帳を調べます。そして、
緯線(緯度)と経線(経度)を使えば、日本の位置を正確に伝えら
れることに気がつきました。子どもたちはみな、緯線と経線の便利
さに感動していました。
そしてその後、日本の領土について、緯線と経線を活用しながら
調べる学習につなげていくことができました。「隠す」ことで児童
の思考を促し、学習意欲を高めることができたのです。
特にも現在の社会科教科書は写真やグラフ、イラストが豊富で、
ビジュアル面で引きつけられる内容になっています。例えば、その
資料の一部を付箋等で隠すだけで、子どもたちの「はてな?」が生
まれます。
誰でもできる簡単な「教材加工」です。
┃┃ 思考を促す社会科授業(4)
ー「隠す」ことで思考を促すー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
社会科授業において、児童の思考を促すために私がよく行うのは
「教材加工」です。社会科の命は資料ですが、例えばその一部を「
隠して」提示するのです。
5年「日本の国土」の授業場面で具体的に説明します。
授業冒頭、プロジェクタで大きな世界地図を提示しました。しか
し実は、その世界地図にはあるものが抜けています。見た瞬間子ど
もたちが叫びました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先生、日本がないですよ!?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実は、世界地図から日本をきれいに消していたのです。そこで、子
どもたちに日本の場所はどこかを「口頭」で説明させました。
「中国の東」「太平洋の西側」「韓国の隣」など、子どもたちは
張り切って発表します。しかしその度に、言葉通りだけれども日本
の位置とは全く違う位置をわざと指差します。子どもたちからは、
「違う、そこじゃない!」とブーイングの嵐です。
指で示せば簡単なのに、言葉で位置を説明するのはとても難しい
事に子どもたちは気が付きました。そこで、もどかしがっている彼
らに発問です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地図帳には国の位置を簡単に説明できる、ある線が2種類あります。
それは何か調べましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子どもたちは、夢中になって教科書や地図帳を調べます。そして、
緯線(緯度)と経線(経度)を使えば、日本の位置を正確に伝えら
れることに気がつきました。子どもたちはみな、緯線と経線の便利
さに感動していました。
そしてその後、日本の領土について、緯線と経線を活用しながら
調べる学習につなげていくことができました。「隠す」ことで児童
の思考を促し、学習意欲を高めることができたのです。
特にも現在の社会科教科書は写真やグラフ、イラストが豊富で、
ビジュアル面で引きつけられる内容になっています。例えば、その
資料の一部を付箋等で隠すだけで、子どもたちの「はてな?」が生
まれます。
誰でもできる簡単な「教材加工」です。
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(3)
ー思考を促す発問の条件②ー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
「思考を促す発問」第二の条件は、「考えることはできるが、簡
単に答えは出ない」というような「揺さぶり」をかけることです。
「揺さぶり」には様々な方法がありますが、今回は以下の二点を紹
介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)二者択一で考えるもの
(2)自分たちの生活に立ち返って考えられるもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深い社会的事象を追究する問いに、当てずっぽうで正解できる子
は多くありません。しかし、二者択一で提示すれば、どの子も予想
をする事ができます。このように解決の手がかりを提示し、その理
由を考える事で全員の思考を促すことができると考えます。
具体的な授業場面(6年生歴史単元:室町時代『金閣と銀閣』)
で説明をします。金閣と銀閣の両方を扱った後、このように発問し
ました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさんは、金閣と銀閣どちらに住みたいですか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
やんちゃ君を筆頭に、最初は金閣派が優勢です。ピカピカの金箔
に囲まれた贅沢な生活をイメージするようです。しかし、話し合い
を深めていくと、その優劣が拮抗してきます。金閣は落ち着かない
という意見も多く出てくるのです。
そこですかさず、補助発問を出します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「そこに(自分が)一生住む」と仮定して考えてごらんなさい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自分たちの生活に立ち返り、揺さぶります。すると話し合いの中
で子ども達は、「銀閣のほうが良い」と言うようになりました。銀
閣は障子、ふすまなど、現代日本の住宅様式の原点でもあります。
その価値に触れる事で、銀閣が作られた室町時代から現代に繋がる
文化の重要性について認識できました。結果、本時の大本命である
「書院造」「日本文化の良さ」に迫っていくことが可能となったの
です。
「銀閣の建築様式は現代の私たちの生活様式につながっているの
ですよ」と、ただ解説するのは簡単です。しかしそれだけでは定着
がおぼつきません。揺さぶりにより児童の思考を促しながら「書院
造」についておさえていくことで、理解及び学力定着面で確かな効
果を得た場面となりました。
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(2)
ー思考を促す発問の条件ー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
「思考を促す発問」の第一条件。社会科授業においては、やはり
「実物資料の提示」です。私の社会科授業において「実物資料」は、
「火縄銃」「赤紙」「自動車のボデー」「投票箱」等(複製品含む)
多岐にわたります。そこでグッと高まった児童の興味・関心を、社
会的思考へ導くのが「発問」なのです。
授業の一場面で説明します。
6年「長篠合戦」の学習。子どもたちに火縄銃の複製品を提示し
ました。当時の火縄銃の構造に忠実に作られており、手にズシリと
重い、そんな火縄銃の質感に子どもたちは大興奮です。実際手に取
り、様々な部位を調べることで、重い火縄銃に弾を詰め発射させる
まで、相当な手間と時間がかかることを実感します。
子どもたちはシミュレーションの結果、弾を詰めてから発射させ
るまで30秒かかることが分かりました。対する武田騎馬隊は最前
線まで20秒で突撃したと言われています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
織田軍の鉄砲(30秒)→ × ←(20秒)武田軍の騎馬隊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
普通に考えると武田軍が勝利します。当然子どもたちも武田軍が勝
ったと予想します。そこで、以下のように発問します。
==============================
実は、この戦いは織田軍が勝利します。
なぜ、織田軍は勝利できたのでしょうか?
==============================
長篠合戦図から、信長が勝った要因を探します。鉄砲の長所も短
所も分かっているので、鉄砲の長所を生かし、かつ短所を殺すポイ
ントを見つけなければなりません、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・(騎馬隊の突進を止める)木柵
・(騎馬隊の”足”を妨害する)堀
・小隊ごとに分散して配置された鉄砲隊 等々
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子どもたちは様々なポイントを見つけ、発表することができました。
実際の火縄銃から戦国時代の戦いに興味を持ち、火縄銃の長所と短
所をとらえた上で、織田軍の戦法の工夫を読み取ることができたの
です。
このように「実物資料」と「発問」を効果的に組み合わせること
で、児童は社会的事象を身近に感じ、夢中で追究します。結果、児
童の社会的思考を促すことにつながるのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「発問」の前に、まずは「モノ」を提示する!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このことを意識するだけでも、社会科授業は変わっていくのではな
いでしょうか。
┃┃ 思考を促す社会科授業(2)
ー思考を促す発問の条件ー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
「思考を促す発問」の第一条件。社会科授業においては、やはり
「実物資料の提示」です。私の社会科授業において「実物資料」は、
「火縄銃」「赤紙」「自動車のボデー」「投票箱」等(複製品含む)
多岐にわたります。そこでグッと高まった児童の興味・関心を、社
会的思考へ導くのが「発問」なのです。
授業の一場面で説明します。
6年「長篠合戦」の学習。子どもたちに火縄銃の複製品を提示し
ました。当時の火縄銃の構造に忠実に作られており、手にズシリと
重い、そんな火縄銃の質感に子どもたちは大興奮です。実際手に取
り、様々な部位を調べることで、重い火縄銃に弾を詰め発射させる
まで、相当な手間と時間がかかることを実感します。
子どもたちはシミュレーションの結果、弾を詰めてから発射させ
るまで30秒かかることが分かりました。対する武田騎馬隊は最前
線まで20秒で突撃したと言われています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
織田軍の鉄砲(30秒)→ × ←(20秒)武田軍の騎馬隊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
普通に考えると武田軍が勝利します。当然子どもたちも武田軍が勝
ったと予想します。そこで、以下のように発問します。
==============================
実は、この戦いは織田軍が勝利します。
なぜ、織田軍は勝利できたのでしょうか?
==============================
長篠合戦図から、信長が勝った要因を探します。鉄砲の長所も短
所も分かっているので、鉄砲の長所を生かし、かつ短所を殺すポイ
ントを見つけなければなりません、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・(騎馬隊の突進を止める)木柵
・(騎馬隊の”足”を妨害する)堀
・小隊ごとに分散して配置された鉄砲隊 等々
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子どもたちは様々なポイントを見つけ、発表することができました。
実際の火縄銃から戦国時代の戦いに興味を持ち、火縄銃の長所と短
所をとらえた上で、織田軍の戦法の工夫を読み取ることができたの
です。
このように「実物資料」と「発問」を効果的に組み合わせること
で、児童は社会的事象を身近に感じ、夢中で追究します。結果、児
童の社会的思考を促すことにつながるのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「発問」の前に、まずは「モノ」を提示する!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このことを意識するだけでも、社会科授業は変わっていくのではな
いでしょうか。
「思考を促す授業」というのは、教師になって十数年
自分が追究している永遠のテーマです。
昨年このテーマについて、メルマガの原稿を書く機会をいただきました。
そして、5回の連載で自分の実践の一部をまとめることができました。
実践の整理という意味も含めて、
(拙い文章ですが)ブログにまとめておこうと思います。
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(1)
ー思考を促すとは?ー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
今夏、新潟県十日町市へ旅する機会がありました。そこでとて
も驚いた事がありました。何と殆どの信号機が縦型だったのです。
豪雪地帯の信号機はみんな縦型。社会科教師であれば常識の事象
ではありますが、やはり実物に接すれば感動するものです。
すぐにデジカメで撮影し、「授業でどのように提示すれば、児童
の思考を促すことができるか?」と、教材化に思いを馳せました。
本稿の題にも掲げた「思考を促す」とは、「なぜ?どのように?」
という思考を児童に強く持たせることです。これは、「思考力・判
断力・表現力等の育成」に直結していく大切な要素だと考えます。
そこで、まずは指導言の吟味から授業を構想していきました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は新潟県に旅行してきました。新潟県は雪の重みで信号機が
壊れないように、縦型になっていたのでした。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これでは講義型の授業になってしまいます。思考を促すとは言い難
い、単なる説明です。そこで説明から発問に変えることにしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は、新潟県に旅行してきました。新潟県の信号機の多くが縦
型になっていました。どうして縦型なのでしょう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この発問だと、児童に「なぜだろう?」という思考が働きます。し
かし、それでもまだ思考を促すには弱いと感じました。そこで、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は今夏、ある県へ旅行しました。そこではこの縦型信号機が
数多く設置してありました。さて、何県へ旅行したのでしょう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この発問は、児童に「判断」と「根拠」という二重の思考を促しま
す。実際児童は、信号機の形から「雪国」ということまでは予想し
ました。しかし新潟以外でも雪が多い県は存在します。児童は、言
語活動を通して、降雪量の多い都道府県について議論を始めました。
そこで、ご当地マーク(今回は「米」という文字)が入ったマン
ホールの写真や県章を提示します。これらの資料を比較・関連づけ・
総合させ、児童の思考を「新潟県」へ収斂させていきました。
このように指導言の一部を変えるだけで、児童の言語活動も大き
く変化します。「児童の思考を促す」ためには、様々な要素が考え
られますが、今回の例は「発問の工夫」によるものでした。そこで
次回は、「思考を促す発問の条件」について改めて考えてみます。
自分が追究している永遠のテーマです。
昨年このテーマについて、メルマガの原稿を書く機会をいただきました。
そして、5回の連載で自分の実践の一部をまとめることができました。
実践の整理という意味も含めて、
(拙い文章ですが)ブログにまとめておこうと思います。
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
┃┃ 思考を促す社会科授業(1)
ー思考を促すとは?ー
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
今夏、新潟県十日町市へ旅する機会がありました。そこでとて
も驚いた事がありました。何と殆どの信号機が縦型だったのです。
豪雪地帯の信号機はみんな縦型。社会科教師であれば常識の事象
ではありますが、やはり実物に接すれば感動するものです。
すぐにデジカメで撮影し、「授業でどのように提示すれば、児童
の思考を促すことができるか?」と、教材化に思いを馳せました。
本稿の題にも掲げた「思考を促す」とは、「なぜ?どのように?」
という思考を児童に強く持たせることです。これは、「思考力・判
断力・表現力等の育成」に直結していく大切な要素だと考えます。
そこで、まずは指導言の吟味から授業を構想していきました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は新潟県に旅行してきました。新潟県は雪の重みで信号機が
壊れないように、縦型になっていたのでした。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これでは講義型の授業になってしまいます。思考を促すとは言い難
い、単なる説明です。そこで説明から発問に変えることにしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は、新潟県に旅行してきました。新潟県の信号機の多くが縦
型になっていました。どうして縦型なのでしょう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この発問だと、児童に「なぜだろう?」という思考が働きます。し
かし、それでもまだ思考を促すには弱いと感じました。そこで、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「先生は今夏、ある県へ旅行しました。そこではこの縦型信号機が
数多く設置してありました。さて、何県へ旅行したのでしょう?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この発問は、児童に「判断」と「根拠」という二重の思考を促しま
す。実際児童は、信号機の形から「雪国」ということまでは予想し
ました。しかし新潟以外でも雪が多い県は存在します。児童は、言
語活動を通して、降雪量の多い都道府県について議論を始めました。
そこで、ご当地マーク(今回は「米」という文字)が入ったマン
ホールの写真や県章を提示します。これらの資料を比較・関連づけ・
総合させ、児童の思考を「新潟県」へ収斂させていきました。
このように指導言の一部を変えるだけで、児童の言語活動も大き
く変化します。「児童の思考を促す」ためには、様々な要素が考え
られますが、今回の例は「発問の工夫」によるものでした。そこで
次回は、「思考を促す発問の条件」について改めて考えてみます。