研究主任の仕事を初めて拝命したのは、
教職4年目でした。
しかしそのときは、本当にわけが分からなかったので、
「研究部通信」を発行する余裕は全くありませんでした。
3校目で研究主任となったとき、
初めて、「研究部通信」というものを発行してみました。
(年間30数号発行していました)
6、7年ぶりに読み返し見ると、
その青臭い文面に、ちょっと引いてしまいました(苦笑)
でも、その中で、8年後の今の自分と
ぶれていないところもちょっとあったので、そこが嬉しくも思いました。
これは6年前の4月に発行した第3号です。
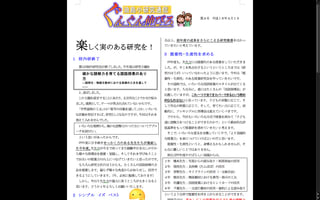
(↑こういう文章だけの、堅苦しい内容から、5年間の試行錯誤と学びを経て
研究部通信は、劇的に中身が変わります。これは後ほど)
楽しく実のある研究を!
1 校内研終了
第1回校内研究会が終了しました。今年度は研究主題を
==========================
確かな読解力を育てる国語授業のあり方
―説明文・物語文教材における指導の工夫を通して――
==========================
と、設定しました。
この主題を設定することにあたり、
文言的なことでかなり悩みました。
漠然として、テーマが焦点化されていないからです。
「学習過程の工夫」とか「視写の活動を通して」とか、
いろいろな活動を明記すれば、研究らしくなるのですが、
今回はそれを敢えて入れませんでした。
いろいろな視野から、確かな読解力のつけ方についてアプローチを図りたい。
という思いがあったからです。
昨年度に引き続きせっかく力のある先生たちが集結した今年度。
先生方が今まで培ってきた経験や引き出しの中から様々な指導法を提案・実践し、
そしてそれを学びあうことでお互いの授業力の向上につなげていきたいと思ったのです。
もちろん研究主任のほうからも、たくさんの国語指導の方法を提案します。
偏らず様々な角度からお知らせし、活用できるようにしていきます。(今、必死に勉強しております)
しかし、やはり先生方の協力に負うところが大きくなると思います。どうか1年よろしくお願いいたします。
2 シンプル イズ ベスト
目指すことは単純です。
============================
・ やっていて辛くない、楽しい研究にしよう。
・ 教師の指導力を高める、役に立つ研究にしよう。
・ 退職まで使える、薄くて中身のある研究収録を作ろう
============================
研究計画を作る過程で、前年度のK研究主任が作ったものに大きく頼りました。
準備の周到さ、系統立てられた計画の鋭さに感動させられました。
プレッシャーも正直大きいです。でもやるしかありません。
前年度までの良いところを踏襲しながら、そして研究である以上、
前年度の成果をさらにこえる研究推進をはかっていきたいと考えています。
3 提案性・生産性を求める
昨年度も、先生方には提案性のある授業をしていただきました。
が、そこを焦点化するというというところまでは
(研究のほうが)いっていなかったように思います。
今年は「提案性・生産性」のある授業研究会を作っていきたいです。
その過程では、いろいろな国語授業のスタイルが出てくると思います。
ちなみに、巷にはたくさんの「国語指導法」が氾濫していますが、
これ一つで全てをカバーできるという絶対的なものはないと思っています。
子どもの実態に応じて、そして作品の特質に応じて、
そして、育てたい力に応じて、流動的に、フレキシブルに指導法は変えていくべきです。
ですから、今回もいろいろな方式で授業を試みて
「子ども達に読解力をつけることができたのか?」
という絶対的な評価基準をもって授業研を進めていきたいと考えます。
そこで、いろいろな意見を交換していく中で、
「より実践的な授業力」を身につけていけばよいのだと思います。
提案性・生産性というと、身構えるかもしれませんが、
そんなに難しいことではありません。
例えば昨年度のすばらしい実践からは、
1年 A先生:写真からの読み取り・短冊黒板の活用
2年 B先生:具体物(たんぽぽ)の活用
3年 C先生:サイドラインの活用(一文総合法)
4年 D先生:物語教材における発問・指示の工夫
5年 E先生:国語授業におけるヒントカードの活用
6年 F先生:一文改行教材の活用・要約による読み取り
というような形で提案性を浮き上がらせることができます。
研究会では、
果たしてこの指導法が子ども達の読解力を高めるために効果的であったか?
という1点で議論を深めていけばよいわけです。
もちろん教材が決まれば、それに適した効果的な指導法の資料を準備しますし、
当然事前研でもその提案性については揉みたいと思います。
教材文は事前研よりも前に先生方全員にお配りする予定です。
4 気楽に
ここまで書くと「やっぱり 大変そう」と思われるかもしれませんが、
【特別なことは一切しないで、自分の意識だけ変える】
そういうとらえで大丈夫です。
楽しく、役に立ち、そしてシンプルで硬質な研究を目指していきましょう。
教職4年目でした。
しかしそのときは、本当にわけが分からなかったので、
「研究部通信」を発行する余裕は全くありませんでした。
3校目で研究主任となったとき、
初めて、「研究部通信」というものを発行してみました。
(年間30数号発行していました)
6、7年ぶりに読み返し見ると、
その青臭い文面に、ちょっと引いてしまいました(苦笑)
でも、その中で、8年後の今の自分と
ぶれていないところもちょっとあったので、そこが嬉しくも思いました。
これは6年前の4月に発行した第3号です。
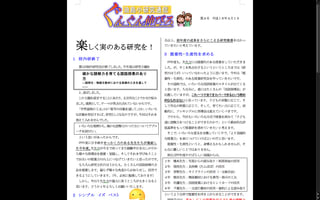
(↑こういう文章だけの、堅苦しい内容から、5年間の試行錯誤と学びを経て
研究部通信は、劇的に中身が変わります。これは後ほど)
楽しく実のある研究を!
1 校内研終了
第1回校内研究会が終了しました。今年度は研究主題を
==========================
確かな読解力を育てる国語授業のあり方
―説明文・物語文教材における指導の工夫を通して――
==========================
と、設定しました。
この主題を設定することにあたり、
文言的なことでかなり悩みました。
漠然として、テーマが焦点化されていないからです。
「学習過程の工夫」とか「視写の活動を通して」とか、
いろいろな活動を明記すれば、研究らしくなるのですが、
今回はそれを敢えて入れませんでした。
いろいろな視野から、確かな読解力のつけ方についてアプローチを図りたい。
という思いがあったからです。
昨年度に引き続きせっかく力のある先生たちが集結した今年度。
先生方が今まで培ってきた経験や引き出しの中から様々な指導法を提案・実践し、
そしてそれを学びあうことでお互いの授業力の向上につなげていきたいと思ったのです。
もちろん研究主任のほうからも、たくさんの国語指導の方法を提案します。
偏らず様々な角度からお知らせし、活用できるようにしていきます。(今、必死に勉強しております)
しかし、やはり先生方の協力に負うところが大きくなると思います。どうか1年よろしくお願いいたします。
2 シンプル イズ ベスト
目指すことは単純です。
============================
・ やっていて辛くない、楽しい研究にしよう。
・ 教師の指導力を高める、役に立つ研究にしよう。
・ 退職まで使える、薄くて中身のある研究収録を作ろう
============================
研究計画を作る過程で、前年度のK研究主任が作ったものに大きく頼りました。
準備の周到さ、系統立てられた計画の鋭さに感動させられました。
プレッシャーも正直大きいです。でもやるしかありません。
前年度までの良いところを踏襲しながら、そして研究である以上、
前年度の成果をさらにこえる研究推進をはかっていきたいと考えています。
3 提案性・生産性を求める
昨年度も、先生方には提案性のある授業をしていただきました。
が、そこを焦点化するというというところまでは
(研究のほうが)いっていなかったように思います。
今年は「提案性・生産性」のある授業研究会を作っていきたいです。
その過程では、いろいろな国語授業のスタイルが出てくると思います。
ちなみに、巷にはたくさんの「国語指導法」が氾濫していますが、
これ一つで全てをカバーできるという絶対的なものはないと思っています。
子どもの実態に応じて、そして作品の特質に応じて、
そして、育てたい力に応じて、流動的に、フレキシブルに指導法は変えていくべきです。
ですから、今回もいろいろな方式で授業を試みて
「子ども達に読解力をつけることができたのか?」
という絶対的な評価基準をもって授業研を進めていきたいと考えます。
そこで、いろいろな意見を交換していく中で、
「より実践的な授業力」を身につけていけばよいのだと思います。
提案性・生産性というと、身構えるかもしれませんが、
そんなに難しいことではありません。
例えば昨年度のすばらしい実践からは、
1年 A先生:写真からの読み取り・短冊黒板の活用
2年 B先生:具体物(たんぽぽ)の活用
3年 C先生:サイドラインの活用(一文総合法)
4年 D先生:物語教材における発問・指示の工夫
5年 E先生:国語授業におけるヒントカードの活用
6年 F先生:一文改行教材の活用・要約による読み取り
というような形で提案性を浮き上がらせることができます。
研究会では、
果たしてこの指導法が子ども達の読解力を高めるために効果的であったか?
という1点で議論を深めていけばよいわけです。
もちろん教材が決まれば、それに適した効果的な指導法の資料を準備しますし、
当然事前研でもその提案性については揉みたいと思います。
教材文は事前研よりも前に先生方全員にお配りする予定です。
4 気楽に
ここまで書くと「やっぱり 大変そう」と思われるかもしれませんが、
【特別なことは一切しないで、自分の意識だけ変える】
そういうとらえで大丈夫です。
楽しく、役に立ち、そしてシンプルで硬質な研究を目指していきましょう。















 。
。