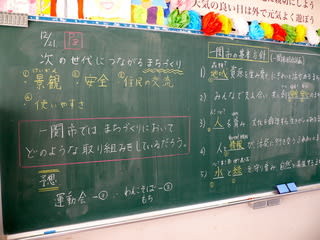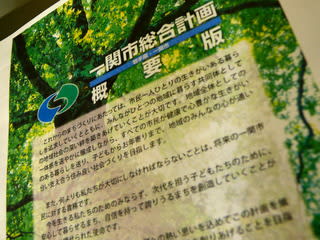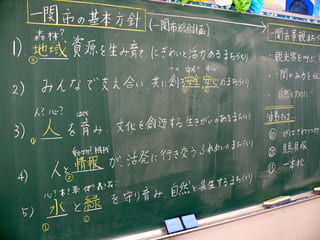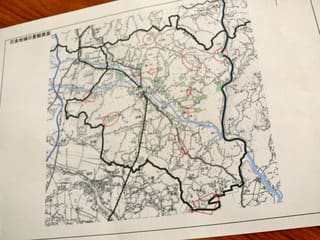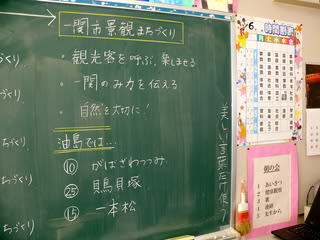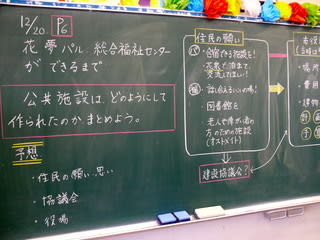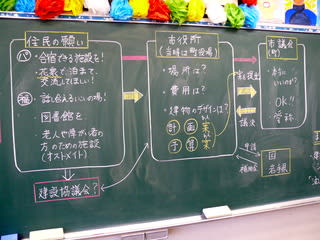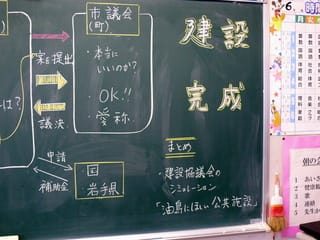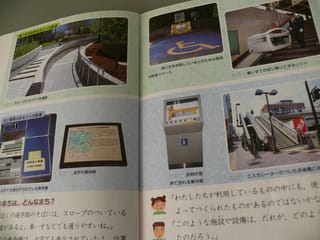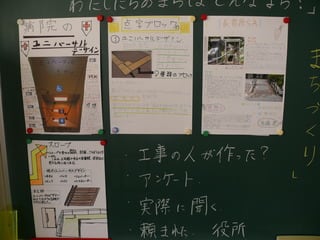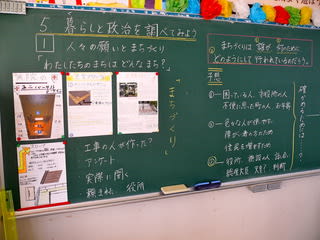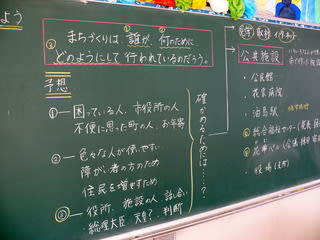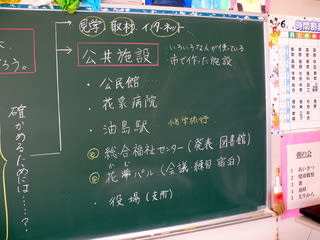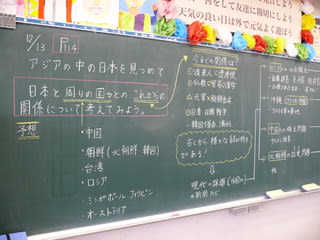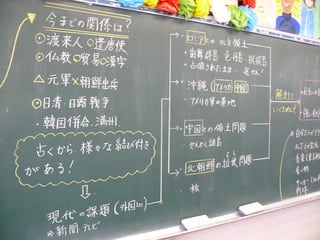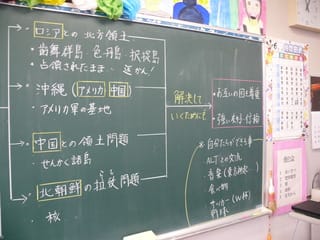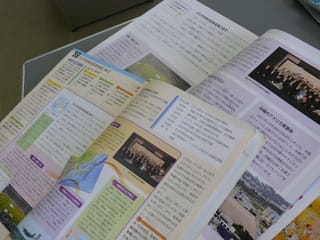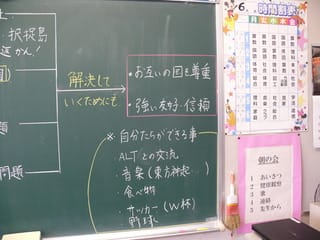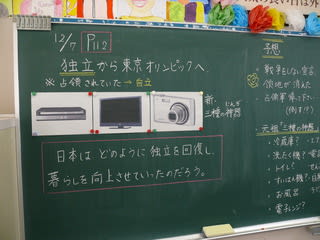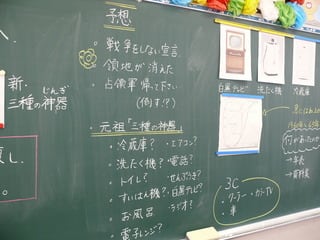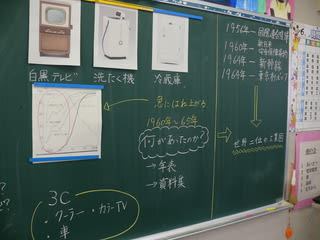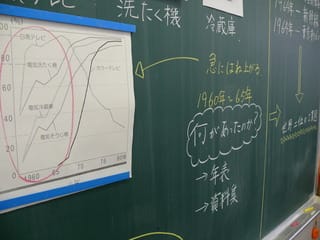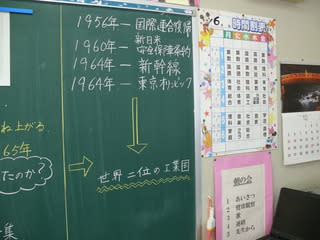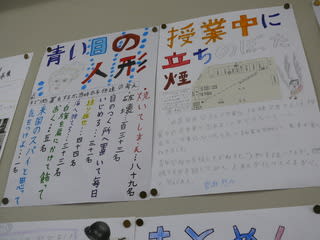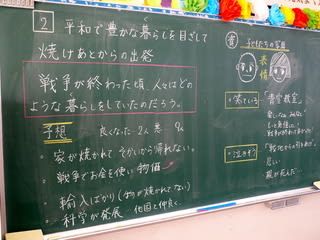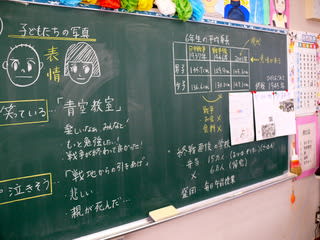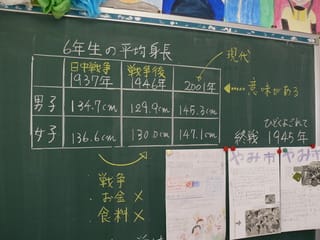「地方公共団体を学習する小単元」最後の授業である。
住民の暮らしと地方公共団体が
どのようにかかわり合っているかを理解させる。
導入で使ったのが
=========
広報いちのせき
=========
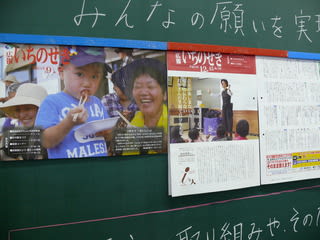
表紙や中身で紹介されているイベントを読み取らせる。
ーーーーーーーーーー
・もちつき大会
・マジックショー
・予防接種
ーーーーーーーーーー
参加は「無料」と記してある。
====================
これらのイベントは、誰が企画し、
誰がお金を出して運営しているの?
====================
と発問。
子どもたちは、
ーーーーーーーーーーー
・ボランティア
・税金
・寄付
ーーーーーーーーーーー
などと答える。
誰が?どうやって?と投げかけると、
子どもたちは「分からない」という。
そこで、学習問題を子どもたちに作らせた。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一関市の取組みやその費用は
誰が、どのように決めているのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
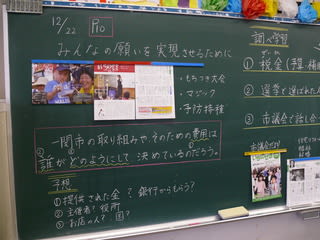
子どもたちが調べるポイントは3点。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①費用はなにから出ているのか?
②誰が決めているのか?
③どのように決めているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを、教科書本文資料を読ませ、調べさせた。
教科書は、情報が本当にコンパクトに、的確にまとめられている。
地域素材を扱った授業であれ、
やはり自分は教科書は必ず使うように心がけている。
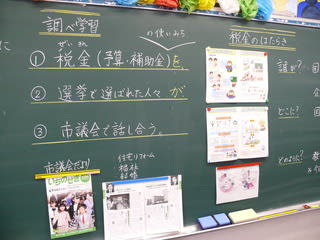
子どもたちは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①税金(予算・補助金)の使い道を
②選挙で選ばれた人たちが
③市議会で話し合って決める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とそれぞれまとめた。
=======================
③市議会でどんな風に話し合われているのか?
=======================
この学習活動で提示した資料が
ーーーーーーーーー
一関市議会だより
ーーーーーーーーー
である。
議員さんたちの「予算」に対する答弁が詳しく分かりやすく載っている。
(しかも、写真付き)
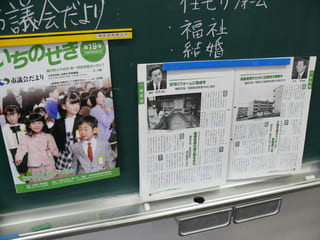
読んでいくと
ーーーーーーー
福祉
ーーーーーーー
教育
ーーーーーーー
建設
ーーーーーーー
結婚問題
ーーーーーーー
いろいろなことで、予算についてのやり取りがあった。
子どもたちにとっても、身近な話題が多かった。
=================
こんなに金がかかっているんだ。
=================
と子どもたち。
では、、実際一関市の予算の歳入・歳出状況はどうなのかを確認。
これは、市のホームページからダウンロードした円グラフを提示。

教科書資料と同様、我が市においても
「福祉」「公共施設の整備」「教育」について大部分が使われていることを確認。
歳入では、半分以上が「税金」で占められていた。
==============
そもそも税金って何?
==============
分かっているようで、分かっていない子どもたち。
ここで、子どもたちに出した資料は
春に県から配布され、この日のために保管しておいた
「税の資料」
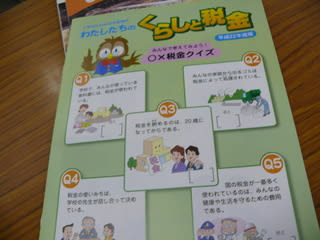
クイズ形式で、税金について楽しく学べる作りになっている。
○×で、子どもたちも楽しそうに手を挙げる。
これらのページを使って、税金の働きについてまとめていく。
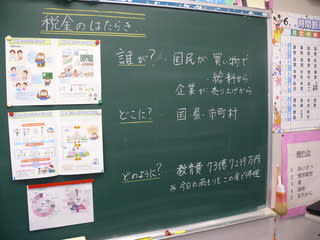
ここで、丁度時間が終了。
宿題では、日記のテーマとして
======================
自分たちの学区で、税金を有効に使うとしたら
どんなことが考えられるか。
======================
を提示した。
子どもたちは翌日、1ページしっかり書いてきた。
「福祉」「教育」関係が多かった。

今回の授業で、2学期の社会科は全て終了。
なんとか、終業式の前日で終えることができて、ホッと一息。
子どもたちの食いつきも良く、定着もそれなりにしたと思う。
あとは自分の授業技量。
今回も資料が多かった。
============
メイン資料はなに?
============
と突っ込まれたら、多分答えられないだろう。
使う必然性はそれぞれそれなりにあったのだが、
上手な先生は、それでも一つの資料を通して、多分45分を組み立てるだろう。
ある意味「資料の数」に逃げて、深い教材研究を怠った証明。
ただただ反省である。
残りの単元は、冬休みにしっかり教材研究をして、
きちっとした授業をしていけるようにしよう。
子どもたちのために。
住民の暮らしと地方公共団体が
どのようにかかわり合っているかを理解させる。
導入で使ったのが
=========
広報いちのせき
=========
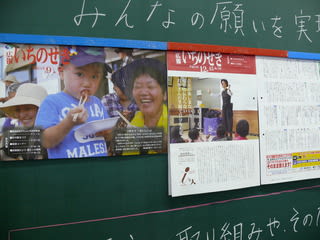
表紙や中身で紹介されているイベントを読み取らせる。
ーーーーーーーーーー
・もちつき大会
・マジックショー
・予防接種
ーーーーーーーーーー
参加は「無料」と記してある。
====================
これらのイベントは、誰が企画し、
誰がお金を出して運営しているの?
====================
と発問。
子どもたちは、
ーーーーーーーーーーー
・ボランティア
・税金
・寄付
ーーーーーーーーーーー
などと答える。
誰が?どうやって?と投げかけると、
子どもたちは「分からない」という。
そこで、学習問題を子どもたちに作らせた。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一関市の取組みやその費用は
誰が、どのように決めているのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
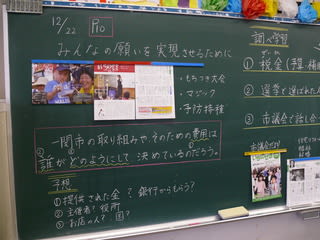
子どもたちが調べるポイントは3点。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①費用はなにから出ているのか?
②誰が決めているのか?
③どのように決めているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを、教科書本文資料を読ませ、調べさせた。
教科書は、情報が本当にコンパクトに、的確にまとめられている。
地域素材を扱った授業であれ、
やはり自分は教科書は必ず使うように心がけている。
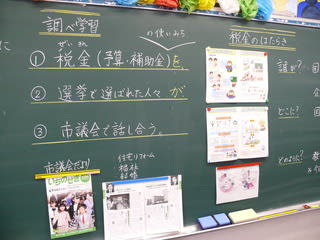
子どもたちは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①税金(予算・補助金)の使い道を
②選挙で選ばれた人たちが
③市議会で話し合って決める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とそれぞれまとめた。
=======================
③市議会でどんな風に話し合われているのか?
=======================
この学習活動で提示した資料が
ーーーーーーーーー
一関市議会だより
ーーーーーーーーー
である。
議員さんたちの「予算」に対する答弁が詳しく分かりやすく載っている。
(しかも、写真付き)
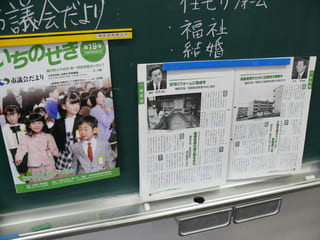
読んでいくと
ーーーーーーー
福祉
ーーーーーーー
教育
ーーーーーーー
建設
ーーーーーーー
結婚問題
ーーーーーーー
いろいろなことで、予算についてのやり取りがあった。
子どもたちにとっても、身近な話題が多かった。
=================
こんなに金がかかっているんだ。
=================
と子どもたち。
では、、実際一関市の予算の歳入・歳出状況はどうなのかを確認。
これは、市のホームページからダウンロードした円グラフを提示。

教科書資料と同様、我が市においても
「福祉」「公共施設の整備」「教育」について大部分が使われていることを確認。
歳入では、半分以上が「税金」で占められていた。
==============
そもそも税金って何?
==============
分かっているようで、分かっていない子どもたち。
ここで、子どもたちに出した資料は
春に県から配布され、この日のために保管しておいた
「税の資料」
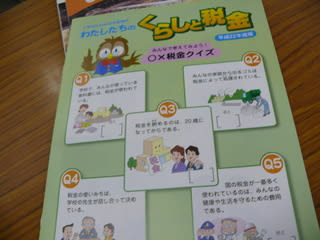
クイズ形式で、税金について楽しく学べる作りになっている。
○×で、子どもたちも楽しそうに手を挙げる。
これらのページを使って、税金の働きについてまとめていく。
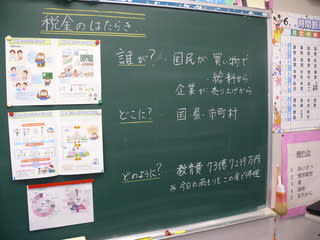
ここで、丁度時間が終了。
宿題では、日記のテーマとして
======================
自分たちの学区で、税金を有効に使うとしたら
どんなことが考えられるか。
======================
を提示した。
子どもたちは翌日、1ページしっかり書いてきた。
「福祉」「教育」関係が多かった。

今回の授業で、2学期の社会科は全て終了。
なんとか、終業式の前日で終えることができて、ホッと一息。
子どもたちの食いつきも良く、定着もそれなりにしたと思う。
あとは自分の授業技量。
今回も資料が多かった。
============
メイン資料はなに?
============
と突っ込まれたら、多分答えられないだろう。
使う必然性はそれぞれそれなりにあったのだが、
上手な先生は、それでも一つの資料を通して、多分45分を組み立てるだろう。
ある意味「資料の数」に逃げて、深い教材研究を怠った証明。
ただただ反省である。
残りの単元は、冬休みにしっかり教材研究をして、
きちっとした授業をしていけるようにしよう。
子どもたちのために。