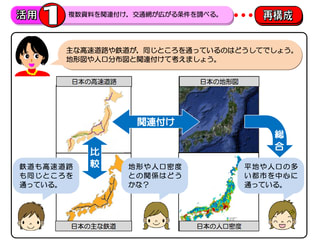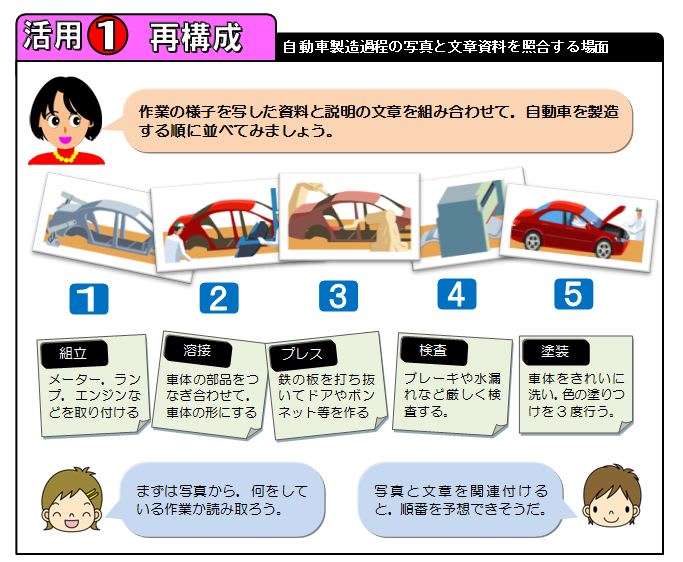教育センター長研時代に、
尊敬するS指導主事先生から「本質を外すな」と何度も何度もご指導頂いた事。
それ、今回の文章にも生きているなぁと改めて思いました。
ただただ、感謝です。
------------------------------------------------------
本連載では「思考を促す社会科授業」として、これまで4回に渡
り、【読み取り】、【再構成】、【表現・説明】、【話し合い】と
いう言語活動について示してきました。
しかし、中には、
==============================
こんな当たり前のこと、自分は昔からやってきている!
==============================
なにを改まって、こんな普通の事を書いているんだ?
==============================
と思われた方も、(少なからず)いらっしゃると思います。
確かに私自身も、「目新しい事はそう多く書いていない」と認識
しています。私が提示した実践例は、社会科を専門とする方にとっ
ては、まさに「当たり前」な指導事項だったかもしれません。あわ
せて「提案性」という意味では、少々語弊があったかもしれません。
しかし、こういった本来「当たり前」であるべきことが、今現在
「当たり前」でなくなってしまっていることも、残念ながら事実で
す。若い教員が増え、「社会科の授業が分からない」という声も多
く聞かれます。また、ベテラン教師も日常の多忙感に追われ、自身
の授業を振り返る余裕がない現状です。
だからこそ文部科学省は、「言語活動の充実」という新しき題目
を示して教師たちの興味を引き、そこで改めて「学習指導の本質」
に気づいてもらおうと思ったのではないでしょうか。
ですから、今回の連載で示した事項は、全て「教育の原点」であ
る、と自負しております。そして、これらの活動を確実に、地道に
続けていくことが、子どもたちに力をつける一番の近道だとも確信
しております。
教育に「不易と流行」があるとすれば、今回示した「言語活動」
は、「不易」に当たります。すなわち、我々の先人時代から脈々と
受け継がれてきた、「当たり前」の指導事項を「当たり前」に、確
実に指導していくことが我々の原点でもあるのです。
ならば、「当たり前」な言語活動を、一単位時間、もしくは単元
全体をとおして、意図的計画的に位置付けていきましょう。そして
子どもたちの思考をぐんぐん促していきましょう。それが、子ども
たちの思考力・判断力・表現力等の育成に繋がっていくのだと思い
ます。
「当たり前のことを当たり前に」
簡単そうでいて実はとても難しいことです。だからこそ、それを
着実に実践できるよう、日々努力し続けたいものです。
------------------------------------------------------
尊敬するS指導主事先生から「本質を外すな」と何度も何度もご指導頂いた事。
それ、今回の文章にも生きているなぁと改めて思いました。
ただただ、感謝です。
------------------------------------------------------
本連載では「思考を促す社会科授業」として、これまで4回に渡
り、【読み取り】、【再構成】、【表現・説明】、【話し合い】と
いう言語活動について示してきました。
しかし、中には、
==============================
こんな当たり前のこと、自分は昔からやってきている!
==============================
なにを改まって、こんな普通の事を書いているんだ?
==============================
と思われた方も、(少なからず)いらっしゃると思います。
確かに私自身も、「目新しい事はそう多く書いていない」と認識
しています。私が提示した実践例は、社会科を専門とする方にとっ
ては、まさに「当たり前」な指導事項だったかもしれません。あわ
せて「提案性」という意味では、少々語弊があったかもしれません。
しかし、こういった本来「当たり前」であるべきことが、今現在
「当たり前」でなくなってしまっていることも、残念ながら事実で
す。若い教員が増え、「社会科の授業が分からない」という声も多
く聞かれます。また、ベテラン教師も日常の多忙感に追われ、自身
の授業を振り返る余裕がない現状です。
だからこそ文部科学省は、「言語活動の充実」という新しき題目
を示して教師たちの興味を引き、そこで改めて「学習指導の本質」
に気づいてもらおうと思ったのではないでしょうか。
ですから、今回の連載で示した事項は、全て「教育の原点」であ
る、と自負しております。そして、これらの活動を確実に、地道に
続けていくことが、子どもたちに力をつける一番の近道だとも確信
しております。
教育に「不易と流行」があるとすれば、今回示した「言語活動」
は、「不易」に当たります。すなわち、我々の先人時代から脈々と
受け継がれてきた、「当たり前」の指導事項を「当たり前」に、確
実に指導していくことが我々の原点でもあるのです。
ならば、「当たり前」な言語活動を、一単位時間、もしくは単元
全体をとおして、意図的計画的に位置付けていきましょう。そして
子どもたちの思考をぐんぐん促していきましょう。それが、子ども
たちの思考力・判断力・表現力等の育成に繋がっていくのだと思い
ます。
「当たり前のことを当たり前に」
簡単そうでいて実はとても難しいことです。だからこそ、それを
着実に実践できるよう、日々努力し続けたいものです。
------------------------------------------------------