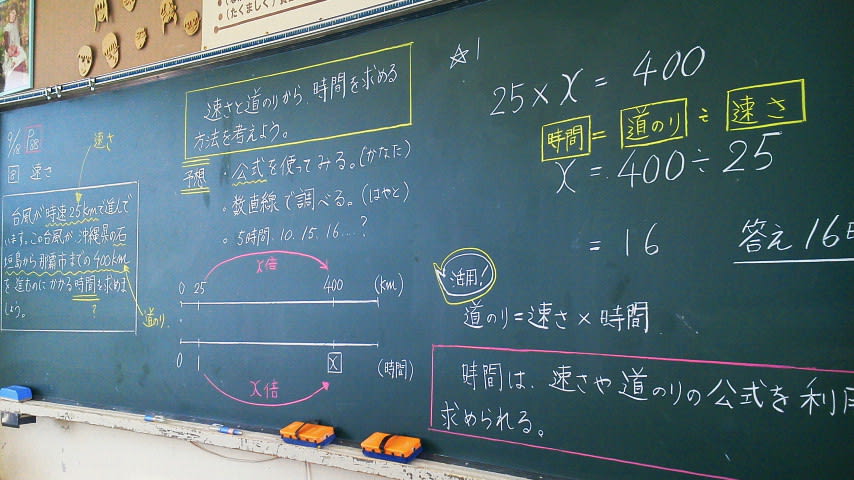初任時代からの親友であり、盟友でもある男と、
酒席で激論を交わした事があります。
とある(大人相手の)研究会における
提案授業の、中身についてです。
その中身
書こうとしましたが、いろいろ考えて
やっぱり書けませんが、一つだけ。
自分は
「授業者さんの心意気」
だけは、やはりすごいと思いました。
みんなが
「いい」
という無難な発想の中で生まれた案は、
それなりだと思います。
ただ、
みんなが
「だめだ」
という荒波の中で敢えて吐き出した案は、
「全然だめ」か「すごい!」
のどちらかなのだと思います。
「全然だめ」でも、
それはそれで、
「何がだめだったのか」を一目瞭然にする意味で、
提案性はあるものだと思います。
そしてそれ以上に、
そんな荒波を超え(ようとし)た提案には、
荒削りでも、参観された人に、
ほんの少しでもなんらかのインスパイアを与えたのではないかなぁと思います。
研究というものは、大体が「ある位置まで」行きついてしまう
ことが多いのですが、
そこを突破するのは、やはり
「そんなのだめだろう?」という
既成概念を壊すことなのではないのかなぁと思っています。
もう10年近く前の事ですが、
いつかあらためてこのことについて、
盟友と話をしてみたいと思っています。
※
たぶん、もめるのでしょうが、
それもまた楽しい(同期の)やりとりです。
酒席で激論を交わした事があります。
とある(大人相手の)研究会における
提案授業の、中身についてです。
その中身
書こうとしましたが、いろいろ考えて
やっぱり書けませんが、一つだけ。
自分は
「授業者さんの心意気」
だけは、やはりすごいと思いました。
みんなが
「いい」
という無難な発想の中で生まれた案は、
それなりだと思います。
ただ、
みんなが
「だめだ」
という荒波の中で敢えて吐き出した案は、
「全然だめ」か「すごい!」
のどちらかなのだと思います。
「全然だめ」でも、
それはそれで、
「何がだめだったのか」を一目瞭然にする意味で、
提案性はあるものだと思います。
そしてそれ以上に、
そんな荒波を超え(ようとし)た提案には、
荒削りでも、参観された人に、
ほんの少しでもなんらかのインスパイアを与えたのではないかなぁと思います。
研究というものは、大体が「ある位置まで」行きついてしまう
ことが多いのですが、
そこを突破するのは、やはり
「そんなのだめだろう?」という
既成概念を壊すことなのではないのかなぁと思っています。
もう10年近く前の事ですが、
いつかあらためてこのことについて、
盟友と話をしてみたいと思っています。
※
たぶん、もめるのでしょうが、
それもまた楽しい(同期の)やりとりです。