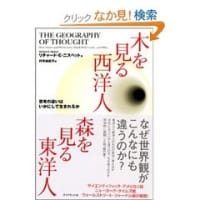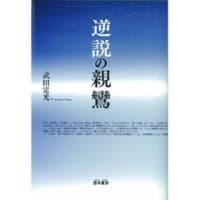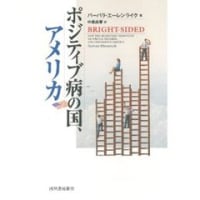●イスラムの怒り 内藤 正典 著
近頃、「これから世界を相手にグローバルに経済活動をする上でイスラム教への理解は不可欠だ」と言った発言が目に付いていた。アメリカ・ヨーロッパ経済の失速は自明、中東・アラブ諸国の台頭は著しい。のは誰でも知っている。が、アメリカ経済が発展する途中に「キリスト教への理解が重要だ」という発言はほとんど目にした事がない。となれば、イスラム教ってどんな宗教??と知りたくなるのは必至である。
イスラム教って何となく禁欲的で過激的なイメージを、勝手に持ってしまっている。と思って本書に出会ったものだからタイトルだけ見て「やっぱり!!」。だってわざわざタイトルに「怒り」だもの。。でも、読んでみて分かった。今私が抱いているようなイスラム教への「イメージ」は、その昔、ヨーロッパが物事を自分たちに有利なように進めるために解釈されたものだということに。
イスラム的道徳は「困ったときは助け合う」であり、「一滴の水は分け合う」なのである。そして、すべてが「神(アッラー)のご意志」なのだ。そして、来世をとてもとても信じている。みんな天国に行きたい。だから、家族の誰かが亡くなったら(とりわけ家族を大切にするので)、その悲しみ様は尋常ではないのだが、少し落ち着くと「ま、神のご意志で命が尽き、来世で楽しく暮らすのだからいいではないか」と拍手でも起きそうな雰囲気に一変するのだそうな。それに、イスラムではお酒はタブーだが、それでも隠れて飲む人がいる。そんな人に「酒なんか飲んで天国に行けるの?」と聞くと「酒は飲んでいても善行も積んでいるから行ける」と言い張るらしい。日本人からすれば「なんと都合のいい人間・・・」となりそうだが、それとこれとは別みたい。あ、そう。結構、楽観的で寛容な宗教だ。そうは言っても、イスラム教徒の一部はテロも起こすし、2006年には人気サッカー選手だったジダンが相手チームの選手に頭突きを喰らわせて退場となった。
やっぱり怒っている・・・
では、彼らは何をされると瞬間湯沸かし器のように突如としてメラメラとした怒りを抱き、それをコントロールできずに暴走させてしまうのか。私たちが何をすると彼らの逆鱗に触れるのか。著書によれば、こうである。
1.弱い者いじめ(とくに、女性・こども・高齢者)
2.聖典コーラン、預言者ムハンマド、神を侮辱、嘲弄、揶揄、不適切なかたちで使用する
3.イスラムに由来する価値観や生活習慣を「遅れている」と侮辱する
この3つをしないように心がければ、突然頭突きをされるようなことはないようだ。と言って、これは人として当然な心がけであろう。1.は良いとして、2.、3.も、人はそれぞれ違う価値観を持っていてそれは優劣はない。その価値観が信仰に関するものであればなおさら他宗教の人間が善悪や優劣を持ち出せる範疇のものではない。日本とて、信仰の自由を謳っているくらいなのだから・・・。
弱い者いじめは、こんなエピソードが紹介されている。
西洋医学を学んで母国で医者をしているトルコ人。びっくりするほどの血糖値でげっそりしている患者を前に、欧米人や日本人は「あなたはこういう不摂生をしたからこうなりました。これからも今の状態を続けるとこうなります。」と原因と結果をこれでもかと説明し、その後の危機感を募らせる。でも、そのトルコ人は「甘い(いい)男からは糖が出るのさ」とニヤリと笑うのだそうだ。弱者を前にして因果関係を説くことは非人間的だとして・・・。んん?その「弱っている者=弱い者」の解釈はどうだろうか。ちょっとこじつけっぽくて微笑ましい。でも、彼らは本気でそう判断するのだ。
本書を読んでいて、心に留まった一説があった。
信仰を持っている人は、ある意味で、ラクに人生を生きてゆくことが出来る。困ったときには、神様に丸投げすることも出来るし、現実的には、宗教指導者の判断を仰ぐことも出来る。信仰をもたないと、何事も自分の頭と理性で処理しなければならない。頼れる神様を失ってしまうと、生きていくことの辛さを味わうことになる。
「神様に丸投げ」という表現が面白いが、これは親鸞のいう「南無阿弥陀仏」と同じであると思う。つまり、自分ではどうにもできないところにすべてを委ねるのだ。どうにもできないもの(人)が神である。親鸞を学び始めて、自分なりにその教えを日々の生活に人生に、どう活かせばよいのかを考えているときに、「自分の力ではどうにもならない。自分(人間)は非力だ」というところから始めれば、ずいぶんと気を楽にして生きられるのではないかと思い至った。現代は、信仰を持つ人が少なく、みんな自分で何とかしなくてはいけないと思い込んでいるから、うつ病が増えたり、やたらと癒しを求める人が増えたのだと思う。「えいっ」と丸投げできる対象がいつも自分の心にあれば、悩むこともない。常に癒されているからわざわざお金を払って癒された気になりに行く必要もないのかもしれない。