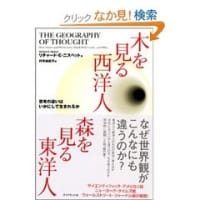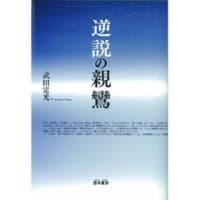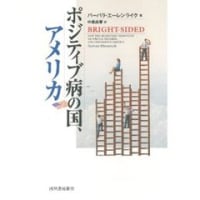舶来屋 幸田 真音 著
「舶来」という単語が好きです。なんとなくワクワクしませんか?
子どもの頃、祖父母の家に長く預けられていたので、私の心には、昭和どころか大正時代のことが色濃く染み込んでいる自覚があります。そんななかで「舶来モノのウイスキー」なんて聞くと、異人さんが作ったお酒が長い期間船に揺られて、はるばるこの小さな島国にやってきたのかと勝手にロマンを感じて、ちょっとじぃんとしたりします。祖父が時計屋さんだったので、舶来モノ・日本製と、よく時計をそんなふうに言い分けていたせいもあるのかもしれません。「これは舶来モノだ」という時の祖父の言葉にはちょっとした憧れが宿り、それでいて「日本製だ」という時には、ちょっとどころではない誇りを、子ども心に感じていたのです。
この本、帯には「エルメス、グッチ、セリーヌを日本に紹介した男の痛快で心にしみる一代記」とありますが、最初の200ページくらいは主人公(80代)が体験した戦争を語るかたちで話が進んでゆきます。そして、復員して戦後の闇市の「ルール」を体験して、そこからビジネスを展開してゆく。そこには様々な紆余曲折やもどかしい思い、商人としての信念、商人であるからこそ得られる喜びがちりばめられています。
語る相手は、偶然喫茶店で居合わせた若い男性とその女友達。男性の方は、家業を継ぐべく「社長」のタマゴとして勉強中、女友達はバリバリ働くキャリアウーマンといったところ。「イマドキの」よろしく、すぐに結果を求めたり、理に適わないこと、損をすることに敢えて手を出すのはナンセンスと考える世代で、その疑問を主人公にぶつけます。そのたびに主人公は、自分の考え方やビジネスの根幹は「人と人との心のつながり、信頼」であるということを丁寧に優しく語ってゆきます。結果、それが今の若い人へのメッセージになっています。
しかし、そのパターンが基本最後まで続くので、正直・・クドい。説教くさいといってもいいかもしれません。ただ、肯定的にみれば主人公は戦後の何もない中から、外貨の制限といった社会の規制もありながら、このすばらしい外国の品々を、ブランドに誇りを持って働いている店員の姿勢を、日本に商品としてあるいは「文化」として広めたい、その情熱をいかに伝えるか。。その対極になるものとして若い人の考え方を利用しただけであって、若い世代への批判がメッセージとは思えなくもありません。
しかし・・若い人の「合いの手」がいつも否定的、主人公の対応が過剰に肯定的。もう少し違う形でその情熱を「浮かび上がらせる」手法はなかったのかと、少し悔やまれます。
ただ、人生は月と同じ。「満ちたら欠ける、欠けたらまた満ちる」が、響きました。満ちたところにあぐらをかかず欠け始めるときに備える、欠けてしまってもくよくよせずに満ち始める楽しみを胸に耐える・・・シンプルだけれど、妙に納得。