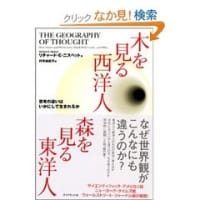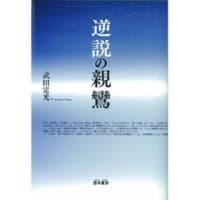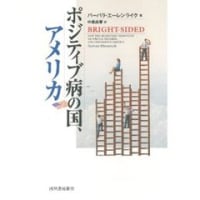●民衆が語る貧困大国 アメリカ スティーヴン・ピムペア 著
人を見た目で判断してはいけないように、本を値段で判断してはいけませんが・・・この本は3800円いたします。出しているのは「明石書店」。と言っても「魚ん棚」ではなく、外神田にある「東京の」出版社です。では、さっそく「東京の」出版社が出している「3800円の」本を読み進めましょう。
世界一といわれる国、アメリカのほころびが噴出している今、この本を手に取れたことを幸運に思います。この本は9章で構成されています。
生きのびる ねぐら 食べる 働く 愛する 尊敬 逃亡 降伏 抵抗
タイトルどおり民衆が赤裸々に語っています。 例えば「食べる」であれば、「○曜日の朝は○時からどこどこの裏口から何メートルのところに息を潜めている者が多くいる。その前夜はパーティがあって「豪華な残飯」にありつけるのをみんな知っているからだ。」という具合に。他にも「教室でぐったりしている少女に声をかけると「大丈夫。おなかが空いているだけだから」と答えた。家でなにか食べてくるように、と言うと「今日はお姉ちゃんが食べる日だから」と返ってきた。」なんていうのもありました。
サブタイトルに「福祉小国」のフレーズがあるのですが、読んでいくうちに決して福祉が整っていないのではなくて、福祉を受ける者に対する社会の扱い方が辛辣だというところに問題があるのではと思うようになりました。福祉を受ける者は常に劣等扱いされ、嫌がらせを受け、人権は与えられません。それをみせれば無料になるというフードチケットを店頭で見せると大声で罵られるか、屈辱以外のなにものでもないような視線を向けられるか・・・。安い日給で厳しい任務に耐え、空腹に耐え、やっと子どもに新しい服を買ってやれた・・・そんな努力も調査員は踏みにじり、「服が買えるなら、福祉手当の支給は打ち切りね」と言い放って帰ってしまう、そんな国のようなのです。女性は言います、「手当は明日の生活には役立つ。でも、本当に欲しいのは「仕事」なのだ」と。
日本でも生活保護受給者には多少の偏見はあることとは思いますが、社会からあからさまに否定されることはないと思います。「かっこ悪いから」と言って受給を進めても拒む人はいても「社会から劣等扱いされ、自由や人間の尊厳を奪われるから」と答える人はいないのではないでしょうか。もちろん、手当で贅沢していては打ち切られるでしょうが、先述の「母親心」への理解はあるように思います。
さらに思い進めると、アメリカという国は、そうして国のバランスを取っている「小さな国」なのではないかということです。日本で言う「」のような。社会が貧民を作り出して、厳しい環境におくことで、そうでない人々の均衡が保たれる、そしてその自覚がない、そんな国ではないかと思います。なぜ、そんな風な均衡の保ち方をするのか・・・各々の中に潜在している「ネガティブ」の投影とみればどうでしょうか。排除したいネガティブを持ち続けるのが辛くて、それに立ち向かうのではなくて、他人に具体的な形をもって投影して、それを痛めつけることで自らのポジティブを護る・・・ちょっと突飛でしょうかね。