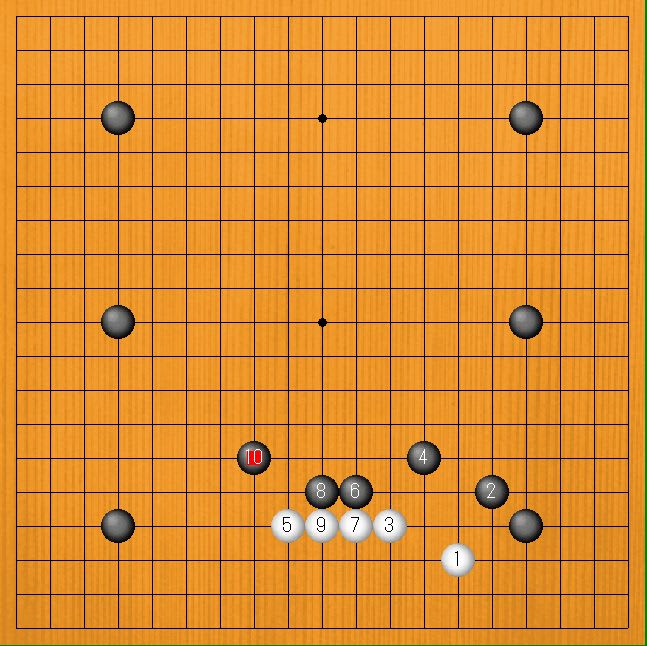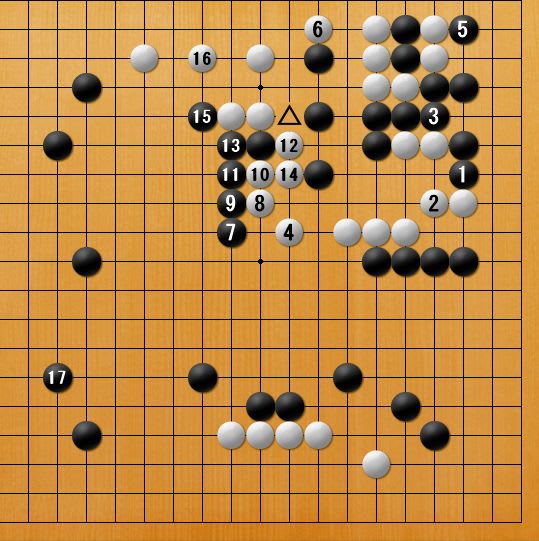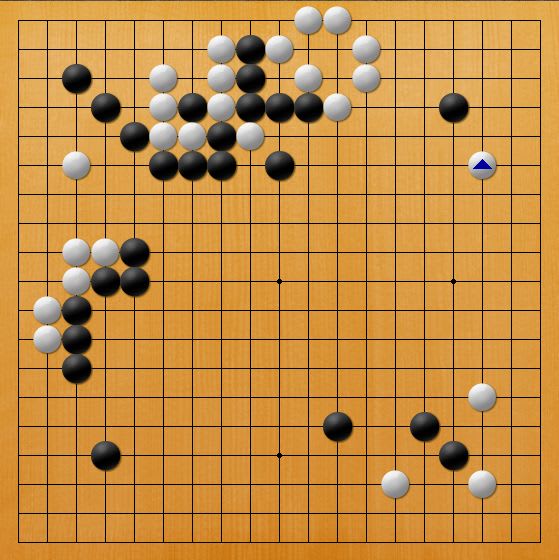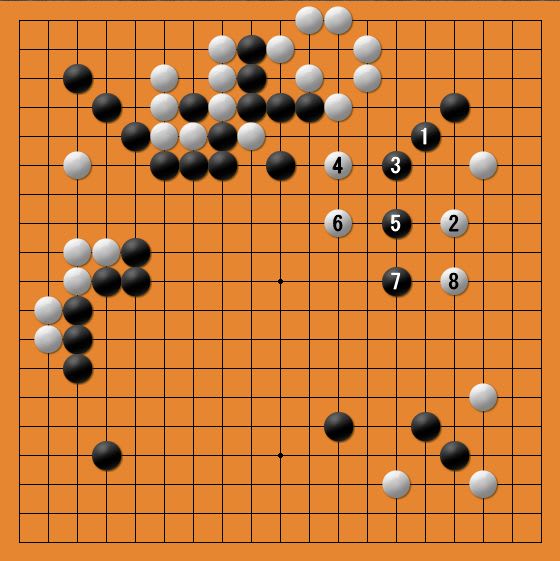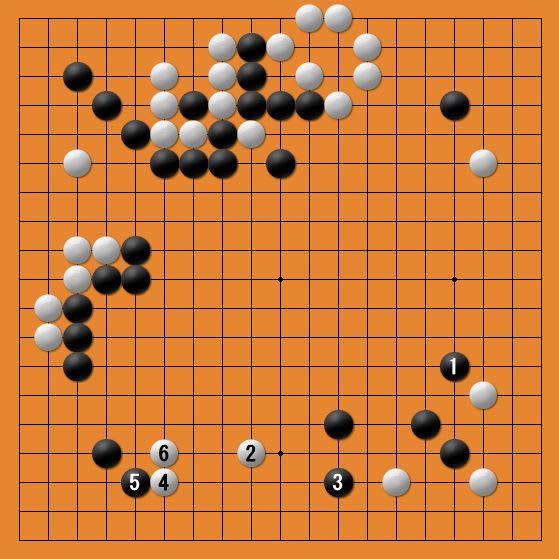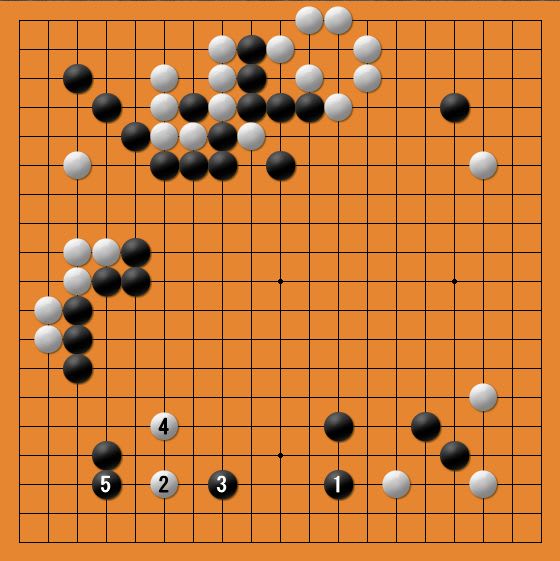本日は私の対局に出来た手筋を問題にします。
といっても難易度は非常に高いので、観賞用と思って頂いて結構です。

白に手番が回りました。
左辺の黒はダメヅマリで味が悪いですが、どう咎めますか?

白1と直接動くのは、これ以上続きません。

こちらも同様です。

これもダメです。

色々な動き方を保留して、単に白1とツケました。
利きが複数ある時は決めないのが手筋です。
実はこれで黒は困っています。

黒1なら白2、4です。
攻め合い白勝ちです。

黒1ならば白2が良い手です。
黒はダメヅマリに泣きます。

実戦は黒1と我慢しましたが、白は黒1子を切り離して成功です。
今回題材にした形は難しいものですが、ダメヅマリの恐ろしさはプロもアマも変わりません。
皆様もダメヅマリにはご用心ください!
といっても難易度は非常に高いので、観賞用と思って頂いて結構です。

白に手番が回りました。
左辺の黒はダメヅマリで味が悪いですが、どう咎めますか?

白1と直接動くのは、これ以上続きません。

こちらも同様です。

これもダメです。

色々な動き方を保留して、単に白1とツケました。
利きが複数ある時は決めないのが手筋です。
実はこれで黒は困っています。

黒1なら白2、4です。
攻め合い白勝ちです。

黒1ならば白2が良い手です。
黒はダメヅマリに泣きます。

実戦は黒1と我慢しましたが、白は黒1子を切り離して成功です。
今回題材にした形は難しいものですが、ダメヅマリの恐ろしさはプロもアマも変わりません。
皆様もダメヅマリにはご用心ください!