春めいた日差しで暖かく 着物日和ですね
暖かいのは嬉しいけど その分花粉が・・・・
鈴木和美さんの帯では フルーツ柄が可愛い、と人気ですし
季節ならではの桜や藤、コスモスなどのお花も綺麗~~と言われます。
中でも 足を止めて下さるのが 正倉院写しの帯。

何の樹だか花だか分からないけど 惹かれる、と好評です。
やはり 正倉院の時代から続く 重みというか格が感じられるのでしょうか。
正倉院、といえば 奈良です。
奈良と言えば・・・鹿?柿の葉寿司??
修学旅行以外でも 何度か行きましたけど
京都とは違ういにしえを感じます。
三輪のお山の辺りが好きです。古墳とか古代石とか。
ロマンですよね~~
奈良にお住まいの方がうらやましい位です。
ところで 正倉院。
元々奈良・平安時代の中央・地方の官庁や大寺には重要物品を納める倉庫的なものを
正倉と呼び、正倉が幾棟も集まっている一廓が正倉院と呼ばれたのです。
長い年月で現存するのは,東大寺正倉院内の正倉一棟だけになってしまいました。
様々な宝物が収められていますが
その中で染織品を 正倉院裂、と呼びます。
絹や麻が多く ウールや木綿が少しあるそうです。
織は平織から綾織、羅、経錦、緯錦、刺繍などの技法で
時代に従って 単調な模様から唐草や連珠、オリエンタル色の濃いものになります。
染も草木染では 茜・紅・蘇芳・紫草、黄蘗・刈安・櫨、藍などが用いられていて
纐纈や頬纈などの防染技術を持っていたことが分かります。
天平の三纈、と呼ばれる染についでは いづれ書きたいと思います
(昔書いたんですけど もうどこに行ったのやら・・・2世代位前のHPで書いたような?)
当時 大陸から入ってきた貴重な布と 国内最高技術を使った布が
今も保存されているのは 世界的にもとても貴重なものです。
奈良が戦争による被害が比較的少なかったのは ありがたいことでした。
正倉院裂は 有職模様にも繋がるもので
天平時代の文様が最も多いですが、飛鳥、白鳳時代の文様も含まれます。
正倉院はシルクロードの終着駅ともいわれ、
ローマ、ペルシア、インド、西域、中国など西方諸国の影響を受けた文様が多く伝えられています。
文様は多種多様で、大別すると、
鳳凰、花喰鳥、くじゃく、おうむ、おしどり、鶴、鴨、獅子、虎、羊、象、
鹿、馬、竜、きりん、うさぎ、亀などの動物文様。
唐草、唐花、牡丹、ぶどう、宝相華、蓮などの植物文様、
連珠、円文、亀甲、石畳、菱形などの幾何模様、
雲、月、日、星、海、山などの自然現象などに分類されます。

幾何学文様である 太子間道

樹下獅子紋

正倉院華紋。
それぞれ 宝物そのまま、ではありませんが
正倉院に遺された裂から 写された文様です。
正倉院がなければ 着物の世界は かなり味気ないものだったことでしょう。
茶道なんか 正倉院裂に囲まれてるようなものですしね。
また 奈良に行きたくなりました。
奈良には 櫻子ちゃん、ってお名前の可愛い赤ちゃん(お客様のお孫さん)が
いることですし^^
奈良の皆様 いつも ブログをお読みくださりありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします
ランキングに参加しています。今日も1ポチっと、どうぞよろしくお願いします。
=== 横浜元町・普段着物のじざいや 紬と木綿が得意です ====










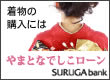 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン



