これをアップする頃には逆転してるかも!?
上の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして
暑さ寒さも彼岸まで、と言いますけど
彼岸花がもう咲いていました!
彼岸花は毎年 ちゃんとお彼岸に咲くんですけどねー
今年は植物たちも なんだか変な具合です。
なかなか難しい問題です
生紬のシャリ感や 絹縮の柔らかなサラサラ感が良いのですが
比較的値ごろで手に入りやすくお勧めなのが
新潟産の本塩沢です。
こりらが本塩沢。

こちらが白鷹お召です。

どちらも表面に縮緬皺、とも呼ばれるシボがあるのがお分かりいただけると思います。
シボの角?が 本塩沢の方が尖っていて 白鷹お召は丸い感じです。
白鷹お召の特徴の1つに 板締め絣、という技法があります。
板締め絞り、ではありません。
絣を板締めで作っているのは現在は 白鷹お召のみ、それも2軒しか残ってません。
以前は 群馬県の高崎や桐生の銘仙やお召にも板締めの技法が使われていたようですが
現在は廃れてしまいました。
板締め、というからには板で締め付ける訳ですが
板は、絣の文様の設計図に合わせて、数ミリ単位で溝が掘られている板染め専用のものです。
ただし、近年は複雑な文様を彫ることのできる板大工がいなくなったため、
新たな文様の板製作は難しくなりました。
その板の一枚ずつ板に糸を巻きつけながら、板を重ねていきます。
この時、糸の張り具合が変わってしまうと、織り上がった時に柄がずれてしまいますので
細心の注意をはらって糸を巻き付け行きます。糸を巻き付けたら重ねていきます。
柄により、30~50枚の板を重ね、上下に押し木を当てて仮締めをして、
板溝の微妙なずれを木ベラで合わせていきます。
この時、溝をきちんと合わせないと、糸に絣文様がつきません。
板を重ねて上下を締めた状態です。
彫られた溝が重なって柄を構成しています。これは経涌。
横から見ると
白い糸が板の幅分脇に出ていますので ここは絣にならず、
白鷹お召の絣柄の特徴である反耳の輪っかになります。
この耳の輪っかは 仕立てる時には切り落とします。
単衣で仕立てると透けて見えてしまいますし・・・
締めあげた板は 上から熱い染料を何度も掛けまわして染め上げます。
1時間ほど染料をかけ続けます。
この工程を「ぶっかけ染」と言いますが
拝見した佐藤さんは ぶっかけたりしないで丁寧に丁寧に掛けてますよ、と
おっしゃってました。
その後板を外すと
溝の部分に染料がしみこみ、溝の無いところは板で絞められて染まらない絣糸が出来上がります。
この後 経糸と緯糸として機にかけられ
お召なので 強撚糸を交互に織り込みながら なおかつ柄合わせをしつつ織り上げられます。
細かい作業なので 1日に織り進めるのは20~30センチだそうです。
これが白鷹お召しです。
残り2軒の織元では 白鷹お召以外にも 白鷹紬や帯を織っていて
佐藤さんの工房では 白鷹お召を織ることが出来るのは高齢の織子さん
一人だそうです。
後継者はいないので この方が織れなくなったらおしまい。
織元としては存続していても 商品の中から白鷹お召が無くなる日は遠くないのです。
ぜひ触り比べにいらしてください











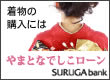 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン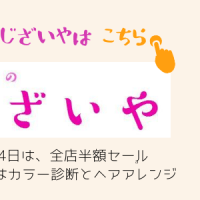











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます