秋になったんだなぁと思いますね。
昨日ご来店されたお客様とお話ししたのですが
東京と横浜では 着物姿が違う気がるす・・と。
鋭いです。
関西と関東ほどの差ではありませんが
江戸と港町横浜の違いは 色や着方に表れています。
江戸は昔から 小股の切れ上がった、と言われるように
粋でキリっとした風情が良しとされ
垢ぬけないのは野暮と言われます。
なので 着方は 衣紋を抜き加減でしっかり巻き付ける感じ。
色目はアースカラー基調で引き算のコーディネイトが主流です。
横浜は港町特有のおおらかに開けた雰囲気があり
洋風なものを取り込みやすい下地があるせいか
色数が多く華やかな雰囲気が多いです。
。。。というのは 私の主観ですが。
関東と関西にははっきりとした違いがあります。
関東と関西の違いは
帯を着付ける時に 関東巻き(時計回り)と
関西巻き(逆時計回り)があることが知られていますし
お襦袢の仕立て方にも
関西仕立て(衽と別衿付)と
関東仕立て(衽無し通し衿)があることも有名です。
今では お襦袢は関西仕立てが主流になっています。
仕立てや着付けの方法だけでなく
寸法の採りかたにも 関東と関西では違いがあります。
同じ3サイズから割り出した場合
関東の店と 関西の店では 微妙に違いが出てきます。
それは 着姿の好みの差でもあります。
関東は江戸前に代表されるように
キリっと小股の切れ上がった タイトな着姿が粋(いき)とされます。
一方関西では おっとりとした ゆるやかなラインが上品とされています。
なので 関東の採寸は 体にフィットしてお尻が小さく見えて
裾すぼまりになるよう割り出されます。
衽を裾に向かって狭くする仕立てや 抱き幅を詰める仕立てがあり
同じ3サイズなら 後ろ幅は関東の方が1,2分狭めです。
対して関西では 後ろ幅がゆったりと割り出され
前幅も 衽を狭ばめることのない通し仕立てが多く
それは お茶を習っている方が多いせいでもあるかと思います。
お茶のお稽古をされる方は にじった時に乱れないよう
前幅を広めにされます。
小物や草履、足袋にいたるまで
関東は細め、密着型が多く
関西は ゆったり余裕のあるものが好まれます。
今は 人間の移動も簡単になり 関東、関西の差は薄くなっています。
それでも DNAに組み込まれているのか
幼い頃からそういった物に囲まれているので馴染んでいるのか
やはり 好みの違いははっきりとあるようです。
ネットが普及して 地域による差は少なくなってきていますが
ネットでお住まいの地域とは違う店に仕立てを依頼するときには
割り出しではなく 今お召の着物の寸法を伝えたほうが
思っている寸法に仕立てあがってくると思います。
今日の着物はこちら。

山崎さんの紫根染絞り 経涌。帯は首里花織。
反物を縦に畳んで 縫い締めの絞りをするのですが
この13メートルの生地をまっすぐに小さく畳むのがとにかく一苦労だそうです。
畳まれた内側は染料が入り込みにくく、ぼかしたような太いラインになり
外側はしっかり染料がしみ込んで濃く染まります。
その差がかえって面白い味わいになっています。

色が再現できていません~~~
ぜひ実物をご覧になりにいらしてください
最後までお読み頂きありがとうございます。
着物屋さんのブログの集まった、ランキングページへ飛びます。
ただいま、じざいや一位継続中!
ランキングページから、またこのブログに戻ってきてくれるとポイントが入ります。
応援クリック、よろしくお願いします。










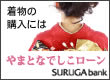 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン
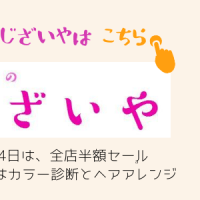











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます