
〈自民党の杉田水脈(みお)衆院議員(比例中国ブロック)が月刊誌への寄稿で、同性カップルを念頭に「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」と行政による支援を疑問視した。人権意識を欠いた記述だと批判が上がっている〉
*朝日新聞デジタル:同性カップルは「生産性なし」 杉田水脈氏の寄稿に批判
→https://www.asahi.com/articles/ASL7R4SB9L7RUTFK00L.html?iref=pc_ss_date
「何でわざわざ、そんな危険な言葉を使うかなあ」というのが最初の印象でした。ご本人的には、ちょっと刺激的に言ってみようくらいのつもりだったかもしれません。あえて「 」を付けているわけですしね。
で、その結果がこの騒ぎ。杉田さんも驚いていることでしょうけど、それより何より、一番迷惑しているのは、当の「LGBT層=セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)」の皆さんではないかと思います。
件の記事(というか杉田水脈さんという人)について、懸命に擁護する人から猛烈に非難する人まで、ま「みんなちがって、みんないい」んですけど、意見を言うなら、少なくとも自分で全文を読むか、あるいはせめて、記事のタイトル(=趣旨)が〈「LGBT」支援の度が過ぎる〉であり、〈日本を不幸にする「朝日新聞」〉という特集(→朝日批判)内の一本だったということくらいは押さえておかないとね、とは思います。

*新潮社:『新潮45』2018 8月号
→http://www.shinchosha.co.jp/shincho45/backnumber/20180718/
で、ワタクシ的に全文読んだ上での感想を言えば「別に、大したことは言ってないなあ」です。「度が過ぎる」かどうかも、つまりは主観、というか相対性理論ですから。
ただ「生産性」という言葉はもちろん、それを含む段落自体、全体の趣旨に照らして、はたして書く必要があったのかなという疑問もあります。
前段落末尾の、
〈「生きづらさ」を行政が解決してあげることが悪いとは言いません。しかし、行政が動くということは税金を使うということです〉
を受けての部分です。
〈例えば、子育て支援や子供ができないカップルへの不妊治療に税金を使うというのであれば、少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります。しかし、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり「生産性」がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか。にもかかわらず、行政がLGBTに関する条例や要綱を発表するたびにもてはやすマスコミがいるから、政治家が人気とり政策になると勘違いしてしまうのです〉(『新潮45』 2018 8月号 P.58)
これ、ちょっと言葉が足りないと思いませんか?
不妊治療・少子化対策に特化した話をしているように読めるわけですけど、LGBTのカップルに対して不妊治療の支援をしようという主張がどこかにあるんでしょうか? もし、第三者の卵子提供、精子提供、代理出産等に関する支援を指しているとしたら、それはそれなりに「生産性」のある話になってしまいますし・・・いや、いずれにしても、支援する・しない、税金を使う・使わないの例として、あまり好ましくないんじゃないかって気がするんですけど。
ついでに言えば、記事後半の〈LGBとTを一緒にするな〉に関しても、もともと「LGB-T」だったというのは確かにそうなんだろうけれども、現状「レズビアン(女性同性愛者)+ゲイ(男性同性愛者)+バイセクシュアル(両性愛者)+トランスジェンダー(性同一性障がいなど)」という単純足し算ではなく、「セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)の総称のひとつ」として使われているわけで、さらに言えば、「T」は障害だけれども「LGB」は性的嗜好という割り切り方も、ちょっと違う気がします。
おっと、随分批判めいたことを書いてしまいましたが、ワタクシ、杉田さんの仕事ぶりは買っている方でございますよ。民間人としての国連での活動もですけど、国会議員になってからの委員会質問なんかでも、頑張ってるなと思ってます。このブログでも取り上げたことありますからね。
*#243 (遅れ馳せながら)これが、いわゆる従軍慰安婦問題に関する「政府見解」です。
→https://blog.goo.ne.jp/kawai_yoshinori/e/a0c572ff37f43cbd95c6d437cc3bb73b
それだけに、今回のこの「政治家として、やや迂闊であり雑だった」言葉遣いを残念に思ってます。半端に反論して、でも結局(ビミョーに言い訳しつつ)引っ込めちゃったという対応も感心しないし。

→https://twitter.com/miosugita/status/1021213480571973633
さて、話は飛びますが(というか、ここからがワタクシ的にメインなんですが)、今年の集英社文庫「ナツイチ」に『にじいろガーデン』(小川糸)という小説がラインナップされてます。

→http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-745582-3&mode=1
カバー裏の惹句に・・・
夫との関係に悩む泉は、ある日女子高生の飛び込み自殺を止める。事情を聞いているはずが、知らず知らずのうちに自らの身の上話をしていた泉。やがて二人は魅かれ合い、お互いをかけがえのない存在だと知る。家族として共に歩むことを決意し、理想の地を求めて山里へ移り住んだタカシマ家は、母二人、子二人での生活を始めて―――。
たくさんの喜びを紡いだ一家の軌跡を描く、愛と再生の感動長編。
とあります。
ぶっちゃけ、レズビアン・マザーのお話なんですけど、ワタクシ、そうとは思わずに買ってしまいまして。「え〜、そっち行っちゃうの〜」なんて思いつつ読み進めていくと、いつの間にやら女同士二人で子育てするとか、息子と娘はそれぞれ片方の親としか血がつながっていないとか、そういうことは置いといて、真に「家族の物語」として感情移入してしまうというね。たぶん現実にセクシュアル・マイノリティと知り合った時、そうなるんだろうなという疑似体験したような気分になる小説でした。
以下、その中から娘に「だったらさ、ママたちの役割って、何なんだろうね?」と問われた泉(事実母)のセリフです。チョコちゃんというのは、もうひとりの母(実母)千代子のこと。
「それを突きつけられるのが、昔はすごく嫌だった」
「子孫を残す、ってことが生物的な意味での最大の役割だとしたら、うちらは、はなからそれができないんだもの。役割って言葉を聞くたびに、ろくでなしって言われている気分になって落ち込んじゃったの。でも今は、なんかちょっと違うよね」
「役割って言葉が、以前は否定的な響きにしか聞こえなかったけど、最近は、すごく肯定的に感じるようになったの。使命って言葉のニュアンスに近いのかしら? 同性愛者ってひとくくりにしちゃうと難しいけど、少なくともおチョコちゃんに与えられた使命って考えると、それはね、たぶん、いたわることだと思うの。うちらは、世の中のはじっこで生きているから、そういう少数派の人たちの気持ちが理解できる。だからその分、優しくなれるの。いろんな弱い立場の人の気持ちが、わかるから」
もうひとつ、上のセリフよりもずっと前のシーンですけど、こんなのもありました。
泉「そんなに自分たちの存在を主張して、どうするの?」
千代子「でも、こういう人間も世の中にはいるんだ、ってことをちゃんと知らせなきゃ、いつまで経っても変わらない。どんどん大多数と同じ色に塗られるんだよ。大声出さなきゃ、聞いてもらえないもの」
さて、どうしたものでしょうか?










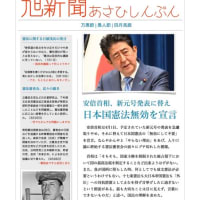
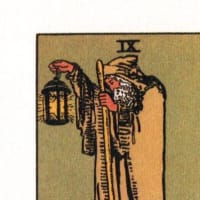





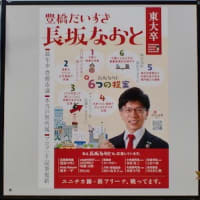
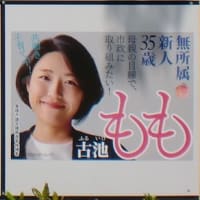

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます