天体望遠鏡:MAK127SP[1-4]にイメージセンサSV305[5-8]を取り付けて、木星[9]、土星[10]、火星[11]の直焦点撮影を試みた[23]。
(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要
MAK127SPにイメージセンサSV305を取り付け、ポルタ経緯台に搭載し、木星、土星、火星の撮影を行った[23]。
SV305からの映像信号は、SharpCap3.2[12]を用い、WindowsノートPCに取り込んだ。
天体の望遠鏡の視野への導入は、付属のファインダ(レッド・ドット式)を用いてアライメントし、ノートPCの画面に天体が写ることを確認することで行った。
木星、土星、火星の撮影は、ノートPCの液晶画面を見ながらピントを合わせ、SharpCap3.2のキャプチャ機能を用いてaviファイルを取り込んだ。
撮影時間は、木星、土星、火星で、それぞれ約20秒(約600フレーム)である。
取り込んだaviファイルは、RegiStax6[13]を用いて、スタック処理、および、Wavelet処理を行った[14]。
(2)木星の撮影結果

2020-08-07 22:05 木星(等級:-2.7、視半径:23.4")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 13.7ms, WB(B=235 G=100 R=131), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍

※ImageMagick[16]でトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"[17]
・イメージセンサ分解能:0.80"相当[17]
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[18])
(3)土星の撮影結果
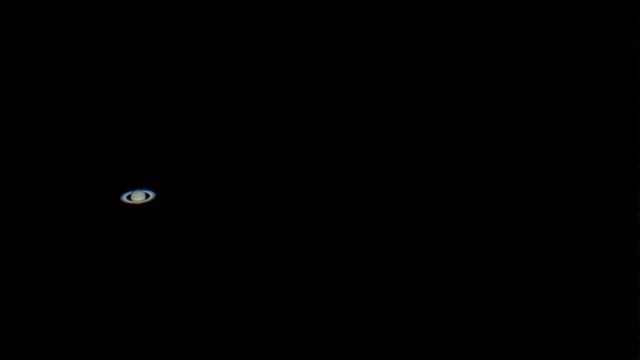
2020-08-07 22:45 土星(等級:0.2、視半径:9.2")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 54.7ms, WB(B=235 G=100 R=131), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍相当

※ImageMagickでトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"
・イメージセンサ分解能:0.80"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm)
(4)火星の撮影結果

2020-08-08 00:54 火星(等級:-1.2、視半径:7.7")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 4.1ms, WB(B=233 G=100 R=135), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍相当

※ImageMagickでトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"
・イメージセンサ分解能:0.80"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm)
(5)まとめ
MAK127SPにSV305を取り付け、木星、土星、火星の直焦点撮影を行った。
木星の撮影結果では、木星の縞模様やガリレオ衛星[19-20]を確認できた。
土星の撮影結果では、カッシーニの間隙[21]を確認できた。
火星の撮影結果では、火星の模様や南極冠[22]を確認できた。
今回、使用したソフトShrapCap3.2、RegStax6の優れた機能に改めて感動した。
一方で、画像処理に用いたWavelet処理パラメータは、今回、画像を見ながら主観的に設定したが、そのパラメータが適切かどうか、あるいは、他により良いパラメータがあるかどうかは、依然として勉強不足でよくわからない。
この辺は、今後の課題である。
参考文献:
(1)Maksutov Cassegrains
(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia
(3)Sky-Watcher-Wikipedia
(4)Sky-Watcher Global Website
(5)SV305デジアイピースの使用方法
(6)SVBONY SV305 取扱説明書
(7)Svbony SV305 Camera FAQ
(8)SVBONY
(9)木星-Wikipedia
(10)土星-Wikipedia
(11)火星-Wikipedia
(12)SharpCap
(13)RegiStax6
(14)RegiStax-Wikipedia
(15)今日のほしぞら
(16)ImageMagick
(17)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(18)IMX290NQV
(19)ガリレオ衛星-Wikipedia
(20)Galilean Moons of Jupiter
(21)カッシーニの間隙-Wikipedai
(22)極冠-Wikipedia
(23)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影-goo blog
(24)新規購入したCMOSカメラで木星と土星を試写しました
(25)8月6日夜半、梅雨明けの火星
(26)”2500倍”で火星を覗いてみた
(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要
MAK127SPにイメージセンサSV305を取り付け、ポルタ経緯台に搭載し、木星、土星、火星の撮影を行った[23]。
SV305からの映像信号は、SharpCap3.2[12]を用い、WindowsノートPCに取り込んだ。
天体の望遠鏡の視野への導入は、付属のファインダ(レッド・ドット式)を用いてアライメントし、ノートPCの画面に天体が写ることを確認することで行った。
木星、土星、火星の撮影は、ノートPCの液晶画面を見ながらピントを合わせ、SharpCap3.2のキャプチャ機能を用いてaviファイルを取り込んだ。
撮影時間は、木星、土星、火星で、それぞれ約20秒(約600フレーム)である。
取り込んだaviファイルは、RegiStax6[13]を用いて、スタック処理、および、Wavelet処理を行った[14]。
(2)木星の撮影結果

2020-08-07 22:05 木星(等級:-2.7、視半径:23.4")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 13.7ms, WB(B=235 G=100 R=131), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍

※ImageMagick[16]でトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"[17]
・イメージセンサ分解能:0.80"相当[17]
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[18])
(3)土星の撮影結果
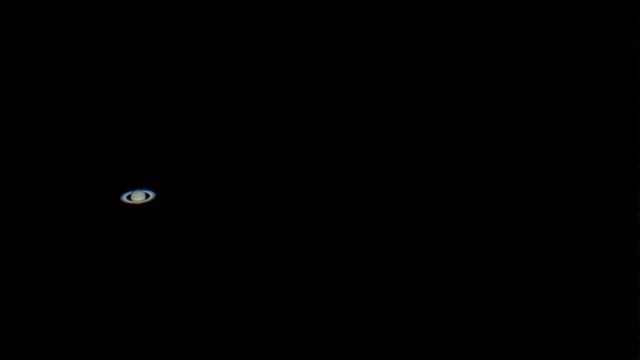
2020-08-07 22:45 土星(等級:0.2、視半径:9.2")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 54.7ms, WB(B=235 G=100 R=131), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍相当

※ImageMagickでトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"
・イメージセンサ分解能:0.80"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm)
(4)火星の撮影結果

2020-08-08 00:54 火星(等級:-1.2、視半径:7.7")[15]
SV305, MAK127SP 1500mm F12
SV305, Gain 30, 露出 4.1ms, WB(B=233 G=100 R=135), 1920x1080, RGB24, 30fps
※RegiStax6でスタック処理、および、Wavelet処理実施
※望遠倍率:400倍相当

※ImageMagickでトリミング

※RegiStax6でのWavelet処理パラメータ例
・対物レンズ口径:127mm
・ドーズの分解能:0.91"
・イメージセンサ分解能:0.80"相当
(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm)
(5)まとめ
MAK127SPにSV305を取り付け、木星、土星、火星の直焦点撮影を行った。
木星の撮影結果では、木星の縞模様やガリレオ衛星[19-20]を確認できた。
土星の撮影結果では、カッシーニの間隙[21]を確認できた。
火星の撮影結果では、火星の模様や南極冠[22]を確認できた。
今回、使用したソフトShrapCap3.2、RegStax6の優れた機能に改めて感動した。
一方で、画像処理に用いたWavelet処理パラメータは、今回、画像を見ながら主観的に設定したが、そのパラメータが適切かどうか、あるいは、他により良いパラメータがあるかどうかは、依然として勉強不足でよくわからない。
この辺は、今後の課題である。
参考文献:
(1)Maksutov Cassegrains
(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia
(3)Sky-Watcher-Wikipedia
(4)Sky-Watcher Global Website
(5)SV305デジアイピースの使用方法
(6)SVBONY SV305 取扱説明書
(7)Svbony SV305 Camera FAQ
(8)SVBONY
(9)木星-Wikipedia
(10)土星-Wikipedia
(11)火星-Wikipedia
(12)SharpCap
(13)RegiStax6
(14)RegiStax-Wikipedia
(15)今日のほしぞら
(16)ImageMagick
(17)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(18)IMX290NQV
(19)ガリレオ衛星-Wikipedia
(20)Galilean Moons of Jupiter
(21)カッシーニの間隙-Wikipedai
(22)極冠-Wikipedia
(23)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影-goo blog
(24)新規購入したCMOSカメラで木星と土星を試写しました
(25)8月6日夜半、梅雨明けの火星
(26)”2500倍”で火星を覗いてみた

















