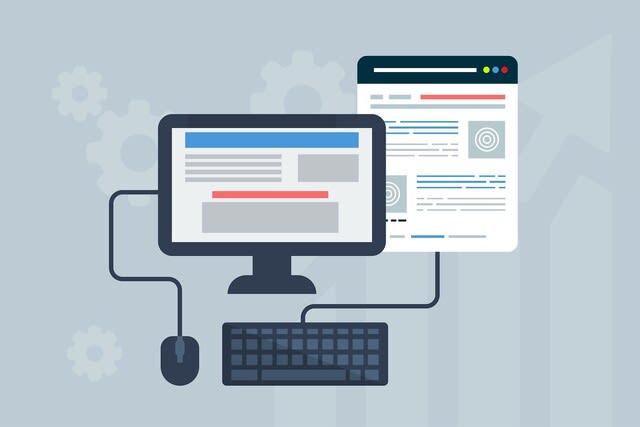私たちが紙面上やインターネット上などで目にするニュース記事の裏には、内容や構成を考える編集者が存在する。作田裕史さんは、ニュースサイト「AERA dot.(アエラドット)」の副編集長。ニュースネット委員会が以前取り上げた、神戸大学国際文化学研究推進インスティテュートの協力研究員である植朗子さんがアエラドットで連載している人気コラム、『鬼滅の刃』考察記事の編集も担当している。(記事は
こちら)【前編】では作田さんに、編集者の仕事や、ウェブメディアと紙メディアとの違いについて話を聞いた。
記者)作田さんのキャリアについて教えてください。
作田)私はニュースサイト「AERA dot.」の記者兼編集者なのですが、最初は自分が記者になるとは全く思っていませんでした。新卒のときは、教育系の会社に就職して小学生向けの教材の編集をしていたのですが、自分には合わないなと感じていました。パワポで資料をつくって社内でプレゼンするといった仕事が多かったのですが、もっと社外の人と会って経験を積みたいという思いがありました。そこで、その会社を3年半で退社し、中堅出版社に入りました。そこで週刊誌の記者を初めて経験し、書籍編集者の仕事も少しかじりました。2010年に朝日新聞出版に転職して、『週刊朝日』や『AERA』 の記者、『アサヒカメラ』の編集者をへて、今の「AERA dot.」には3年目になります。キャリアとしては、週刊誌記者が一番長いことになります。
記者)副編集長の仕事にはどのようなものがありますか。
作田)8割が他の執筆者の記事の編集、1割が自分の記事の執筆、残り1割がサイトの全体的な分析です。企画が部員から毎週3つぐらい上がってくるので、週1回の会議で企画を割りふります。こういったことから時間に制約があるので、自分で記事を書くことはなかなかできないのですが、自分にしかできない内容の場合は、私が担当することもあります。
記者)自分にしかできない内容とは、具体的にどのような内容のものですか。
作田)取材相手との距離感が難しかったり、人脈を他の人に紹介できなかったりする場合です。たとえば、芸能界やアウトロー系の取材ではどこまで踏み込むかが難しく、相手との関係性を冷静に見極めながら取材する必要があるので、他の人に任せるよりも自分でやることの方が多いです。
紙記事は分量に制限 ウェブ記事は記事単体の見せ方がポイント
記者)ウェブ記事と紙記事の違いは何ですか。
作田)最も違うのは、紙は文字数が限られており、書ける分量が非常に少ないことです。ですので、企画の通りやすさは、紙の方が厳しくなります。かつ、明確な締切があるのもウェブと違う点です。また、紙は定期的な購読者がいるので、雑誌のカラーに合わせて記事を作りますが、ウェブ記事では「AERA dot.だから記事を読もう」という人はまだ少数派です。そのため記事単体の訴求力を高めることに労力をさくことになります。
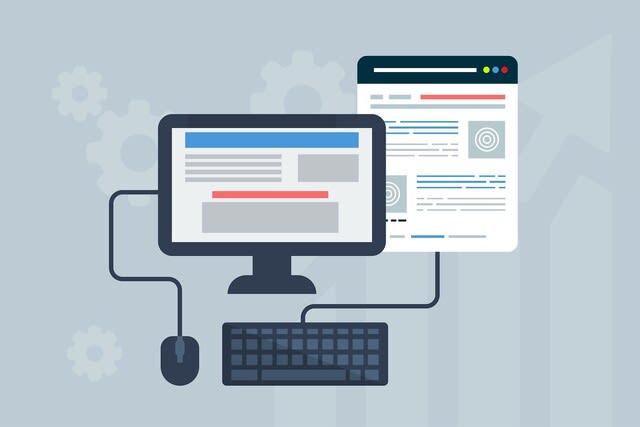 ウェブ記事は800字くらいが読みやすい?
ウェブ記事は800字くらいが読みやすい?
記者)ウェブ記事は字数に制限がありませんが、分量で気をつけている事はありますか?
作田)あまり長すぎるものは最後まで読まれない傾向にあります。例えば、Yahoo! の記事は1ページ800字以上になると改ページができる設定になっています。個人的にも、1ページあたりの分量は800~1000字くらいが読みやすいと思います。
作田)さらに、記事を何ページにするのかも大切な要素です。「速報のニュースだから、2ページくらいかな」とか、「もう少し詳しい分析記事なら、4~5ページまでいけるかな」というように、内容と分量を考えています。一般的に3000字以上あると、読者が相当好きなテーマでないとウェブで集中して読み切るのは厳しいと思います。2000~3000字が適量であると思います。
紙記事は、読者とリテラシーが共有できる
記事)字数についてもかなり違うのですね。では、ウェブ記事と紙記事で、それぞれ一番重きを置いていることは何ですか。
作田)ウェブと紙とでは、届く人が違います。紙は、雑誌なり新聞なりというパッケージがあり、情報が欲しい人たちは、能動的に行動して、お金を出してそれらを買います。そのため、出版する側は「この雑誌を買う人は、これぐらいのリテラシーがあるだろう、こういう価値観をもっているだろう」とある程度想像できます。つまり、出版社と読者でリテラシーの土台が共有できているのです。ですから、そこに沿って記事を書いて、文章のレベルもそこに合わせます。
 ウェブ記事は、どこからアクセスされるか見極めて発信
ウェブ記事は、どこからアクセスされるか見極めて発信
作田)一方、ウェブの場合は読者のリテラシーが一定ではありません。どの人たちにどういうふうに読んでほしいのか考えないと、よい記事でも読まれなかったり、読者にとって、全くとんちんかんなものになったりすることがあります。もちろんウェブの形もポータルサイトの形もどんどん変わると思うのですが、今は「Yahoo! ニュース」「LINEニュース」などのポータルサイトが主流であるため、それら最初のアクセスポイントに最適化したものを出していかないと読んでもらえません。
今後のウェブ記事、紙記事の在り方
記者)現在、雑誌を購読しているのは、どのような年齢層なのでしょうか。
作田)雑誌の購読者は年齢層が上がってきています。特に週刊誌は、昔は20代の人でも読んでいましたが、今はほぼ30代まで読んでいないと思います。若くても40代以降が購読者層です。老舗の週刊誌なんかもほとんど読者層は60代以上で、特集では「死に方」や「相続」ばかりというのが現状です。そうした状況なので、全般的に紙の雑誌は部数的には相当厳しい。雑誌業界の人はみんな危機感を持っていると思います。
ウェブ記事有料化の難しさ
記者)最近ウェブ記事がどんどん増えてきているように感じます。中には有料の記事も出てきていますが、今後ウェブ記事はどうなっていくと思いますか。
作田)ウェブ記事が単体で有料化できるかというと、まだ難しいと思います。例えばいわゆる芸能記事で、芸能人の写真など、そこでしか見られないものを読者が買ってでも見たいことはあると思います。ただ、そうではなくて、記事を読みたい、情報が欲しいというだけで、記事を買うというのは、まだかなりハードルが高いと思います。なぜなら、ほかの記事やメディアが後追いするからです。例えば芸能記事では、スポーツ新聞、ワイドショーなどはある記事で出た情報を重ねて報じます。それを見れば、大体元の記事を見なくても、何が書いてあるか分かってしまいますよね。その構造が変わらない限り、読者が記事に課金するのは難しいと思います。間口が広い芸能記事でさえ厳しいので、より専門的なものについて、「もっと深く知りたいからお金を払う」という人はほとんどいないと思います。
読者のターゲットを絞って、会員制にする方法も
作田)例えばビジネス誌である『東洋経済』や『プレジデント』は、ビジネスマンにターゲットを絞ってメルマガなどのサービスを作り、新たな会員をクロージングしています。ウェブ記事を有料化できるとすれば、そのようにある程度ブランディングをして、顧客をクロージングするという方法はあると思います。ただそれ自体はまだ大きなマーケットではないので、マネタイズするには限界があります。また、ブランディングは長い時間をかけてできるものなので、そこが難しい部分でもあります。
【前編】では紙メディアとウェブメディアとの違いについて話を聞いた。【後編】では、作田さんの編集者としての仕事を、ニュースネットが以前取り上げた、植朗子さんの『鬼滅の刃』考察コラムという具体例に照らして聞く。また、学術の重要性についての見解も聞く。
【後編】=
https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/feab4059dab0ffb6382e16aec1254197
作田裕史(さくた・ひろし)
1977年生まれ。立教大学社会学部社会学科卒。2010年、朝日新聞出版に入社。週刊朝日記者、AERA記者、アサヒカメラ副編集長を経て、2020年からAERA dot. (アエラドット)副編集長。
▼AERA dot.サイト=
https://dot.asahi.com
【訂正】
本文の、
記者)ウェブ記事は字数に制限がありませんが、分量で気をつけている事はありますか?
に対する答えとして、
作田)最も違うのは、紙は文字数が限られており、書ける分量が非常に少ないことです。ですので、企画の通りやすさは、紙の方が厳しくなります。かつ、明確な締切があるのもウェブと違う点です。また、紙は定期的な購読者がいるので、雑誌のカラーに合わせて記事を作りますが、ウェブ記事では「AERA dot.だから記事を読もう」という人はまだ少数派です。そのため記事単体の訴求力を高めることに労力をさくことになります。
とありましたが、これは一つ前の質問と回答が重複しており、正しくは、
作田)あまり長すぎるものは最後まで読まれない傾向にあります。例えば、Yahoo! の記事は1ページ800字以上になると改ページができる設定になっています。個人的にも、1ページあたりの分量は800~1000字くらいが読みやすいと思います。
の誤りでした。おわびして訂正します。(2022年7月2日17時20分 編集部)
了