小出しですが、臨時議会の他の議案に対して質問したことについて書きます。
〇「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」の一部改正ということで、条例一項目の追加がありました。
その内容はさておいて、かねてから疑問にあった次のような質問をしました。
①職員の物産展やイベントなどの出張販売について
②昨年採用の職員が2名辞職して、他の自治体に採用となるということについて
①の出張販売ですが、矢巾町のお祭りにも毎年村の職員が出張して出店しています。
矢巾町以外は直接見たことはありませんが、他にも出張していると聞いたことはあります。
村のイベント等にも休日出勤で販売していることは珍しくありません。
販売が職員の仕事なのかと、いつも疑問に思います。特産品の宣伝と言えばそれらしく聞こえますが。
矢巾町は民間業者さんが来ています。
このことは、職員の働き方という問題と、官民の協力体制という2つの問題があります。
矢巾町にも、他地域からの出店は業者さんです。役場職員は普代村のみかも知れません。。(調査確認はしていません。)
職員は休む時は休み、住民サービスのこと、村の事業の進め方や段取りなどじっくり考える時間や余裕があるのだろうか。
村民サービスにも影響しているも知れません。
1つの課で色々な事業を兼務しています。職員も足りません。
「代休を取らせている」とのことでしたが、残念ながら実際は中々取れない人がいることも現実のようです。
勤務時間についても全く外部には分かりません。
総括して、集計把握し職員の健康管理にも配慮しているという状況にもないようです。
休日出勤で代休を取ったにしても、本来の職員の仕事である村の政策事業に携わる時間を販売に奪われていることになります。
「徐々に業者さんへの方向で」との答弁でしたが、議員になって12年変わっていません。
村の商品を宣伝するというのは分かりますが、イベントのたびに特産品や業者さんの商品を職員が販売するというのはどうなのでしょう。
協力店がないので、仕方なく職員がやっている状態では村の発展として問題です。
あくまで村は、その道筋をつけて、業者が利益になる状況を見極めて、必要なら補助金等を付けて損させないように委託する。あとは民間業者に協力をゆだねるようにすることは難しいことなのでしょうか?それが官民共働になるものと単純かも知れませんが思います。
業者がダメであれば、民間の中に人を募り、利益が出るように委託することはできないものでしょうか。しっかりと利益が得られることを示して正当な報酬を得られるようにし、長く続けてもらうようにすべきではないか。
すると職員は本来の職務に専念できます。
可能な業者さんや民間に呼びかけずに、それが村の子会社「青の国」独占だったりするとまた官民共働の後退になります。
「青の国」は確かに法的には民間ですが、村民感情からは違うので、「本当の民間」はハンディがあります。
きらうみ産直施設に協力してもらっている業者さんなどもあるわけです。
協力的なところにはどんどんフォローし依存して、儲けてもらい、職員も時間に余裕が出て住民サービス向上で住民もハッピー。どうでしょうか。(願望)
②について、昨年採用の職員が2名とも辞職です。
むずかしい問題ですが、最初から希望の自治体に合格するまでの「腰掛け」ということでなければいいのですが。
職員が不足して、「常時」臨時で補っている状態です。この春採用される職員も来年は辞職するのでは?と誰も不安に思うはずです。
原因が、職員にあるのか? 職場組織にあるのか? それは分かりません。
新人に仕事を教えるというのは、教える側の労力は大変なはずです。それも一人前に役立ってもらえば皆が助かるからこそです。
そのために自分が処理した方が早くても、時間をかけて、イライラしながらも苦労して教えます。(予想です(笑))
指導した職員の苦労、組織の組み換え、人員計画など組織の中全体に影響してくることです。
体調とか、深い事情などであれば仕方ないことですが、こういうことに関する条例もなければならないのではないかと思ったりします。
自治体とはこんなもので、これも人員ロスとして計算に入っているものなのでしょうか?
3月の定例会では、一般質問の中に「職員が中途でやめる人が多い。何かあるのでしょうか?」と質問した議員がいました。
そんな思いを感じている人も少なくないと思います。どこの自治体でもあるらしいのですが。
微妙な問題で、中にいる職員や当事者でなければ感じ取れないことというのは、どこにでもあるのだろうと思います。
組織の中にいる当事者も、なんで?と思っている可能性もあります。
はっきりした「原因」があれば別ですが、組織のなかで人のモチベーションを上げることの難しさを思います。
もし何かあるにしても、こればかりは内部の自浄作用がなければむずかしく、悩ましい問題でありますが、これでいいのかどうかはかなり疑問とするところです。
これらは、根本的な永遠のテーマなのでしょうか?










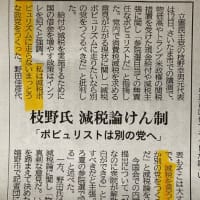









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます