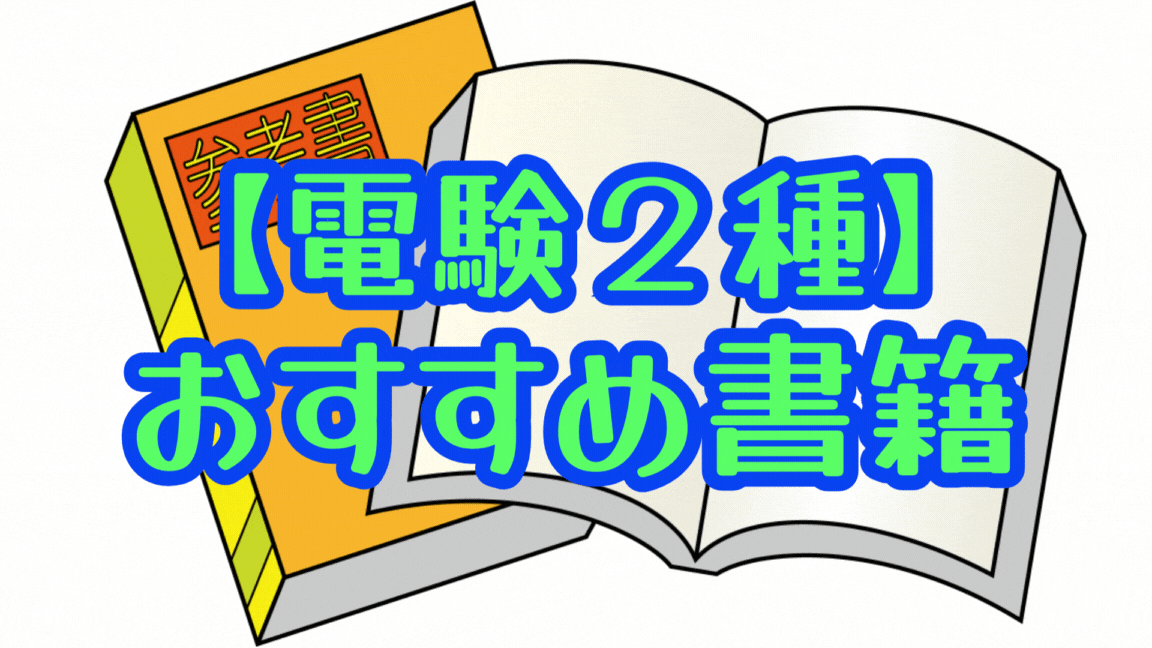確定した和解判決が無効とされ、覆された判例を以下に挙げます。
1. **最高裁判所昭和33年6月14日判決**
ジャムの代金支払い義務に関する和解成立後、ジャムが粗悪品であることが判明した事例です。買主が和解契約の錯誤無効を主張し、裁判所は、和解の前提となる事実に錯誤があったとして、和解契約の無効を認めました。 ([kabarai-sp.jp](https://www.kabarai-sp.jp/wakai.html?utm_source=chatgpt.com))
2. **最高裁判所昭和38年1月25日判決**
建物収去および土地明渡請求に関する和解が成立した後、和解の要素に錯誤があったとして、和解の無効が主張された事例です。裁判所は、裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有するが、私法上の契約としての性質も持つため、無効原因がある場合は初めから無効であると判断しました。 ([ja.wikibooks.org](https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC267%E6%9D%A1?utm_source=chatgpt.com))
3. **東京地方裁判所平成15年1月21日判決**
マンション建築に関する仮処分手続での和解後、和解内容に違反した建築が行われた事例です。購入者が和解の無効を主張し、裁判所は、和解の効力について審理を行い、和解が無効であると判断しました。 ([toben.or.jp](https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2010_09/p02-25.pdf?utm_source=chatgpt.com))
これらの判例では、和解契約の前提となる事実に錯誤があった場合や、和解内容に重大な違反があった場合などに、確定した和解判決が無効とされ、覆されています。和解は確定判決と同一の効力を有しますが、私法上の契約としての性質も持つため、無効原因が認められる場合には、その効力が否定されることがあります。