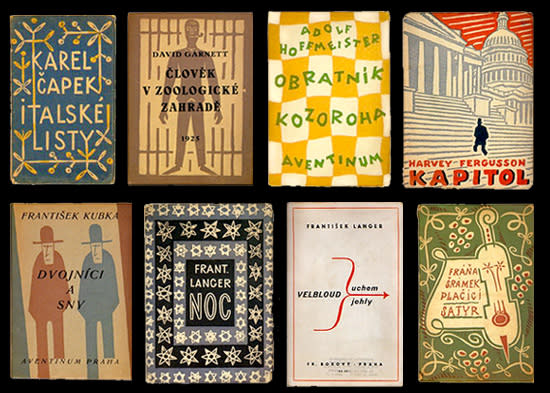あまりにもやる気がないのでごみ箱の内側をクレンザーでぴかぴかに磨き上げてみました。
こうしている間にもどんどん人生の残り時間は少なくなっていくわけでございます。
それはさておき
9/9の続きでございます。
4階に降りると20世紀の絵画における具象表現のセクションが始まります。具象絵画という大きな括りの中ではありますが、幻想的なルドンやシャガールから激しいタッチのキルヒナー、物憂くも華やかなキスリング にスーパーリアルのワイエスと、70年ほどの間に実に幅広い表現が試みられたということが一望できます。
嬉しいことには、モランディの作品が4点も展示されておりました。
モランディ美術館のHP
Home - Museo Morandi
モランディのファンサイト(注:音楽が流れます)
モランディファンの皆様こんにちは
当ブログのモランディについての記事はこちら。
瓶やポットや箱といったモランディおなじみの何の変哲もない「もの」たちが、タッチも色彩も激しいルオーとキルヒナーの間に挟まれて、しんとしておりました。
今回サントリーミュージアムは、この地味な、とはいえ個性的な画家にスポットライトを当て(もちろん物理的にではなく)、20世紀の美術において独特の位置を占める画家として、小コーナーのようなかたちで展示してくれております。そのコーナーにだけモランディの絵から延長したようなベージュ色の絨毯を敷いてあるのも、心憎い演出でございました。
次のセクションへのつなぎとなる「花束の回廊」と題されたコーナーは、展示室を細長く仕切って両壁面に作品を並べた、まさしく絵の回廊のようなしつらえとなっております。この会場風景もサントリーミュージアムのHPで見ることができます。ちっちゃい画像ですけどね。
花を描いた作品が集められたこの「回廊」、ワタシが描くとこうなります、という画家の個性の見本帳のようで面白いものでございました。軽い明るいデュフィのアネモネ、花というより絞り出した臓物のようにおどろおどろしいスーチンのグラジオラス、ひたすらのどかなボーシャンの花々、鋭く厳しいビュフェのミモザ。
最後のセクションは抽象作品で構成されております。真面目な顔で鑑賞するべき所ではありましょうが、ついつい面白がってしまいます。キャンバスそのものを作品にしてしまったフォンタナやカステラーニなんかを前にしますと、ヒャーやりゃあがったなコノ、と思うわけでございますよ。
ここで驚いたのは目の錯覚を利用した表現をよくしたヴァザルリのタピスリー(織り物)作品でございます。ヴァザルリというと幾何学模様を使った理知的な作品のイメージでございましたので、本展の展示作品における色彩とテクスチャのかもし出す温かみは意外でござました。
本展のトリをつとめる、いともポップなホックニーにも驚きました。作品にではなく、「最近はipadで絵を描き友人たちに配信している」という近況にでございます。ポップアート界の寵児も今や御年73歳。この歳で新しい表現媒体に手を出すというのがすごい。
というわけで
閉館まであと数ヶ月を残すのみとなってしまったわびしさを感じつつも、作品そのもののみならずサントリーミュージアムらしさが存分に発揮された展示空間も大いに楽しませていただきました。
いやあ面白かった、ここが閉館してしまうなんてやっぱり惜しいし寂しいや、と頭をふりふり1階のミュージアムショップまで降りてまいりますと、閉店セールということでございましょう、過去の図録が下は200円からという投げ売り価格で販売されておりました。つい喜んでしまった自分が情けない。そうは言ってもお得なものはお得なのであって、いそいそと2冊購入して肩に食い込むカバンと共に帰路についたのでございました。
こうしている間にもどんどん人生の残り時間は少なくなっていくわけでございます。
それはさておき
9/9の続きでございます。
4階に降りると20世紀の絵画における具象表現のセクションが始まります。具象絵画という大きな括りの中ではありますが、幻想的なルドンやシャガールから激しいタッチのキルヒナー、物憂くも華やかなキスリング にスーパーリアルのワイエスと、70年ほどの間に実に幅広い表現が試みられたということが一望できます。
嬉しいことには、モランディの作品が4点も展示されておりました。
モランディ美術館のHP
Home - Museo Morandi
モランディのファンサイト(注:音楽が流れます)
モランディファンの皆様こんにちは
当ブログのモランディについての記事はこちら。
瓶やポットや箱といったモランディおなじみの何の変哲もない「もの」たちが、タッチも色彩も激しいルオーとキルヒナーの間に挟まれて、しんとしておりました。
今回サントリーミュージアムは、この地味な、とはいえ個性的な画家にスポットライトを当て(もちろん物理的にではなく)、20世紀の美術において独特の位置を占める画家として、小コーナーのようなかたちで展示してくれております。そのコーナーにだけモランディの絵から延長したようなベージュ色の絨毯を敷いてあるのも、心憎い演出でございました。
次のセクションへのつなぎとなる「花束の回廊」と題されたコーナーは、展示室を細長く仕切って両壁面に作品を並べた、まさしく絵の回廊のようなしつらえとなっております。この会場風景もサントリーミュージアムのHPで見ることができます。ちっちゃい画像ですけどね。
花を描いた作品が集められたこの「回廊」、ワタシが描くとこうなります、という画家の個性の見本帳のようで面白いものでございました。軽い明るいデュフィのアネモネ、花というより絞り出した臓物のようにおどろおどろしいスーチンのグラジオラス、ひたすらのどかなボーシャンの花々、鋭く厳しいビュフェのミモザ。
最後のセクションは抽象作品で構成されております。真面目な顔で鑑賞するべき所ではありましょうが、ついつい面白がってしまいます。キャンバスそのものを作品にしてしまったフォンタナやカステラーニなんかを前にしますと、ヒャーやりゃあがったなコノ、と思うわけでございますよ。
ここで驚いたのは目の錯覚を利用した表現をよくしたヴァザルリのタピスリー(織り物)作品でございます。ヴァザルリというと幾何学模様を使った理知的な作品のイメージでございましたので、本展の展示作品における色彩とテクスチャのかもし出す温かみは意外でござました。
本展のトリをつとめる、いともポップなホックニーにも驚きました。作品にではなく、「最近はipadで絵を描き友人たちに配信している」という近況にでございます。ポップアート界の寵児も今や御年73歳。この歳で新しい表現媒体に手を出すというのがすごい。
というわけで
閉館まであと数ヶ月を残すのみとなってしまったわびしさを感じつつも、作品そのもののみならずサントリーミュージアムらしさが存分に発揮された展示空間も大いに楽しませていただきました。
いやあ面白かった、ここが閉館してしまうなんてやっぱり惜しいし寂しいや、と頭をふりふり1階のミュージアムショップまで降りてまいりますと、閉店セールということでございましょう、過去の図録が下は200円からという投げ売り価格で販売されておりました。つい喜んでしまった自分が情けない。そうは言ってもお得なものはお得なのであって、いそいそと2冊購入して肩に食い込むカバンと共に帰路についたのでございました。