京都国立博物館で開催中のTHE ハプスブルクへ行ってまいりました。
のっけからラファエロやティツィアーノといった大御所がぽんぽん登場いたします。逸品も多く、充実度の高い展覧会でございました。
常のごとく第一室は押し合いへし合いでございますが、第三室あたりまで来ると意外にゆったりと鑑賞することができました。(ただし平日)。
モデルの性格的特徴をしっかり捉えつつも、威厳をたたえた見目よい姿に描いてのけるティツィアーノの肖像画イザベラ・デステや、いかにも悲劇的な場面でありながら奇妙な静けさの漂うクレオパトラの自害を眺めつつ、ぶらりぶらぶら進んでまいります。
そうしてやや散漫な気分でいた所へズバッと舞い降りたのが

バッティステッロ「オリーブ山のキリスト」
自らの運命を予期したイエスがローマ兵に捕えられる前夜、オリーブ山にて、できることならこの苦しみを取り除いてください、と父なる神に祈りを捧げる場面。いかに人類の罪をあがなうためとは言っても、手足を釘で打ち付けられたり吊るされたりするのはやっぱり嫌だったようでございます。そらそうよねえ。
しかしまあどうです、この劇的な陰影、迫真の描写力。
バロック万歳ののろはこういうものが大好きでございます、ええ。
この主題を扱った作品には、オリーブの林や岩がちの山肌、迫り来るローマ兵や、師匠の苦しみをよそに眠りこける弟子達の姿などが一緒に描かれているものでございます。が、バッティステッロはそうした説明的な付帯物をいっさい廃して、ひたすらイエスと天使にのみフォーカスしております。
暗闇の中、眉間に皺を寄せたイエスの青白い顔と、束縛を待つかのように力なく重ねられた手が、画面左上、即ち天使の来た方向からの強い光に照らし出されております。横ざまに頭を垂れ、視線を上に向けてじっと天の声に聞き入るイエスの姿は、その内面の苦悶を見る者に強く印象づけます。
その「声」たる天使は今しも空から舞い降りた所でございましょう、暗い空間の中に鮮やかな衣をなびかせ、片足を踏み出し、イエスを庇護するように頭上に翼を広げて語りかけます。
天使の表現もちと独特でございます。この場面ではお祈り中のイエスが天使と差し向かいでしっかり見つめ合っている、あるいはがっくりうなだれて天使に抱きかかえられている絵が多いようでございますけれども、そういう作品においては、イエスはいかにも神の子、ワタクシども凡人とは違う、立派で純粋でたいそうなお方、という感じがいたします。
それに対しこの作品のイエスと天使は、視線の上でも身体の上でも、直接触れ合ってはおりません。しかしそれによって、あくまでも霊的な存在としての天使を表現し、かつ、イエスを鑑賞者にとって身近に感じさせる効果を上げております。ここに描かれているイエスは、天使と触れ合ったり視線を交わしたりする幻視者ではなく、後光をいただく超越的な存在でもなく、避けられない運命を思ってひとり身悶えする弱々しい「人の子」だからでございます。
それにしても、逆光をしょったこの天使、恐るべき美青年ではございませんか。難しい角度から光が当たっている顔の陰影や、動きのあるつややかな布地の描写がまた素晴らしい。この作品はカラヴァッジオ作と考えられていた時期があったそうですが、カラヴァッジオの青少年像って、もっとこう、肉感的と申しますか、卑俗な色気を漂わせておりましょう。こういう凛とした雰囲気ではなくて。
イエスのほっそりした手の描写もよろしうございます。下世話ついでに申せば、イエス像はそれなりに細身であってほしいと思うのでございますよ。この人ちっとやそっとのことでは死なんだろうと言いたくなるがっちり体型のイエスを描く方も少なからずおりますけれども、十字架降下の時とか、抱えてる周りの皆さんが大変そうで。
次回に続きます。
のっけからラファエロやティツィアーノといった大御所がぽんぽん登場いたします。逸品も多く、充実度の高い展覧会でございました。
常のごとく第一室は押し合いへし合いでございますが、第三室あたりまで来ると意外にゆったりと鑑賞することができました。(ただし平日)。
モデルの性格的特徴をしっかり捉えつつも、威厳をたたえた見目よい姿に描いてのけるティツィアーノの肖像画イザベラ・デステや、いかにも悲劇的な場面でありながら奇妙な静けさの漂うクレオパトラの自害を眺めつつ、ぶらりぶらぶら進んでまいります。
そうしてやや散漫な気分でいた所へズバッと舞い降りたのが

バッティステッロ「オリーブ山のキリスト」
自らの運命を予期したイエスがローマ兵に捕えられる前夜、オリーブ山にて、できることならこの苦しみを取り除いてください、と父なる神に祈りを捧げる場面。いかに人類の罪をあがなうためとは言っても、手足を釘で打ち付けられたり吊るされたりするのはやっぱり嫌だったようでございます。そらそうよねえ。
しかしまあどうです、この劇的な陰影、迫真の描写力。
バロック万歳ののろはこういうものが大好きでございます、ええ。
この主題を扱った作品には、オリーブの林や岩がちの山肌、迫り来るローマ兵や、師匠の苦しみをよそに眠りこける弟子達の姿などが一緒に描かれているものでございます。が、バッティステッロはそうした説明的な付帯物をいっさい廃して、ひたすらイエスと天使にのみフォーカスしております。
暗闇の中、眉間に皺を寄せたイエスの青白い顔と、束縛を待つかのように力なく重ねられた手が、画面左上、即ち天使の来た方向からの強い光に照らし出されております。横ざまに頭を垂れ、視線を上に向けてじっと天の声に聞き入るイエスの姿は、その内面の苦悶を見る者に強く印象づけます。
その「声」たる天使は今しも空から舞い降りた所でございましょう、暗い空間の中に鮮やかな衣をなびかせ、片足を踏み出し、イエスを庇護するように頭上に翼を広げて語りかけます。
天使の表現もちと独特でございます。この場面ではお祈り中のイエスが天使と差し向かいでしっかり見つめ合っている、あるいはがっくりうなだれて天使に抱きかかえられている絵が多いようでございますけれども、そういう作品においては、イエスはいかにも神の子、ワタクシども凡人とは違う、立派で純粋でたいそうなお方、という感じがいたします。
それに対しこの作品のイエスと天使は、視線の上でも身体の上でも、直接触れ合ってはおりません。しかしそれによって、あくまでも霊的な存在としての天使を表現し、かつ、イエスを鑑賞者にとって身近に感じさせる効果を上げております。ここに描かれているイエスは、天使と触れ合ったり視線を交わしたりする幻視者ではなく、後光をいただく超越的な存在でもなく、避けられない運命を思ってひとり身悶えする弱々しい「人の子」だからでございます。
それにしても、逆光をしょったこの天使、恐るべき美青年ではございませんか。難しい角度から光が当たっている顔の陰影や、動きのあるつややかな布地の描写がまた素晴らしい。この作品はカラヴァッジオ作と考えられていた時期があったそうですが、カラヴァッジオの青少年像って、もっとこう、肉感的と申しますか、卑俗な色気を漂わせておりましょう。こういう凛とした雰囲気ではなくて。
イエスのほっそりした手の描写もよろしうございます。下世話ついでに申せば、イエス像はそれなりに細身であってほしいと思うのでございますよ。この人ちっとやそっとのことでは死なんだろうと言いたくなるがっちり体型のイエスを描く方も少なからずおりますけれども、十字架降下の時とか、抱えてる周りの皆さんが大変そうで。
次回に続きます。










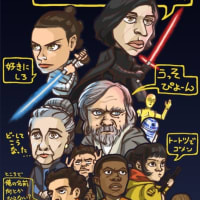
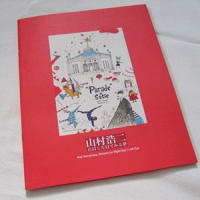
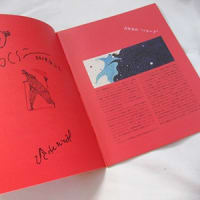
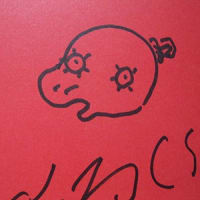
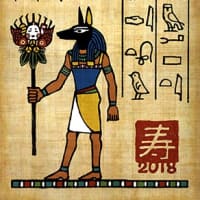





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます