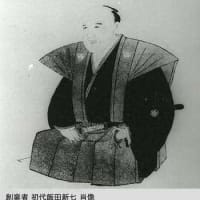三須 宗太郎(みす そうたろう、安政2年8月6日(1855年9月16日) - 大正10年(1921年)12月24日)66歳没は、彦根藩士三須熊次郎の長男。明治の海軍軍人・男爵。近江国(現滋賀県)彦根出身。

海のない内陸県である滋賀県出身の「海軍大将」がいたことを知らなかったが、実は一人だけ海軍大将がいて、それが幕末の彦根藩大老井伊直弼の老臣の子「三須宗太郎」だった。
幕末維新期の彦根藩の二人が明治以降にも活躍していた。
両名とも年齢が近く彦根藩として戊申戦争に従軍し、勤王として武功を上げ、その後、三須宗太郎は軍人、一方の大東義徹は政治家を歩んでいる。
大東 義徹(おおひがし ぎてつ/よしあきら/よしてつ)、
天保13年(1842年) - 明治38年(1905年)63歳没は、官僚、政治家(司法大臣)、滋賀県初の大臣。
大老井伊直弼の老臣、三須熊治の長男三須宗太郎は、日露戦争での戦傷により失明し、独眼龍の異名を持つ勇将山地元治になぞらえ「海軍の独眼龍」と讃えられたほどの勇将と言われる。
三須宗太郎は、明治4年に海軍兵学寮に入り、多くの薩摩藩や佐賀藩の出身者がいる中、頭角を現し、征台の役、西南戦争と相次いで従軍した。戦後、少尉補に任官し、以後累進し日清戦争の頃には官房人事課長を務め、海軍省で後方任務にあたった。
明治30年「須磨」艦長として現場に復帰し、「浪速」「朝日」の各艦長を経て人事局長に就任した。
日露戦争には上村彦之丞大将率いる第二艦隊の第二戦隊司令官として出征、蔚山沖海戦ではウラジオ艦隊を撃破するなどの功をげた。 日本海海戦には第一戦隊司令官に転任し戦ったが敵弾の破片を浴び左目を失明した。このことが海軍の独眼龍」の所以である。
日露戦争後は海軍教育本部長、旅順口鎮守府司令長官、海軍軍令部次長、舞鶴鎮守府司令長官を歴任し大正2年に大将に昇進した。
因みに、
日本海軍には歴代西郷従道を筆頭に77人の海軍大将がいたが三須宗太郎は18番目の大将である。初期の海軍は薩摩人に牛耳られやっと15番が福島、16番は石川、17番は岩手、18番が三須宗太郎だったことからも彼が如何に優れていたかが分かる。
三須宗太郎は海軍省の人事局長、海軍教育本部長や海軍軍令部次長など要職も経歴したが、海上勤務の現場の指揮官が似合った海軍軍人だったと言える。
陸軍には滋賀県からも複数の陸軍大将を輩出しているが海軍は第二次大戦の終戦に至る期間を含めて滋賀県からは三須宗太郎ただ一人だけである。
■経歴
明治4年(1872年)-明治10~11年頃、海軍兵学寮後に兵学校第5期生扱い)。生徒の多くが薩摩藩や佐賀藩の出身者だった。
この5期生には伊集院五郎元帥、出羽重遠大将がいる。出羽も会津出身であり、薩摩人に独占されていた大将の座を初めて勝ち取った三須・出羽の出現は、海軍の藩閥重視の慣習が廃れた象徴といえる。
明治7年(1874年)、陸上での座学を終え、練習艦「筑波」に乗り込んで航海術実習に励む。この年の春に征台の役が勃発。
明治10年(1877年)冬、西南戦争が勃発し、「筑波」は練習艦任務を解かれて戦場に出る。
明治11年(1878年)、少尉補となった。少尉昇進間で2年半、更に中尉昇進には2年弱と5年近く「孟春」・「摂津」・「浅間」の乗組員として下積みを過ごす。
明治18年(1885年)9月、中尉昇進後、最新鋭巡洋艦「浪速」分隊長に命じられ、イギリスまで完成した「浪速」を引き取りに初めて海外へ渡る。
以後、「浪速」で分隊長・砲術長を計2年間務める間に大尉へ昇進。「浅間」に乗り代わってからは「浅間」「龍驤」、9ヶ月の地上勤務を挟み「高雄」「金剛」の副長を歴任した。
地上勤務は横須賀鎮守府参謀・大学校と兵学校の教官といった比較的軽い任務だったという。
明治26年(1893年)9月ー明治30年(1897年)12月、海軍省人事課長に就任。長らく現場で着実に経験と実績を積み重ねてきたが、突然に軍政の中枢部に召集され、人事課長を命ぜられた。
海軍将校の人事は海軍大臣の専権事項であるが、艦隊司令官や海軍省・参謀本部局長はともかく、艦船・部隊の将校人事は大臣一人では手が回らない。そこで大臣官房の中に人事課を設置し、その責任者として三須が選ばれ三須が士官人事を捌いた。
この間に日清戦争が勃発。勝利に必要な人員の配置、黄海海戦での戦死者の埋葬や補償の処理、補充人員の手配、終戦後の人員削減といった人事上欠かせない事務処理をこなし、この時の働きを評価され、日露戦争直前にも人事責任者として海軍省に召集されることになる。この人事課長の任期中に大佐へ昇進。
明治30年(1897年)-明治33年(1900年)
ようやく4年もの海軍省でのデスクワークを終え、久々に「須磨」艦長として海上の現場に復帰。半年後、昔、明治18年(1885年)にイギリスから回航したことがある「浪速」艦長に転出。
同年末に新巡洋艦「出雲」回航のために渡英したが、「出雲」が未完成のため、代わりに戦艦「朝日」艦長に異動して「朝日」を日本まで回航し、明治33年(1900年)に帰国した。三須の艦長生活はこの4年間で終わりを迎える。
明治34年(1901年)7月、
三須は少将に昇進すると同時に、人事局長に任じられる。
かつては大臣官房の小所帯だったこの部署だが、日露戦争に向けた軍拡に対応するために巨大化した部署になり、人事課長時代に比べても扱う人員は増大していた。
明治37年(1904年)から明治38年(1905年)の日露戦争時、東郷平八郎を連合艦隊司令長官指揮下、三須は粗野・蛮勇の気質の上村彦之丞第2艦隊の主力隊である第2戦隊司令官につき、任務を果たしている。
明治38年(1905年)1月、三須は中将に昇進。
東郷直轄の第1戦隊司令官に転任し、日本海海戦に参戦。第1戦隊のしんがりを務める「日進」に同乗した。海戦序盤、「日進」は旗艦「三笠」に次ぐおびただしい敵弾を浴び、戦隊司令部員・「日進」幹部の多数が戦死した。
三須も間近に着弾した弾丸の破片を浴びて左目を失明した。この負傷を機に、「海軍の独眼竜」と三須は呼ばれて賞賛された。
日露戦争の勝利と共に海上生活を終え、
明治38年(1905年)11月、海軍教育本部長
明治39年(1906年)旅順口鎮守府司令長官
明治39年(1906年)11月、海軍軍令部次長を歴任
明治40年(1907年)9月、日露戦争の戦功により男爵に叙せられた。
明治42年(1909年)、現場を離れて将官会議議員へと降りる
明治43年(1910年)、日露戦争のために未完成だった舞鶴鎮守府の整備を再開するため、臨時建築部長として舞鶴に赴任。
明治44年(1911年)1月、最後の任務となる舞鶴鎮守府司令長官に任じられた。
大正2年(1913年)9月、大将昇進を花道に将官会議議員に降板。
大正3年(1914年)12月1日に予備役編入され引退。
大正10年(1921年)12月24日、66歳で没した。
最終階級
海軍大将 正三位勲二等功二級 男爵
<海兵五期>
<Wikipedia引用>