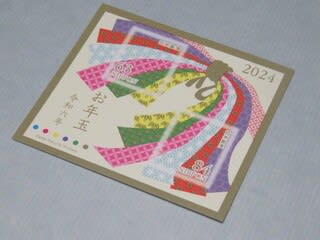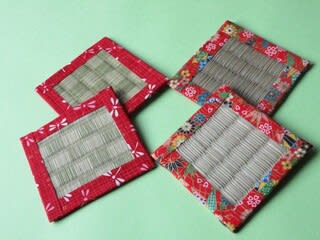以前にも書いたかもの「寒仕込み味噌」
かれこれ何年ぐらい作り続けている私かしら?
チビの幼稚園時代のママ友が初めに教えてくれたから、
かれこれ・・・・何年かナ? 計算は苦手な私でっす!(^^)!
作っていない年もあったのでベテランとは言えないかな?
何人かにおすそ分けはじめたのは、けっこう最近の事。
「美味しい」と言ってくれた方には、次の年にも差し上げる♪
もちろん喜んでもらえるよ(*^^)v
レシピを教えて~とのオッファーが入った!(^^)!
大げさな書き方 えへ♪
本当は!簡単そうだったら作ろうかな~ぐらいの依頼。
私自身、毎年レシピを引っ張り出すのは面倒だから、
ブログに書いておこうと思いついた!!! なかなかのアイディアと自画自賛♪
☆味噌の作り方(寒仕込み)☆
雑菌が繁殖しにくい冬から春の間(1月~3月)がグッドタイミング!(^^)!
この分量で約4kgのみそができる。
●大豆・・・・・1kg
●米麹(生)・・1kg
●海水塩・・・・400g(塩分約10%のみそになる)
●種みそ・・・・250g・・・なくてもよい
前年仕込みの味噌
市販の味噌(原材料に「アルコール」「酒粕」がない酵母菌が生きている味噌)
●消毒用アルコール(アルコール度数35度以上の焼酎・ホワイトリカ)
●重石の塩・・・1・2kg(出来上がりの30%)
(大き目のポリ袋に塩を入れた塩袋を重石として活用)
書き並べると、準備が大変そうだけれど、
要するに、大豆・米麹・塩が必要で、後のものはおまけみたいなもの!!
◎前日の下準備
大豆を洗い、大豆の3~4倍以上の水に一晩浸す(約12時間)
(水を吸うとマメは役2倍の大きさになる)
△器の消毒
アルコールをフキンなどに含ませ、容器の内側を拭く
レッツスタート!(^^)!
①鍋に水気を切った大豆と新しい水(大豆の2倍量)を入れ火にかける。
途中アクをとり、水を足しながら弱火で3~5時間煮る。
(大豆が親指と小指でつぶれるぐらいの柔らかさまで煮る・耳たぶぐらいの柔らかさ)
☆圧力なべを使うと時短になる☆
~~ここでしっかり手を洗う~~
大豆を煮ている途中で、
②麹と塩を混ぜる
消毒したボール(または鍋)に米麹と塩を入れ、両手で下からすくいあげながら混ぜる。
(麹をつぶさないように、すり合わせるようにして混ぜる)
③煮あがった大豆をザルにあげる
(煮汁は後で使うので500ml~600ml取りおく)
④熱いうちに大豆をつぶす
(ポテトマッシャー、フードプロセッサー等・ポリ袋に入れ綿棒でつぶす等)
⑤大豆が人肌に冷めてから②と種味噌をくわえる
(粘土ぐらいのかたさ・指がスッと入る程度)
かたすぎる場合は③で取り置いた煮汁をくわえ調整。
塩がムラにならないように、よく混ぜる。
⑥おにぎり大に丸め、だんご状のみそ玉を作る
(みそ玉は少し柔らかめに握ったほうが、容器に詰めるとき空気が抜けやすい)
⑦容器にみそ玉を叩きつけるように投げ入れ、上から手のひらや甲で押して、空気を抜く。
これを少しずつ繰り返し、最後は表面を平らにする。
⑧表面にふり塩(小さじ1程度)空気に触れないようラップを貼り付け、均等に重石をする。
⑨蓋をしてから新聞紙などをかぶせてひもで縛り、冷暗所へ。
(直射日光の当たらない場所。仕込んだ年月日書く)
➉仕込み後、3か月ほどたった時に「天地返し」をする。
6か月後から食べられる♪
熟成後は冷蔵庫に保存(熟成が進まないように)
こんな感じですね。
私は鍋で大豆を煮る方法なので、寒い日には部屋が温まっていいですよ♪
作業スタイルは、お気に入りの作家さんが作った紺色系の割烹着、首には真白なタオル。
頭はバンダナ・・・・やる時は形から入る私です(*^-^*)
☆わからないことがあったら、訊いてくださいね☆
やさしい陽射しの2月29日 木曜日
うるう年の一日を、思う存分味わおう♪
今日も笑顔ハートで過ごしましょうね
※※安芸の宮島※※
私の父や母が、子育てが一段落した時に初めて旅した「安芸の宮島」
名前だけが私の心の中に深く刻まれている。
画像に出会えたので、うるう年の今日ここに貼り付けておこうと思い立った。
ネットは思い出の世界を膨らませてくれ、身近なものになる・・・ありがたいな♪
ジャスト満潮の時の画像。 すがすがしい空気が流れてくる※
広い広い~板の間

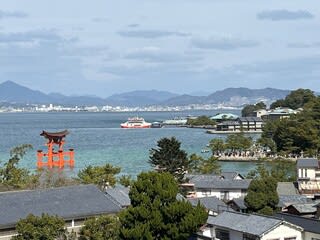
鳥居の向こうには船が見える
石灯籠の向こうに鳥居が見える


厳島神社から鳥居(満潮時)
厳島神社後方に五重塔(満潮時)


五重塔撮影
かつて、両親が見た景色を私が見ることができたことに感謝しかない♪
「ありがとう」って叫ぼうかな(*^-^*)
うるう年の夜記入☆