22.10.27 当ブログの前記事(下記URL)にてご案内しました最新のGPS World誌のカバーストーリー「スマートフォン・デシメータチャレンジSDC」に絡んで,欠落したQZSSと絡めた提案を記録しておきます.
https://blog.goo.ne.jp/qzss/e/3520fdc6d96e847d85e24d6c55be6173
千葉工大の鈴木太郎先生のスマートフォン・デシメータチャレンジSDC連続優勝を機に,是非とも日本でQZSSが受信できるスマートフォンによる「SDCQ」実施の実現を提案したい.スマートフォンGNSS受信とQZSSの受信を追いかけてきた当ブログとしては,鈴木先生のSDC連続優勝という快挙は涙が出るほどうれしいところです.
グーグルのスマートフォン・デシメータチャレンジ(SDC)という試みは,フルオープンな国際的ソフトウェア・デジタル技術の開発競争により,優れて大衆的なスマホデバイスの測位利用技術を公開の場で高めてゆこうとするものであります.ただ一つ,QZSSという日本の測位衛星系が地理的条件により使用できないことが誠に残念であります.
そこで内閣府なり日本の関連学会が中心となって,SDCQとでもいうべき地域衛星系受信を含めた同様なチャレンジを,時宜を失することなく開始すべきと考えます.
喜びすぎて,下手くそに本家の図面に手を加えて提案アピール図を作成してしまいました.
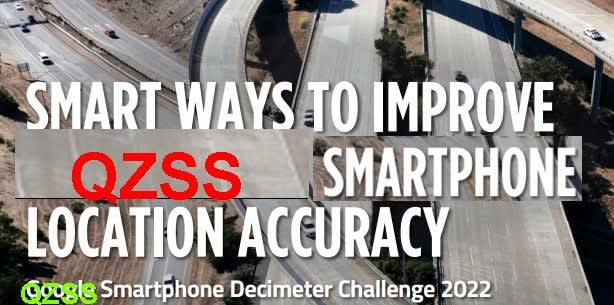
QZSSという衛星軌道系は対地角速度がアポジー周辺ではGPSなどMEOよりも一桁以上小さいという特徴を持っています.この特徴を最大限に活かせば,スマホでの測位精度をMEOよりも高めた特徴ある地域測位・測地アプリの開発に,世界中の叡智を最大限に集約できるでしょう.
当然,大きな課題は,QZSSの受信ができる地域での開発研究やチャレンジが求められることです.このための旅費・滞在費についての資金をどうするかでしょう.
当方としては,例えばデジタルやICTや測位や地震予知などの予算にかかわる省庁と内閣府が連携してひねり出してほしいところです.前世紀に日本が発案したロボコンが,いまや途上国まで巻き込みTV中継を各国の国民が熱狂して見ているという前例からして,次はQZSS受信スマホ測位の高度化競争については,予算の活用について,国民的な支持が得られるのではと,想像しています.
https://blog.goo.ne.jp/qzss/e/3520fdc6d96e847d85e24d6c55be6173
千葉工大の鈴木太郎先生のスマートフォン・デシメータチャレンジSDC連続優勝を機に,是非とも日本でQZSSが受信できるスマートフォンによる「SDCQ」実施の実現を提案したい.スマートフォンGNSS受信とQZSSの受信を追いかけてきた当ブログとしては,鈴木先生のSDC連続優勝という快挙は涙が出るほどうれしいところです.
グーグルのスマートフォン・デシメータチャレンジ(SDC)という試みは,フルオープンな国際的ソフトウェア・デジタル技術の開発競争により,優れて大衆的なスマホデバイスの測位利用技術を公開の場で高めてゆこうとするものであります.ただ一つ,QZSSという日本の測位衛星系が地理的条件により使用できないことが誠に残念であります.
そこで内閣府なり日本の関連学会が中心となって,SDCQとでもいうべき地域衛星系受信を含めた同様なチャレンジを,時宜を失することなく開始すべきと考えます.
喜びすぎて,下手くそに本家の図面に手を加えて提案アピール図を作成してしまいました.
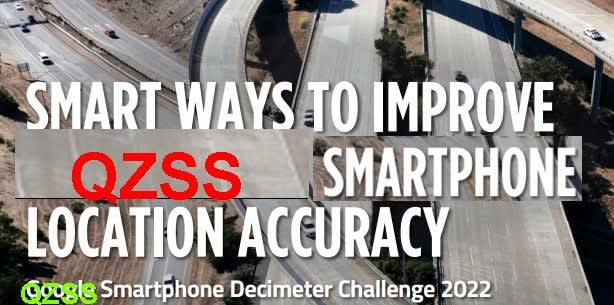
QZSSという衛星軌道系は対地角速度がアポジー周辺ではGPSなどMEOよりも一桁以上小さいという特徴を持っています.この特徴を最大限に活かせば,スマホでの測位精度をMEOよりも高めた特徴ある地域測位・測地アプリの開発に,世界中の叡智を最大限に集約できるでしょう.
当然,大きな課題は,QZSSの受信ができる地域での開発研究やチャレンジが求められることです.このための旅費・滞在費についての資金をどうするかでしょう.
当方としては,例えばデジタルやICTや測位や地震予知などの予算にかかわる省庁と内閣府が連携してひねり出してほしいところです.前世紀に日本が発案したロボコンが,いまや途上国まで巻き込みTV中継を各国の国民が熱狂して見ているという前例からして,次はQZSS受信スマホ測位の高度化競争については,予算の活用について,国民的な支持が得られるのではと,想像しています.















