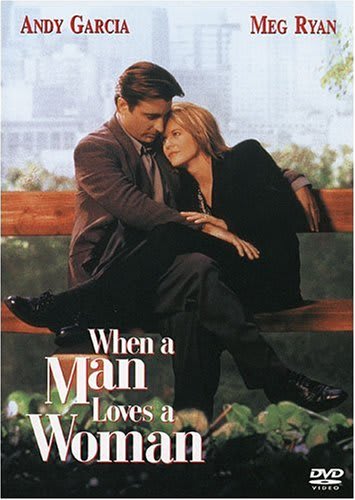
「男が女を愛する時」 When a Man Loves a Woman
アンディ・ガルシア (出演), メグ・ライアン (出演), ルイス・マンドーキ (監督)
アルコール依存症の主人公を描いた最高傑作は、もちろん、ニコラス・ケイジ主演の「リービング・ラスベガス」です。
ハリウッドの脚本家だったニコラス・ケイジは、アルコール依存症。どうしようもない酒浸りの生活でクビにななりました。妻子も愛想を尽かして家を出てしまい、彼はラスベガスで死ぬまで酒を飲み続けようと決めます。
全財産をすべて金に替え、ベガスに着いた彼は、さびれたモーテルの一室に滞在し、ある夜、街で娼婦のサラ(エリザベス・シュー)と出会い、恋に落ちるのですが。。。。。
ホイットニー・ヒューストンの死に関しても書きましたが、ほんとうにアルコール依存症は恐ろしい病気です。エリザベス・シューの聖女ともいえる愛が、果たして、病みに病んだニコラス・ケイジを救うのか。。。。それは、是非、映画を最後まで観て、確かめていただきたいです。

古典で言うと、なんといっても、名優レイ・ミランド主演の「失われた週末」ですね。もう、この人の隠れ飲みというんですか、酒の隠し方の凄いこと凄いこと。見てるこっちが冷や汗が出てきます。まさに、依存症とは酒に「囚われる」病いなのだということがよくわかります。
惜しむらくは、1945年に製作された作品だから、すでにアメリカにはAA(アルコホーリックス・アノニマス=無名のアルコール依存症者たち)という自助グループがその10年前からあるのに、そういう仲間同士の支えあいが全然描かれず、ひたすら主人公の意志の力、自制心の問題にされているところが、残念と言えば残念です。
なにしろ、本人の意志ではどうにもならないからこそ、病気なんですからね。意志の力で何とかなるなら、たとえばホイットニー・ヒューストンのような多くのスーパースターが亡くなるわけがありません。
さらばホイットニー アルコール依存症は飲酒のコントロール障害 原因において自由な行為は自由じゃない

さて、映画を見てると、「どう見てもこの人、アル中(ほんとはこの言葉は使ってはいけません)やろ」という登場人物が出てくる映画はたくさんあるわけですが、はっきりと主人公がアルコール依存症だということを明示した映画となると、なんと、「恋におちたシェイクスピア」のグウィネス・パルトローがアルコール依存症のカントリー歌手を演じた「カントリー・ストロング」があります。
大歌手だけど酒におぼれて落ちぶれた彼女が、再起をかけた大舞台へ、なんと酒を飲んでしまって上がってしまい、よれよれになる前半のシーンは、もう、可哀想で可哀想で、見ていられないほどです。
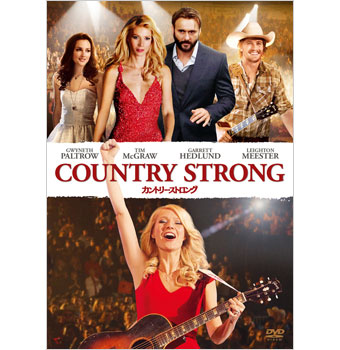
そう、そして、アルコール依存症のカントリー歌手と言えば!
『クレイジー・ハート』で、なんと5回目のノミネートで2009年の第82回アカデミー賞主演男優賞を受賞した名優ジェフ・ブリッジス!
彼って、ロビン・ウィリアムズと共演した、哀しくも切ない人気作「フィッシャー・キング」でも、ある昔の出来事に対する罪悪感で、ほとんどアル中(すみません)に近かったような。まさに、酒を飲む演技をさせたら天下一品というところでしょうか。
彼が、クレイジー・ハートで、とうとう酒で滅びる場面は凄かったんですが(あれは震撼した)、そのあと、なんか、リハビリ・センターだけしか出てこないのね。それで助かる人もいるんでしょうが、アカデミー主演男優賞を獲るなら、もうひと苦労してほしかった(鬼のようなことを言ってすみません)。

というわけで、凄まじく長い前振りでしたが、ここからが本題。
今宵、本当にいい映画を見ました。
アンディ・ガルシアとメグ・ライアンの「男が女を愛する時」 When a Man Loves a Woman (1994)です。同名の名曲がありますよね。
なんと、この作品では、ラブコメの女王、メグ・ライアンがアルコール依存症なんです。そして、この病気が一筋縄ではいかないこと、そもそも「治らない病気」であることがはっきりわかるように作られています。
自由にお酒を飲んだり飲まなかったりというような、普通人のように戻るという意味では、アルコール依存症者は「治らない」。治らないけれども、飲まない生き方をできるように回復はする。しかし、回復はするけれども、それは本人の意志だけでも、家族の支えだけでも回復するのはとても困難。
自分のなにもかもをお互いに話し合え、許しあえる仲間が必要なんです。それは、アルコール依存症患者にはお互いに分かり合える患者同士の自助グループが必要だし、家族には家族の自助グループが必要であることが、この映画では真正面から描かれていました。
アルコール依存症患者の家族は、自分の力で「患者である家族」を「治したい」んですよ。でも、そう思いつめすぎることは、治れはしない依存症者を追い詰める。
そもそも、患者に「ダメなあなた」の役割を押し付けてしまうのは、それは、「共依存」なんですよね。アルコール依存症の患者が家族に依存するだけでなく、家族も患者が「回復しない患者」のままでいることを必要としてしまう。それも一種の依存なんです。
アルコール依存症者もそんな風に「ダメ人間」のまま扱われていては、いつまでたっても自分の尊厳を感じられないことを、メグ・ライアンが素晴らしい演技で示します。
そして、この映画の真の主人公は、アルコール依存症患者を妻に持ったアンディ・ガルシアです。
こんなにも妻を愛しているのに救えない。健常者の自分には、妻のことが理解できない。良かれと思ってすることがすべて相手を傷つけることになってしまう。妻は自分と一緒にいない方がむしろいいのだろうか。それを認めるのがとても辛いんです。そのジレンマを、彼は見事に表現していました。


わたし、120分ほどの上映時間のうち、90分以上、涙と鼻水で、顔がぐちゃぐちゃで、大変でした。なにしろ、この二人の夫婦に子供がいるんですが、その子どもが二人ともうちの娘と同じくらいの女の子なの。
誰も悪くないのに、どうにもならなくて、誰もが無力で。
夫婦も可哀想なら、健気な子どもたちも哀れで、もう、わたし、泣けて泣けて。

それでも、どんなに困難な状況にあっても、人が人を愛することは限りなく素晴らしい。
この女性のような病気でなくたって、思うようにならないのが人生。でも、人はやってしまったことをやり直すことはできないけれど、自分の弱ささえ認めれば、必ず取り返しはつく。
そんな素晴らしい映画です。是非是非、観ていただきたいと思います。
WHEN A MAN LOVES A WOMAN - MICHAEL BOLTON
よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
世界的規模の団体で日本にもある自助グループがAA=アルコホーリクス・アノニマス=無名のアルコール依存症者たち。
日本独自の自助グループが断酒会=全日本断酒連盟。
希望はあります。どちらも全国津々浦々まであります。
是非、お酒に問題があると思われる方ご本人でも、ご家族でも連絡してみてください。
AAの創始者 ビルをジェームズ・ウッズ、ボブをジェームズ・ガーナーという二大名優が演じたテレビドラマを教えていただきました。






























拝読いたします。
今後ともよろしくお願いいたします<m(__)m>
このように人気ブログで取り上げてくださったこと、とてもうれしく思います。
私こと、
北海道大学で「社会問題としての飲酒」という授業を開講・担当しております。
この授業の様子と、
北海道から長崎県の五島列島まで、お訪ねした全国各地の断酒会のみなさまととそのご家族からのお手紙を
学外のみなさまにもお届けしたくて
『お酒を手にした未成年のあなたへ
―断酒会会員と家族からの手紙』を編みました(刊行は2013年)。
http://hdl.handle.net/2115/54716 で、全文を公開しています。
もしよろしかったら、ですが、宮武先生にも、他のみなさまにも、ご一読いただければ幸いです。
紙媒体がお好みの方はamazonでもご注文いただけます(送料無料)。
健常者も病気の人も、何でも話せる友や家族や仲間が必要ですね。
そのためにも自分の弱さを認めることが大切だと思います。
久々のコメントありがとうございました。
以前このブログで紹介されていたやつだと思って
何気なく見ていましたが,
断酒した後からのシーンのどれをとっても,心が痛み,涙が出て,つらかったです。
AAでの発表もあんなふうにやるんだなあと分かってよかったです。
あと,AAの仲間のほうが大切で,普段近くにいる家族や友人の方がすごく遠くにいると感じていることがやりきれない思いになりました。
やはりまわりの方にも仲間が必要なのだとアンディ・ガルシアを見て思いました。
メグライアンが,「自分の面倒をみることが楽しかったでしょ?」とアンディ・ガルシアに聞くシーンがありました。
あそこで私は息が止まりました。心臓ぱくぱく。
そういえば,今日の神戸新聞にも東日本大震災で依存症の方の対策をしないといけないということで,長田区でシンポジウムがあったと書いてありました。
根深い問題なのに,私にとっては遠くにある話です。
それでもやはり他人事には思えませんでした。
せめて病に苦しむご本人とそのご家族に祈りたいと思います。
曲も歌詞も、美しさの中にふと切なさが滲みます。
ところで「酒とバラの日々」はビデオテープで持っております。DVDでないところがいいというか何というか……。
「紫煙とスミレの日々」では映画になりますまいね。
今日は帰ってきてテレビつけたら、ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムズの「レナードの朝」をやっていて、うわあ、これ観たら晩御飯食べられへんと思いながら、思いっきり鼻水と涙流しながらご飯をもしっかり食べてしまいました。
「生きていることの素晴らしさをみんな知らないんだ。生きていることに感謝することを伝えよう」
デ・ニーロ、最高でした。。。。。。
邦画でのアルコール依存症で印象に残るのが、比較的最近の「おとうと」での笑福亭鶴瓶師匠。 「できの悪い弟」を持つ姉の(われらの)吉永小百合さまも、鶴瓶ちゃん怪演の伝播か、珍しく(失礼)現実感のある演技でした。 (テレビドラマ「北の国から」の田中邦衛ほかの酔っ払いシーンも、見つめる側の愛情と哀しみが伝わりました。 渥美清さんも、酒も飲めんのにうまく酔ってくれていましたね>寅さん。)
おっしゃる通り、依存症の患者も、その家族も、それぞれに孤立しがちで、その結果お互いに責め合い、そうした自らをも責めてしまうため、治療できる病気なのに、ビョーキとして扱われる。 患者同士の自助グループを知れば、救われる場合も少なくないでしょう。 日本にも津々浦々存在するということ、よかったと思います。
依存症ではないのですが、HIV感染者の自助グループが描かれた秀作米映画に、「レント」(Rent) があります。 人気群像ミュージカルの映画化ですが(ミュージカルより上出来!)、自助グループに参加し、自分のことを語り、仲間の声に耳傾けて、励ましたり、ただ黙って抱きしめたり……心が救われていく様子などを見ると、自分の中にある偏見や差別観もいくらか洗い流されるような気がしました。 一人、また一人と、自助グループのメンバーが集まるたびに減っていくのが、とても悲しい映画でしたが。
犯罪(いじめといわれるモノも含め)を犯しちまった子供や、その家族、逆の立場の人たちも、なんとかそんな自助グループによる救いができないものでしょうか。 (被害者の会はよく聞きますが)
ところでワタクシ、アンディ・ガルシアは好きなのですが、彼はいつだって「アンディ・ガルシア」。比べては酷ですが、ロバート・デ・ニーロは変幻自在だなあとゴッドファーザー3を見ていて感じました。
観てません!!
しもた。。。。
J・レモンの名演と、本人は恢復するけど悲しい結末。
自助グループも取上げられてましたね。
主人公がアル中(失礼)になる原因が仕事の接待というのも、やりきれんなあ。