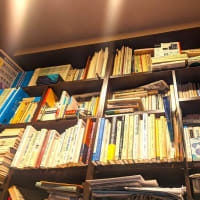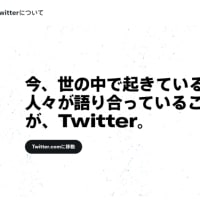クレーマー社会、ニッポン。
この問題を考える上で、海外との比較は欠かせないと思う。
日本人はなぜかくにもクレームが多いのか。
そこで、使いたい言葉が「買い手」と「売り手」である。
古い言葉で言えば、「消費者」と「労働者」ということになるだろう。
(だが、後者の言葉だと色んな「意味」が発生するので使わない)
日本社会はとにかく「買い手中心社会」である。
買い手のニーズにどこまでも合わせ、
買い手の意見や価値観を、売り手がどこまでも受け容れる。
買い手がいつでも買い物をしたいということで、
24時間営業のコンビニエンスストアが生まれたし、
買い手が心地よく買い物ができるように、
売り手は「お客様は神様」という言葉のもので、
どこまでも頭を下げる(本当に下げているとは思えないが)
売り手と買い手は常に反転する。
売り手である人が買い手になる、というのは自明の理である。
サービス産業中心の日本では、売り手である人間と買い手である人間が
パラレルになっていて、人間の二面性を織り成している。
売り手である人間は、買い手にどこまでも従属する。
買い手は買い手であるときは横柄な態度をとるが、
買い手が売り手に転じたときには、とたんにぺこぺこと頭を下げる。
買い手が中心である限り、売り手はどこまでも従属的存在のままとなる。
(資本主義社会では主にそういう傾向になってしまうのだが・・・)
だが、ドイツ(ないしはオーストリア)の事情を見てみると、
この両者の立場が日本とは異なっていることに気づく。
ドイツでは、買い手がそれほど偉そうではないのである。
(同時に、売り手がそれほど従属的ではないのである)
スーパーのレジの店員さんは座って仕事をしているし、
お客さんがたくさんレジで待っていても、店員さんは我かんせず。
もちろんお客さんもそれほどピリピリしていない。
駅で電車が遅れても、乗客はそれほど動じない。
ウィーンやミュンヘンといった大都会でもそうなのだ。
もちろん急いでいる人もいるだろうけれど、
それを駅員にぶつけたり、怒鳴ったりはしない。
レストランで、ウェイターが注文したものを間違えても、
レジで、つり銭の数を間違えても、
売り手は全く動じず、ぺこぺこしたりもしない。
謝ることはまずない(たま~に謝る人もいるが・・・)
こちらが文句を言うと、両者の間で議論になってしまう。
ドイツでは、売り手と買い手の立場が、
日本ほどに上下関係にないのだ。
対等とまではいわないまでも、同じ人間同士のやりとりになる。
***
売り手(働き手)にとっては、どちらが楽だろうか。
買い手にとってみれば、日本のほうがいいに決まっている。
日本の買い手ほど、偉そうで、幼稚な買い手は他国にいるのだろうか。
日本の売り手ほど、頭を下げ、買い手の顔色を窺っている売り手は、
他の国にはいるのだろうか。
働き手にとっては、日本は本当に辛い国だと僕は思う。
働くことはとても大切な人間の行為ではあるが、
我慢し、忍耐し、従属し、ペコペコしている労働が楽しいとは思えない。
(というよりは、苦痛である)
働くということは、一部の幸福な人間を除いては、
やむを得ないこと、しなきゃいけないからすること、である。
「したくて働いている」、という人は幸いである。
だから、日本では、もっと売り手が大切にされなければならないのではないか。
売り手が大切にされれば、働くことももっと平坦なものになるはず。
かつての国鉄(旧JR)は、駅員がすごく横柄だったと言われている。
だが、それはどこまで真実なのかどうかは僕には分からない。
役所の職員たちは今なお横柄だと言われることが多い。
(僕も何度かカチンときたことがあった)
でも、海外的な目線で見れば、それが普通なのかもしれないのだ。
(ただ、日本だとどっちかが偉そうになってしまうのだが・・・)
たしかに買い手がいなければ、売り手は厳しい状況に追い込まれるが、
売り手がいなければ、買い手は困るのである。
売り手と買い手はお互いに支え合って、存在し合っているのだ。
それを忘れてはならないと僕は思う。
売り手が抑圧されればされるほど、
買い手はますます横柄になっていく。
買い手意識が高まれば高まるほど、
買い手はますます売り手に無理難問を言うようになるのである。
そうすると、売り手はますます売ることが辛くなる。
売ることが辛くなればなるほど、「売り手は辛い」という先入観が強化される。
そういう先入観をもって何かを買うと、
その時に、買い手は売り手に辛く当たってしまうのである。
「売り手は買い手と対等の存在」
こういう先入観をみんなが持つことで、
少しは日本の売り手受難の時代は改善されるのではないだろうか。
今回、欧州に行って、このことを強く実感した。

![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/18/76/2fb568a5717bda67be91d432644be3e7.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/1a/8c/f1f51f662c6bb851bda1a6a047e94359.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/66/6c/ce0b6ebd716f4651da5c764d5acdc1ec.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/38/c8/62c131c5e2bec8fa8d60a9b5559e3ea8.jpg)