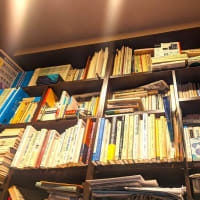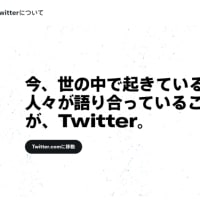先日、「キングオブコント」で興味深いシーンがあった。
それは、ダウンタウンの松本さんのコメントの中で出てきたものだった。
キングオブコントは、数々の実力派の漫才コンビが登場し、審査員が点数をつける番組。
松本さんは、あるコンビに高い点数をつけるときに、こう言った。
「いや~、(会場全体が)ウケてたよね。みんな、笑っていたもんね」。
…
この言葉に、松本さんのある種の「哲学」を見た気がした。
それは、「お客さんにウケるなら、好き嫌いは問わず、いいんだ」、という哲学だ。
多くのお客さんが笑ったものこそが、いいものなんだ、と。
ダウンタウンの人気の秘訣も、そこにある気がした。
本人が「いい」と思っているかどうかは別にして、オーディエンスの反応が全て、と考えている人なんだ、と。
最後の方では、こう言っていた。
「俺がいいと思う芸人は、キングにならないんだよー」、と。
松本さんは、松本さんなりに、「いい」「悪い」の選別があるんだと思う。
でも、松本さんは、それ以上に、「お客さんの反応」を重視していた。
そこに、松本さんのある種の「実践哲学」が示されているように思った。
つまり、「お客さんにウケてこそ、コント・お笑いだ!」、と。
コント芸人の目的は、つまるところ、「お客さんが笑うかどうか」。
そう、教えられた気がした。
***
このことは、音楽にも当てはまる。
今や、音楽は、完璧に「技術」の時代。
とんでもないスキルを習得したミュージシャンはゴロゴロいる。
「巧ければ、それでいいんだ」、という内なる声も聴こえてくる。
でも、音楽もまた、お客さんにウケるかどうかが決め手となるのではないだろうか。
自分が奏でる音楽を聴いて、泣いたり、暴れたり、感動したり、立ち尽くしたり…
「お客さんが自分の音楽を聴いて、それこそ「音」を「楽しんでいる」かどうか。
それが全てのような気がしてならない。
…
演奏がヘタでも、その音楽を聴いて、お客さんが盛り上がっているなら、OK。
MC(しゃべり)がヘタでも、その人の歌を聴いて、酔えるなら、OK。
そういう風に音楽を捉える人が、いったいどれだけいるか。
コントも、お笑いも、音楽も、何のためにあるのかと言えば、「お客さん」のため。
そういうことなんだろう、と改めて思った。
ウケるものが、ただちに、いいものになるわけじゃない。
けど、ウケるものの中には、いいものが含まれている。
善いもの=ウケるものでもない。
けれど、それ自体、善いものであれば、いつかどこかでウケるものになる。
(…と言ってよいか分からないけど、、、)
僕自身も、普段から講義をしていて、「今日はウケたなぁ」とか「ウケなかったなぁ」とか思っている。
ウケりゃいいってもんじゃないにしても、ウケない講義は、つまらないものでしかない。
ウケて、内容もあるものだったら、それがBESTな講義なんだろう、と。
ただ、それはなかなかかみ合うものでもない…
この「ズレ」こそが、更なるいいものを創り出すのかもしれないなぁ、、、と。
今後も考えたいテーマです。。。
…
僕自身も、「ウケてこそ」と思っているし、また、実際にはなかなかウケないことに悩んでいるのかな。
売れるものと善いもの、というのは、ホント、微妙なところにあるものだなぁ、、、、と。
そう思います。
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/18/76/2fb568a5717bda67be91d432644be3e7.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/1a/8c/f1f51f662c6bb851bda1a6a047e94359.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/66/6c/ce0b6ebd716f4651da5c764d5acdc1ec.jpg)
![やまやの[うまだしおにぎりせっと] 羽田空港で見つけた日本エアポートデリカ(株)の素敵な「空弁」!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/38/c8/62c131c5e2bec8fa8d60a9b5559e3ea8.jpg)