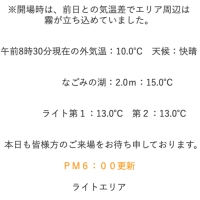家電がエラいことになっている。テレビが売れない。
これを地デジ化とエコポイントによる需要の先食いと見なしてはダメだ。国策無策とコンテンツが問題なのだ。
1. 地デジ化とエコポイント
2.韓国との戦い
4. 体力消耗
そう、どう考えても原価半減て無理。生産規模100倍って・・結局固定費莫大化になる。
5.コンテンツが無い
6.スマートTV(スマートモニター)
7. 国策無策
8. 復活策
9. 雑感
大風呂敷を拡げたが、何もしないままだとギリシャになる。たかがTVだが、その根本は国の円の独歩高への無策が深く寄与している。その理由が一票の格差と公共工事関連に繋がっているという仮説は大胆かもしれないが、的を射ている様な気がしている。第二次産業(特に輸出関連)が衰退すると、国そのものが衰退する。だからTPPも必要だと考えている。
震災後、この国をどうしていきたいのかというビジョンが見えなくなった。円の独歩高は輸出産業を虫の息にした。自動車は補助金で生き延びているが、このままだと海外生産のみになる。
円高を止めると火力発電の燃料費代が大幅に上昇するので、円高で燃料費代の高騰を防いでいるというのなら、燃料費代を節約できる原子力発電を再開すべきだろう。そうすれば円安政策がとれ、輸出産業は一息つける。
産業構造が原発がある事を念頭にしているのだから、変なところでボトルネックを作ると国がこける。確かに放射線は危ない。だがビビりまくって必要な物を止めるのは単なるパニックだ。(まるでアメリカ映画で「もう私達は死んじゃうのよ、どうしようもないのよワー」と叫ぶ女優のようだ)
これを地デジ化とエコポイントによる需要の先食いと見なしてはダメだ。国策無策とコンテンツが問題なのだ。
1. 地デジ化とエコポイント
確かにこの二点に基づく需要の先食いの影響はある。
殆どの家庭が大画面の液晶TVに買い替えた。
デジタル放送のお陰でアナログ放送のときよりも分解能の高い画像の恩恵も受けている。
需要の先食いの影響は見越していて、設備投資ではなく工場の稼働率を上げる方向で対応するものだ。
リーマンショックで米国市場が落ち込み、独占的な利益率の高い大型パネルの製品が売れなかった。
だが、それだけが理由じゃない。
殆どの家庭が大画面の液晶TVに買い替えた。
デジタル放送のお陰でアナログ放送のときよりも分解能の高い画像の恩恵も受けている。
需要の先食いの影響は見越していて、設備投資ではなく工場の稼働率を上げる方向で対応するものだ。
リーマンショックで米国市場が落ち込み、独占的な利益率の高い大型パネルの製品が売れなかった。
だが、それだけが理由じゃない。
2.韓国との戦い
円高、ウォン安。対ドルで見てみよう。為替平均
2007年のドルと韓国Won
2011年のドルと韓国Won
2011年と2007で比べるとWonは9.27/11.21=0.83倍のWon安、円は122.95/78.84=1.56倍の円高である。
価格をみると日本製品は韓国製品の1.56/0.83=1.83倍ということだ。
2007年に共に売価100[US$]だったものが、2011年に韓国製: 83[US$]と日本製: 156[US$]になった。これじゃ日本製品は売れない。(倍払いする価値があるか?)
為替年間平均
| 年 | US$ | EURO | Korea Won |
|---|---|---|---|
| 2007 | 122.95 | 167.56 | 13.26 |
| 2011 | 78.84 | 109.62 | 7.03 |
2007年のドルと韓国Won
⇒122.95[Yen/US$]/13.26[Yen/Won]=9.27[Won/US$]
2011年のドルと韓国Won
⇒78.84[Yen/US$]/7.03[Yen/won]=11.21[Won/US$]
2011年と2007で比べるとWonは9.27/11.21=0.83倍のWon安、円は122.95/78.84=1.56倍の円高である。
価格をみると日本製品は韓国製品の1.56/0.83=1.83倍ということだ。
2007年に共に売価100[US$]だったものが、2011年に韓国製: 83[US$]と日本製: 156[US$]になった。これじゃ日本製品は売れない。(倍払いする価値があるか?)
■条件1:TVは韓国製か日本製しかないので韓国製はWon安で値下げして83[US$]で売ったとする。
日本製は韓国製に対抗するためには156[US$]ではなく46.8%割引の83[US$]で売るしかない。
つまり、同じ様な製品であれば同じ様な価格でないと勝負にならないので値引き販売(売価の低減)が発生する。
日本製は韓国製に対抗するためには156[US$]ではなく46.8%割引の83[US$]で売るしかない。
つまり、同じ様な製品であれば同じ様な価格でないと勝負にならないので値引き販売(売価の低減)が発生する。
■条件2:製造原価の原価率は韓国製も日本製も同じ80%であるとする。
異論はあるが、この条件は判り易くする為の条件だ。日本製品の原価率が高い程円高は利益に直撃する。
韓国製…原価:83*0.8=66.4[US$]、利益:83-66.4=16.6[US$]
日本製…原価:156*0.8=124.8[US$]、利益:83-124.8=-41.8[US$]
日本製は売れば売る程莫大な赤字。
これが、日本から米国に販売しているだけなら、赤字売価(原価を下回る売価)にすることはない。比較的割高な米国製品と近い価格になって米国の消費者が損をし、米国企業が一息つける。一方日本国内では高価だった輸入者の価格が低下する事で日本の消費者と米国企業が少し得をする。
これらの条件から判る様に、円だけ独歩高になることで、日本の輸出産業は壊滅的被害を受けている事が判る。これが米国市場ではなく他の途上国市場を…と述べる人も居るが、円だけが高いと同じ現象が他の通貨でも生じる。
そう、日本国政府は為替戦争をしない。円高を見守るつもりなのだろう。これは自国の産業を守る気がないということと紙一重だ。国策が無い。輸出産業が必要であれば円高を放任できない筈だ。少なくとも韓国Wonと同程度の円高率でないと輸出企業は太刀打ちできない。雇用を守るためには輸出企業が必要なんだけど、その危機感がないことは別に述べる(基本的に一票の格差が原因だ)。
そう、韓国との戦いの前に条件面で差を付けられているのだ。
異論はあるが、この条件は判り易くする為の条件だ。日本製品の原価率が高い程円高は利益に直撃する。
韓国製…原価:83*0.8=66.4[US$]、利益:83-66.4=16.6[US$]
日本製…原価:156*0.8=124.8[US$]、利益:83-124.8=-41.8[US$]
日本製は売れば売る程莫大な赤字。
これが、日本から米国に販売しているだけなら、赤字売価(原価を下回る売価)にすることはない。比較的割高な米国製品と近い価格になって米国の消費者が損をし、米国企業が一息つける。一方日本国内では高価だった輸入者の価格が低下する事で日本の消費者と米国企業が少し得をする。
これらの条件から判る様に、円だけ独歩高になることで、日本の輸出産業は壊滅的被害を受けている事が判る。これが米国市場ではなく他の途上国市場を…と述べる人も居るが、円だけが高いと同じ現象が他の通貨でも生じる。
そう、日本国政府は為替戦争をしない。円高を見守るつもりなのだろう。これは自国の産業を守る気がないということと紙一重だ。国策が無い。輸出産業が必要であれば円高を放任できない筈だ。少なくとも韓国Wonと同程度の円高率でないと輸出企業は太刀打ちできない。雇用を守るためには輸出企業が必要なんだけど、その危機感がないことは別に述べる(基本的に一票の格差が原因だ)。
そう、韓国との戦いの前に条件面で差を付けられているのだ。
■条件3:円高は止まっているとし、売価を83[US$]とする。
さて、儲けを出すための製造原価を売価の83[US$]より低くしなければならない。
韓国製と同じ利益を得るためには製造原価が66.4[US$]であればいい。
ではどうすればその製造原価を低減できるのか。124.8[US$]の原価を66.4[US$]に出来るのか。そしてその影響は?
さて、儲けを出すための製造原価を売価の83[US$]より低くしなければならない。
韓国製と同じ利益を得るためには製造原価が66.4[US$]であればいい。
ではどうすればその製造原価を低減できるのか。124.8[US$]の原価を66.4[US$]に出来るのか。そしてその影響は?
4. 体力消耗
製造原価に占める割合は以下になる。それぞれをどうすれば小さくできるか考えてみよう。
# 直接/間接材料費
# 直接/間接労務費
# 直接/間接経費
# 直接/間接材料費
直接/間接を問わず、規模のメリットが出る。同じ仕様の材料を一括大量購入及び継続購入する事で材料単価を大きく下げることが出来る。ちょっとした仕様の違いで多くの材料を少量ロットで発注すること。
いわゆる業務用のケチャップと数g毎に仕分けられたケチャップを比べれば良い。他にも飲料水を買うときの3Lのペットボトルと550mLのペットボトルなど。大量に買う方が安い。
いずれにしても同じ仕様のモノを大量購入することが重要であり、買い叩くという問題ではない。また、安かろう/悪かろう(品質保証期間を満たさない、危険な化学物質の含有、性能バラツキが大きい、仕様外製品混入率が高い等)の材料は、ブランド価値の毀損になるため、なかなか難しい。この辺は調達部門(間接部門だが)の力に依る。ただし、生産規模を100倍にすれば材料費はかなり下がる。# 直接/間接労務費
人件費削減。給与削減、間接部門の人員削減等のリストラ。海外展開も含まれる。調達部門等を削りたがるが、人員疲弊による影響を考えていない。次世代製品開発のタネを播かない事となり、大抵は様々な事で一歩出遅れる。誰かの後ろを追うだけの時代では研究開発、法務、環境、顧客満足、知的財産等は最低限でよかった(今の中国みたい)だろうが、世界に伍していくというかLEADING COMPANYとなっていくにはこの辺が結構大事。
# 直接/間接経費
本社ビルの電気代等は微々たるものであるが、歩留まりやリワーク、修理も経費である。ま、無駄を省けという精神論の世界。海外展開による労務費と間接経費削減は含まれているが、それでも厳しい。
そう、どう考えても原価半減て無理。生産規模100倍って・・結局固定費莫大化になる。
5.コンテンツが無い
世界的なTV需要の低減は確かにある。そうなると価格競争になる。
そしてより安い価格のTVを買おうとする。その原因(需要低減)が腐ったコンテンツに基づく。
技術のトピックスとオリンピック特需を考えてみよう。実はそれほど関係がない事が判る。オリンピックへの情熱が低下すると共にオリンピックとの関連性が失せている。
そして地デジとBDのハイビジョン。番組登場者の服や髪の質感が際立つ様になった。これ以上の高画質は不要かも。画面も十分に大きい。そしてコンテンツ。オリンピックは素晴らしい。しかしそれ以外のコンテンツはどうだ?
質が低下しているだろう。先が読めるシナリオに学芸会の様なドラマ、気分が悪くなる3DTV、グルメ、旅行、改装・・・。「見たい」から「暇つぶし」になっている。
同じ暇つぶしのネタでも画質が悪かろうが、Youtubeとかネットの特集とかの方が自分にとってためになりそうなネタが転がっている。
実際、ニュース以外(若干バイアスが気になるが)のコンテンツは存在意義がかなり薄れている。天気予報なんか典型的だ。気象庁のサイトを見たらいい。天気予報番組は必要ではない(気象予報士を見たいという特殊事情は除く)。
TV番組全体が凋落していて、コンテンツが要望と乖離しだしている。
今、情報入手のために放送局都合で番組編成を待つ(ニュースは仕方ない)よりも、オンデマンドで簡単に動画情報を入手したいと思う。結局それをスマホやタブレット、PCが実現していて、TV放送である理由が無くなっている。
上記は為替による損失を述べたが、国内需要(なんやかんや言っても1億人ほど居ます)を開拓する為にはハードとソフトが必要。ソフトの出来が悪いからハードを買い替える理由が無い。
3Dだらけにするという血迷った事はして欲しくないが、情報のオンデマンドはそのままスマートTVと発展するだろう。
そしてより安い価格のTVを買おうとする。その原因(需要低減)が腐ったコンテンツに基づく。
技術のトピックスとオリンピック特需を考えてみよう。実はそれほど関係がない事が判る。オリンピックへの情熱が低下すると共にオリンピックとの関連性が失せている。
初めてのTV放送
ラジオ放送(音声のみ)だったのが白黒だろうが画像が見られるのだ。期待値バリバリ高い。短波ラジオは生中継だが、普通のラジオでは特集でしかない。それでも音声ではなく映像を「見たい」という願望が強いからTVが売れた。
初めてのカラー放送
白黒画像からカラーになるのだ。やはり期待値は高い。TVは売れた。なにもオリンピックだけではないと思うが・・・
衛星中継
ついに生中継だ。リアル感溢れる。ステレオ放送、そして少し大画面化が進む。
ビデオ(VHS/ベータ)
自分で録画して「あとから」楽しむ事が出来る。ビデオ入力端子の付いているTVが欲しい。
衛星放送
若干画質が良くて、田舎でも見えるし、通常番組とは違う番組も見る事が出来る。マニアックな映像も楽しめる。BSアンテナと共に…
大画面、フラット画面
殆ど究極のブラウン管。スケバン刑事ではこの大画面による電力不足をネタにしていたこれ以上巨大になると家庭に入らないという懸念が出てきた。しかしAudio Visual化でLaser Diskと共に隆盛だ。ハンディビデオも大ブーム。運動会とか子供の成長を録画。アナログハイビジョンもちょっとは寄与したか。
フラットTV(液晶、プラズマ)
ついに家庭に30インチ以上のTVで大画面の迫力。プロジェクタの様に暗くする必要は無い。
録画媒体の高機能化(Disk録画)
製品のコモディティ化が進みだす。特別な技術(特に組み込み調整)は要らない。
LSIによる信号処理。自動補正回路(元はCDのエラー補正)。画質の差が消えた。
LSIによる信号処理。自動補正回路(元はCDのエラー補正)。画質の差が消えた。
そして地デジとBDのハイビジョン。番組登場者の服や髪の質感が際立つ様になった。これ以上の高画質は不要かも。画面も十分に大きい。そしてコンテンツ。オリンピックは素晴らしい。しかしそれ以外のコンテンツはどうだ?
質が低下しているだろう。先が読めるシナリオに学芸会の様なドラマ、気分が悪くなる3DTV、グルメ、旅行、改装・・・。「見たい」から「暇つぶし」になっている。
同じ暇つぶしのネタでも画質が悪かろうが、Youtubeとかネットの特集とかの方が自分にとってためになりそうなネタが転がっている。
実際、ニュース以外(若干バイアスが気になるが)のコンテンツは存在意義がかなり薄れている。天気予報なんか典型的だ。気象庁のサイトを見たらいい。天気予報番組は必要ではない(気象予報士を見たいという特殊事情は除く)。
TV番組全体が凋落していて、コンテンツが要望と乖離しだしている。
今、情報入手のために放送局都合で番組編成を待つ(ニュースは仕方ない)よりも、オンデマンドで簡単に動画情報を入手したいと思う。結局それをスマホやタブレット、PCが実現していて、TV放送である理由が無くなっている。
上記は為替による損失を述べたが、国内需要(なんやかんや言っても1億人ほど居ます)を開拓する為にはハードとソフトが必要。ソフトの出来が悪いからハードを買い替える理由が無い。
3Dだらけにするという血迷った事はして欲しくないが、情報のオンデマンドはそのままスマートTVと発展するだろう。
6.スマートTV(スマートモニター)
TV番組が、スポンサーのCMの為にあるので、出来が悪くてもそのまま残るだろう。だが、折角の大画面なのでモニターとして活用する必要がある。
これは思いつきだから、あまり突っ込まれても困る。
これは思いつきだから、あまり突っ込まれても困る。
大画面/マルチ画面制御
画面のポップアップ(PCだね)で玄関のモニターが写る。選択肢で自動音声回答を選ぶことが出来る(まるで留守電だ)。
同様に家の監視カメラを制御できても良いだろう。こんなんはWebカメラと多分iPhoneのシリーで出来る様な気がする。
他にも電話がかかってきた事を示すメッセージ、E-mailの着信も有効だろう。
冷蔵庫にカメラをしこんでおけば、何があるかも表示できる。Webカメラを拡張すれば、倉庫の中とか、戸棚の中とかも確認可能だろう。
こういう所にある(冷蔵庫や戸棚)の消耗品類を画像認識としてとらえておけば、冷蔵庫の中の数ヶ月前のなんたらを忘れる事も無い。
戸棚にあるお土産も・・・ってこの辺画像検索機能を持ったGoogleみたいだ。
家の中を検索してしまう(笑)。そういう機能は家電に必要なんだろう。何をいつどうしたかというめんどくさい情報の記憶。
カメラが認識した画像が変化したか、変化しなかったか、(定期的な確認とかが必要だが)、などを覚えておいてくれて、必要な時に検索したら出てくるってかんじだ。
テレビの顔をした執事。これがスマートTVなんだろうね。
ただ今留守にしています。ご用件を・・・。
ご用件は何でしょう?・・・
ご用件は何でしょう?・・・
応対しますので暫くお待ちください。
当方では必要としないご用件ですのですみやかにお引き取りください。
防犯設備があなたをロックオンしました。5秒以内に立ち去ってください。
当方では必要としないご用件ですのですみやかにお引き取りください。
防犯設備があなたをロックオンしました。5秒以内に立ち去ってください。
5秒以内に立ち去らない場合は警備会社と警察に連絡致します。
5.4.3.2.1.0警察に通報しました。警察に通報しました。
5秒以内に立ち去らない場合は防犯設備による自衛行為が開始されます。
5.4.3.2.1.0「....」(冗談ですが)
5.4.3.2.1.0警察に通報しました。警察に通報しました。
5秒以内に立ち去らない場合は防犯設備による自衛行為が開始されます。
5.4.3.2.1.0「....」(冗談ですが)
同様に家の監視カメラを制御できても良いだろう。こんなんはWebカメラと多分iPhoneのシリーで出来る様な気がする。
他にも電話がかかってきた事を示すメッセージ、E-mailの着信も有効だろう。
冷蔵庫にカメラをしこんでおけば、何があるかも表示できる。Webカメラを拡張すれば、倉庫の中とか、戸棚の中とかも確認可能だろう。
こういう所にある(冷蔵庫や戸棚)の消耗品類を画像認識としてとらえておけば、冷蔵庫の中の数ヶ月前のなんたらを忘れる事も無い。
戸棚にあるお土産も・・・ってこの辺画像検索機能を持ったGoogleみたいだ。
家の中を検索してしまう(笑)。そういう機能は家電に必要なんだろう。何をいつどうしたかというめんどくさい情報の記憶。
カメラが認識した画像が変化したか、変化しなかったか、(定期的な確認とかが必要だが)、などを覚えておいてくれて、必要な時に検索したら出てくるってかんじだ。
テレビの顔をした執事。これがスマートTVなんだろうね。
7. 国策無策
上述の円の独歩高に対する政治家の無反応について考えてみた。
情報産業だ!とSNSサイトを開いても、広告がなぜ機能しないのか。簡単だ。
普通に働いている人が働いた分だけ稼ぎを得て、その稼ぎで欲しいものを買う。広告を撃たれても、金がなければ買わない。ウィンドウショッピングでおしまい。
ま、情報産業というのは出版業のビジネスモデルと同じなのかもしれんが。
さて、そろそろ復活策へもっていかないといけない。
一票の格差が理由だろう。
最高裁判所は、衆議院で約2倍以上、参議院で約6倍以上の差が生じた場合には、違憲ないしは違憲状態と判決を下した。
2009年衆院は2.3倍で違憲。2007年参院が4.46倍で合憲。とあるが、どちらも2倍以内に是正すべきだろう。しかし、是正されない。
この格差は都市の住民の意見を国策に反映する為には、農村部の住民よりも多くの議員を必要とする事を意味する。
■都市部の住民。
主に第二次産業、第三次産業の従事者である。第二次産業は輸出関連企業が多い。
円高による輸入消耗品の低価格化の影響は受ける。しかし輸出物品の利益削減の影響は莫大で、退職、減給等が生じる。海外の動向を受けるが、国内需要が旺盛であればその影響は小さい。ただし海外利益を喪失すると可処分所得が急減するため、第三次産業へ影響する。
第三次産業は国内サービス産業であり、輸出減の影響は少ない様に見えるが、主要顧客である第二次産業従事者の可処分所得が減少すると第三次産業の売上が減少する。
■農村部の住民。
主に第一次産業の従事者である。国内市場での消費動向が最も気になる。円高によって海外の生鮮食品が安価に流通することを極端に嫌う。そのため高関税による輸入措置を取ろうとする。
しかし、円高では原油等が安く購入でき、経費削減となる為円高の維持を望んでいる。関税さえあれば、輸入製品を止められるが、その円高差益を還元しようとしない傾向がある。それは老後が心配、孫が心配、土地を維持する為には金がいる。といってもの凄いため込んでいる筈だ。農協バンクがバンバン広告をうってくるのもそのせい。溜め込んだ金を使わないから、国内需要は先細り。バブルとは全く逆。
また、インフラ整備となる公共工事の主な担い手である。
ちょっと整理してみよう。
関税で生鮮品の価格を高く維持。これらで儲かった金を農協バンク等で溜め込んでいる。その有権者は農村部の住民であるから、金を使わずに溜め込むための政策と円高を重視する。
公共工事が主に農村部で行われている事(人口の割にってこと)を考えると、インフラ整備で潤った金をやはり溜め込んでいるのだろう。円高になると資材を安く買えるから、材料費低下、燃料費低下で内需産業としては言う事が無い。
政府が円の独歩高に無関心になるのは都市部の二倍以上の農民票を考えているからだろう。だからTPP反対なんだ。
しかし、外貨稼ぎ頭である輸出産業が衰退すると国内インフラ産業と農業だけではギリシャの様に破綻する事が容易に想像できる。
想像してみよう。第一次産業と公共工事、そして観光産業しかない国。
どうやって外貨を稼ぐのだろう。自国製の工業製品とは縁が無くなる。そういう社会を我らは望んでいるのだろうか。
情報産業や金融で・・・虚業だろう。
情報産業といわれて華々しいFaceBook。あれがなぜ市場でもてはやされ、そして冷ややかに見られるようになったか考えればわかる。友人との接点は非情に良い事だ。だが、それがFBの価値ではない。FBの価値は参加者がどういうものに興味を示すかというデータを得る事だ。。たくさんの人が「いいね」をする情報を集め、その情報とリンクする商品を広告として表示する。
例)A氏が琵琶湖でアレキサンドリアを使ったらでかいビワマスが釣れた!とFBで日記を書いた。
Aが実名登録だ。Bや、Cが「いいね」を押す。友人の友人へと情報が流れていく。それはいいね。中にはBの友人であるHが「俺も琵琶湖でアレキサンドリアを使ってビワマスを釣ったぜ」と写真付きで・・・という風に広がっていく。
実名情報だ。アレキサンドリア、琵琶湖、ビワマス、釣りというキーワードが広がる。同時に相関性があるキーワードになる。これをもっと引っ張っていくと、アレキサンドリア、フライ、ブラウントラウト、ニュージーランドとかでガンガン広がっていく。そうなるといつの間にかAに「ニュージーランドでフライフィッシングをするならPPP社へ」とか「フライ・・・いう広告が入る。冒頭で述べたAは「フライ」とは書いていない。広告業界に取ってそういう口コミ情報を元にして、ターゲットへ直接広告を撃つ事は非情に効果的と考える。
しかし、FaceBookの参加者がそういう広告を「うざい」と感じだすと・・・隠語を使う様になる。するとFaceBookの集めた情報によるターゲット広告の効率性が、Googleの検索情報を元に撃ってくる広告を同定の効率になり、Amazonに負けそうだと、クライアントが判定したら・・・広告を出す意味が無いと考えてFaceBookの株価は下がる。かといってFaceBookがこっそりと収集した個人情報を企業に売ると、Googleたたき以上の事が発生するだろう。
最高裁判所は、衆議院で約2倍以上、参議院で約6倍以上の差が生じた場合には、違憲ないしは違憲状態と判決を下した。
2009年衆院は2.3倍で違憲。2007年参院が4.46倍で合憲。とあるが、どちらも2倍以内に是正すべきだろう。しかし、是正されない。
この格差は都市の住民の意見を国策に反映する為には、農村部の住民よりも多くの議員を必要とする事を意味する。
■都市部の住民。
主に第二次産業、第三次産業の従事者である。第二次産業は輸出関連企業が多い。
円高による輸入消耗品の低価格化の影響は受ける。しかし輸出物品の利益削減の影響は莫大で、退職、減給等が生じる。海外の動向を受けるが、国内需要が旺盛であればその影響は小さい。ただし海外利益を喪失すると可処分所得が急減するため、第三次産業へ影響する。
第三次産業は国内サービス産業であり、輸出減の影響は少ない様に見えるが、主要顧客である第二次産業従事者の可処分所得が減少すると第三次産業の売上が減少する。
ファーストフードの従業員の人件費は国際競争に晒されていない。ファーストフード店員の時給はサービスが同じであれば日本とインドで同じであるべきだ。しかし、日本の方が圧倒的に高価だ。これは日本語空間という閉鎖的な空間が成せる技(日本語で会話する技術を持っている)とみなす事も可能であるが、それでも高すぎる。ただし、インフラ使用料等を考えるとその時給でないと働く意味が無くなる。そう、国際競争に晒されていないのは公共交通機関の運賃やインフラ(電気、水道、ガス・・・)である。これらはひっくるめて第三次産業と言え、暴利をむさぼっていると言える。
インフラ価格が低下すれば、第二次産業の可処分所得が増え、第三次産業のサービス業が潤う。じゃ、そのインフラ価格の元ってかなり政治に関わる。工事費は談合最低価格で決めるため、絶対に利益が出る。そうやって政治主導のインフラ(コンクリート)で潤った金を使わずに貯めているならば、日本の景気を損なう行為であり犯罪者なみに悪いと言える。金を使わないと景気は良くならないのだから。■農村部の住民。
主に第一次産業の従事者である。国内市場での消費動向が最も気になる。円高によって海外の生鮮食品が安価に流通することを極端に嫌う。そのため高関税による輸入措置を取ろうとする。
しかし、円高では原油等が安く購入でき、経費削減となる為円高の維持を望んでいる。関税さえあれば、輸入製品を止められるが、その円高差益を還元しようとしない傾向がある。それは老後が心配、孫が心配、土地を維持する為には金がいる。といってもの凄いため込んでいる筈だ。農協バンクがバンバン広告をうってくるのもそのせい。溜め込んだ金を使わないから、国内需要は先細り。バブルとは全く逆。
また、インフラ整備となる公共工事の主な担い手である。
ちょっと整理してみよう。
関税で生鮮品の価格を高く維持。これらで儲かった金を農協バンク等で溜め込んでいる。その有権者は農村部の住民であるから、金を使わずに溜め込むための政策と円高を重視する。
公共工事が主に農村部で行われている事(人口の割にってこと)を考えると、インフラ整備で潤った金をやはり溜め込んでいるのだろう。円高になると資材を安く買えるから、材料費低下、燃料費低下で内需産業としては言う事が無い。
政府が円の独歩高に無関心になるのは都市部の二倍以上の農民票を考えているからだろう。だからTPP反対なんだ。
しかし、外貨稼ぎ頭である輸出産業が衰退すると国内インフラ産業と農業だけではギリシャの様に破綻する事が容易に想像できる。
想像してみよう。第一次産業と公共工事、そして観光産業しかない国。
どうやって外貨を稼ぐのだろう。自国製の工業製品とは縁が無くなる。そういう社会を我らは望んでいるのだろうか。
情報産業や金融で・・・虚業だろう。
情報産業といわれて華々しいFaceBook。あれがなぜ市場でもてはやされ、そして冷ややかに見られるようになったか考えればわかる。友人との接点は非情に良い事だ。だが、それがFBの価値ではない。FBの価値は参加者がどういうものに興味を示すかというデータを得る事だ。。たくさんの人が「いいね」をする情報を集め、その情報とリンクする商品を広告として表示する。
例)A氏が琵琶湖でアレキサンドリアを使ったらでかいビワマスが釣れた!とFBで日記を書いた。
Aが実名登録だ。Bや、Cが「いいね」を押す。友人の友人へと情報が流れていく。それはいいね。中にはBの友人であるHが「俺も琵琶湖でアレキサンドリアを使ってビワマスを釣ったぜ」と写真付きで・・・という風に広がっていく。
実名情報だ。アレキサンドリア、琵琶湖、ビワマス、釣りというキーワードが広がる。同時に相関性があるキーワードになる。これをもっと引っ張っていくと、アレキサンドリア、フライ、ブラウントラウト、ニュージーランドとかでガンガン広がっていく。そうなるといつの間にかAに「ニュージーランドでフライフィッシングをするならPPP社へ」とか「フライ・・・いう広告が入る。冒頭で述べたAは「フライ」とは書いていない。広告業界に取ってそういう口コミ情報を元にして、ターゲットへ直接広告を撃つ事は非情に効果的と考える。
しかし、FaceBookの参加者がそういう広告を「うざい」と感じだすと・・・隠語を使う様になる。するとFaceBookの集めた情報によるターゲット広告の効率性が、Googleの検索情報を元に撃ってくる広告を同定の効率になり、Amazonに負けそうだと、クライアントが判定したら・・・広告を出す意味が無いと考えてFaceBookの株価は下がる。かといってFaceBookがこっそりと収集した個人情報を企業に売ると、Googleたたき以上の事が発生するだろう。
情報産業だ!とSNSサイトを開いても、広告がなぜ機能しないのか。簡単だ。
普通に働いている人が働いた分だけ稼ぎを得て、その稼ぎで欲しいものを買う。広告を撃たれても、金がなければ買わない。ウィンドウショッピングでおしまい。
ま、情報産業というのは出版業のビジネスモデルと同じなのかもしれんが。
さて、そろそろ復活策へもっていかないといけない。
8. 復活策
1) 先に述べたスマートモニター
これはTVコンテンツというよりも、何でもモニターしてやれという発想。モニターは情報の窓。情報は何もインターネットから引っ張ってくるだけじゃない。日々の生活も情報に包まれている。
そして、この高解像度モニターとできのよいWebカメラが一体化すれば、医者との診断も楽になる。高齢者が医者に通うのではなく、特定時間に医者とコンタクトすれば良い。「どうですか」をもっと気軽にすることもできるだろう。特に荒天時に役立つと思われる。こういう管理もスマートTVの執事がやってくれたらいいね。薬のデリバリーサービスとも連携して欲しい。単に繋ぐだけじゃなく「執事コンテンツ」が重要になりそうだ。
そして、この高解像度モニターとできのよいWebカメラが一体化すれば、医者との診断も楽になる。高齢者が医者に通うのではなく、特定時間に医者とコンタクトすれば良い。「どうですか」をもっと気軽にすることもできるだろう。特に荒天時に役立つと思われる。こういう管理もスマートTVの執事がやってくれたらいいね。薬のデリバリーサービスとも連携して欲しい。単に繋ぐだけじゃなく「執事コンテンツ」が重要になりそうだ。
2) 規制緩和と一票の格差解消
規制緩和。これは景気を良くするための手段だ。既得権益が高い利益をむさぼって金を溜め込んでいるなら、景気抑制のため、ここの利益を他の人々に配布すべきだ。これが規制緩和になる。関税廃止も規制緩和になるかもしれんな。
景気をよくするには金を使うしかない。必要以上に(レベルは難しいが)金を溜め込んでいるということは経済が止まるという事だ。
一票の格差の解消は、地方の公共工事や第一次産業の投資効率向上に繋がる。
公共工事はやればいい。だが、その金がどう使われてどの様に景気に影響したのか、景気を刺激したのか?それを実証しないのなら、全くダメだ。
関税廃止、TPP導入という楽市楽座的発想へ持っていく為には一票の格差を解消するしかない。単純に一票の格差が2倍ということは、国民の1/3が都市で2/3が農村ということか。都市の意見は農村にかき消されるが、本当に国策を考えた議員なんだろうか?ってのが気になるな。
景気をよくするには金を使うしかない。必要以上に(レベルは難しいが)金を溜め込んでいるということは経済が止まるという事だ。
一票の格差の解消は、地方の公共工事や第一次産業の投資効率向上に繋がる。
公共工事はやればいい。だが、その金がどう使われてどの様に景気に影響したのか、景気を刺激したのか?それを実証しないのなら、全くダメだ。
関税廃止、TPP導入という楽市楽座的発想へ持っていく為には一票の格差を解消するしかない。単純に一票の格差が2倍ということは、国民の1/3が都市で2/3が農村ということか。都市の意見は農村にかき消されるが、本当に国策を考えた議員なんだろうか?ってのが気になるな。
9. 雑感
大風呂敷を拡げたが、何もしないままだとギリシャになる。たかがTVだが、その根本は国の円の独歩高への無策が深く寄与している。その理由が一票の格差と公共工事関連に繋がっているという仮説は大胆かもしれないが、的を射ている様な気がしている。第二次産業(特に輸出関連)が衰退すると、国そのものが衰退する。だからTPPも必要だと考えている。
震災後、この国をどうしていきたいのかというビジョンが見えなくなった。円の独歩高は輸出産業を虫の息にした。自動車は補助金で生き延びているが、このままだと海外生産のみになる。
円高を止めると火力発電の燃料費代が大幅に上昇するので、円高で燃料費代の高騰を防いでいるというのなら、燃料費代を節約できる原子力発電を再開すべきだろう。そうすれば円安政策がとれ、輸出産業は一息つける。
産業構造が原発がある事を念頭にしているのだから、変なところでボトルネックを作ると国がこける。確かに放射線は危ない。だがビビりまくって必要な物を止めるのは単なるパニックだ。(まるでアメリカ映画で「もう私達は死んじゃうのよ、どうしようもないのよワー」と叫ぶ女優のようだ)
追記
ここも参照にした方が良いだろう。
ハードの向上を目指すのではなく、情報処理能力の向上を目指す。
一方、いわゆるコンテンツ(音楽、映像、画像、書籍)はデジタル化されたが、家電製品の目的である「快適な生活空間の実現」ではデジタル化が難しい。白物家電。調理、洗濯、空調、照明...これらは人間の欲望というよりも如何にして快適を得るかに繋がる。家内労働(家事)の時間短縮。心地よい空間(アメニティっていうのかな)と時間の創出だ。キツい家事から解放され、自由時間を得る(それでボケッとTVを見てるかもしれんが)。白物家電そのものが執事である。音楽にせよ「コンテンツ」は全部まがい物だ(目の前で本当に生じている事象ではないということ。)記録をデジタル化することはできたが、アメニティの「感覚」をデジタル化する事は難しい。
一方、快適、心地よい、いい気持ちってのはコンテンツに依る感動等以外に、空調や味覚や臭覚も寄与している。さらに製品に関する情報も寄与してくる。これは製品の心地よいデザインだけじゃない。地球環境維持を心がけた材料であるなどの「エコロジー」も関わってくるだろう。
ま、長くなるのでここまでにするが、IT(コンテンツ)以外で勝負するしか無いと思う。白物家電の情報処理ってのはこれから必要になるかもしれない。HEMSとは別に。
これは少し簡略化しすぎたかもしれないので、補足する。
電子情報機器は情報(コンテンツ)フリー(無料という意味じゃない)の為の一つの歯車。「オンデマンドで簡単に動画情報を入手したい」と上述している。
これはまさにCloudの考えで、リンク先はもう少し盛り易く説明している。概要はこうだ。iPhoneで電子書籍をP200まで読む。P201からはiPadで。だが、その電子書籍を開くと勝手にその既読箇所まで行く。次にPCで見てもその既読ポイント迄自動的に行く。
こういう機能はデバイス、商品単品ではあり得ない。教材でも良いし、映画でも同じ事が言える。そういうコンテンツ管理がしっかりなされていれば・・・ってiCloudも同じ発想である。iCloudにあるデータはそれぞれのデバイスでいじった内容がそのまま反映される。iMacで作成したテンプレートを新幹線(東海道N700)車内でiPadを開いて修正。ローカル線では3G回線だけどiPhoneで確認。さらに共通IDでログインできれば、同僚による修正も可能。この辺はITっぽさが出ているが、我々の普段の生活に置き換えてみると、連絡事項はスマートフォンでもPCでも何でも共有ってことになるだろう。となれば、セキュリティ部門が色々頑張って製品開発できそうだ。電子情報機器は情報(コンテンツ)フリー(無料という意味じゃない)の為の一つの歯車。「オンデマンドで簡単に動画情報を入手したい」と上述している。
これはまさにCloudの考えで、リンク先はもう少し盛り易く説明している。概要はこうだ。iPhoneで電子書籍をP200まで読む。P201からはiPadで。だが、その電子書籍を開くと勝手にその既読箇所まで行く。次にPCで見てもその既読ポイント迄自動的に行く。
一方、いわゆるコンテンツ(音楽、映像、画像、書籍)はデジタル化されたが、家電製品の目的である「快適な生活空間の実現」ではデジタル化が難しい。白物家電。調理、洗濯、空調、照明...これらは人間の欲望というよりも如何にして快適を得るかに繋がる。家内労働(家事)の時間短縮。心地よい空間(アメニティっていうのかな)と時間の創出だ。キツい家事から解放され、自由時間を得る(それでボケッとTVを見てるかもしれんが)。白物家電そのものが執事である。音楽にせよ「コンテンツ」は全部まがい物だ(目の前で本当に生じている事象ではないということ。)記録をデジタル化することはできたが、アメニティの「感覚」をデジタル化する事は難しい。
そりゃ脳みそに電極ぶち込んでくそ暑い中を寒いと思わす事は可能だが、熱中症で殺すことになる。
香りをまき散らす事、触感(これはVRでかなり改善されてきた)や温感、冷感は難しい。だが、情報は使える筈だ。エアコンを入れてどういう設定にしたのか?温度を下げたのか、除湿なのか?扇風機も一気に廻した。なぜ?その前に風呂に入っていた。熱いから涼しくしている。という行動なら家屋内で行動が読める筈だ。この辺は行動心理学の世界かもしれないが・・・。一方、快適、心地よい、いい気持ちってのはコンテンツに依る感動等以外に、空調や味覚や臭覚も寄与している。さらに製品に関する情報も寄与してくる。これは製品の心地よいデザインだけじゃない。地球環境維持を心がけた材料であるなどの「エコロジー」も関わってくるだろう。
ま、長くなるのでここまでにするが、IT(コンテンツ)以外で勝負するしか無いと思う。白物家電の情報処理ってのはこれから必要になるかもしれない。HEMSとは別に。