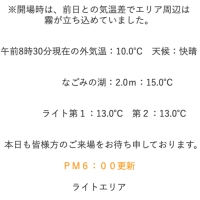新技術としてもてはやされている。金型不要が売りだが、本当に優れているのか疑問。
加工は削り出しと鋳型注入に分けられる。
削り出し
鋳型注入
3Dプリンターで使える材料はUV硬化樹脂(光成形、光造形)と一部の金属粉末の溶融焼成(セラミックは無理と思う)となる。
UV樹脂
金属粉末の溶融焼成
というわけで、新技術だぁと騒ぐ前にちょっと考えたり思い出したり、調べれば色々わかる。
この辺の欠点が克服されていれば脱帽だ。
加工は削り出しと鋳型注入に分けられる。
削り出し
無駄の極致だが、残留熱応力が少ないため、工作物の寸法精度が高い。通常は鋳型注入よりも高精度のものを作ることが出来る。ただし、加工歪みの限界があるため、薄いものを削りだす事は叶わない。その場合は板を加工する。
また、あまりにも複雑なものは困難だ。そして量産性は悪い。石をノミで削りだすようなものだ。
また、あまりにも複雑なものは困難だ。そして量産性は悪い。石をノミで削りだすようなものだ。
鋳型注入
加熱溶融後、冷却固化する材料はなんでもOK。しかし溶融時と冷却後の収縮に基づく内部残留応力が課題。
一方で、少量の合金を鋳型に流し込むので材料の特性を活かすこともできる。
樹脂であれば強度向上の為の繊維や無機材料(フィラーというが)を分散させる事もできる。
コンクリートの塊り等も鋳型注入と考えてよいだろう。なお、鋳造勝つ鍛造も不可能ではない。実際、アルミホイール等は鋳造でありながら鍛造である。
一方で、少量の合金を鋳型に流し込むので材料の特性を活かすこともできる。
樹脂であれば強度向上の為の繊維や無機材料(フィラーというが)を分散させる事もできる。
コンクリートの塊り等も鋳型注入と考えてよいだろう。なお、鋳造勝つ鍛造も不可能ではない。実際、アルミホイール等は鋳造でありながら鍛造である。
3Dプリンターで使える材料はUV硬化樹脂(光成形、光造形)と一部の金属粉末の溶融焼成(セラミックは無理と思う)となる。
UV樹脂
アクリル樹脂やポリスチレン等のビニル基を持つラジカル重合型のUV硬化樹脂を使うことになる。
一般的にはこういう作り方だ。
しかし、エンジニアリングプラスチック(エンプラ)であるポリカーボネート、ナイロン系、POM、PEN等は使えない。
UV硬化樹脂に剛性、寸法安定性、柔軟性(粘り)などを分子設計で持たす事は不可能ではないが、特別注文の樹脂材料はちょっと扱いにくいかもしれない。
光硬化以外にマシニングセンターでの削りだしも不可能ではないが、これは3Dプリンターとは違う様な気がする。
つまり、材料選択幅が狭くなるという事だ。
一般的にはこういう作り方だ。
液体状態で未硬化のUV樹脂液を容器に展開する。
液体の表面をUVレーザーでなぞり、レーザー照射部だけを硬化する。
硬化後、液を追加充填し、またレーザーを照射する。
そうやって光硬化しながら未硬化の液体を注ぎ足して行くと螺旋(階段)状にモノが形作られる。
最後は液体から取り出し、貧溶媒であるエタノール等で未重合のモノマーを洗い落とせば完成。
光硬化システムから酸素と除く事で硬化反応は速くなると思われる。
液体の表面をUVレーザーでなぞり、レーザー照射部だけを硬化する。
硬化後、液を追加充填し、またレーザーを照射する。
そうやって光硬化しながら未硬化の液体を注ぎ足して行くと螺旋(階段)状にモノが形作られる。
最後は液体から取り出し、貧溶媒であるエタノール等で未重合のモノマーを洗い落とせば完成。
光硬化システムから酸素と除く事で硬化反応は速くなると思われる。
しかし、エンジニアリングプラスチック(エンプラ)であるポリカーボネート、ナイロン系、POM、PEN等は使えない。
UV硬化樹脂に剛性、寸法安定性、柔軟性(粘り)などを分子設計で持たす事は不可能ではないが、特別注文の樹脂材料はちょっと扱いにくいかもしれない。
光硬化以外にマシニングセンターでの削りだしも不可能ではないが、これは3Dプリンターとは違う様な気がする。
つまり、材料選択幅が狭くなるという事だ。
金属粉末の溶融焼成
考え方は同じ。金属粉末の表面に赤外線レーザーを照射し、照射部を溶融固化し、粉体から片にする。
固化後、金属粉末を振りかけ、改めてレーザーで溶融固化。これを繰り返すと3Dプリンターとしてモノを作る事は出来る。
しかし、金属とはいえ微結晶のサイズが問題である。完全非晶質(アモルファス)でいくのか、多結晶で作るのかってことになる。
まだ、金属の結晶サイズは制御出来ないと思う。各層が薄ければ・・・?多分無理だろう
固化後、金属粉末を振りかけ、改めてレーザーで溶融固化。これを繰り返すと3Dプリンターとしてモノを作る事は出来る。
しかし、金属とはいえ微結晶のサイズが問題である。完全非晶質(アモルファス)でいくのか、多結晶で作るのかってことになる。
まだ、金属の結晶サイズは制御出来ないと思う。各層が薄ければ・・・?多分無理だろう
というわけで、新技術だぁと騒ぐ前にちょっと考えたり思い出したり、調べれば色々わかる。
この辺の欠点が克服されていれば脱帽だ。