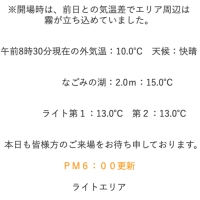結論は印刷物並みの表示品位を反射型表示素子で達成することはほぼ不可能であるということ。つまり蓄電池の進歩に期待したAppleのiPadが我々の欲する方向なんだって事。
電子ペーパーの表示素子は透過型なので自発光に近い液晶表示素子かE-inkの闘いになる。
液晶の優位点
動画対応・フルカラー
E-inkの優位点
目に優しい・長電池寿命・装置軽量
液晶の欠点
透過型で目が疲れる・電池寿命が短い・バックライトで重い。
E-inkの欠点
白黒のみ。部分書き換えも困難。だから電子辞書に採用されていない。
さて、最近QualcomがMirasol(実はiModという干渉系)をアピールしてきた。
最も近い表示方式は富士通のコレステリック液晶になる。
だが、どちらも時代の徒花になるだろう。
まず、iModつうかMirasolは3分割のため明るい白が出せない。
これは画素分割型反射型表示素子の最大の欠点である。これに気づかない人は多いようだ。
さて、確かにiModは干渉色で有名なモルフォ蝶の鱗粉を模した干渉構造であり、人工的にその色を出せる。しかし、干渉色でモンシロチョウの白は出せない。
モンシロチョウの白は拡散光(リンクはpdf)のためだからだ。
RGBで面内分割した構造では灰色は出せても明るい白は出ないし、演色性も悪くなる。
RGBダイアゴナル配列ではこのようになる。

赤はRGBのRだけを点灯して他は非点灯。同様に青はBだけ、緑はGだけ。そしてRGBをフル表示させても白にならない。ここで目前のパソコンモニタが白を表示しているのになぜ白にならない?となる。
それには「白」とは何かという問題が絡んでくる。
白とはRGBのバランスが均一化されている状態である。
バランスが崩れて特定波長の光が強いか弱いと着色して見える。
ここで、自発光表示と反射型表示の大きな違いがある。
上図で自発光表示の場合、黒い領域にR,G,Bがそれぞれ点灯しているわけで夜空の星みたいなものだ。だからRGBそれぞれがそれなりに見える。
(だから太陽光の下では相対的に暗い自発光型は殆ど見えない。ノートPCを屋外に持って行けばよくわかる。)
だが、反射型になると屋外では明るくなるはずだが実際はそうならない。下に縮小表示したようにかなり暗くなる。これは「赤・黒・黒」という表示のためだ。

その辺の印刷物を見て欲しい。表示は「赤点」「青点」「緑点」そして重なって「黒」となっている。最小分解能はドットサイズで全てが「赤」だ。
逆に一画素(ドット)が「赤・黒・黒」となると暗い赤になる。さらに、RGBがフル点灯しても灰色にしかならない。

縮小するとこの様にRGBが入り交じって灰色になる。




この白の明るさはE-inkに叶わない灰色だし、それでいてiPadの自発光白にも及ばない。
というわけで、干渉色を使おうが面内分割している限り反射型では暗いってのが致命的。強烈な太陽光(まぶしい世界)では確かに暗い反射型表示素子でも明るく見える。だが、それは我々が欲しい物ではない。我々はあくまでも屋内のせいぜい1000Lx程度で本を読むようにしたいのであって、真夏の砂浜で本を読みたいわけじゃない。
なお、E-inkカラー商品が無いのは構造的に画素分割RGBのカラーフィルターを設置するしかなく、どうやっても暗くなるためであろう。
となると、我々に残された電子ブックの選択肢は下記の2点となる。
1)Apple iPadの様に通常液晶と今後の高性能蓄電池。
2)画素積層型カラー表示素子(富士通方式)。・・・これも徒花と書いた。
個人的には1)じゃないかと思う。
2)が徒花と書いたのはフレッピアが売れていないことに起因する(話題にもなっていない)。
他の理由も知っているが、それは秘密だ。
電子ペーパーの表示素子は透過型なので自発光に近い液晶表示素子かE-inkの闘いになる。
液晶の優位点
動画対応・フルカラー
E-inkの優位点
目に優しい・長電池寿命・装置軽量
液晶の欠点
透過型で目が疲れる・電池寿命が短い・バックライトで重い。
E-inkの欠点
白黒のみ。部分書き換えも困難。だから電子辞書に採用されていない。
さて、最近QualcomがMirasol(実はiModという干渉系)をアピールしてきた。
最も近い表示方式は富士通のコレステリック液晶になる。
だが、どちらも時代の徒花になるだろう。
まず、iModつうかMirasolは3分割のため明るい白が出せない。
これは画素分割型反射型表示素子の最大の欠点である。これに気づかない人は多いようだ。
さて、確かにiModは干渉色で有名なモルフォ蝶の鱗粉を模した干渉構造であり、人工的にその色を出せる。しかし、干渉色でモンシロチョウの白は出せない。
モンシロチョウの白は拡散光(リンクはpdf)のためだからだ。
RGBで面内分割した構造では灰色は出せても明るい白は出ないし、演色性も悪くなる。
RGBダイアゴナル配列ではこのようになる。

赤はRGBのRだけを点灯して他は非点灯。同様に青はBだけ、緑はGだけ。そしてRGBをフル表示させても白にならない。ここで目前のパソコンモニタが白を表示しているのになぜ白にならない?となる。
それには「白」とは何かという問題が絡んでくる。
白とはRGBのバランスが均一化されている状態である。
バランスが崩れて特定波長の光が強いか弱いと着色して見える。
ここで、自発光表示と反射型表示の大きな違いがある。
上図で自発光表示の場合、黒い領域にR,G,Bがそれぞれ点灯しているわけで夜空の星みたいなものだ。だからRGBそれぞれがそれなりに見える。
(だから太陽光の下では相対的に暗い自発光型は殆ど見えない。ノートPCを屋外に持って行けばよくわかる。)
だが、反射型になると屋外では明るくなるはずだが実際はそうならない。下に縮小表示したようにかなり暗くなる。これは「赤・黒・黒」という表示のためだ。

その辺の印刷物を見て欲しい。表示は「赤点」「青点」「緑点」そして重なって「黒」となっている。最小分解能はドットサイズで全てが「赤」だ。
逆に一画素(ドット)が「赤・黒・黒」となると暗い赤になる。さらに、RGBがフル点灯しても灰色にしかならない。

縮小するとこの様にRGBが入り交じって灰色になる。



この白の明るさはE-inkに叶わない灰色だし、それでいてiPadの自発光白にも及ばない。
というわけで、干渉色を使おうが面内分割している限り反射型では暗いってのが致命的。強烈な太陽光(まぶしい世界)では確かに暗い反射型表示素子でも明るく見える。だが、それは我々が欲しい物ではない。我々はあくまでも屋内のせいぜい1000Lx程度で本を読むようにしたいのであって、真夏の砂浜で本を読みたいわけじゃない。
なお、E-inkカラー商品が無いのは構造的に画素分割RGBのカラーフィルターを設置するしかなく、どうやっても暗くなるためであろう。
となると、我々に残された電子ブックの選択肢は下記の2点となる。
1)Apple iPadの様に通常液晶と今後の高性能蓄電池。
2)画素積層型カラー表示素子(富士通方式)。・・・これも徒花と書いた。
個人的には1)じゃないかと思う。
2)が徒花と書いたのはフレッピアが売れていないことに起因する(話題にもなっていない)。
他の理由も知っているが、それは秘密だ。