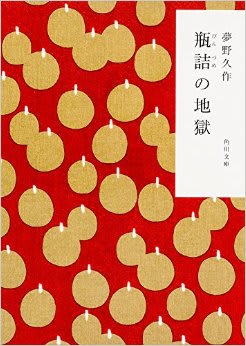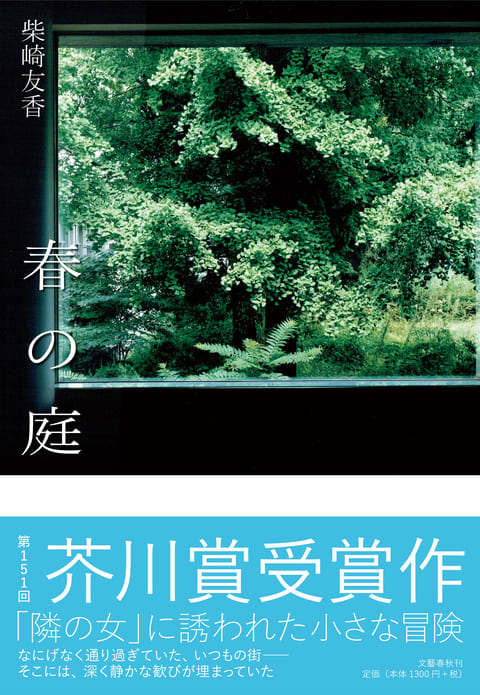こんにちは、暑くなってきましたね。最近寝不足なただけーまです。中堅社員になりつつあるので早寝を心がけたいものです。
久しぶりに文学の更新です。日本ホラー小説大賞を受賞した澤村伊智さんの『ぼぎわんが、来る』を読みました。
ホラー小説はかなり久しぶりで、赤川次郎の『忘れな草』以来だったかも?夢野久作もホラーっぽいのは何点かありますが、ホラーと銘打つほどではないですね。
この作品、本当に面白いで . . . Read more
おはようございます。ようやく暖かくなってきましたね。落ち着いたら誰かお花見でも行きましょう。
桜庭一樹さんの『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』を読みました。
映画化された桜庭一樹さんの『私の男』は観ましたが、小説は初めて読みます。こういう口語調のライトな小説を読むのは久しぶりでしたが、扱っているテーマが重く心にずっしりくる内容。救えない結末がなんとも哀しい物語ですが、横行している児童虐待の問 . . . Read more
おはようございます。東京都で一番治安の良い区から一番悪い区に引越してカルチャーショックを受けているただけーまです。
久しぶりに文学の更新ということで、本谷有希子さんの『異類婚姻譚』の感想を書かせていただきます。
第154回芥川賞を受賞した本作。タイトルのインパクトもそうですが、物語の構成も最近の芥川賞とは一線を画す、夫が人外に成っていくという奇妙な物語です。『聊斎志異』を彷彿とさせる奇譚設定 . . . Read more
公約通り、大江の各短編の所感を書いていきます。全部書けるかはわかりませんが、とりあえず書けそうなものから。
【死者の奢り】
大学生である僕と女学生が、死体処理室に保管されていた遺体を新しい水槽に移し替える仕事に従事していく中で、死と生と身体の在り方に関する問いが繰り広げられていく非常に哲学的な小説です。
特に女性アルバイトが妊娠していたことが発覚するシーンでは、新しい生命を宿した妊婦が死体を扱う . . . Read more
こんばんは。久しぶりに文学での更新。ずっと読もうと思っていた大江健三郎の短編作品集を読みましたので、その所感を記します。
文壇デビュー作である『死者の奢り』と芥川賞受賞作『飼育』を表題とするこの短編集、全部で6篇収録されていましたがどれも非常に読み応えのある短編ばかりでした。
■『死者の奢り・飼育』収録目録
死者の奢り (「文學界」昭和32年8月号)
他人の足 (「新潮」昭和32年8月号)
飼育 . . . Read more
性欲と異性愛は表裏一体で不可分でしょうか。異性愛あるところに性欲があり、性欲があるところに異性愛がある。それでは純粋な異性愛や純粋な性欲は実現し得ないのでしょうか。
そんな疑問を投げかけてくれるのが、デカダン文学を代表する川端康成の「眠れる美女」です。決して目覚めない若い裸の女性と眠る場を提供するある館と、その館にのめりこんでいく江口老人というエロジジイの話です。
三島由紀夫をして「形式的完成美 . . . Read more
◇第三の瓶の内容(全文)
オ父サマ、オ母サマ。ボクタチ兄ダイハ、ナカヨク、タッシャニコノシマニ、クラシテイマス。ハヤク、タスケニ、キテクダサイ。
市川太郎
イチカワアヤコ
◇第一の瓶の内容(抜粋)
ああ、手が慄えて、心が倉皇て書かれませぬ。涙で眼が見えなくなります。私達二人は、今から、あの大きな船の真正面に在る高い崖の上に登って、お父様や、お母様や救いに来て下さる水夫さん達によく見えるように、 . . . Read more
こんにちは。お久しぶりです。ただけーまです。もう年も暮れると思うとやる瀬ない感情に陥りますね。2014年も本当にあっという間で、社会に出てからの圧倒的時間の流れの早さにしみじみ感じ入っております。(本当に今の学生諸君は楽しんでおきなさい!)
というわけで(?)珍しくも文学の連続更新になるわけですが、前回の第150回芥川賞受賞作『穴』に続き、今回は最新の第151回芥川賞受賞作である『春の庭』の書評 . . . Read more
おひさしぶりです。三連休前半は京都に旅行に行ってきましたが人が多すぎてげっそりしてしまったただけーまです。はい、人ごみ苦手です。学生時代に平日に行った京都が如何に居心地が良かったかが思い出されます。やっぱり観光名所は平日に行くに限りますねぇ。
久しぶりに小説の更新です、と言っても大分前のことですが……第150回芥川賞受賞作の『穴』を読みました。受賞作は「穴」という作品ですが、「いたちなく」と「雪 . . . Read more
「…………ブウウ――――――ンンン―――――――ンンンン……………。」
夢野久作の代表作、そして日本一の奇書でもある『ドグラ・マグラ』の冒頭は、このような奇妙なボンボン時計と思しき音からスタートします。
この音は物語の終盤、小説の循環構造を支える決定的に重要な音と成ってくるのですが、小説を読み終えたところで我々読者はこの音の正体を見失ってしまいます。「はて?この音は果たして本当に . . . Read more