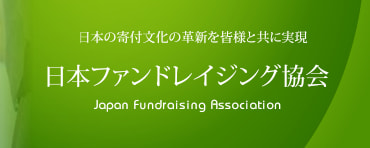市民の方から、「(私の)一般質問が午後だと思っていたら、午前中に終わってしまっていて傍聴できなかった」とお声をいただきました。申し訳なさ半分、うれしさ半分です。平日は仕事があって傍聴に行けない、とのお声をいただくこともあります。
傍聴に行こう、と思っていただけるのはうれしいこと、都合が合わないのは申し訳ないことです。せっかくインターネット録画中継が始まりましたから、そちらで見ていただけたら、と申し上げたら、すでに前の議会のは見ていただいたとのこと。答弁をもっとしっかりするといいのに、読んでいるだけで気持ちがないように見える、とのコメントをいただきました。私の質問の至らないところをご指摘いただけると勉強になるのですが、面と向かって厳しいことをいわない奥ゆかしさ・日本人気質なのでしょうか・・・
インターネット中継をご覧いただいた方も、傍聴に来てくださった方も、どうぞ遠慮なく感想をおっしゃってくださいね。私の質問に限らず、全体のことでも結構です。議会広報委員会の委員の一人として、市民のみなさまのありのままの感想もたいせつな情報です。
私の今回の一般質問の動画公開は、木曜日からになります。いましばらくお待ちくださいませ。
ところで今回の一般質問で、(仮称)おおぶ文化交流の杜について質問したところ、「建物の寿命は100年と考えていた」との答弁がありました。
考えさせられます。100年後の公共図書館の姿は想像つきません。さらに情報化がすすめば、書籍という媒体のあり方すらも変わっていくことでしょうし、収蔵という機能、リファレンス機能、まちのみんなで使えるデータベースとして、などなど、すでにいろいろな可能性を秘めています。音楽ホールも、技術革新で音響など時代とともによりよいものが出てくることでしょう。まちの姿も、ひとが一箇所を目指して移動してくるスタイルで暮らしているか、より小さいコミュニティ単位での生活&情報化や宅配の進歩で「人が動かなくても情報やモノが動いてやってくる」という時代が来るのかもしれませんし。
そもそも、100年後の公共のあり方全体のなかで、市町村行政が占めるもの・求められる役割がどうあるか?それすらも変化の中にあると思います。