小樽で観光タクシー·ジャンボタクシーの北海道個人髙橋タクシーです。
目玉焼きをトッピングして見ました。
親父のランチ·自作ソース焼きそばです。

目玉焼きをトッピングして見ました。
うぉー 美味しそうに出来上がりました。(^o^)v
ლ(´ڡ`ლ)

田中酒造㈱「亀甲蔵」


伏流水(地下水)

酒と水
明治32年(1899年)に創業した田中酒造㈱が平成8年(1996年)に設置した酒造工場と見学施設です。
約10種類以上なお酒が試飲できるミュージアムです。



伏流水(地下水)
山から流れてくるみずには地上を流れる「川」と、地下に水系を持つ「地下水」とがあります。現在、小樽市内の水道水の原水は「川」や川を堰き止めた「ダム」から取水していますが、小樽の主に酒造メーカーでは、地下水をポンプで汲み上げて使用しています。
田中酒造は地下75㍍の水を原料に使用し、北海道ワインは地下152㍍から吸い上げた水をワインは冷却用に、また地ビールは原料として使用しています。


酒と水
1升(1. 8㍑)の酒をつくるには10升の水を使うといわれるように、酒の10倍以上の水が様々な段階で必要です。
「洗米」米を洗う水、「浸漬」米を適度に潤す水、「蒸米」米を蒸気で蒸す水、「仕込水」米と麹とを一緒にタンクに入れる水、「割水」度数調整のための水といったほとんど全てのプロセスで水を使用します。

小樽の親方
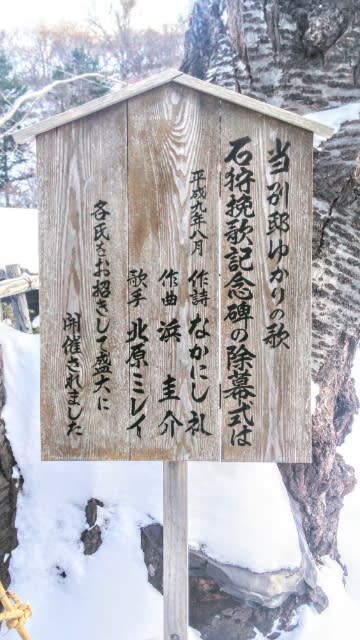
このうち青山家の番屋は札幌市の北海道開拓の村に移設されましたが、いくつかの番屋は今でも残っています。また石造倉庫も多く残されていて、番屋とともにかつてのままの配置で並び、鰊漁が盛況だった頃の雰囲気を伝えてくれています。
青山家は、天保7年(1836年)に山形県遊佐町に生まれた青山留吉が、江戸時代から祝津に出稼ぎし、明治になって同地に居を構えたものです。同家は規模を拡大し、明治20年代には祝津、高島地区の総建網数102統のうち、青山家所有のものが16統を数えるほどになりました。
高島や祝津地区の鰊漁は江戸時代から盛んで、近代には青山家、白鳥家、茨木家といった大漁家がいました。

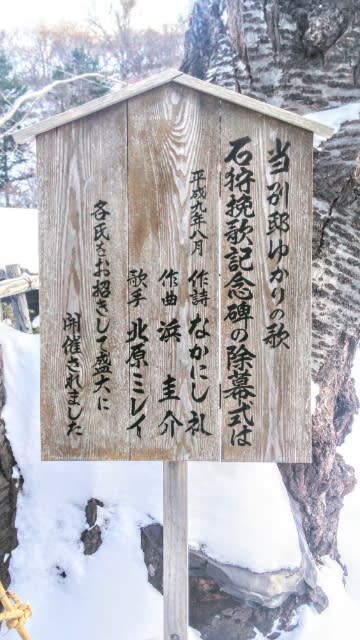
このうち青山家の番屋は札幌市の北海道開拓の村に移設されましたが、いくつかの番屋は今でも残っています。また石造倉庫も多く残されていて、番屋とともにかつてのままの配置で並び、鰊漁が盛況だった頃の雰囲気を伝えてくれています。

青山家は、天保7年(1836年)に山形県遊佐町に生まれた青山留吉が、江戸時代から祝津に出稼ぎし、明治になって同地に居を構えたものです。同家は規模を拡大し、明治20年代には祝津、高島地区の総建網数102統のうち、青山家所有のものが16統を数えるほどになりました。
茨木家も青山家と同じく山形県遊佐町出身で、江戸時代に鱈釣り漁夫として雇われて祝津へ出稼ぎに来ていました。秋には鮭漁の漁夫として石狩で働いて資金を蓄えた後、鰊漁に進出し、明治10年(1877年)以降には4統の建網を持ち、他4統の経営に関わっていました。





















