明治から大正に掛けて、北海道の日本海沿岸各地は江戸時代から続いていた鰊漁が最も盛んに行われていた時代でした。

鰊はアイヌ民族によって古くから捕獲されていたものと思われますが、本州から北海道へ渡って来た人々による捕獲の記録は、江戸時代以前の15世紀中頃までさかのぼります。

高島や祝津地区の鰊漁は江戸時代から盛んで、近代には青山家、白鳥家、茨木家がいました。
漁期中の3月〜5月は、雇いの漁夫や手伝いの人々で集落は一挙に人が増えました。浜も鰊の運搬や加工を担った出面(日雇い)の人たちや物売りで祭りのような賑やかさでした。
かつて聞かれた「群来」という言葉は、大群で押し寄せた鰊の放出する白子によって海が白濁する現象を言います。この群来によって海ははるか沖まで白くなり、海面はお湯が煮だつように見えるほどで、まさに浜は鰊と人で沸き返りました。鰊の活況は過去のものになりましたが、小樽市内の祝津、高島、忍路地区に今でも残る番屋などの建築物や、保存伝承されているソーラン節などで、在りし日の鰊場を感じることが出来ます。


鰊はアイヌ民族によって古くから捕獲されていたものと思われますが、本州から北海道へ渡って来た人々による捕獲の記録は、江戸時代以前の15世紀中頃までさかのぼります。
江戸時代になると北海道の産物として鰊製品が注目され、北前船の日本海航路が整備される大型網の導入などによって、幕末にかけて漁獲量は大きく伸びました。人々が鰊を求めたのは本州、とくに西日本で、鰊を原料とする肥料の需要が高まっていたことが有りました。
北海道全体の漁獲量はえとから明治30年(1897年)頃まで、高い値を示していました(漁獲高は「石」で表し、乾燥した製品40貫(150kg)を作るために必要な生鰊200貫(750kg)を1石とします。)
江戸時代の天保9年(1837年)には15万石余、安政元年(1854年)には24万石と増えて行きます。明治20年には62万石、24年(1891年)には100万石を越え、30年(1897年)には130万石に迫る勢いをみせ、この頃が北海道全体での最高値でした。以降、明治36年(1903年)に100万石を越えましたが、その後は60万石台を上下し、大正2年(1913年)に再び103万石を越えたものの、次第に豊凶の波が激しくなりました。
北海道沿岸に集落の基礎を作った鰊でしたが、明治時代末から漁獲が全くない地域が見られるようになります。道南から漁獲がない地域があらわれ、昭和はじめにはそれまで豊漁地帯とされていた積丹半島でも凶漁になるところが有りました。昭和20年代には一時回復し、石狩以北からオホーツク沿岸ではまとまった漁獲高を見せましたが、昭和30年頃には漁獲が途絶えました。
鰊が激減した原因には海水温の変化や乱獲など様々な説がありますが、現在も不明です。石狩湾の鰊は平成9年(1997年)以降急増し、まとまった漁獲が報告されています。

高島や祝津地区の鰊漁は江戸時代から盛んで、近代には青山家、白鳥家、茨木家がいました。
このうち青山家の番屋は札幌市の北海道開拓の村に移築されましたが、いくつかの番屋は今でも残っています。また石倉庫も多く残されていて、番屋とともにかつてのままの配置で並び、鰊漁が盛況だった頃の雰囲気を伝えてくれています。
青山家は、天保7年(1836年)に山形県遊佐町に生まれた青山留吉が、江戸時代から祝津に出稼ぎし、明治になって同地に居を構えたものです。同家は規模を拡大し、明治20年代には祝津、高島地区の総建網数102統のうち、青山家所有のものが16統を数えるほどになりました。
茨木家も青山家と同じく山形県遊佐町出身で、江戸時代に茨木與八郎が鱈釣り漁夫として石狩で働いて資金を蓄えた後、鰊漁に進出し、明治10年(1877年)以降には4統の建網を持ち、他4統の経営に関わっていました。

先月、東京の会社へメデタク就職が決まって、東京で憧れの1人暮らしを始めた次女から昨日バレンタインチョコレートとケーキが送られて来ました。

手紙には、東京での憧れの1人暮らしは楽しいと書いてありまずは、一安心です。
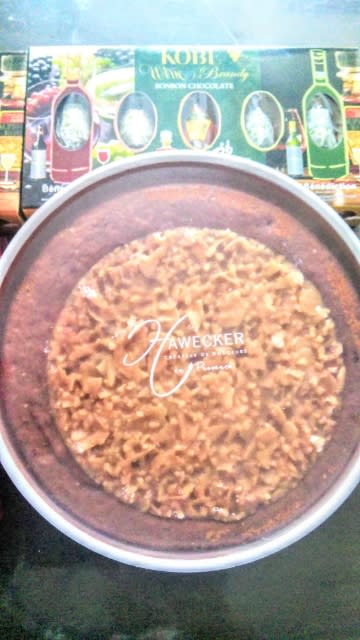

手紙には、東京での憧れの1人暮らしは楽しいと書いてありまずは、一安心です。
家にいた時は、1人暮らしなんてちゃんと出来るのかー?と不安な所も有りましたが、やれば出来るものなのですねー(笑)
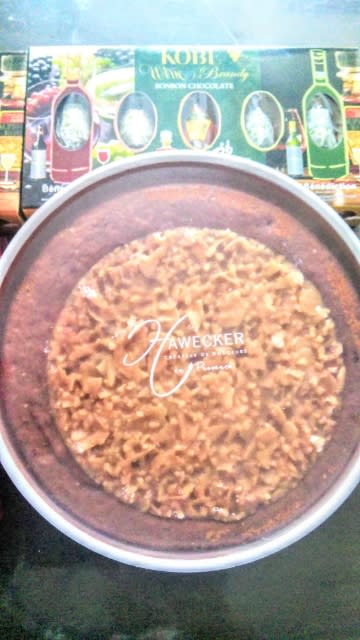
バレンタインのチョコレートとケーキ有り難う。
3人で美味しく頂きまーす。(^o^)v
自分の夢に向かって歩き始めた娘よ、頑張れ!!




















