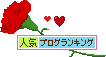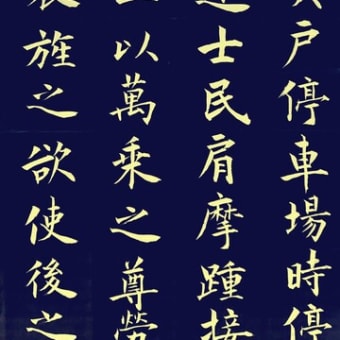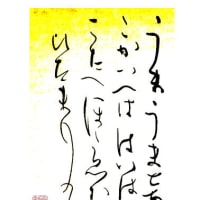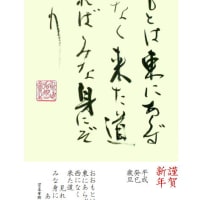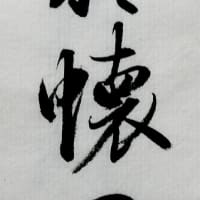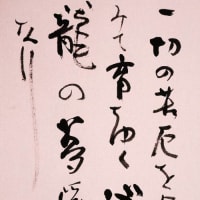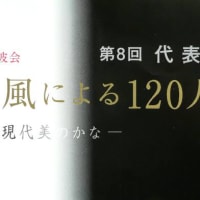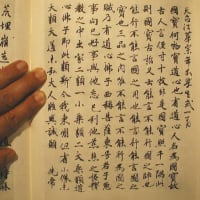王羲之の尺牘二十九帖を収むるも十七帖といふ 丹人
おうぎしの せきとくにじゅう きゅうじょうを おさむるもじゅう しちじょうといふ
これが名は帖の数にはあらずして「十七日」にてはじまるがゆへ 丹人
予が法書「十七帖」を求むるは
昭和四十七年十一月二十一日 時年十六にあり
日立駅前平和通りの書道専門店「永盛」にて
二玄社書籍跡名品叢刊「東晋 王羲之 十七帖二種」を
五百五十円にて購入したる
此帖の特色は
松井如流氏の言を借りれば以下の如し
**********
草書の典型といわれる王羲之の草書は
この十七帖によつてその面目をうかがうことができよう
結体があくまでも安定し
古雅な形を保っている
そして
草法が自然瀟洒をきわめているが
少しも浮薄ではない
重さがあり厚みがあって
ぐつとわれわれの胸を打つてくるのである
唐代の草書とくらべてみるとよくわかるが
形意ともに備わつて高い響きを立てている
**********
まず御覧いただくは
上野本(上野有竹齋蔵本)なり

十七日先書都・・・
即日得之下書・・・
具示復数字・・・
真蹟を見るようなおおどかな筆致である
羲之の面目をまず遺憾なく伝えているといえよう
(松井如流氏の言)
続いて御覧いただくは
三井本(三井聴氷閣蔵本)なり

筆の方向が変つてゆくところを断切して
筆の向きを明らかにした一種変つた刻法を用いている
しかし文字の結構や崩し方においては
一として悪いところがなく首尾完全な姿を持つ
鋭くつよい線がいきいきとして他本を圧しているようである
線の断切のところを手加減して学ぶなら
王羲之の筆法を会得するには
もつてこいのものといえよう
(松井如流氏の言)
十代は三井本にて学びきて二十代には「ああ上野本」 丹人
じゅうだいは みついぼんにて まなびきて にじゅうだいには ああうえのぼん
ああ上野駅 !?
次回以降は予が二十五歳時の十七帖(上野本)全臨を掲載する予定なり~