ところで、これが切っ掛けとなって「いろは」とはそもそも何だろうかと考えるようになった。
たまたま司馬遼太郎の「空海の風景」を何十年振りかに読み返していたところであり、その影響もあったのかもしれない。
戦前に生まれた我々世代では、誰もが物心つく頃から「いろは四七文字」を習い覚えさせられたものである。
仮名四七字すべてが一字も重複することなく、語呂よくなめらかに口ずさめて幼児でも記憶できるので、「いろは」とは勉強=文字の習い始めだった。
「いろは」は七文字区切りで機械的に覚えさせられたが、最後に「ん」を付けるのが習わしだったと思う。「いろはカルタ」というのが教材によく使われた。
だが、長ずるに及んで、この「いろは」が七文字区切りで覚える単なる文字の連続ではなく、七五調八句で構成される意味深い歌であることを知るようになったのは、いつのことだったのだろうか。
その点について一向に記憶がない。学校での正規の授業や講義などで学んだものでないことだけは確かである。
色は匂えど 散りぬるを 我が世誰ぞ 常ならむ
有為の奥山 今日越えて 浅き夢みじ 酔いもせず
この格調高く意味ありげな歌は、これまで弘法大師=空海が作ったものだとされてきた。
一二世紀に空海の弟子筋に当たる覚鑁が「いろは歌」は涅槃経の
「諸行無常 是生滅法
生滅滅巳 寂滅為楽」
の和訳だとしている。
この歌の字句を正しく読み解くことはできないとしても、中学生くらいなら
「この世の存在はうつろい行くもの 存在に不滅不変なものはありえず 生じ滅する」
とでもいった無常観を歌った歌であるらしいことはムード的には理解できたであろう。
しかし、考えてみれば、人の世のはかなさを歌ったこのような歌が果たして幼児の文字習いの教材として適当だったのであろうか。
内容的には子供にはおよそ不似合な暗い歌が長く語り継がれて教育に使われてきた理由はなんなのだろうか。
「いろは歌」には、すべての日本人が共有している「世のはかなさ」を素直に受け入れさせる心情もしくは感性みたいなものが読み込まれているからなのだろうか。
中世文学の傑作とされる鴨長明の「方丈記」には
「ゆく川の流れは絶えずして しかも本の水にあらず よどみに浮かぶうたかたは かつ消えかつ結びて 久しくとどまることなし 世の中にある人とすみかと またかくの如し」 とあるし
「平家物語」の冒頭は
「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす おごれる人は久しからず ただ春の夜の夢のごとし たけき人もついには滅びぬ ひとえに風の前の塵に同じ」 とある。
また、織田信長が好んだという「幸若舞」の一節
「人生五十年 化天のうちを比ぶれば 夢幻の如くなり ひとたび生を得て 滅せぬもののあるべきか」 もよく知られている。
こうした無常観は必ずしも人生否定的なものではなく、日本人の心に潜む宗教的心情というより、むしろ風土に培われたある種の「美意識」ともいうべきものでもあるように思える。
ダイヤモンドに永遠の輝きを見て美を感じる西欧人とは異なり、桜が散りゆく姿にこそ美を感じ取るのが日本人なのである。
教える側の親や教師にこうした美意識なり感性があったから「いろは歌」が教育の場に受容されてきたのかもしれない。
ところで、この「いろは歌」は一般には弘法大師=空海が作ったものだと信じられてきていたが、最近の史的考証から空海の作ではないとするのが通説となっているようである。
なるほどそう言われてみると、司馬遼太郎が「空海の風景」で描いている空海の人物像や仏教思想からは「いろは歌」はおよそ似つかわしくない内容にも思えてくる。
仮名文字すべてを重複することなく読み込み、しかも仏教思想の深い意味合いを持つ歌に作り上げるなど神業に近く、そんなことができたのは超人的才能を持つ空海くらいしかいないと思われてきたからではないであろうか。
かといって、誰が作ったのか、となると今のところ皆目分かっていないようである。





















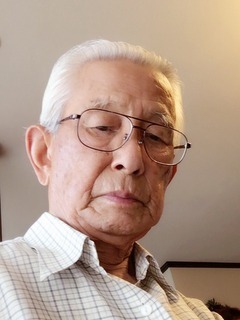





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます