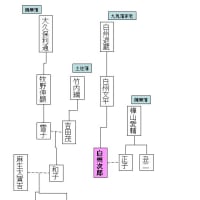それでも近隣の40ヶ村からなる村々の意思を統一するのは難しく、洪水への恐怖や灌漑事業の失敗、村ごとに違う水利事情などから、全村の意見統一をすることは不可能と思えた。そこで助左衛門は隣り合う5ヶ村の庄屋と計らい、5ヶ村の庄屋の意見として、筑後川の堰建設を藩に上訴した。もちろん、費用は5人の庄屋が負担する覚悟であり、先祖から引き継いだ田畑屋敷を売り払っても灌漑事業を成功させたいという重い決断であった。それを聞いたそれ以外の村では喧々囂々の議論が巻き起こり、14ヶ村からは反対上訴が藩にあげられ、それ以外の村は様子見を決め込んだ。しかし、心苦しく感じていたのは様子見を決め込んだ村人たちであった。8ヶ村の村では、5人の庄屋の応援をしようではないかと話し合いが持たれた。そして、手柄を横取りせず、しかし応援する気持ちを表す、ということから、追加の応援上訴という形で8ヶ村の庄屋から堰建設支援の声が上げられた。
藩の財政は苦しく、それまでも参勤交代や日光東照宮の賦役などで借金が嵩んでいた。それでも、筑後川堰建設による灌漑が成功すれば水田耕作面積は激増し藩の石高が上がれば財政も改善できる。藩の普請奉行は藩の面目を保ちながら、灌漑事業が失敗した時には百姓の浅知恵だったと責任回避をする、という案を提示して上訴を取り上げることとした。5人の庄屋には費用は庄屋もち、失敗の時には5人の庄屋は磔刑に処する、という条件で藩として堰建設を行うことが決定された。
ここまでが上巻のストーリー。百姓たちの苦労、そして藩の小役人たちの悪知恵、そして役人の中にも百姓たちの苦労と心意気を感じ取れる侍たちもいて、貧しい中で先祖の苦労と子孫の繁栄を願う百姓たちの心意気が示されて気持ちいい。一日中続く元助と伊八の打桶の掛け声「オイッサ、エットナ、オイッサ、エットナ」が頭の中で渦巻くようだ。