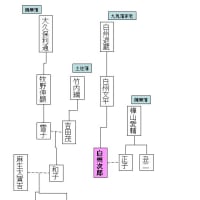火星に取り残された宇宙飛行士が、火星の砂と凍結乾燥した「ウンコ」を混ぜた土でじゃがいもを作り生き延びる、というSF映画「オデッセイ」があった。火星や月の砂だけでは植物は育たないのだということ。つまり地球の土には死んだ動植物の死骸が混ざっているので栄養分となっていて、そもそも火星の砂は土ではない。植物が腐る土は腐植と呼ばれる、それが黒い土の正体。その腐植をミミズが食べて排泄するとミミズの腸内にあったヒアルロン酸やコンドロイチンが混ざった土壌ができる。他にも、アリやヤスデ、ダンゴムシ、フンコロガシも土壌づくりには活躍する。それに白色の砂、黄色や赤色の粘土が混ざるので様々な色がつく。
赤色の土は沖縄、小笠原、東南アジア、アフリカの熱帯地方・亜熱帯地方に多く鉄分が多いヘマタイトを含む。土の種類は類似する土壌をまとめて類型化することで12種類になるとされる。色で分けると黒い土が3種類、赤が1種類、黄色が1種類、白が二種類、茶色が1種類、残りは色に関係なく凍土、水浸しの土、乾いた土、特徴のない土。別の分類をすると、極寒の乾燥した土が永久凍土、乾燥した砂漠土、肥沃な黒土であるチェルノーゼム、寒冷森林のポドソル、粘土の多い粘土集積土壌、風化鉄が多い強風化赤黄色土、更に風化したオキシソル、火山灰の多い黒ボク土、玄武岩と粘土が多いひび割れ粘土質土壌、水浸しの泥炭土、それに土になり始める未熟度とそれが少し風化してきた若手土壌がある。これで12種類。
日本に多いのは若手土壌と黒ボク土、世界で最も肥沃なのが北米のプレイリーとカスピ海周辺北部から中央アジアに広がるチェルノーゼム土壌地域、こうした土の特性を知らなければ豊かな農作は難しい。現在のように化学肥料を大量に投下して行う農業だけではやがて来る100億人の人口を地球上で養うのは難しい。日本に多い黒ボク土、リン酸が不足していて実は肥沃ではないため、石灰を加えて施肥していかなければまともに収穫は望めない。黒ボク土を耕すと腐植の分解や侵食によって肥沃な表土が失われ、連作障害が起きる。リン酸不足でも救世主となったのがソバ、北海道、東北、信州などでは黒ボク土での特産物となった。その他、リン酸を吸収しやすいのが高原野菜、じゃがいも、さつまいも、こんにゃく、ゆり根などで、日本特有の野菜も多い。
田んぼには肥沃な稲作が出来ている。これは酸性土壌の問題を水を張ることで解消している。酸性土壌でも水を張ることで鉄さび粘土が水にとけ、鉄さび粘土に拘束されていたリン酸イオンが開放されて稲が育つ。水田耕作には連作障害もない。水をはったり抜いたりすることで土壌中の病原菌の一人勝ちが防がれる。水が豊富なアジアでのコメ耕作アイデアである。雪国で稲作が盛んなのも、雪解け水の恵みがあるから。こうした日本の土は日本の財産、生かしていく方法を考える必要がある、ここまでが本書内容。
日本は食料自給率が4割しかない、という議論があるが、それはカロリーベースで価値ベースで言えば65%、この価値総額で言えば日本の農業生産額は世界で五位だという本を読んだことがある。土壌が農作物を産み出し、それを人が食べて育つ、人間の体と土地は同じものであるという考えが「身土不二(しんどふじ)」、人間は生まれ育った土地でできた食物が体に合う、と言う考え方。地産地消だけで日本の農業問題が解決できるとは考えられないが、農業を別の視点から振興するという手助けになる。自分でもできそうなことはまず実行して、さらにもう少し前を向いて歩いていきたいものだ。
土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて (光文社新書)