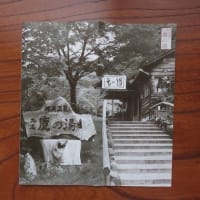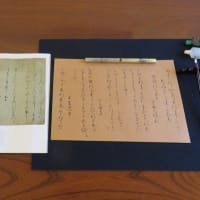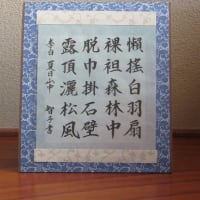先の5月1日から4日まで、三泊四日で東北の被災地を訪ねました。
震災から1年たち、段々、私たちの心の中で風化しつつあることを憂い、
せめて、忘れてはなるまいと、心に刻むべく、旅行することにしました。
当時は衝撃が大きく、考えることも多く、ブログに記載することを躊躇われましたが、
記憶の風化を恐れ、約半年後の今になって記すことにしました。
前夜、宿を急遽手配し、5月1日早朝出発したものの、
3t吊トラック盗難未遂事件が発覚し、高速道をとんぼ返りして、警察に通報するなど対応に追われ、
最初の目的地、宮城県仙台の松島に到着したのは、夕方の4時ごろであった。

民家の経営する駐車場に車を停め、家主に被災の状況を伺った。
「点在する松島と、岩盤のお陰で、この辺は3メートルの津波で、
この目の前の道路まで、黒い海水が押し寄せたが、家には浸水してこなかった」
実際に、港の岸壁は、崩れた跡が随所に見られたが、
港沿いの商店街は、一見するときれいで、被災の事実がピンとこなかった。
遊覧船乗船場に、被災直後の写真と、町民総出で掃除している写真をみて、
商店街の合間、合間の一階が閉鎖されている様子が目に入ってきた。
瑞巌寺も岩盤の上に立ち、これまで幾度もの地震や津波に耐えてきたことを知った。
悲惨な状況を想定して来て、なんだか出鼻をくじかれたような、不思議な面持ちで、
仙台から内陸郊外の宿、作並温泉岩松旅館へ向かった。
仙台市は、TVでも紹介されていた通り、復興バブル、にぎやかであった。

二日目は、岩手県平泉の中尊寺の金色堂と、毛越寺の庭園を散策しました。
奄美大島の阿古屋貝を奥州まで運び、螺鈿に細工し、金銀宝玉でちりばめた金堂、
藤原三代の栄耀栄華、美意識の高さ。
この日は、岩手県花巻温泉 藤三旅館に宿を取りました。
三日目は、いよいよ被災地巡り。
折りしも雨が降り始め、悪路ならぬ土砂崩れが予想された。
花巻から遠野経由、釜石市に入った。
突然始まった。
基礎のコンクリートだけが残された、平地。
言葉も無く、わけがわからぬまま、海沿いの国道を通って、大船渡市へ。
大きな船が打ち上げられている。
そして陸前高田市、あの一本松もぽつんと立っていた。
気仙沼。南三陸町。
鉄筋コンクリートの建物が、転がっている。
海辺の巨大な施設が、空洞の黒い廃墟となっている。
報道で紹介された大きな街と街の間には、小さな村が無数にある。
リアス式海岸の急峻な岩山に、細い谷間にある港に面した小さな漁村。
地形に沿ってアップダウンを繰り返す道。
ダウン、つまりそこは入り江があり、人々が住む村であった。
基礎のコンクリが、それを示していた。
低地から少し上がると、がらんどうの建物が残され、
ある高さから上には、普通の家が、普通どおり、建っている。
さらに上には山道、尾根の狭い場所を切り開いて、仮設住宅が並ぶ。
ある入り江は、棚田のようであった。
でも良く見ると、田畑でなく、家の基礎が草むらに隠れていた。
一つの集落が消えていた。
雨が激しくなり視界も悪く、地盤沈下した海沿いの国道に、波が打ち寄せてくる。
食欲も無くし、血の気が引いて、雄勝町から女川町に入り、
おトイレをずっと探したが、やっと見つけた、高台にある女川町立病院のを借りた。
守衛さんにお礼を言って、正面玄関の正面の柱を見やると、
「津波は、この高さまで来ました。→」
一階天井まで達していた。
こんな、こんな、高い所まで来たのか、、、
病院まで急な坂道を、車で何度か折り返して上がって来た。
こんな高い所まで逃げないと、助からないのか、、、、
後日、実家の母にこの話をすると、母は朝日新聞の震災記事のスクラップを持参して、
「忘れないよう、保管すべきと思ってね」
と各地の津波高が一目で分かる記事を見せてくれた。
女川町は27mであった。
女川から石巻に向かい、被災地にお別れを告げて、
福島県堺にある鎌先温泉、最上屋旅館に泊まった。
最終日4日目は、猪苗代湖畔の野口英世記念館、写真は猪苗代湖

会津若松の鶴ヶ城
を訪ねて、帰路についた。
一番、衝撃を受けたのは、被災した人と、免れた人、被災した土地、免れた場所、
標高のラインで、明暗が分かれている。
同じ村、町であっても、免れた家は、普通どおりの生活ができる。
その下では、全てを失った隣人がいる。
明と暗が、隣り合わせで、同居している。
断絶と孤独に耐えて生きるのは、大変辛いことです。
震災から1年たち、段々、私たちの心の中で風化しつつあることを憂い、
せめて、忘れてはなるまいと、心に刻むべく、旅行することにしました。
当時は衝撃が大きく、考えることも多く、ブログに記載することを躊躇われましたが、
記憶の風化を恐れ、約半年後の今になって記すことにしました。
前夜、宿を急遽手配し、5月1日早朝出発したものの、
3t吊トラック盗難未遂事件が発覚し、高速道をとんぼ返りして、警察に通報するなど対応に追われ、
最初の目的地、宮城県仙台の松島に到着したのは、夕方の4時ごろであった。

民家の経営する駐車場に車を停め、家主に被災の状況を伺った。
「点在する松島と、岩盤のお陰で、この辺は3メートルの津波で、
この目の前の道路まで、黒い海水が押し寄せたが、家には浸水してこなかった」
実際に、港の岸壁は、崩れた跡が随所に見られたが、
港沿いの商店街は、一見するときれいで、被災の事実がピンとこなかった。
遊覧船乗船場に、被災直後の写真と、町民総出で掃除している写真をみて、
商店街の合間、合間の一階が閉鎖されている様子が目に入ってきた。
瑞巌寺も岩盤の上に立ち、これまで幾度もの地震や津波に耐えてきたことを知った。
悲惨な状況を想定して来て、なんだか出鼻をくじかれたような、不思議な面持ちで、
仙台から内陸郊外の宿、作並温泉岩松旅館へ向かった。
仙台市は、TVでも紹介されていた通り、復興バブル、にぎやかであった。

二日目は、岩手県平泉の中尊寺の金色堂と、毛越寺の庭園を散策しました。
奄美大島の阿古屋貝を奥州まで運び、螺鈿に細工し、金銀宝玉でちりばめた金堂、
藤原三代の栄耀栄華、美意識の高さ。
この日は、岩手県花巻温泉 藤三旅館に宿を取りました。
三日目は、いよいよ被災地巡り。
折りしも雨が降り始め、悪路ならぬ土砂崩れが予想された。
花巻から遠野経由、釜石市に入った。
突然始まった。
基礎のコンクリートだけが残された、平地。
言葉も無く、わけがわからぬまま、海沿いの国道を通って、大船渡市へ。
大きな船が打ち上げられている。
そして陸前高田市、あの一本松もぽつんと立っていた。
気仙沼。南三陸町。
鉄筋コンクリートの建物が、転がっている。
海辺の巨大な施設が、空洞の黒い廃墟となっている。
報道で紹介された大きな街と街の間には、小さな村が無数にある。
リアス式海岸の急峻な岩山に、細い谷間にある港に面した小さな漁村。
地形に沿ってアップダウンを繰り返す道。
ダウン、つまりそこは入り江があり、人々が住む村であった。
基礎のコンクリが、それを示していた。
低地から少し上がると、がらんどうの建物が残され、
ある高さから上には、普通の家が、普通どおり、建っている。
さらに上には山道、尾根の狭い場所を切り開いて、仮設住宅が並ぶ。
ある入り江は、棚田のようであった。
でも良く見ると、田畑でなく、家の基礎が草むらに隠れていた。
一つの集落が消えていた。
雨が激しくなり視界も悪く、地盤沈下した海沿いの国道に、波が打ち寄せてくる。
食欲も無くし、血の気が引いて、雄勝町から女川町に入り、
おトイレをずっと探したが、やっと見つけた、高台にある女川町立病院のを借りた。
守衛さんにお礼を言って、正面玄関の正面の柱を見やると、
「津波は、この高さまで来ました。→」
一階天井まで達していた。
こんな、こんな、高い所まで来たのか、、、
病院まで急な坂道を、車で何度か折り返して上がって来た。
こんな高い所まで逃げないと、助からないのか、、、、
後日、実家の母にこの話をすると、母は朝日新聞の震災記事のスクラップを持参して、
「忘れないよう、保管すべきと思ってね」
と各地の津波高が一目で分かる記事を見せてくれた。
女川町は27mであった。
女川から石巻に向かい、被災地にお別れを告げて、
福島県堺にある鎌先温泉、最上屋旅館に泊まった。
最終日4日目は、猪苗代湖畔の野口英世記念館、写真は猪苗代湖

会津若松の鶴ヶ城

を訪ねて、帰路についた。
一番、衝撃を受けたのは、被災した人と、免れた人、被災した土地、免れた場所、
標高のラインで、明暗が分かれている。
同じ村、町であっても、免れた家は、普通どおりの生活ができる。
その下では、全てを失った隣人がいる。
明と暗が、隣り合わせで、同居している。
断絶と孤独に耐えて生きるのは、大変辛いことです。