「昔はじょみず屋さんがいたのにな」
妻が生ごみを指定のゴミ袋に放り込んでいるのを見て、私は何気なく呟いた。
「じょみず屋さんって?」
「知らないのか?」
妻とは二つ違いなので、知っていると思っていたが、意外と二歳の世代間は重い。時々こういった疑問が私に投げかけられる。
「リヤカーで各家庭を回って、生ごみを回収する仕事を生業としている人のことさ。まあ、言ってみりゃ、残飯屋さんってことかな」
「残飯ってまた懐かしい言葉ね。で、その残飯屋さんは生ごみを集めてどうするのよ」
「養豚場にね、持っていくんだ。豚の餌にするんだ」
「へー、結構エコな仕事なのねえ、そんな仕事あったのねえ」
妻の間抜けた顔を見て、私は可笑しくなった。同じ昭和30年代生まれ、じょみずやさんは昭和40年代半ばまでは存在していたはずだから、その言葉は知らなくてもそういった職業があったことは憶えていなくてはならない。
「お前はお嬢だからなあ」
私はそう茶化しながら、ふと記憶の奥底にあるものがひょっこり姿を現したのを感じた。
そういえば、のぶくんはどうしているのだろう?
私はたばこを一本胸ポケットから取り出し、換気扇のスイッチを入れ、その下で吸った。
のぶくんと出会ったのは私が9歳のころのことだっただろうか。
そのころ私は県営のアパートに住んでいて、孤独な毎日を過ごしていた。
3年生になって半年、内気な私はクラスに馴染めず、特にこれといった友達もいなかった。
毎日、学校から帰ってくるとまず学校の宿題をかたづけ、それからゴムボールを持って外に出た。
外に出た私はアパートの角を回り、アパートの壁の前に立つ。それから10メートル程離れると壁にボールを投げつけては跳ね返ったボールを素手で捕球する。私は時間が過ぎるのも忘れて毎日その遊びに没頭した。
そんな私が遊びにきりをつけるのは決まって”じょみず屋さん”がリヤカーを引き、姿を現す時刻だった。
じょみず屋さんの姿を認めると、くさい、くさいと言って鼻をつまんで家に避難するのである。
その日も一人遊びをしている最中に、こちらに向かってくるじょみず屋さんの姿を発見し、家に帰りかけたときであった。
ふと振り返りみると、じょみず屋さんの様子が普段と違うことに気が付いた。
いつもは大人一人でリヤカーを引いているのだが、リヤカーの後ろにもう一人こどもの姿があった。
恐らく中学生になったばかりの少年だ。
私はその場に佇み、リヤカーが私の前を横切るのを見、少年を見ていた。
すると少年は私の視線に気が付き、すれ違いざま、私に向かってニコッと笑いかけてきたのである。
ちょっと待って。
少年が前の大人に声をかけると私が立っている少し先でリヤカーは止まった。
彼は振り返った大人に「ここでいいか」と言うと、その場を離れ私のもとに近づいてきた。リヤカーはまた動き出すと先を行ってしまった。
「野球か?」
私の前に立った少年は私が握っているゴムボールをちらりとみてそう言った。
「・・・そ、そそうだけど」
私は知らない人間に突然話しかけられ、ドギマギした。
「ひとりか?」
「う、・・うん」
「なら、俺と一緒に遊ばんか。キャッチボールくらいできるだろ?」
「で、でも、さっきの人に付いてかないといけないんじゃ・・・」
「大丈夫、このアパートひと回りしたらまた戻ってくるから」
「うん、それなら・・・」
私は仕方がなく、少年とキャッチボールをした。
キャッチボールをしながら短い会話をした。
名前が信夫だということ、中学生だということ、今日からお父さんの手伝いをしているのだということ等々その短い会話の中で知った。
最初はいやいや始めたキャッチボールだったが、こうして二人でボールを交換していると少しづつ楽しくなってくる。
やっぱり、ひとりよりふたりだ。私がそう思っていると彼の父親がリヤカーを引いて戻ってきた。
僅か15分のキャッチボールだった。
私は名残惜しかったが、辺りも暗くなってきたし、やめる他なかった。
「じゃあな、また明日」
私にボールを返すと信夫と名乗った少年はリヤカーの後ろに回り、後部を押し押しもと来た道を帰って行った。
それから私とのぶくんは毎日15分のキャッチボールを楽しむことになった。
勿論、天気の悪い日はのぶくんは来ることが出来なかったが、それ以外は毎日彼が来るのを心待ちにしていた。
たった15分、限られた時間だったがそれで十分だった。
私たちは毎日顔を合わせ、キャッチボールだけではなく会話を楽しむ関係にまで進展していった。
私が友達がいないと嘆くと彼は一生懸命”友達ができる方法”なるものを練ってくれた。
私が虐められたと聞くといじめっ子撃退法なるものを伝授してくれたりもした。
そして日を追うごとに、彼は私にとって、なくてはならない存在になった。
いつのまにか、のぶくんは私の友人と呼べる間柄になったのだった。
そんなのぶくんとの付き合いが8か月ほど続いたある日、私の家にある問題が持ち上がってきた。
父が夕食のあと、息子たちを呼び、ちゃぶ台を挟んでみなを自分の前に座らせた。
何を言うのだろうと身構えていたところ開口一番こう言ったのだ。
「夏にはここを出る予定だ。S町に今家を建てている。転校することになるので、今から心しておくように」
父の言葉に私は驚きを隠せなかった。
友達と離れちゃうの?いやだよ。
そう思わず父に直訴した。
だが、決定事項は決して翻ることはなかった。
父にしてみれば、一国一城の主になるチャンスだ。それにもう事態は動き出している。
父が考え直すはずがなかった。
私は明日のぶくんになんて言おうと考えて、その日一晩眠られなかった。
次の日、眠い目をこすりながら、のぶくんを私は待っていた。
ともかく父の決定のことを話さなければ、と思っていた。
引っ越しをすると言えば彼はどんな顔をするだろう。
そんなことばかり考えていた。
もうすぐ彼が来るころだ。そう思っていたところにリヤカーが来た。
「よお」
のぶくんはいつもと同じようにリヤカーの後ろを押しながら私に笑いかけてきた。
リヤカーを先に行かすとのぶくんは私のもとに近づいてきた。
彼が一歩一歩こちらに向かってくるたびに心臓の音が激しく波打った。
「あと一歩・・・」彼が私の前に来たとき、私は心の中の「えいや」という掛け声とともに口を開いた。
「僕、引っ越しすることになったんだ」
それを聞いたのぶくんは一瞬驚いたような顔を見せ、でもすぐに笑顔に戻った。
「はは、そりゃ良かったじゃん」
「良かった?」
「だってそうじゃん。ここら一帯はうちもそうだけど貧乏人の巣窟だぜ、お前は一生ここにいるつもりだったの?」
「・・・・そんな」
思わぬ彼の答えに私は絶句した。言葉がそこから先、続かなかった。
「俺は出ていきたい。こんなとこできることならすぐにでも出ていきたいよ」
笑いながらそう言う彼の言葉には毒があった。毒は彼の口からまき散らされ、私を包み込む。
私は我慢ができず、そこから逃げ出してしまった。
「おい、どうした」彼の言葉が後ろから追いかけてきたが、私は構わず逃げた。
逃げて逃げて、気が付いたときには家の中で膝を抱えて泣いていた。
その日を境に私はもうのぶくんを待つことをしなくなった。
彼が怖くてしかたなかった。またあんなことを言われたらと思ったらいてもたってもいられなかった。
私は家に閉じこもり、必要なときにしか外出しなくなった。
彼に会いたくなかった。
でも一方で、彼に会わなければと思う気持ちもなくはなかった。
彼は友人だ。それは変わることはなかったのだ。
私はもんもんと家に閉じこもり、日々葛藤していた。
その間に6月になり、7月が過ぎ、8月を迎え、ついに引っ越しの日を迎えることになった。
午前中に大型トラックが来て、家族総出で荷物をトラックに積込み、私は母とともにトラックの助手席に乗り込んだ。
父と兄たちは後ろの荷台の空いたスペースに乗った。
それではさあ出発という段階になったときに何やら声がする。
サイドミラーを見ると、のぶくんがこちらに駆けてくる姿が映し出されていた。
「ああ、友達ね。行ってあげなさい」
母の声に押されて私はトラックのドアから飛び降り、おずおずとのぶくんのもとに近づいて行った。
「これ」
のぶくんは虫の入った虫かごを差し出した。
これはなんだと覗くとカブトムシが一匹いた。
カブトムシは大きな角を持った赤茶色い光沢のある立派な雄だった。
「これさあ、この間、愛宕山に行って捕って来たんだ」
「すごい」
「これ、お前にやるよ。・・・ええと、なんてったけ。・・・そうそう餞別ってやつよ」
「いいの?」
「いいさ、そのために捕って来たんだ」
「・・・ありがとう」
私はこの三か月の間、のぶくんに会わなかった自分を恥じた。
いろいろと葛藤はあったけどのぶくんはやっぱり自分の好きなのぶくんだった。
私はかごを受け取ると、再度トラックに乗り込んだ。
そしてサイドの窓を開け、身体を乗り出し、のぶくんにバイバイをした。
運転手が「さあ行くよ」という仕草をし、トラックが動き出した。
すこしずつのぶくんから離れてゆく。
のぶくんは離れていくトラックを確認すると、もう我慢できないといったように声を張り上げた。
「俺、偉くなるぞ!!偉くなっていつかお前に会いに行くんだ!!」
その言葉を合図にしてトラックはスピードをあげたようだ。のぶくんの姿はどんどんどんどん小さくなり、やがて見えなくなってしまった。
「ここでたばこを吸わないでって言ったでしょ。外で吸いなさい、外で・・・」
妻が角を出してきた。
私は「おお怖い」とキッチンを抜け出し、灰皿を持ってベランダに出た。
外を眺めると、真ん前に富士山がどんと構えていた。
私はあれ以来自分の生まれた土地を訪れたことがない。
のぶくんともそれっきりだ。
今度の休みにでも行ってみようか。
そして今もその場所に住んでいるであろうのぶくんに会ってこういうのだ。
よう、年取ったな。
Mary Hopkin - Those were the days













![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


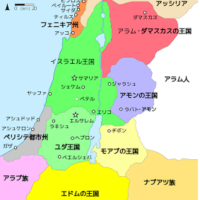



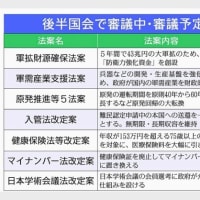






長い文章もものかは、私小説の掌編を読んでいるようで、感心しています
これからのご投稿を、楽しみに待っています
ペテロさま、コメントありがとうございます。
私の拙文を読んでいただいて恐縮しきりです。
これからもよろしくお願いいたします。
みんな一生懸命だったし、努力すれば報われたのはむしろ昭和の時代だったのかも知れませんよね。
しゃちくんさん、コメントありがとうございます。
「・・・努力すれば報われた」、確かにそう思います。
今の世の中、閉塞感で一杯です。もう一度原点に立ち返って昭和の時代の良い面を見習うべきだと思うのですが・・・・。
私は昭和29年札幌生まれ。
じょみずさんと言う言葉は聴いたことがありませんが、残飯屋さんという言葉はうっすらと覚えています。丸井さんの前に立っていた丸いサングラスをかけた傷痍軍人も思い出します。
でも当時は誰もが貧しかったですね。貧しいのが普通だった。
よい話、ありがとうございました。
妻と話をしたあと、他の人に”じょみず屋さん”について話をしてみました。その人もその言葉を知りませんでした。
もしかしたら、昔私の住んでいた地域特有の言葉だったのかもしれません。
昔は皆貧しかったですよね。でも今より希望があり、夢があったように思います。
私の拙い文章、読みづらくありませんでしたか?
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
「じょみずやさん」をこちらの記事で初めて知りました。
昔はそういう方がいて残飯( ほんとに久しぶりにこの言葉も聞きました。 )をあつめてくださっていたのですね。
私は以前は長野県に住んでいたので、裏の畑のコンポストに生ごみを捨てていたので何も気づかずにいました。
東京に越して来てから、土が無いことによる不便さを感じるこの頃です。トイレも実家は汲み取り式だったので腐るものなら万が一落としても大丈夫でしたが、水洗トイレは本当に気を遣います。一長一短ありますね。
面白い記事をありがとうございます。これからも楽しみにしております。
ぱくぱくるんるんさま、コメントありがとうございます。
そう、現代は便利な世の中になりましたが、無くしたものが沢山ありますよね。
私はそれを忘れないようにしたいなと常々思っています。
これからもよろしくお願いいたします。